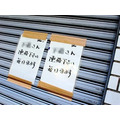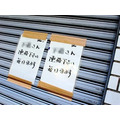怖いという感情は相手の行動が予測できない場合に生じる。相手の行動が予測できる場合にはその対策を考えればいい。
それでは、借金取り(債権者)の行動パターンについて考えてみよう。債権が遅延した場合、債権者はまず郵便や電話での督促を繰り返し、それでも入金がなければ借主(債務者)宅を訪問する(融資残高が少額、遠方の場合は省略することもある)。
訪問の目的は、督促のほかに、生活振りを見て目ぼしい資産があるかどうかを現認することにある。不動産があればその管理状況を、車両等の有体動産についてはその保有の有無・管理状況の確認を行う。
回収財源になる資産(不動産、動産、預金、売掛金、ゴルフ会員権、生命保険等々)の保有が判明した場合は、まず債権の保全を図るため仮差押を検討する。訴訟をしている間に資産が処分されてしまうのを防ぐためである。次いで訴訟により勝訴判決を取得し、その後本差押を実行する。

回収財源が無い、又は配当が見込めない(抵当権付不動産等)と判断した場合には交渉を継続する以外に方策はなく、交渉のみでは進展が見込めないと判断した場合には、債権者名や弁護士名での催告、内容証明、訴訟等を活用して事態の進展を図ろうとする。
債権者が一番困るのは、資力がなく督促や催告等にも全く反応がないケースである。
したがって、不幸にして資金繰りに行き詰った債務者のとるべき行動は、以下のようになる。
2. 利息すら支払えない状況になった場合には、内容証明や裁判にも動じず、無いものは無い(払えない)と開き直る。一定期間耐えて債権者が諦めれば、時効(5年または10年)の援用もできる。
3. 開き直ることが出来ない人は自己破産を活用する。金策に行き詰まって夜逃げを考える位であれば、将来再起のチャンスも期待できる自己破産を選択することである。不動産を所有していなければ、自己破産の手続きは比較的容易である。
以上です。読者の参考になれば嬉しい限りです。(執筆者:遠藤 力)