※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事
2024年12月からマイナ保険証や資格確認書の再交付制度が拡充され、紛失防止や迅速な再発行が可能になる。
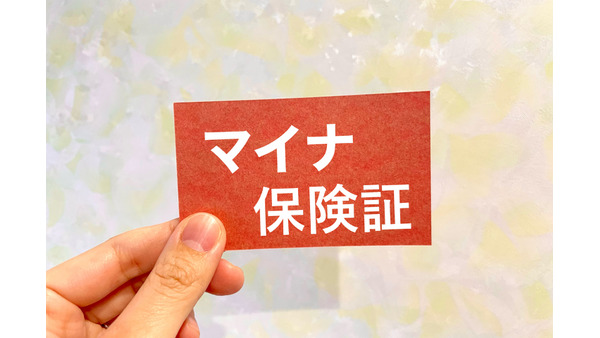
政府のマイナ保険証一本化計画は、一部の健康保険組合の対応により延期の可能性が浮上しており、約8割が赤字見通しの組合が重要な鍵を握る。
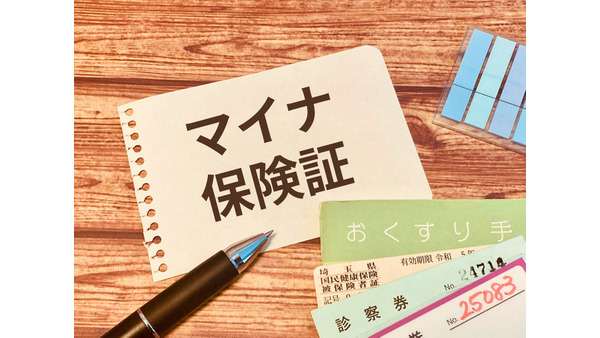
マイナ保険証の利用率が低迷する中、75歳以上には資格確認書を全員交付する方針が示された。理由は利用率が低く窓口混雑が懸念されるため。電子証明書更新忘れも問題視される。
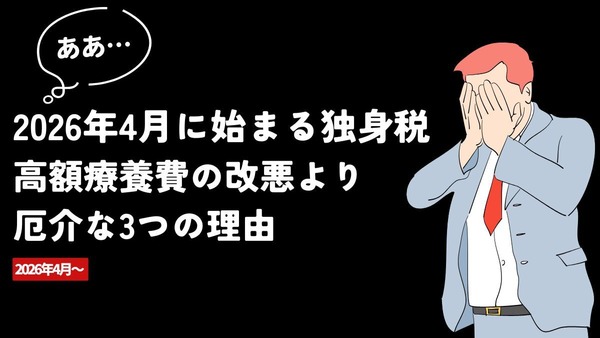
2026年4月から導入される独身税は、負担が長期化し、対策が難しく、周知が不十分なため、高額療養費の改悪より厄介とされる。保険料が直接的な恩恵なしに増える点が問題視されている。
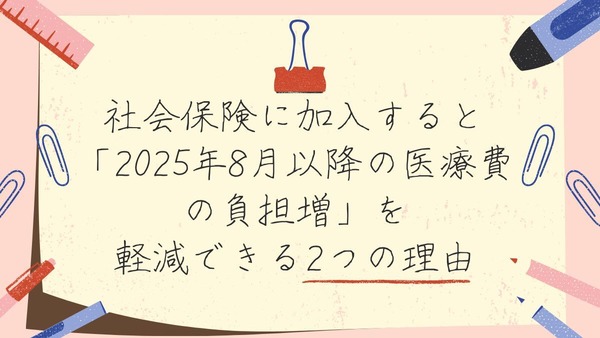
2025年8月以降、社会保険に加入することで医療費負担が軽減される理由は、高額療養費制度の活用と自己負担限度額の算出基準が変わるためです。
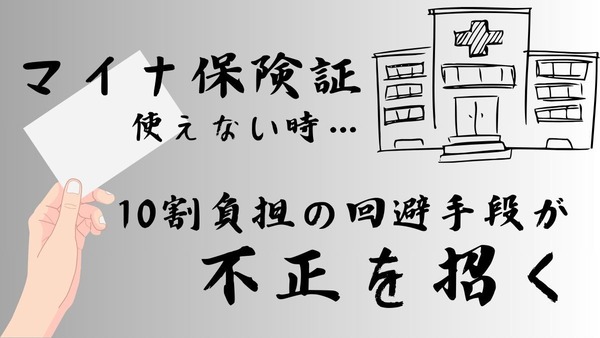
マイナ保険証の利用に伴うトラブルが懸念され、特に偽造や10割負担の問題が多い。政府は不正防止策を提案するが、目視確認が不正を招く可能性がある。資格確認書の導入も同様のリスクを抱える。
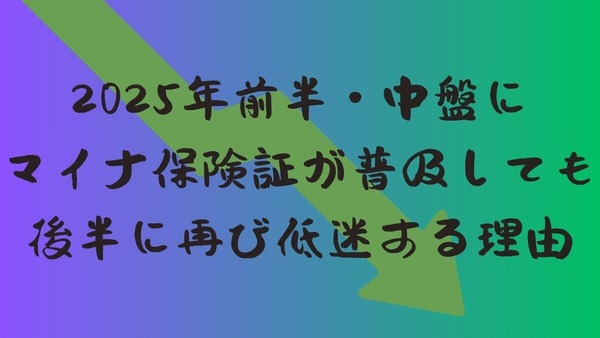
2025年前半にはマイナ保険証が普及する見込みだが、2025年後半には電子証明書の更新手続きの負担から利用率が再び低迷する可能性がある。
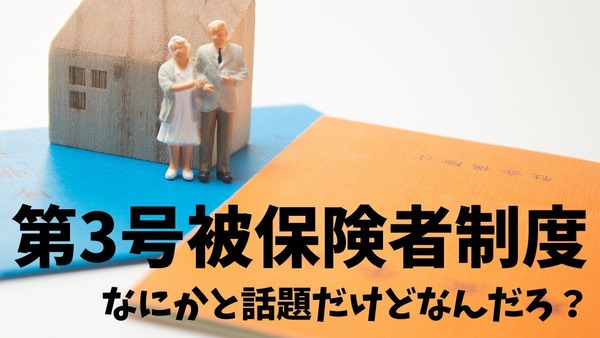
国民年金の被保険者は第1号(自営業等)、第2号(会社員等)、第3号(第2号の扶養者)に分かれ、それぞれ保険料負担が異なる。第3号被保険者は自己負担なしだが、制度見直しの可能性もある。

2025年の雇用保険改正で、マイナンバーカードが利用しやすくなり、給付制限が短縮されるなど、受給条件が緩和される。本改正は教育訓練や育児休業に関連する給付の拡充も含まれる。
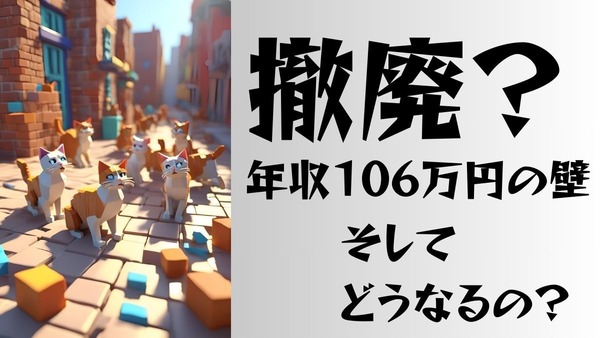
厚生労働省は、2026年10月に年収106万円の壁を撤廃する調整を進めている。これにより、短時間労働者が社会保険に加入しやすくなるが、手取りが減る可能性もある。
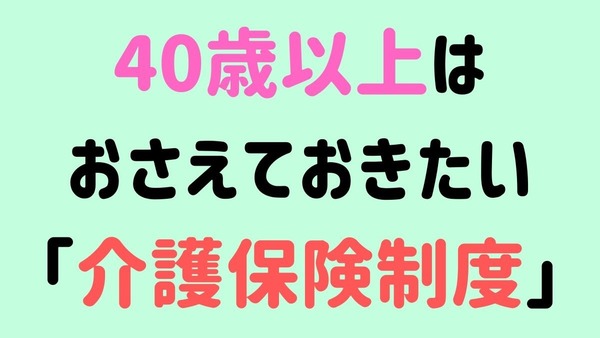
介護保険制度は2000年に創設され、40歳以上が対象。65歳以上は第1号被保険者、40~64歳で医療保険加入者は第2号。介護サービス利用には認定が必要で、要介護度に応じてサービスが提供される。

マイナ保険証の強制や義務化は誤情報であり、実際には資格確認書も選択肢がある。誤った認識が広がると「予言の自己成就」に繋がる可能性があるため、信じるべきではない。
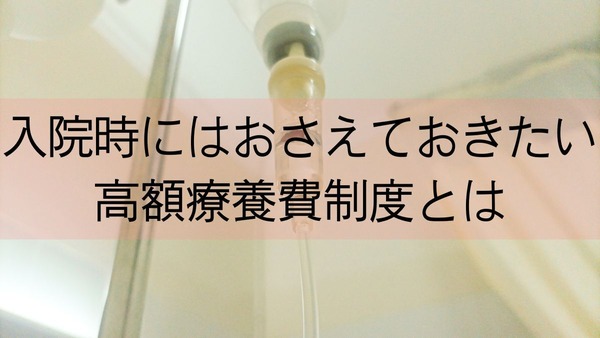
高額療養費制度は、医療費が高額な際の自己負担を軽減する制度で、申請が必要です。同月内にかかった医療費が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻されますが、適用外の費用もあります。
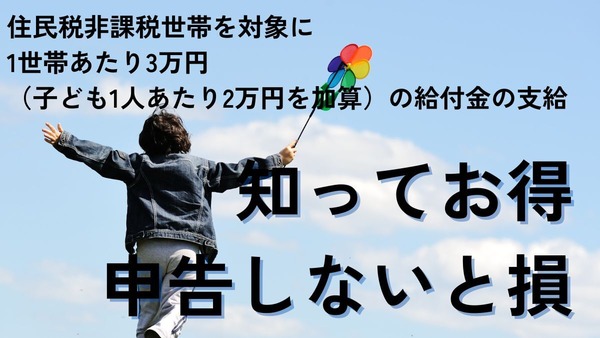
政府は住民税非課税世帯に1世帯3万円の給付金を支給する方針を決定したが、詳細は未定である。住民税非課税世帯には各種優遇措置も存在する。
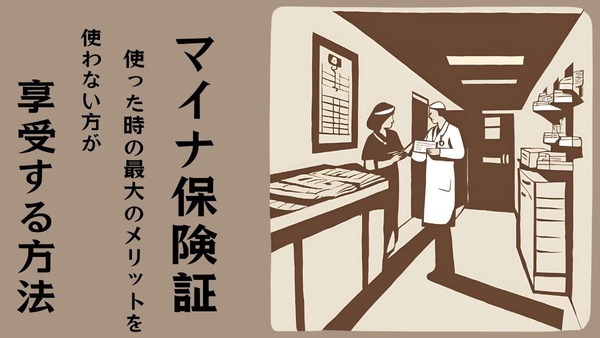
2024年12月に健康保険証が廃止されマイナ保険証に一本化されるが、経過措置で一時的に健康保険証が使える。マイナ保険証の最大のメリットは高額療養費の軽減で、医療機関での手続きが簡略化される点にある。
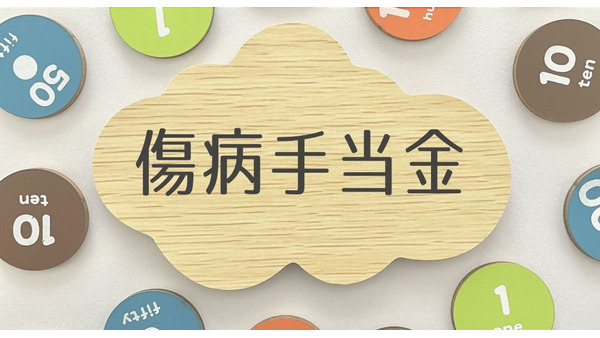
傷病手当金は、私的な理由で働けなくなった際の生活を保障する制度で、複数の疾病がある場合も一つの手当金しか受け取れません。また、待期期間や申請要件にも注意が必要です。

2025年4月から、育児と仕事の両立支援が強化され、子の看護休暇の取得理由拡大や残業免除対象が小学生までに広がるなど働きやすい制度が導入される。
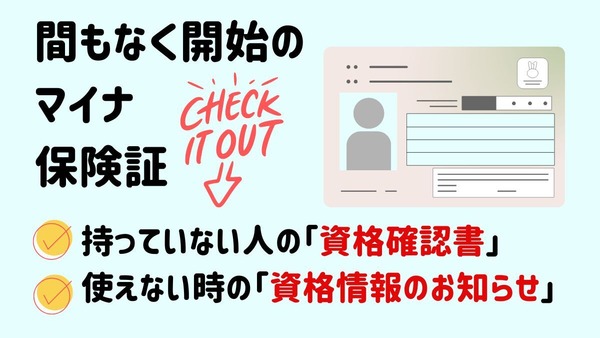
マイナ保険証の本格運用が始まり、未取得者向けに「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」が発行される。これにより、保険診療が受けられる手段が提供される。
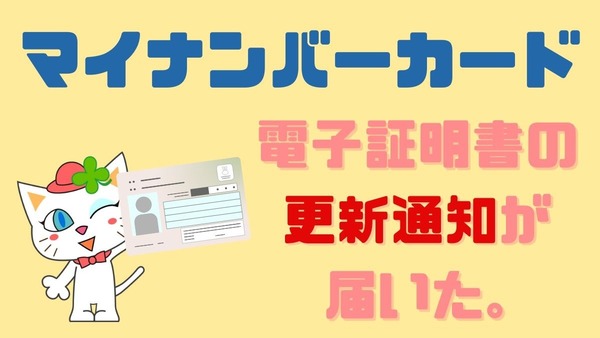
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が近づき、更新通知が届きました。手続きは無料で市区町村窓口で行え、誕生日の3か月前から可能です。更新しないと、各種手続きができなくなるため、早めの更新を推奨します。

児童扶養手当が11月に改正され、所得制限が引き上げられ、金額も増額されます。医療費助成の所得制限も緩和され、対象者が増える可能性があります。
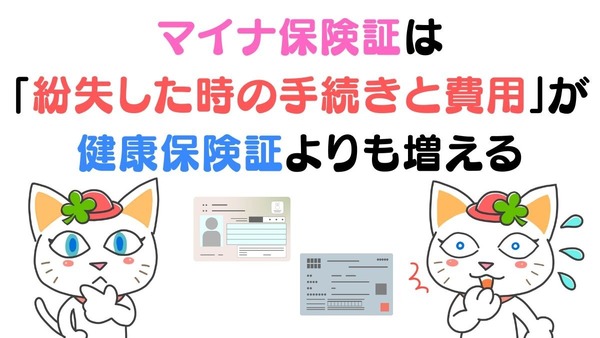
2024年12月2日以降、健康保険証が廃止されマイナ保険証に一本化される。紛失時の手続きが増え、費用も発生するため注意が必要。
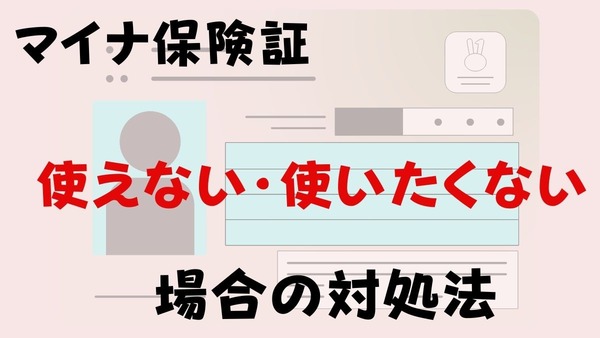
2024年12月2日から現行保険証の新規発行が停止し、マイナ保険証の利用が必須となる。使えない場合は「資格確認書」で対応可能で、メリットやデメリット、注意点も解説されている。
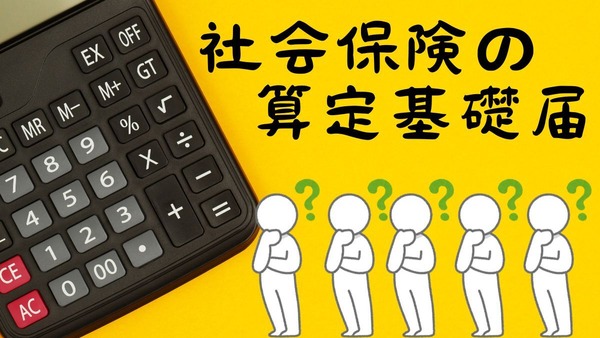
算定基礎届は、4月から6月の給与を基に社会保険料を計算し、10月の給与に反映される手続きです。主に社会保険適用事業所が対象で、誤解を避けるために基礎知識が重要です。

マイナンバーカードが2025年3月24日から運転免許証と統合され、手続きが簡素化される。取得は任意だが、多機能化が進むことで利便性は向上する。
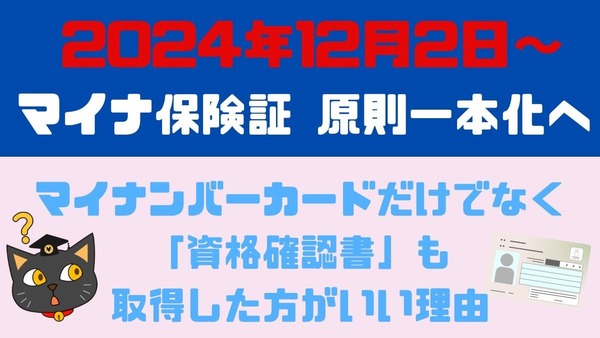
2024年12月から健康保険証が廃止され、マイナ保険証に一本化される。経過措置中は健康保険証も利用可能だが、取得しない場合は資格確認書が発行される。トラブル回避のため、マイナ保険証と資格確認書の併用を推奨。
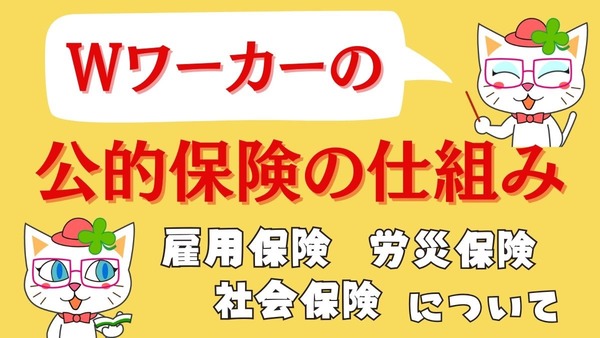
Wワーカーの公的保険について、雇用保険、労災保険、社会保険の制度が異なることを解説。副業や兼業の際は各保険の加入要件を理解し、注意点を把握することが重要。

マイナンバーカードは、運転免許証や保険証と統合され、手続きが簡略化・費用が軽減される便利な制度です。2025年から導入され、コンビニでの証明書交付も可能になります。
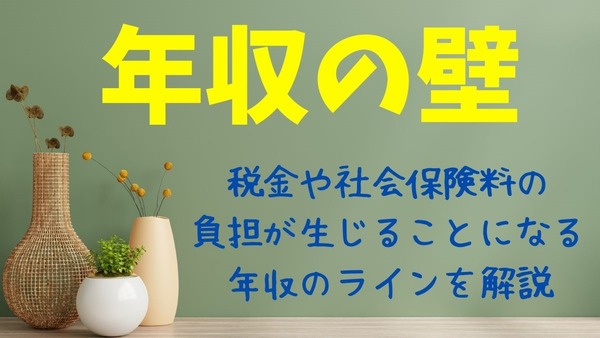
年収の壁とは、税金や社会保険料が発生する年収のラインを指す。主な壁は106万円と130万円で、それぞれ社会保険料負担が変わる。収入調整時はメリット・デメリットを考慮する必要がある。

中高年は医療費が増えるため、健康的な生活や定期的な検診、病院選びを工夫し、費用を抑える努力が重要。病気を未然に防ぐことが節約の基本。

老齢年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の65歳以上の年金受給者に支給されるもので、金額は保険料納付・免除期間により異なる。
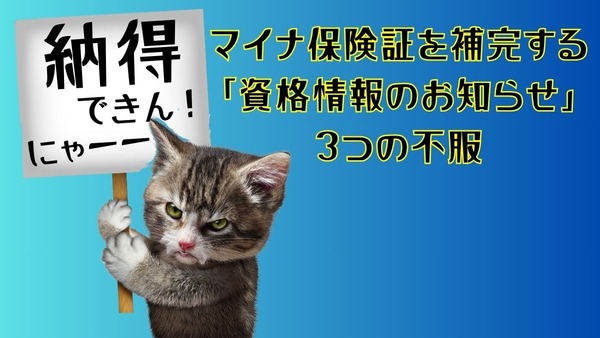
マイナ保険証を補完する「資格情報のお知らせ」の利用に対し、単独使用不可、手間やコストが削減されない点、再交付までの期間が不明な点に不満がある。
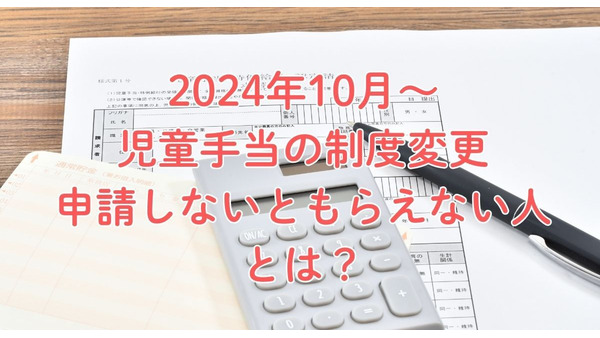
2024年10月より児童手当が改定されます。
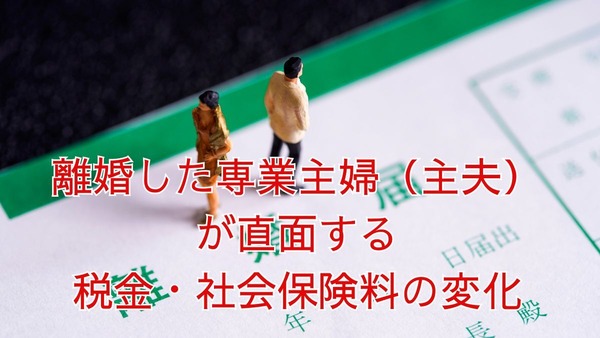
離婚した専業主婦(主夫)は、税金と社会保険料の変化に直面します。収入が得られるようになると所得税と住民税が発生し、国民健康保険に加入が必要になります。また、離婚後に控除が適用できる場合もあります。

2024年10月より、児童手当制度が改正されます。

2025年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証が一体化される。便利な点もあるが、紛失時や手続きの面で懸念も残る。利便性向上にはまだ課題が多い。
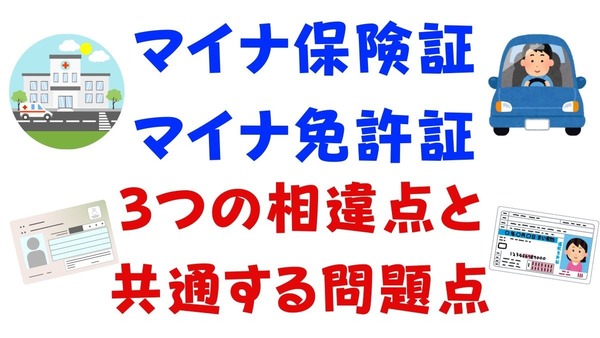
マイナ保険証とマイナ免許証の相違点として、ICチップの役割、一本化の有無、穴埋め制度が挙げられます。共通する問題点はICチップ関連のトラブルで、利用に影響を与える可能性があります。