※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事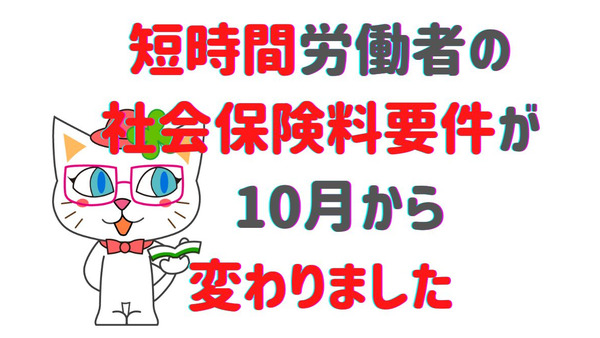
令和4年(2022)10月からパート、アルバイトなどの短時間労働者の社会保険(厚生年金保険+健康保険)加入義務が拡大しています。 要件に合致すれば、年収106万円を超えると社会保険料支払いで手取り額が減少することになりま

年末調整や確定申告の時期になると、収入と所得の違いや、収入から所得を算出する方法を、ニュースサイトなどで解説する方がおります。 例えば自分で事業を行っている個人事業主は、年収(1~12月までの事業収入の合計)から、その事
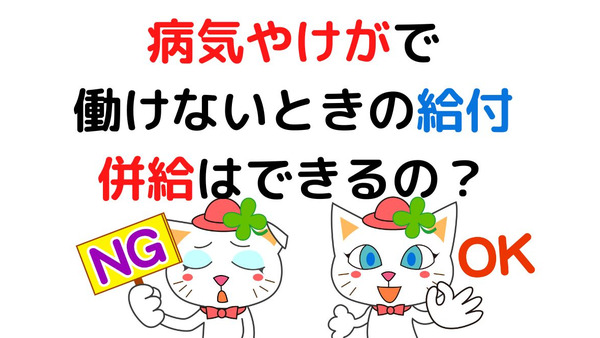
病気や怪我で働くことが難しくなった場合には、いくつかの給付金制度があります。 例えば複数の給付を受給できる権利が発生した場合、それらを併給(同時に両方もらう)できるのかという問題も生じます。 今回は、このような場合の併給
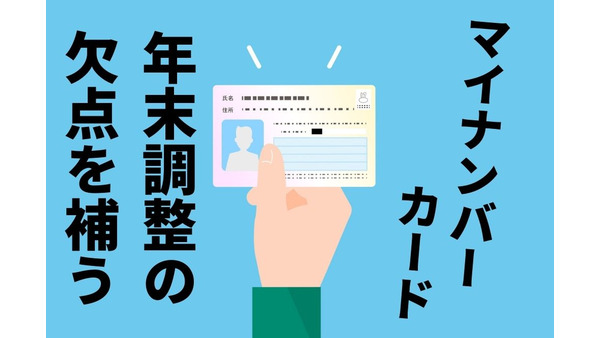
会社員(正社員だけなく契約社員、パート、アルバイトなども含む)として働いている方に課税される所得税は、簡潔に表現すると次のような手順で算出します。 (A)1~12月に支払われた給与の合計額-給与所得控除(年収によって
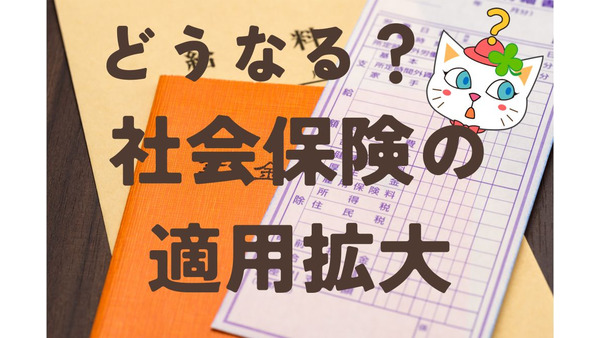
ニュース等でも報道されているとおり、2016年10月から始まった社会保険の適用拡大は、2022年10月、2024年10月を経てさらなる拡大が予定されています。 退職または労働時間を減らして家族の扶養に入るという場合、 誰

老後の年金は原則として、65歳以後は亡くなるまでもらえますが、障害年金は障害の状態によっては一度もらえることが決定したとしても、その後も必ずもらい続けられるとは限りません。 これは更新をする必要があるためですが、今回は障
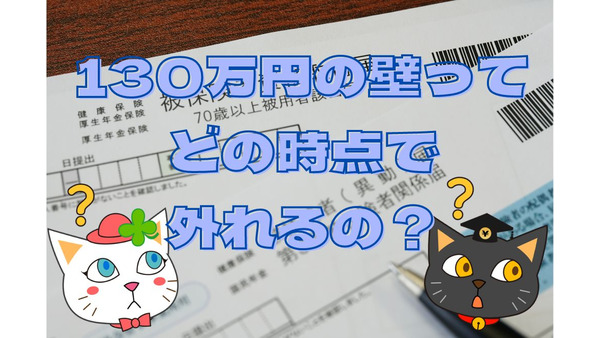
配偶者や家族の扶養になれば、健康保険に被扶養者として加入でき、国民年金では第3号被保険者としてどちらも保険料はかかりません。 しかし、扶養から外れてしまうと自らが健康保険の被保険者となり、国民年金や厚生年金保険に加入しな

誰でも安く医療を受けられる「国民皆保険」は、日本が誇る優秀な制度です。 健康保険の主なメリットは、安く医療を受けられることや、「マイナ保険証」でポイント還元を受けられることが、真っ先に思い浮かびますよね。 しかし、健康保

2016年10月から新基準が始まったため、パートやアルバイトなどの短時間労働者は、次のような5つの要件をすべて満たすと、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する必要があります。 (A)1か月あたりの決まった賃金が、8
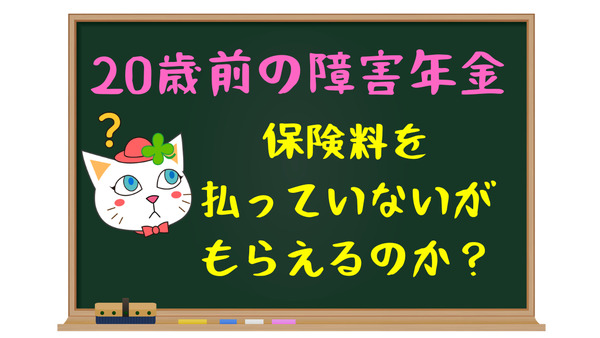
会社員になるような場合を除き、年金制度は20歳から加入対象となります。 そこで、子供が既に障害状態になっているような場合、障害年金はどうなるのかという相談があります。 今回は年金制度に加入できる年齢よりも前に障害状態とな

令和4年10月1日から75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が2割になりました。 昨今、色々な食品や料金が値上がりしている中で、医療費が2割負担になることは、高齢者の方にとって、負担感が大きいで
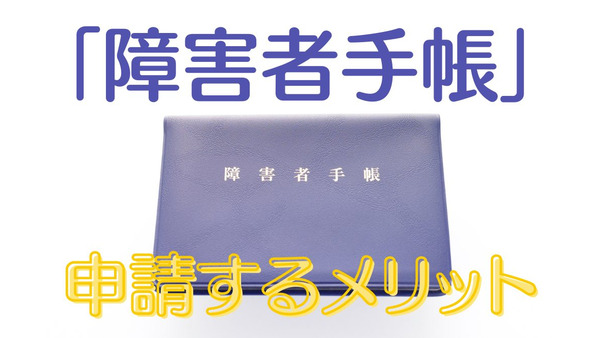
障害年金と並びよく聞くキーワードとして、「障害者手帳」があります。 障害者手帳には3つの種類があり、いずれも申請先は市区町村の窓口になります。 該当する可能性がある場合、申請することでどのようなメリットがあるのかを解説し

河野太郎デジタル大臣が 「2024年秋に、現行の保険証を廃止してマイナンバーカードと一体化した“マイナ保険証”に切り替える」 という発言し、波紋を呼んでいます。 厚生労働省が公表している10月2日時点での「マイナ保険証」

日本には約930万人の障害者がいると推計されており、これは人口の約7.4%に相当する数です。 その場合、生活の一助になる社会保険制度の一つとして、障害年金が挙げられます。 障害年金を受給するためには初診日を明らかにする必

育児休業復帰後に短時間勤務制度を活用した結果、月々の給与が下がることを制度としてカバーする養育特例という制度があります。 端的には子供が3歳になるまでの間、年金額の計算に限って月々の給与が下がる前の水準で計算をかけてくる
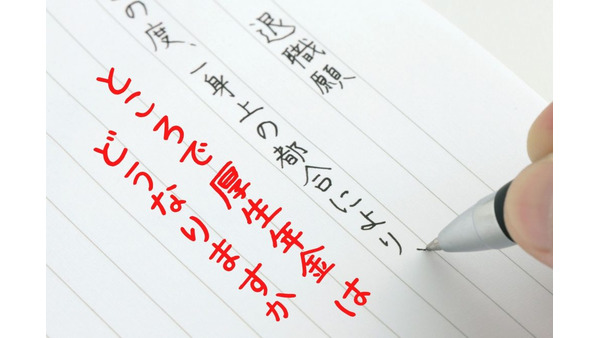
厚生年金とは、公的年金制度のひとつで、厚生年金の適用事業所に常時使用される70歳未満の会社員や公務員などが加入します。 厚生年金の被保険者は、厚生年金保険料を会社と折半で給与からの天引きによって支払います。 このように、

障害年金を申請する前に多くの方がどのようなデメリットがあるのかという不安材料を持たれています。 今回は障害年金を申請するデメリットについて解説します。 扶養から外れてしまう 現在、社会保険上の扶養に入っている場合、障害年
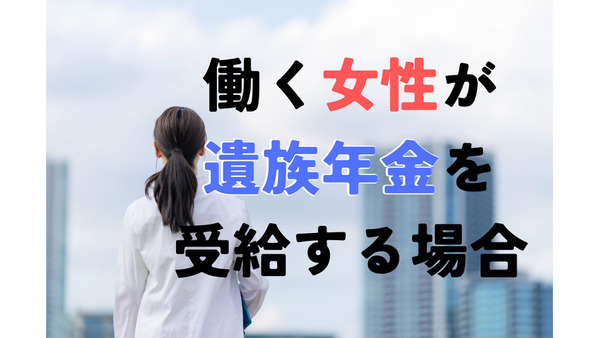
配偶者を看取った後の生活の補填となるものの1つに、遺族年金があります。 遺族年金は夫が受給する場合と妻が受給する場合で要件が異なりますが、女性の社会進出が増えており、働きながら遺族年金を受給するというケースも想定されます
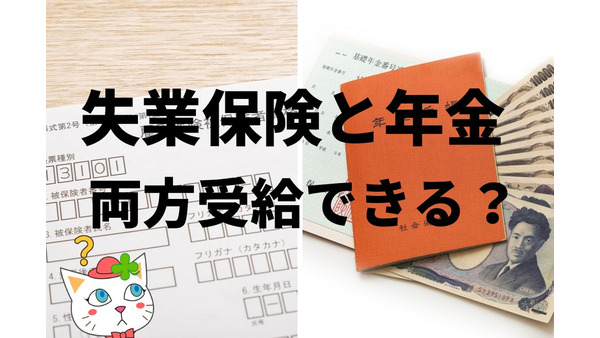
失業保険とは、雇用保険の基本手当のことを指す場合もあります。 また、昭和50年に失業保険法が廃止され、それに変わる法律として雇用保険法が施行されたことから、雇用保険の失業に関する給付全体のことを指す場合もあります。 今回

狭い意味での社会保険とは、原則75歳まで加入する健康保険と、原則70歳まで加入する厚生年金保険の、2種類を示す場合が多いのです。 またパートやアルバイトなどの正社員以外の方は、次のような2つの要件を満たした時に、これらの
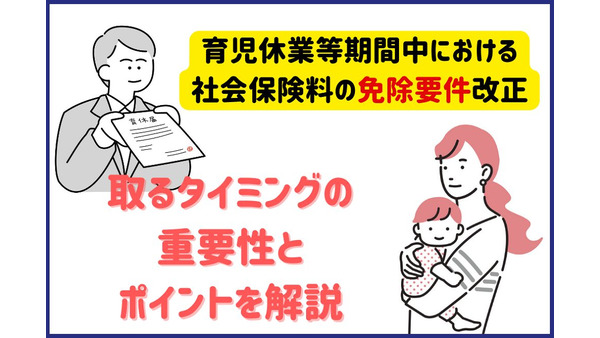
2022年10月1日から育児休業等期間中の社会保険料の免除要件が改正されます。 一部の厳格化により、これまで制度の隙間を突いた裏技的な免除申請もこれで封じられることになりました。 ポイントも含めてお話させていただきます。
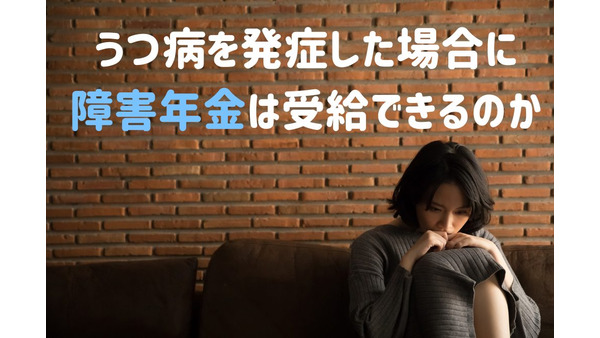
日本の公的年金の中に、障害年金があります。 障害年金とは、疾病や負傷によって所定の障害認定基準に達した方が受給できる年金です。 このストレスの多い現代では、うつ病になってしまう方も数多くいます。 うつ病を発症した場合でも

年金制度には大きく分けて3つの種類があり、「老齢」、「障害」、「遺族」の年金です。 この中で若い世代でも対象となり得るのが、障害年金です。 今回は障害年金について、概要的な解説をします。 障害年金とは 障害年金とは、病気

現在の日本は国民皆保険になっているため、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入しているのです。 例えば中小企業に勤務している会社員と、その扶養家族になっている方は、全国健康保険協会が運営している協会けんぽに、加入してい

日本では60歳を下回る定年は違法とされ、定年退職者から求めがあれば65歳までの継続雇用が義務(65歳から70歳は努力義務)とされます。 しかし多くの場合、給与額は定年前後では下がることが一般的です。 それでも年金支給開始

日本は国民皆保険(すべての国民が公的医療保険に加入し、病気やケガになった時に必要な保険給付を受けられる状態)を、1961年に実現しております。 ただ各人の職業や年齢などによって、加入する公的医療保険に違いがあるのです。
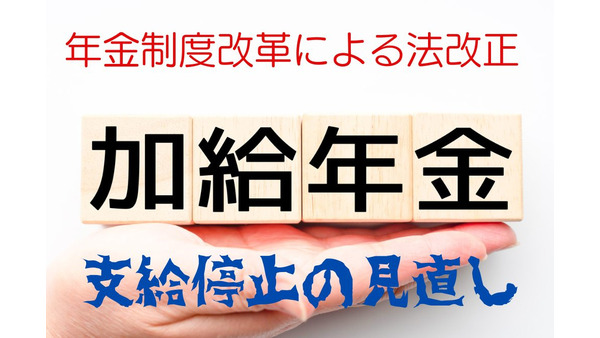
2022年4月からの年金制度改革による法改正により、加給年金の支給停止規定の見直しが行われました。 この改定により、これから65歳になり老齢厚生年金を受給する方の中にも、年金制度改革前であれば加給年金が受給できたのに、法

総務省のウェブサイトの中にある、「マイナンバーカード交付状況について」というページを見てみると、現在のマイナンバーカードの交付状況がわかります。 最新のデータ(2022年7月末時点)を見てみると、「人口に対する交付枚数率
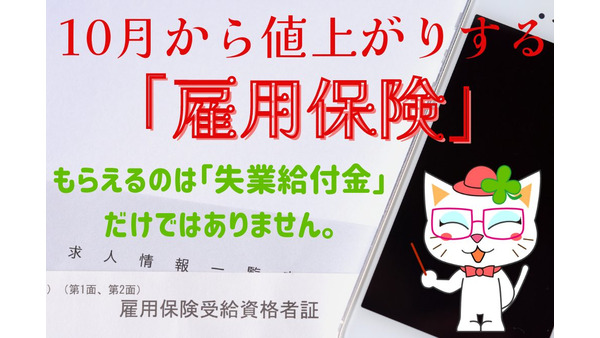
10月から、「雇用保険」の個人保険料が値上がりします。 企業側の負担増はすでに4月から始まっていて、3月までの0.6%が、4月以降は0.85%にアップしています。 本来ならば個人の「雇用保険」も同じ時期に0.3%から0.

マイナポイント第2弾が推進されて、マイナンバーカードと健康保険証の機能を併せ持つ「マイナ保険証」の拡充が着々と進行しています。 最近では、医療機関や薬局でマイナ保険証のカードリーダーを見かけることも多くなってきました。
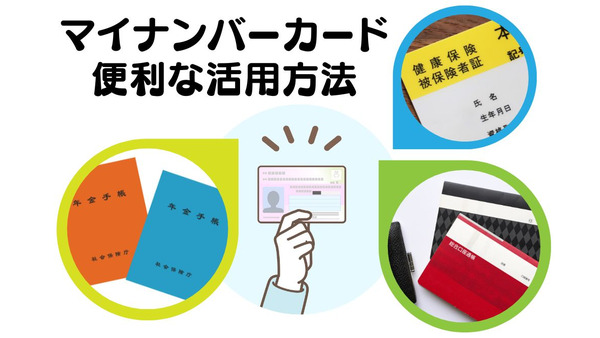
マイナンバーカードの新規取得、健康保険証として利用するための申込み、公金受取口座の登録を行った方に、最大で2万円分のマイナポイントを付与するキャンペーンを、政府が実施しております。 キャンペーンは2022年6月30日から
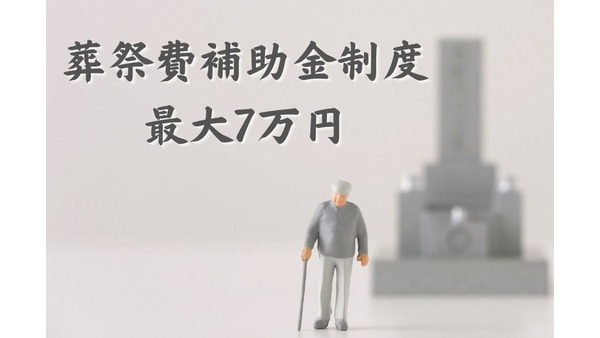
亡くなった人を「埋葬」をすると最大7万円の給付金がもらえる制度があります。 2022年に公開された日本に住む約30万人を対象にした「全国エリア別葬儀費用に関する調査」によると、葬儀費用の全国平均はもっとも多かった「家族葬
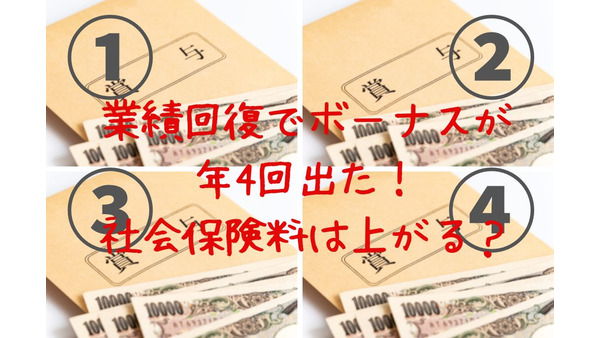
緊急事態宣言時と比べ、徐々に以前の生活スタイルに戻りつつあり、会社によってはボーナスの支給が「復活」するといった動きもみられます。 またボーナスの支給は継続していたものの、決算ボーナスとして通常の年よりもボーナスの支給回
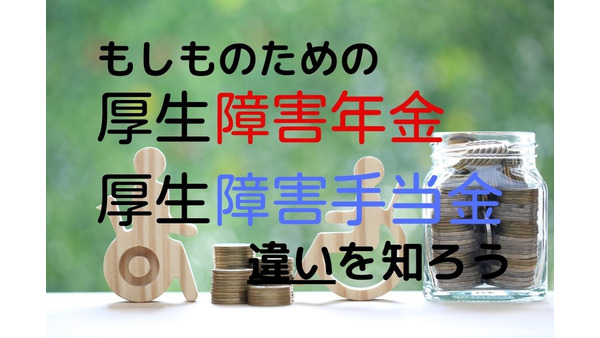
日本の公的年金の中に、病気やけがが原因で日常生活に著しい制限を受ける場合に、生活保障を行う「障害年金」があります。 障害年金の中には、国民年金の給付である「障害基礎年金」と、厚生年金の給付である「障害厚生年金」があり、加
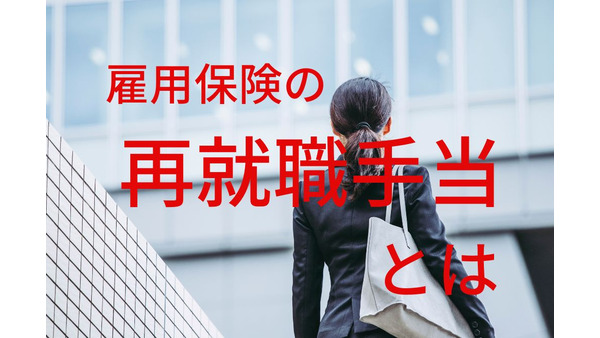
多様な働き方が一般化しつつある現代において、転職活動は旧来よりも増えています。 転職するということは退職と再就職がセットとなることを意味します。 その際に、雇用保険制度から「再就職手当」をもらえる場合があります。 今回は
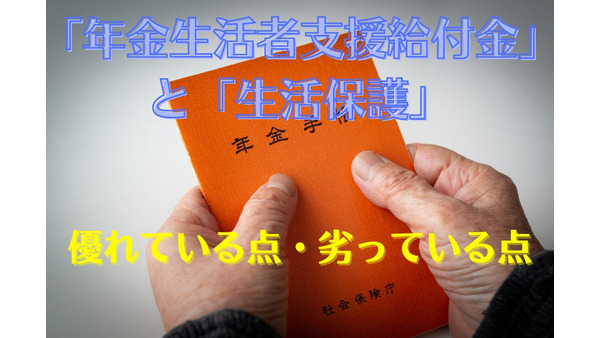
2019年10月からは消費税率の引き上げ分を財源にした、次のような年金生活者支援給付金が、基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の受給者に支給されます。 ・ 老齢基礎年金の受給者を対象にした「老齢年金生活者