※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事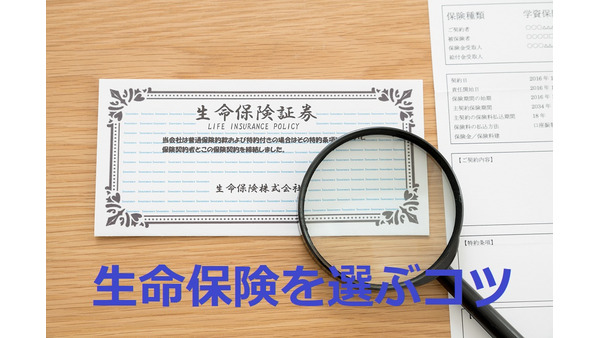
保険への加入は、 「家の購入に次いで高額な買い物」 と言われていると知っていますか? 平成27年に生命保険文化センターが実施した調査によると、個人年金保険を含む全世帯の平均的な保険料は年間38.5万円にも上ります。 これ

新しい会社で働きはじめるあなたへ 新年度が始まる4月から、期待に胸を膨らませて、新しい会社で働き始める方がいると思います。 しかし実際に働いてみたら、面接の時に聞いた労働条件とはまったく違い、例えば、過労死が心配になるほ
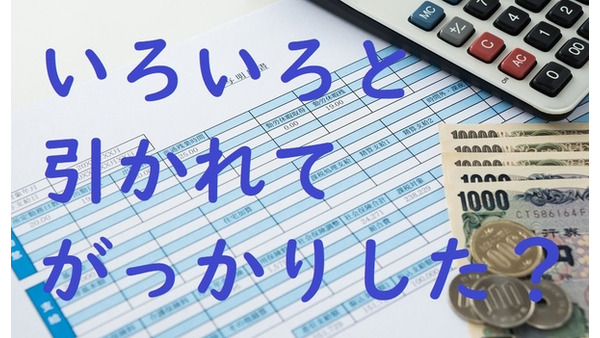
そろそろ初給料日 社会人として新たなスタートを切られた皆さん、ご就職おめでとうございます。 既に配属され社内の雰囲気に慣れてきたという方もいれば、まだ研修中の方もいらっしゃるかと思います。 仕事を通じてどのように成長でき

新年度が始まって、職場では人事異動で不慣れな仕事に就いた方もいらっしゃるでしょう。 学校でもクラス替えで新しい担任やクラスメートに慣れるのに、慌ただしい日々を送ってらっしゃる方も多いでしょう。 平成30年4月より日常生活

夫の転勤で退職したA子さん A子さんのご主人が、4月から東京から大阪への転勤を命じられました。 A子さん夫妻は結婚2年目で現在は東京在住です。転勤に伴いA子さんも一緒に大阪へ引っ越すことにしました。 結婚前から勤めていた

サラリーマンの方や一定時間以上働いているパートの方など「社会保険」に加入されていることと思います。 一般的に「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」のことをいいますが、実はそれぞれの保険料率の改定の時期が違います。
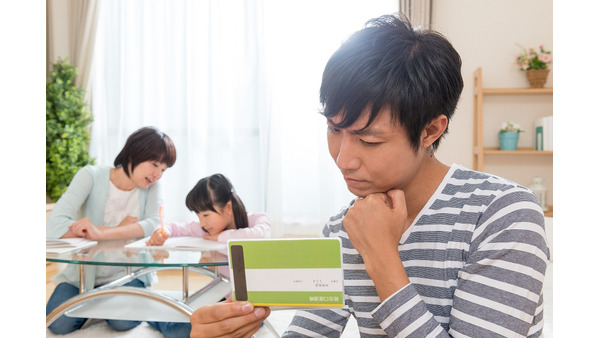
2019年度以降で予定されていますが、 児童手当の対象者が限定される改正 が検討されています。 これまで主たる生計維持者(いわゆる一家の大黒柱)の所得を基に支給が決められてきましたが、夫婦合算されて判定されます。 あと1

前回の記事では、就業不能保険や所得補償保険を検討する前に知っておきたい公的保障制度について紹介しました。 医療費支出を抑えるための ・ 高額療養費制度 ・ 自立支援医療制度 収入をまかなう ・ 傷病手当金 ・ 労災保険の

「就業不能保険」と「所得補償保険」 私たちの多くは、日々働くことによってお金を得ていますが、もしも何らかの理由で働けなくなった場合、どのようにして生計を立てるべきか考えたことはありますか? 社会にはさまざまなセーフティネ

特例が、2018年内に次々と終了します 国民年金の保険料は原則として、翌月の末日までに納付しなければならないため、例えば2018年1月の保険料は、2018年2月28日が納付期限になります。 その一方で保険料の徴収権の時効

知らないともらえない「給付制度」 家族にとって、子供の誕生は大変喜ばしいことです。 その一方、出産から子育て、教育に至るまで、それに関わる金銭的な不安も出てきます。 そこで、家計の負担を減らすために、国は出産・育児に関す
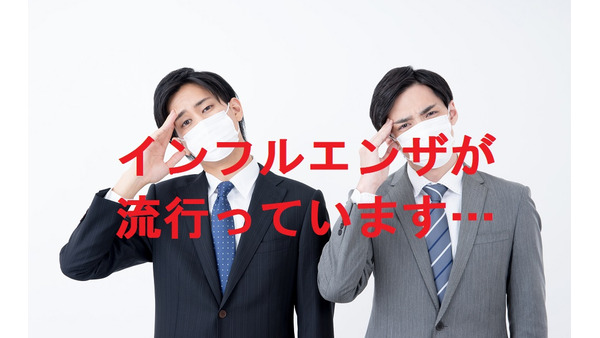
インフルエンザが流行っている時期になっていますが、皆様はいかがお過ごしですか? 職場でインフルエンザが流行っていると最近ではお聞きすることが多々あります。 インフルエンザで休むとなると1週間など長期間となってしまいます。

都内在住の読者の方から 「子供が2人いるが、今後の学費はどうなるのか。高校まで無償化するのか?」 という質問がありました。 そこで「教育無償化」についてのアンサー記事を書こうと思います。 子供1人の教育費ってどのくらいか

雇用保険に加入されている方について、2018年1月以降に受講を開始する「専門実践教育訓練」から、教育訓練給付金の支給率、上限額や支給対象者の要件などが変わります。 また、雇用保険に加入されていた方(失業中の方)についても

将来の退職金(老後資金)に対する不安をお持ちの方も多くおられると思います。 今年より加入対象が広がったiDeCo(イデコ)も退職金を積み立てるには素晴らしい制度です。 それ以外にも、あまり有名ではありませんが、小規模企業

「就業規則」の作成 常時10人以上の従業員を使用する使用者は、従業員の賃金や労働時間などについて定めた「就業規則」を作成して、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。 これは労働基準法に定められた義務のため、就

iDeCoをもっと活用しよう 2017年1月より、会社員の妻(いわゆる第3号被保険者)も個人型の確定拠出年金(iDeCo)に加入できるようになったことはご存じの方も多いでしょう。 確定拠出年金は、その掛金が全額所得控除に
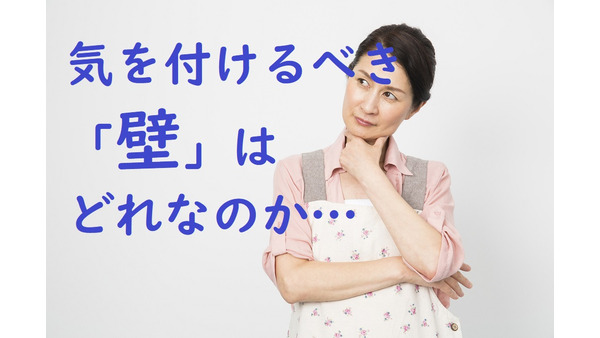
働く主婦が注意する「3つの壁」 2018年から、主婦の働き方が変わりました。 主婦がパートで働く場合、収入によって注意する3つの壁があります。 ・ 壁1 配偶者控除の壁 ・ 壁2 会社の社会保険に入る壁 ・ 壁3 夫の扶

介護保険の使い方はなんとなくわかってきたけど、介護保険料、いつから徴収されるのかご存じですか? 社会保障制度の1つである介護保険制度の被保険者は一定の条件に該当することで本人の加入や非加入の意思の確認なく、また手続きもな
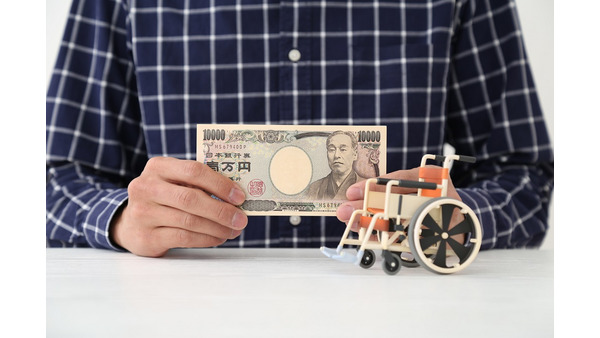
社会保障制度に関する衆院選公約で、「総合合算制度」という言葉を聞いたことがあるかと思います。 医療・介護・障害・子育て(保育)などに直面すると大きな負担を覚悟しないといけませんが、それらを合算して上限額を設定する制度です

2018年以降は新聞や雑誌などで特集されているように、夫が38万円の配偶者(特別)控除を受けるための妻の年収制限が、「103万円以下」から「150万円以下」に拡大されます。 また2018年以降は夫の年収が「1,120万円

2017年衆院選で、希望の党の公約に挙がって話題になった「ベーシックインカム」。 労働の担い手が人工知能にとって代わられた場合に、国民はベーシックインカムによって生活が保障されるという話があります。 ただ、政党公約と

これから仕事を辞める予定のシングルマザー(ファーザー)の皆さん、収入が減れば母子(父子)家庭の手当は増えると思っていませんか?(以下母子家庭に省略) また、今まさに離婚を考えているワーキングマザー(ファーザー)の皆さんは

「高額療養費制度」で一定金額以上の自己負担はありません。 我が国は、国民皆保険制度を通じて世界最高レベルの平均寿命と保健医療水準で、安全・安心な暮らしを保障しようとしています。 「高額療養費制度」は、家計に対する医療費の

マネーポストWEBに掲載されていた、「70歳以上の自己破産が急増 2005年は3.05%で2014年は8.63%」という記事によると、高齢者の自己破産が増えているようです。 この記事の中で紹介されている、日弁連が実施した
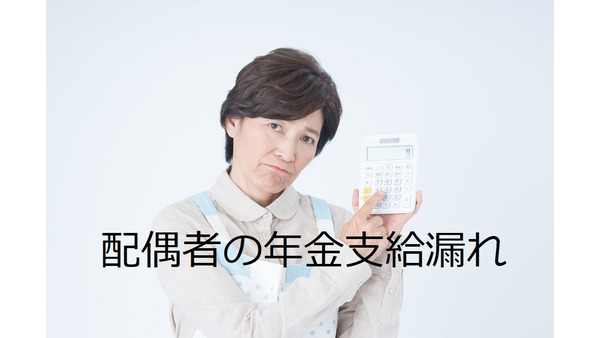
配偶者の加算年金、「振替加算」支給漏れ! 9月13日に厚生労働省より公表され、世間を騒がせているのが配偶者の年金支給漏れです。 「振替加算」の支給漏れのことですが、日本年金機構では11月上旬から、把握できる対象者(約10

少子高齢化が進む中で人口増加につなげようと、各自治体は子どもに対する医療費助成を充実させてきましたし、国も後押ししてきました。 幼児教育無償化の動きもあり、この先続いていくようにも見えますが、批判もあるため楽観視はできな

児童扶養手当の一部支給停止と適用除外申請 児童扶養手当をもらい始めてから5年以上経っている人はご存知だと思いますが、児童扶養手当をもらい始めてから5年、または支給要件に該当した月から7年経つと「一部支給停止」の対象です。

傷病手当金 健康保険には、病気やケガをした時の生活保障のために傷病手当金という制度があります。 メンタル等の不調により会社を休職し「傷病手当金」を受給している方が多数いらっしゃいます。 今回は、休職中に傷病手当金を受給し

教育無償化 教育無償化をめぐってはこども保険で国民負担する案が出ていますが、一方で教育国債を発行する案も依然としてあります。 こども保険 幼児教育(保育料)無償化 教育国債 高等教育(大学授業料)無償化 どのステージを無

「妻が会社を退職して、今までの収入(1月~退職月まで)が130万円を超えていますが、健康保険の被扶養者に入れますか?」 といった質問を受けます。 このようなケースな方々はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は
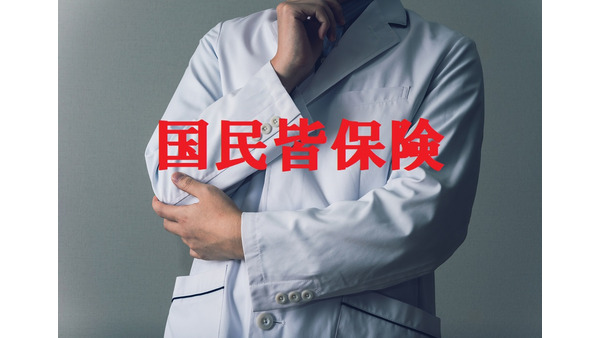
現状の皆保険制度に基づく医療は今後も持続可能なのか すべての国民が等しく医療を受けることができる国民皆保険制度について、医師の半数が維持できないと考えているそうです。 医師向け情報サイトであるメドピアと日本経済新聞が全国

健康保険の扶養に入れば、健康診断を受診できます(詳細は加入先による差異はありますが)。 しかし被扶養者の未受診が多く、来年度からは健康保険料に跳ね返りそうな動きも出ています。 健康保険被扶養者の受けられる保障 健康保険が

1. 高額療養費制度 誰もが健康でありたいとは思っていますが、長い人生の中では入院が必要になることもあり得ます。 急性の疾患ですぐに入院が必要な場合は別ですが病状によっては数週間から1か月程度の範囲で入院日を選べる場合も

新年度が始まる4月に「やっと保育園の入所が決まった」なんて方も多いかと思います。 4月に職場に復帰された方については、短時間勤務などで給与も減額されているため、「社会保険料の負担が重い」というような方も多いのではないでし

内閣府の有識者会議である「高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会」は、 年金の支給開始を繰下げ(遅くする)すると、年金額が増額する「繰下げ制度」の上限を、現在の70歳から75歳程度まで、延長する案 を発表しました。