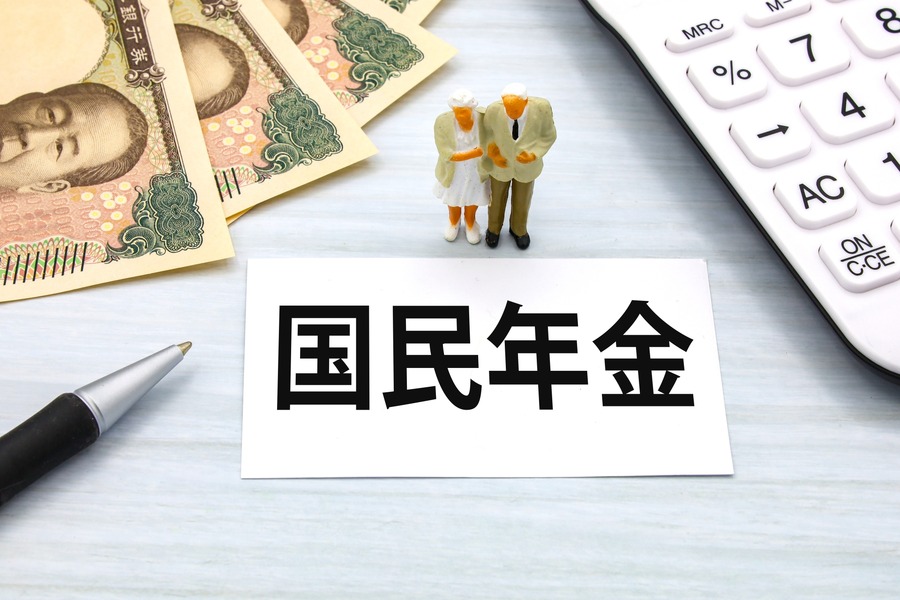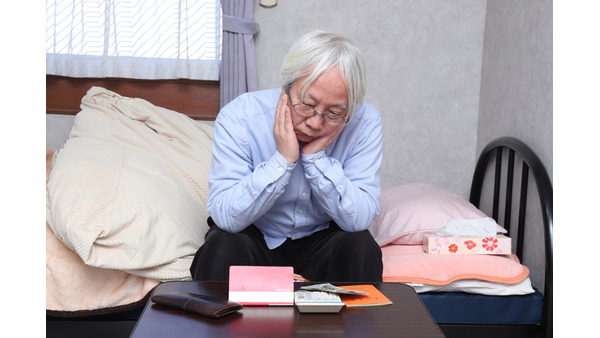日本の公的年金は、国民年金と厚生年金保険の2階建ての構造になっています。国民年金とは、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入する年金のことです。また、厚生年金保険とは、厚生年金保険の適用事業所に勤務する70歳未満の会社員や公務員などが加入する年金のことです。
国民年金と厚生年金保険の被保険者の違いによって、将来受給できる年金の種類や年金額に大きな違いが生まれます。厚生年金に加入している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の第2号被保険者でもあるため、国民年金だけに加入している方よりも将来受給できる年金額が多くなります。
今回は、国民年金の被保険者と国民年金と厚生年金の被保険者の将来受給できる可能性のある年金の違いについて解説していきます。
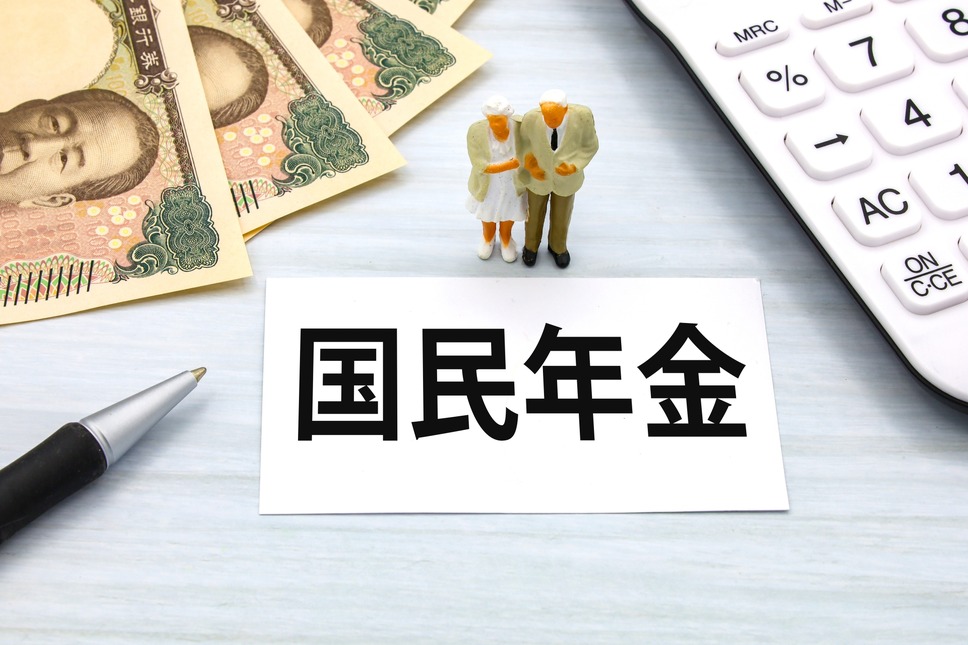
国民年金の給付
以下は国民年金の被保険者や被保険者だった方、その家族が受給要件を満たした場合に受給できる給付です。
老齢基礎年金
国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある方が、原則65歳から受給できる老齢のための給付です。
障害基礎年金
国民年金の被保険者期間中などの病気やケガが原因で、障害等級1級または2級の障害状態になった方が受給できる給付です。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者などが死亡した場合、死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」や「子」が受給できる給付です。
この場合の子は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満の障害等級1級または2級の状態にある子になります。
付加年金
国民年金の第1号被保険者が、国民年金保険料に月額400円の付加保険料を上乗せすることで、200円×付加保険料納付月数の付加年金が受給できます。
付加年金に加入できる国民年金の被保険者は、第1号被保険者だけです。
振替加算
加給年金の対象だった配偶者が65歳になった場合に、自分の老齢基礎年金に加算される給付です。
受給対象者は、昭和15年4月2日~昭和41年4月1日生まれの配偶者です。
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上ある夫が年金を受給する前に死亡した場合、生計を維持されていた死亡当時65歳未満の妻が受給できる給付です。
寡婦年金は、10年以上婚姻関係が継続していている妻に60歳から65歳まで受給できます。
死亡一時金
国民年金保険料を第1号被保険者として36か月以上納付していた方が、年金を受給する前に亡くなった場合に遺族が受給できる一時金です。
厚生年金保険の給付
以下は厚生年金保険の被保険者や被保険者だった方、その家族が受給要件を満たした場合に受給できる給付です。
老齢厚生年金
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上ある方が、原則65歳から受給できる老齢のための給付です。
障害厚生年金
厚生年金保険の被保険者期間中などの病気やケガで、障害等級1級~3級の障害状態になった方が受給できる給付です。
遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者などが亡くなった場合、生計を維持されていた一定の遺族が受給できる給付です。
一定の遺族とは、以下になります。
・妻(30歳未満の子のない妻は5年間の有期年金)
・18歳になった年度の3月31日までにある、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
・55歳以上である夫
・55歳以上である父母
・18歳になった年度の3月31日までにある、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある孫
・55歳以上である祖父母
加給年金
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方の65歳到達時点に、生計を維持されている65歳未満の配偶者や子がいる場合に加算される給付です。この場合の子は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満の障害等級1級または2級の状態にある子になります。
障害手当金
厚生年金保険の被保険者期間中などの病気やケガで、障害基礎年金、障害厚生年金の受給要件に満たない程度の障害状態になった場合に受給できる一時金です。
自分の将来受給できる年金の種類を知っておくことが大切
自分が将来どの種類の年金を受給できるかを知っておくことで、将来設計が立てやすくなります。
特に、国民年金だけしか加入していない方は、国民年金と厚生年金保険と両方に加入している方よりも将来受給できる年金が少なくなりますので注意が必要です。