※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事
離婚に伴う財産分与や養育費が贈与税の課税対象となるケースがあり、特に過剰分や税負担回避目的の場合には注意が必要です。養育費の使途も重要で、預貯金や不動産購入に充てた場合は課税されることがあります。

亡くなった方に、子どもがいない確認

相続人は誰になるのか

贈与税は、個人から財産を無償で贈与された際にかかる税金で、110万円未満は無税。受贈者が申告し、確定申告期間は翌年2月1日から3月15日。

余命宣告を受けた場合、残された家族のために保険の確認や金融機関の一覧表作成が必要。相続についての事前準備が大切で、家族に知らせておくことが重要。
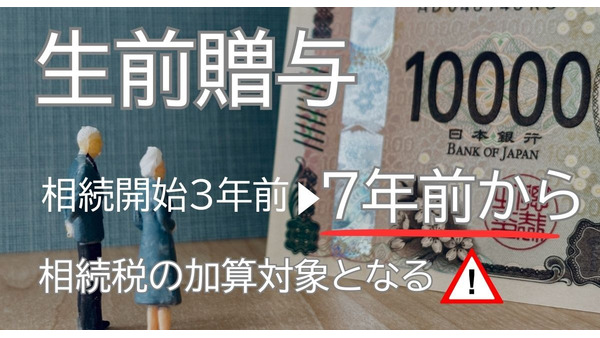
相続税は相続開始時に保有していた財産に課され、相続前に贈与を受けると加算対象となる。令和6年から加算対象期間が3年から7年に拡大され、注意が必要。基礎控除内なら影響を受けないが、法改正に注意が求められる。

相続税は相続財産に課され、不動産に替えることで評価額を下げることが可能です。特に「小規模宅地等の特例」により、最大80%減額できますが、リスクもあるため注意が必要です。
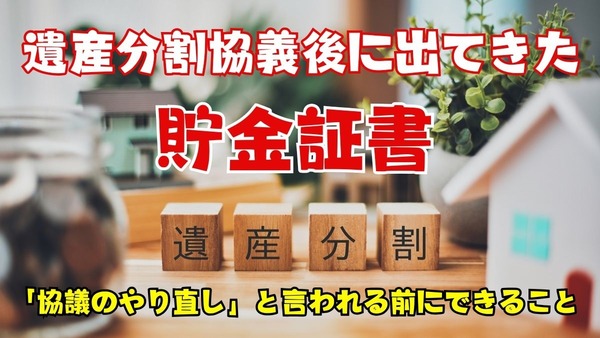
亡くなった夫の貯金証書が分割後に出てきました

養子縁組は相続対策として有効だが、複雑な関係を生む可能性がある。特に再婚者の連れ子や孫を養子にすると、他の相続人との衝突が生じることがある。

「不動産と預金」相続するならどっちら

離婚時に受け取る財産分与や慰謝料は基本的に贈与税の対象外。しかし、過大な分与や節税目的の場合は課税されることがある。贈与税の申告は金額が110万円を超えると必要。
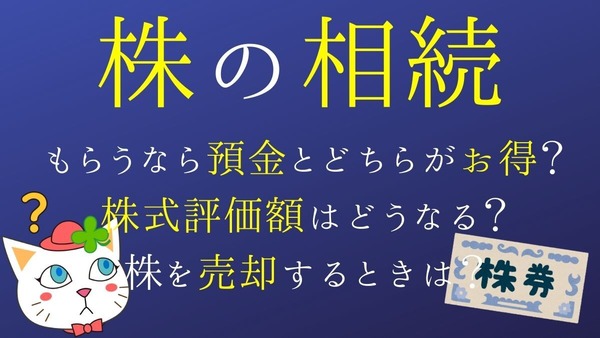
売却時のタイミングで大きく変わる株式の評価
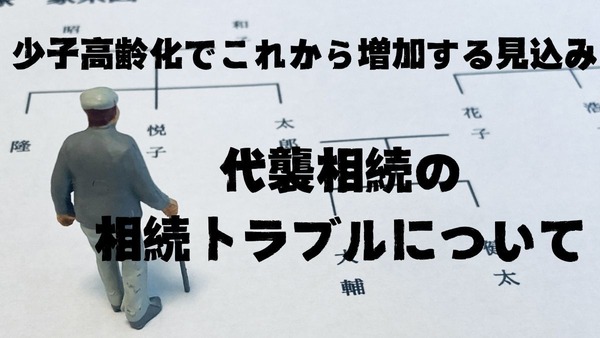
日本の平均寿命(令和5年)は女性が87.14歳、男性が81.09歳と長寿大国であり、寿命が延びたことで相続人が高齢者となるケースも増えています。

マイホームを購入した際、一定の要件を満たすことで所得税の住宅借入金等特別控除(通称:住宅ローン控除、住宅ローン減税)を適用することができます。

失敗しても勉強代では済まない住宅の購入
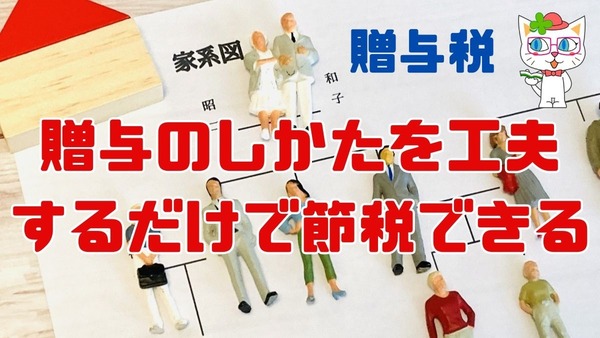
贈与税は、財産を無償でもらった際に課される税金であり、贈与税の申告手続きは財産を受け取った側(受贈者)が行うことになります。
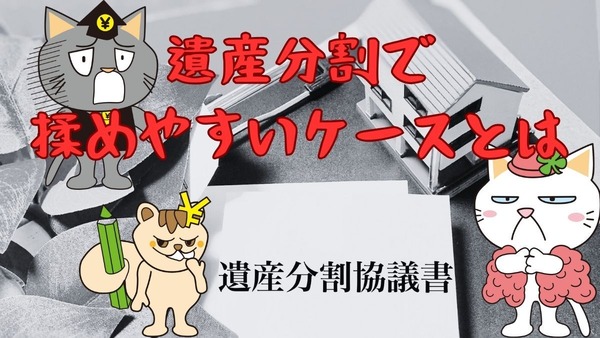
相続税は相続人が取得した財産の割合に応じて納めることになりますが、遺産をどのように引き継ぐかは相続人間で話し合って決めます。
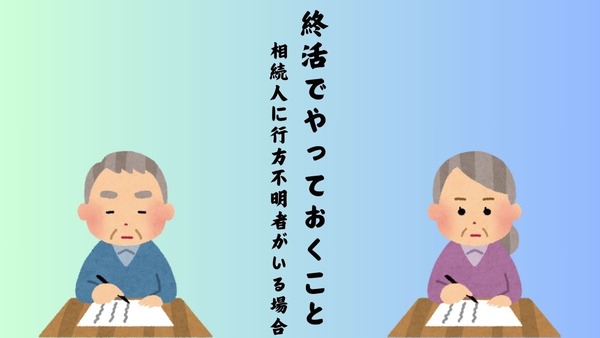
不動産がある場合は、まずは推定相続人の確認を

内閣府の令和5年高齢社会白書によれば、日本の65歳以上の人口は3,624万人で、高齢化
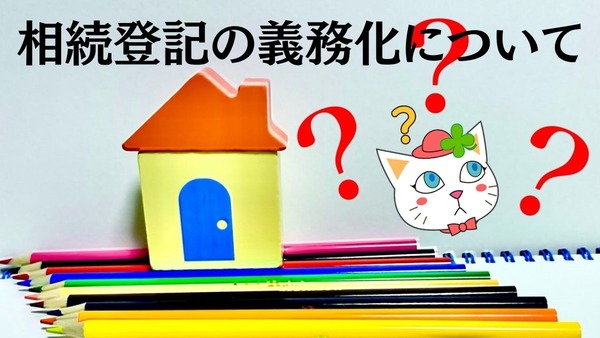
適用開始は、いつから

令和6年4月1日から、離婚後300日問題等を解消するために改正した民法が施行されます。

相続で不動産を取得した際の登記名義変更手続きは、今まで任意となっていましたが、令和6年4月1日からは義務化されます。
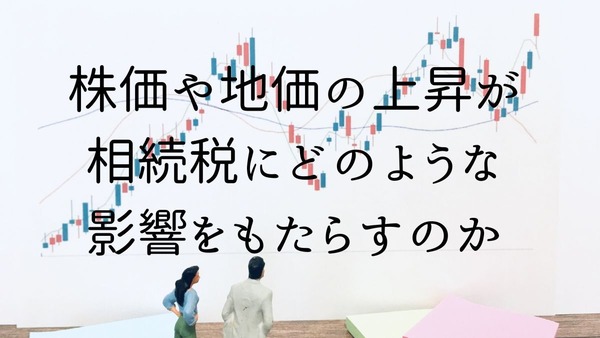
日経平均株価は史上最高値を更新しましたし、東京23区における新築マンションの平均価格は初めて平均1億円を超えました。

「老後の不安」と聞いて思い浮かべるのは、それぞれの立場や環境により内容は異なりますが、全体的に先行しているイメージでは「老後資金不足」に関しての不安感だと思います。
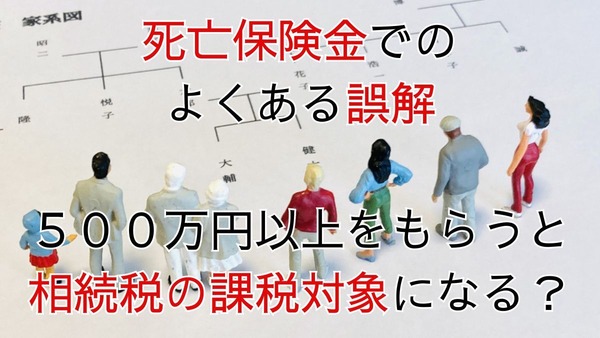
一人500万円までは非課税?
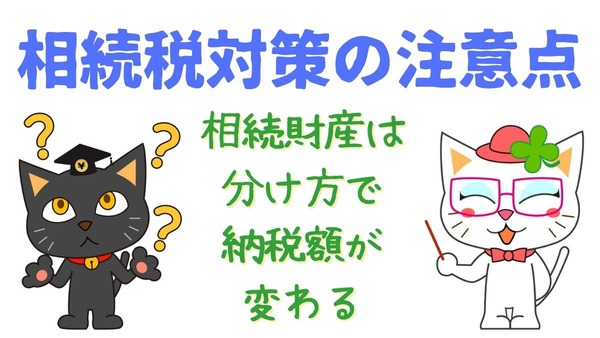
相続税・贈与税関係で 2024年1月から変更があります。相続税の生前贈与(生前加算年数が3年以内から7年以内に延長)や相続時精算課税制度の改正です。相続税対策を考える時の注意点について解説します。
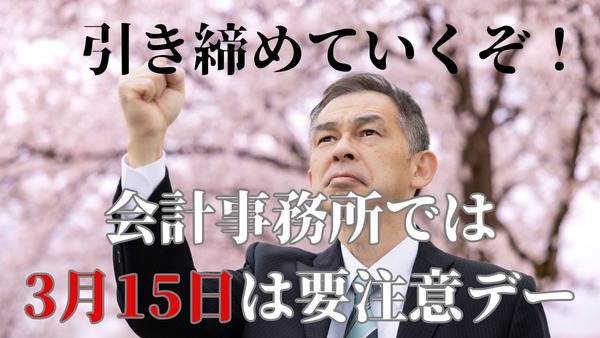
会計事務所では、「恐怖の3月15日」と呼ばれています。
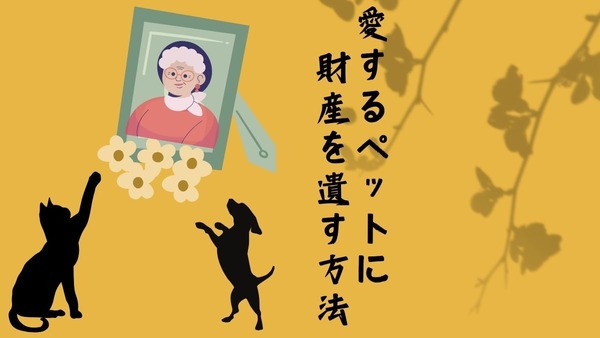
ペットは法律上は「モノ」という扱い
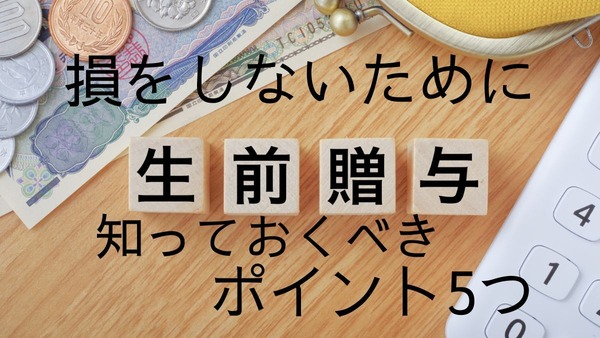
節税などを理由に、生前贈与をするか迷っている方もいるかもしれませんが、何となく贈与するのは少々もったいないです。

相続税の計算をする場合、最初に「相続財産の合計額が基礎控除額を超えるか」判断することになります。 基礎控除額は相続人の数によって変化し、養子も相続人に含まれることから、養子縁組をすることで相続税を節税する方法も存在します
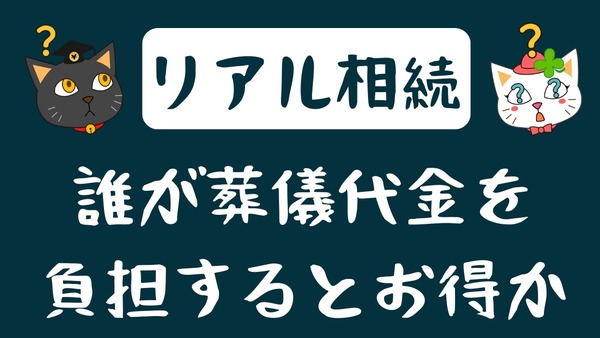
筆者は、かつて会計事務所に勤務して数多くの相続申税告のお手伝いをしてきました。 おかげで、リアル相続がどんなものか知ることができました。 親が亡くなられた場合、子が成人していれば、一般に長男が喪主を務められます。 喪主が

今年中(令和5年12月31日)に贈与をし、3年超生きれば、相続税の節税ができます。 もっとも、贈与先が相続人でない孫への贈与であれば、贈与後3年以内の相続が発生しても、相続税法上、3年以内の持ち戻しはありません。 私事で
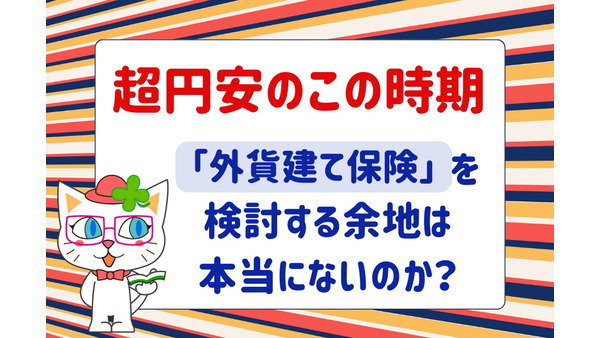
「外貨建て保険はやってはいけない」などの記事が散見されるようになってきました。 今回は一時払ドル建終身保険を念頭に、本当はどうなのか解説します。 外貨建て保険をやってはいけないと言われている主な理由 外貨建て保険をやって

親や祖父母など直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅用家屋を取得する資金の贈与を受ける場合、一定の条件を満たせば500万円(省エネ・耐震・バリアフリー住宅1,000万円)まで贈与税が非課税になり、しかもこの特例を使用し
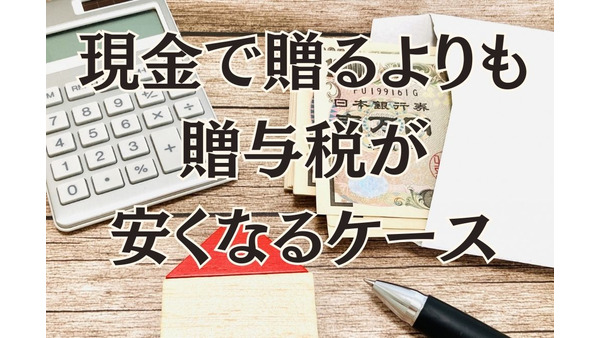
贈与税は財産をもらった人に対して課される税金ですが、贈与税の節税を第一に考える場合には、現金ではなく株式や不動産を贈与することも選択肢です。 今回は贈与財産の種類を変えるだけで贈与税を節税できる理由と、株式と不動産の贈与
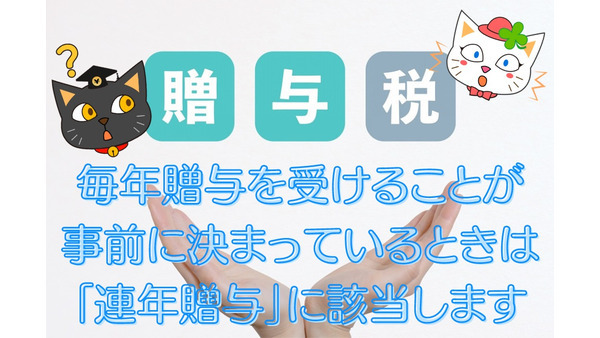
贈与税には毎年利用できる110万円の非課税控除額がありますので、年間の贈与金額が110万円以下であれば、基本的に贈与税を支払うことにはなりません。 しかし、毎年贈与を受けることが事前に決まっているときは「連年贈与」に該当