※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事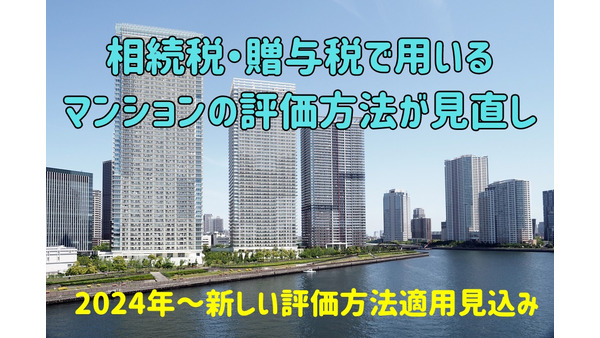
国税庁は、相続税・贈与税で用いるマンションの評価方法の見直しを検討しており、2024年(令和6年)1月1日以後の相続や贈与から、新しい評価方法が適用される見込みです。 新しいマンションの評価方法は、今まで効果的とされてい

佐藤守(仮名)さんは、10年前に父と続けて母を亡くしました。 先に亡くなった父の遺産は両親の住んでいた、居住用不動産と農地のみでした。 相続人である、守さん(弟)と幸子さん(姉)の二人とも結婚し、いずれも県外に居住してい
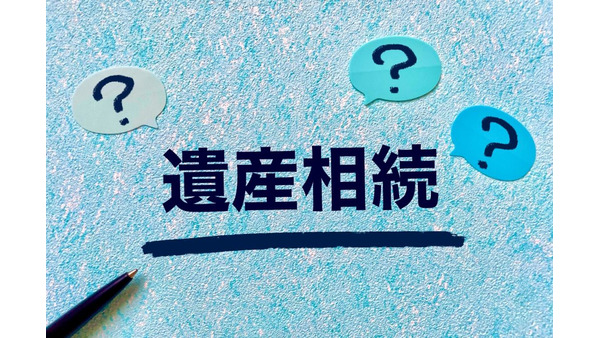
相続が発生した場合、相続人同士で話し合って遺産を分けることになります。 換価分割は不動産などの相続財産を売却し、売却代金を分配する方法で、換価分割は取得割合を均等にしたいときなどに有効な手段です。 一方で、相続財産を売却
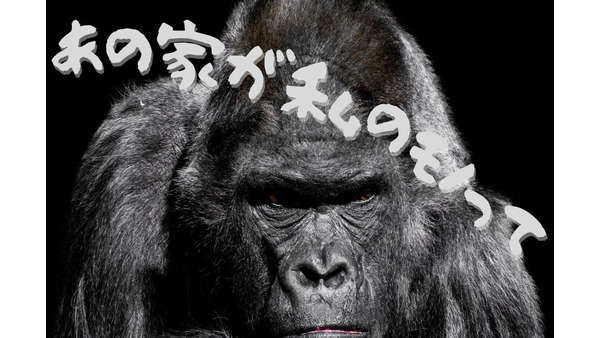
近年、空き家問題が起こっています。 現在住んでいる家がある場合、他の家を相続しても住めないので借り手がないと空き家として放置されます。 長期間空き家になると、放置された庭木が隣の家の迷惑にかけることや全く関係のない人が、
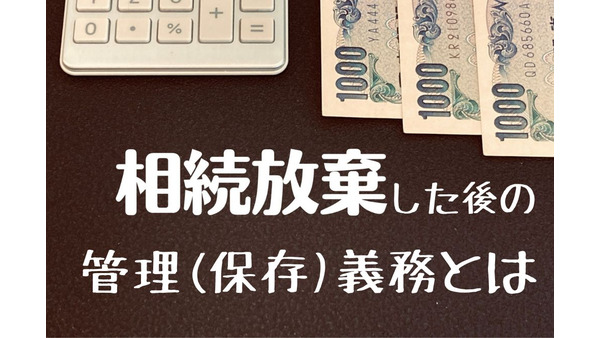
被相続人(故人)に資産よりも多くの負債等があった場合は「相続放棄」をすればすべて大丈夫だと思い込んでいる人がいます。 実際にはそう簡単でない場合もあります。 今回は相続放棄後の管理(保存)義務について解説します。 注)令
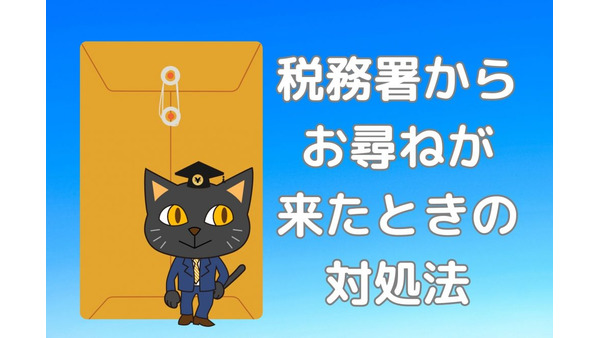
相続が発生してから数か月経過した後、税務署から「相続税についてのお尋ね」の文書が送られてくることがあります。 税務署から突然書類が届くと驚いてしまいますが、少しでも知識を有していれば不安を和らげることができます。 本記事

核家族化が進んでいる現在、親が住んでいた家を相続し、空き家にしてしまうことが起こりやすくなっていると言えます。 そのまま空き家を放置していると、瓦などが落ちて通行人や隣の家に被害が及んだ場合、所有者に損害賠償が請求されま

遺産は相続人間で話し合って取り分を決めることになりますが、相続財産を単純に振り分けるだけが遺産分割の方法ではありません。 本記事では、遺産分割の3つの方法とそれぞれの特徴、そして遺産分割時の注意点について解説します。 1

いままでの相続時精算課税制度を利用して贈与をした場合、生前の贈与分した財産は全て持ち戻して相続税を精算することになっていました。 そのため相続税の節税にはならないとされていました。 令和6年1月1日からの相続時精算課税制

相続が発生した際、誰が・どの財産を・いくら取得するかについて、相続人間で話し合うことになります。 相続財産が現金・預金だけであれば、法定相続分などでキレイに分けることが可能です。 一方で、実家については誰が相続するかで悩
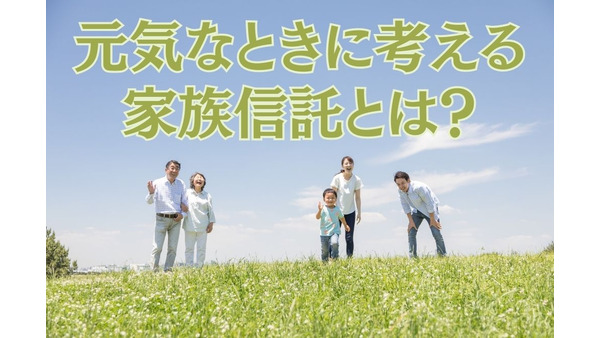
家族信託は、自分が認知症になったとき、介護が必要になったときに備え、元気なうちに財産の管理や処分を家族に託しておく制度です。 本記事では、家族信託の仕組み、家族信託をすることで得られるメリット、家族信託の注意点ついて、は
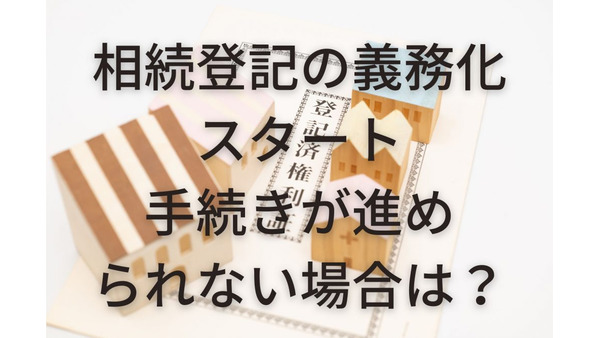
令和6年(2024年)4月1日から「相続登記の義務化」がスタートします。 この制度で気になるのは、 10万円以下の過料が科せられる可能性があることと、 この制度がスタートする前に発生した相続についても、義務化の対象となる

相続税の納税額を抑えることができれば、その分だけ財産を多く引き継ぐことができます。 しかし、相続税対策は状況に応じて適度に実施するのが望ましく、過度に対策を講じてしまうと、相続税の支払いが多くなってしまう可能性すらありま
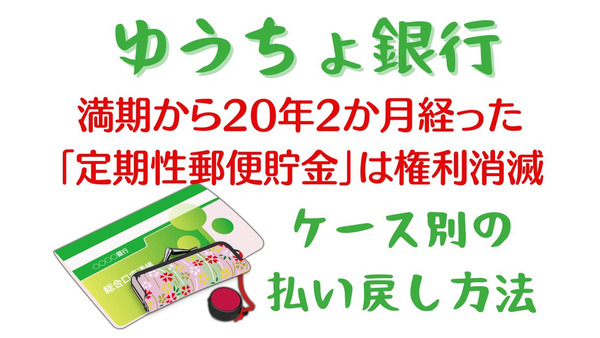
筆者の父は転勤が多く、祖母に「どこでも使える郵貯にしておきな」と言われたそうです。 確かに、全国津々浦々にゆうちょ銀行TMはあります。 そんな郵便貯金ですが、放置しておくと消滅するという話がありましたので、紹介しましょう
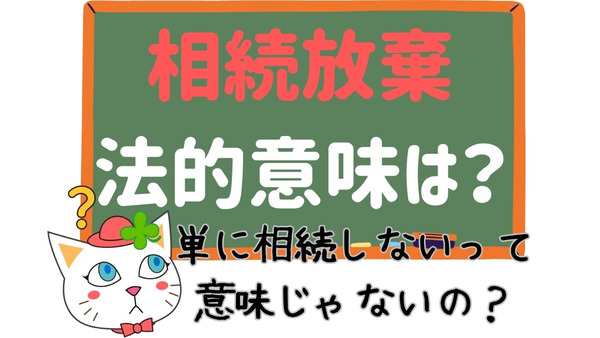
相続が発生した場合、遺産の分け方について話し合いますが、相続人の中には遺産を相続しない人もいるかもしれません。 相続財産を取得しないことを「相続放棄」と表現することもありますが、一般的に使われる「相続放棄」の意味と、法的

主人公(作者と思われる)が、高額納税者として新聞に掲載されてしまったことが、事件の発端です。 今は、廃止されていますが、昔(2005年まで)は、あったこの制度おかげで、主人公(Mさんとします)が名実ともに売れっ子作家にな
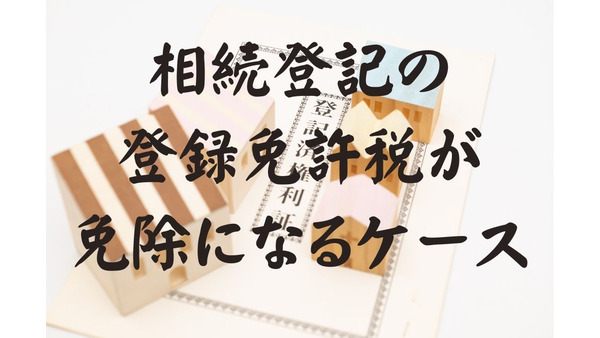
相続により不動産を取得し、登記名義を変更する場合、登録免許税を支払わなければなりません。 しかし、一定の要件を満たす相続登記については、登録免許税の支払いが免除されるケースがありますので、今回は相続登記の登録免許税の免税

個人が申告する税金には所得税や贈与税などありますが、相続税はそれらの税金とは手続き方法が少し違います。 実際に申告手続きをすることになってから慌てないためにも、相続税の申告特有のポイントを3つご紹介します。 ポイント1:

国は空き家対策の一つとして、空き家対策特別措置法を改正し、管理不全空き家に該当した不動産に対する固定資産税を6倍にする可能性が出てきました。 今回は固定資産税のしくみと、固定資産税が6倍になるケース、そして固定資産税を抑
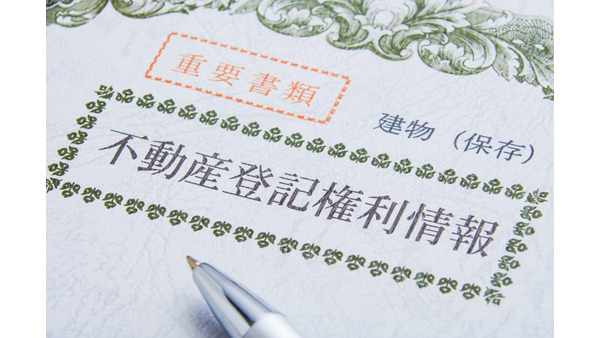
令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されます。 義務化された以後は、一定期間内に登記手続きを行わなければならず、違反した場合の罰則規定もありますのでご注意ください。 不動産の相続登記が義務化される経緯 相続が発

相続の仕事を長年していて分かったことがあります。 税金以外で相続の相談にいらっしゃるのは、子供のいない夫婦からの相談が意外に多かったことです。 そしてその相談は、配偶者のどちらかが亡くなられて、問題に気づいてからの駆け込
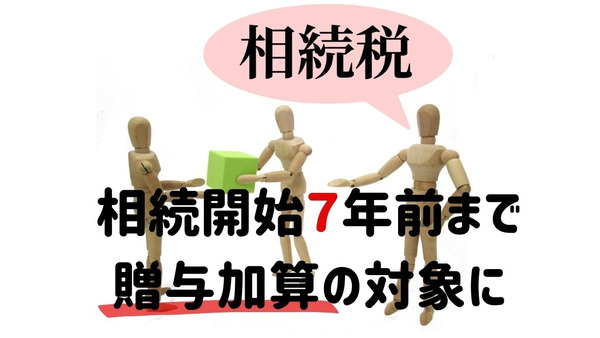
令和5年度税制改正により、相続税の贈与加算の対象期間が3年から7年に延長することが決定しました。 今回は税制改正のポイントと、贈与加算の対象期間が延びたことによる相続税への影響について解説します。 相続税の贈与加算の概要

あまり大きな話題になってはいませんが、相続税の申告書の提出件数は年々増加しています。 申告が必要な方が手続きをしていなかった場合、税務署から連絡・指摘される可能性があります。 今回は相続税の年間の申告件数と、申告件数が増

相続が発生した場合、相続人は原則として亡くなった人の財産をすべて引き継がなければなりません。 しかし令和5年4月27日からスタートする「相続土地国庫帰属制度」を活用すれば、相続した土地の権利を放棄することが可能となります

お子さんがいない家庭は、相続でさまざまな問題がでてきます。 今回は、保険の受取人の確認と検討について考えてみたいと思います。 子供がいない夫婦で、配偶者が親より先に亡くなっている場合 例えば、夫が、夫の親より先に亡くなっ

相続人が遺産を取得できる割合(相続権)は民法で規定されていますが、相続人全員が合意していれば、遺産をどのように分割しても問題ありません。 一方、相続税は遺産を「誰が・いくら」取得したかによって、納税額が変動することがあり

贈与税には「住宅取得等資金の非課税制度」など、多くの節税特例が用意されています。 特例を適用するためには申告手続きが必要ですが、贈与税の特例制度は申告期限を過ぎてから適用することはできませんので注意してください。 特例制
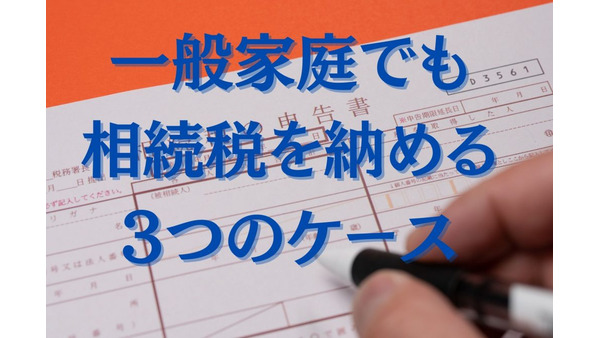
相続税は富裕層が支払うイメージの強い税金ですが、亡くなった人が会社員・公務員だった場合など、一般家庭においても相続税を支払う可能性はあります。 そこで今回は、一般家庭で相続税が発生しやすい3つのケースをご紹介します。 1

「子どもの通帳を作ったのですが、転勤族なので遠くに引っ越した場合、解約するときとかに、大変にならないか不安です」 これは銀行で私の窓口にいらっしゃったお客様から聞いた言葉です。 子どもの通帳を作ったあとでいろいろ心配にな
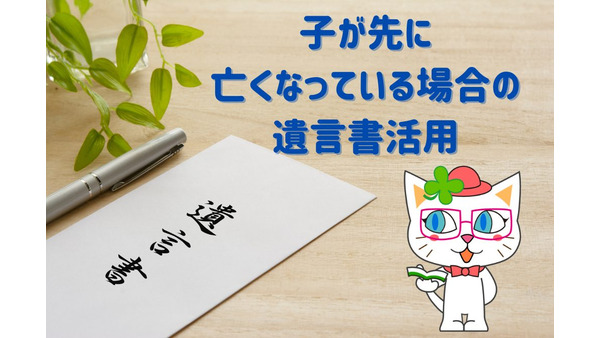
会計事務所の相続実務でまれに「故人の子が先に亡くなっている」というケースがありました。 子が先に亡くなっていますと代襲相続人としてその子の子(孫)が相続人になります。 そこで、故人の子が複数いると、代襲相続人である、子の

贈与税の申告手続きをした経験がある人は少ないと思います。 贈与税は所得税と同様、申告・納付期限が定められており、申告を忘れてしまうとペナルティを課される可能性がありますのでご注意ください。 贈与税の対象者は「財産をもらっ
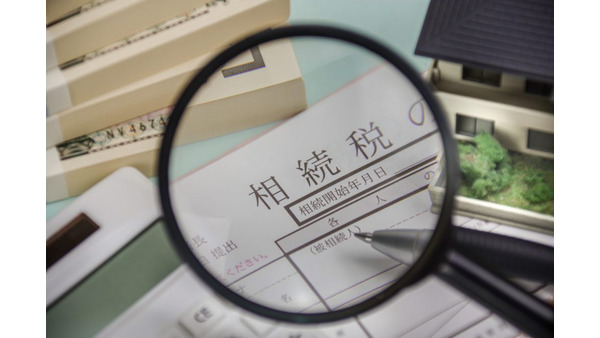
令和5年度の「税制改正大綱」では、NISAと相続税の贈与加算期間の拡大が注目されていますが、相続時精算課税制度の制度内容も大きな改正事項です。 使い方次第で以前よりも高い節税効果が期待できますので、今回は税制改正で「相続
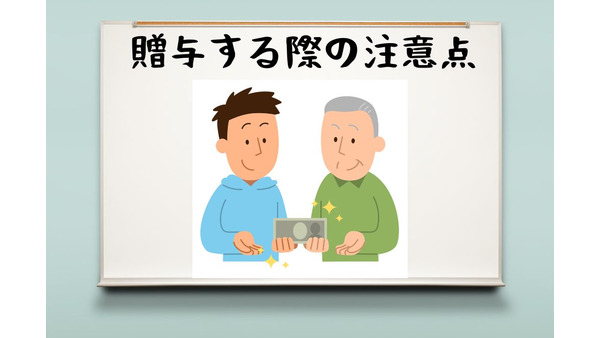
財産贈与は贈与税の対象となるので、税務署にバレないように贈与した方がいいと思っていませんか。 節税の観点で考えた場合、税務署に見つからないように贈与した方が後々問題になるケースがあるので注意しましょう。 今回は税務署に贈

令和5年度の税制改正大綱が発表されましたが、資産税関係では相続税の贈与加算の期間が3年から7年に拡大することが注目されています。 今回は贈与加算制度の概要と、加算対象期間の拡大がどのくらい影響するのかについて解説します。
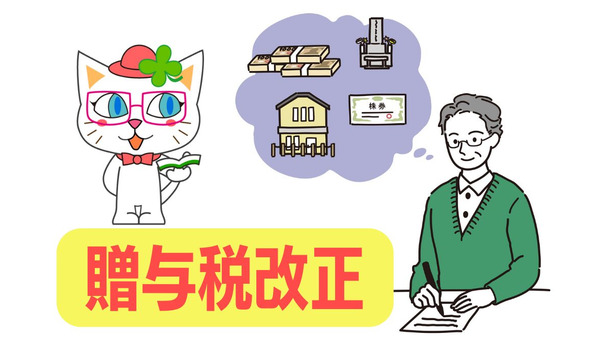
遺産が、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)以上あると、相続税申告が必要になります。 この相続税の対象になる遺産には、相続開始前3年以内の暦年贈与も含まれ、原則課税対象となります。 ただし相続人以外への贈与
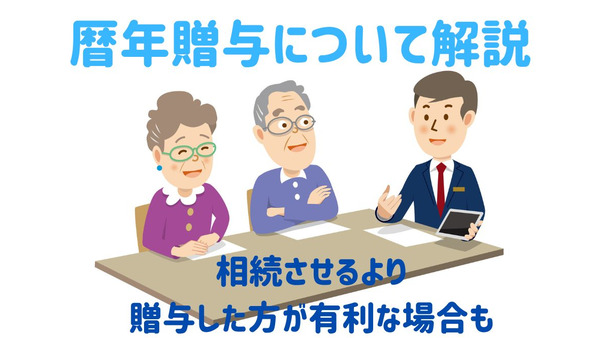
記事掲載時点には令和5年度税制改正大綱が公表されました。 執筆時点で既に増税色が濃そうな内容が漂っていますが、今回は改正が囁かれている暦年贈与について解説します。 暦年贈与とは? 暦年贈与とは簡単に言えば、毎年少しづつ贈