※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事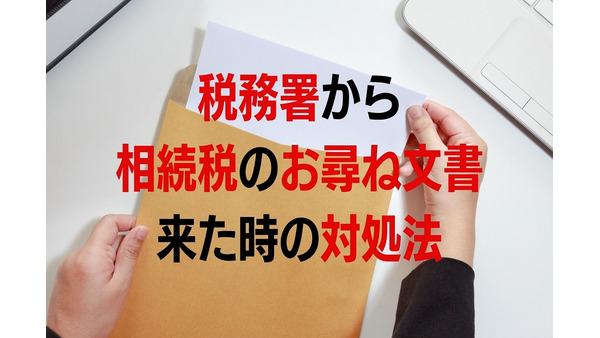
相続税は、富裕層だけが支払う税金だと思っていませんか。 亡くなった人が相続税の基礎控除額を超える財産を保有していた場合、サラリーマン家庭でも相続税の申告をしなければなりません。 相続税の基礎控除額の計算式は以下です。 3
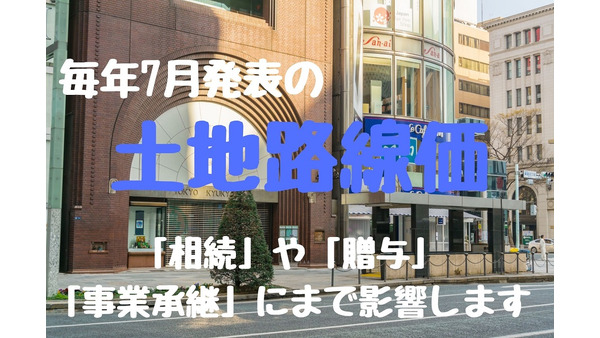
地価の発表は1年の間に複数回行われますが、土地の値段は一物四価と言われ、目的に応じて別々の団体が地価を発表します。 国税庁が毎年7月に発表するのが路線価で、相続税計算上の評価額算定が目的です。 土地の相続だけに影響するの

今回は相続財産としての不動産ならびに投資用不動産のお話です。 自宅と投資用不動産両方を持っている方はそのどちらもが対象ということです。 相続税の対象となるものは不動産だけではなく、現金や預貯金、株式、有価証券や動産など多

認知症が心配になってくる高齢の親がいる世代では、万一の時の親のため、自分たちのための成年後見人制度に興味がある人が多いと思います。 そんな後見人(任意・法定ともに)になれるのは親族か専門家だけという訳ではありません。 実

相続が発生した場合には相続税がかかる場合があることはほとんどの方がご存じのことでしょう。 しかし、「家族信託を利用する場合にどのような税金がかかるのか」をご存じの方は少ないのではないでしょうか。 たとえば、 ・ 家族信託
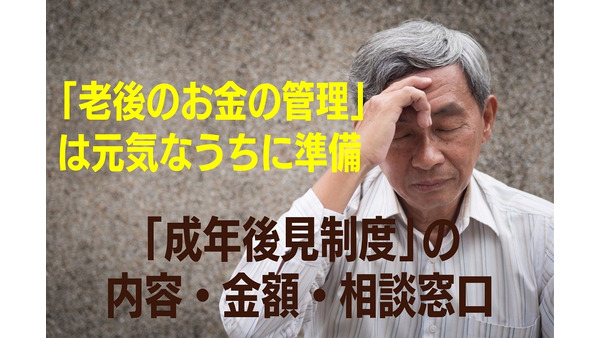
高齢化社会から超高齢化社会へと加速してきた日本社会ですが、誰しもが避けることができないのが老後のお金問題です。 皆さまはどのような準備をしていますか。 今回は、社会問題にもなっている認知症とお金についてのお話をしたいと思

高齢者の財産の管理や相続に役立つ制度として「家族信託」が近年、注目を集めています。 遺言書や成年後見制度では解決できない問題にも対処することが可能で、大きなメリットがある制度です。 ただし、家族信託には手続費用が非常に高
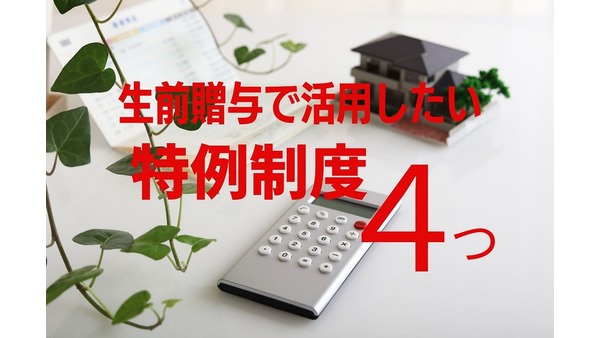
人が亡くなった時に相続や遺言により遺産を引き継いだ場合、相続税がかかります。 相続税は基礎控除額が大きいため、相続した財産の金額が大きい場合にしかかかりません。 しかし、相続した財産が大きければ大きいほど、相続税も大きな
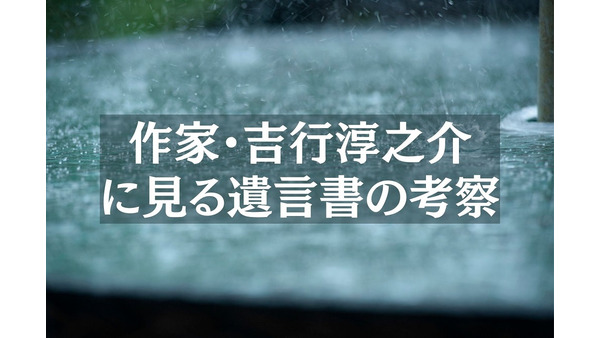
今回は、作家・吉行淳之介の相続についてお話ししたいと思います。 遺言書を書かねばならなかった作家・吉行淳之介 遺言書は「書かなくてもよい人」と、「書く必要のある人」がいます。 作家・吉行淳之介は書く必要のある方でした。
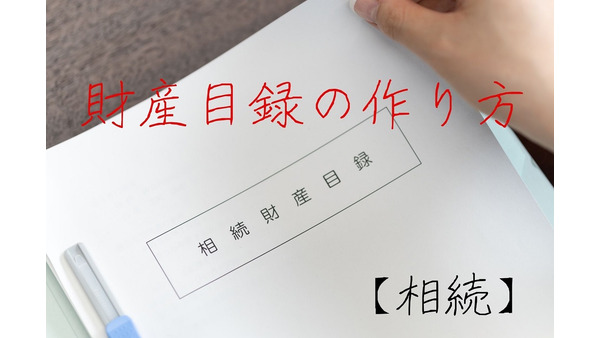
相続・遺言に関する民法の大改正や、新たに始まった自筆証書遺言書保管制度などにより、遺言書の作成や保管のハードルが下がりました。 遺言書の作成自体抵抗のない方も増えています。 ただし、せっかく遺言をきちんとしても、肝心の財
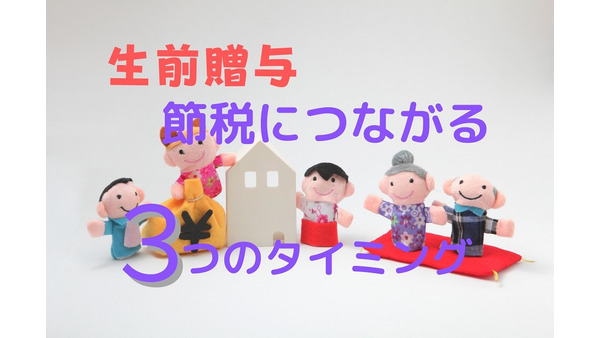
贈与税には110万円の基礎控除額があるため、贈与金額を110万円以内に抑えると贈与税を支払わずに済みます。 また110万円控除や特例制度の特徴を把握していれば、より効果的に贈与することも可能です。 そこで今回は、生前贈与

これまで何度か任意後見制度について記事にしてきました。 【関連記事】:「任意後見」は自分の将来を後見人と話し合える制度 「法定後見」との違いも説明 【関連記事】:自分の生活を守る老後対策 違いをしっておきたい「民事信託」
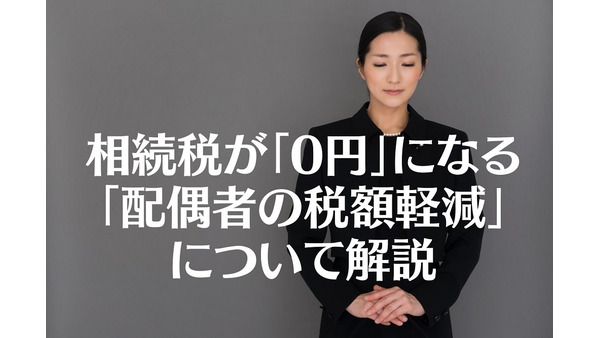
相続税は、亡くなった人が相続財産を一定以上保有していた場合に課される税金です。 しかし、配偶者の相続した財産が1億6千万円までの場合、配偶者が支払う相続税をゼロにできる「配偶者の税額軽減」の制度を適用できます。 相続税の
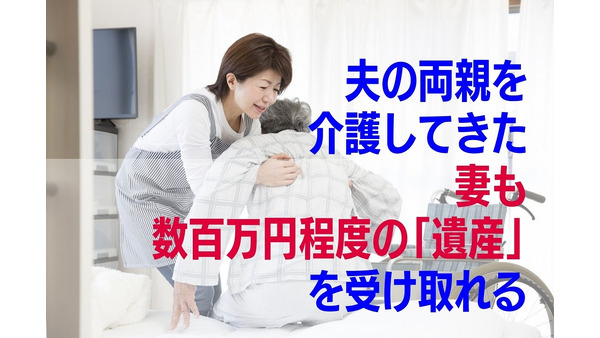
長年にわたって夫の両親の介護をしてきたが、夫の両親の相続では遺産を一銭ももらえなかった。 従来はこのようなケースが多く、相続における親族間の紛争の一因となっていました。 今回の相続法の改正により、このようなケースでも「特
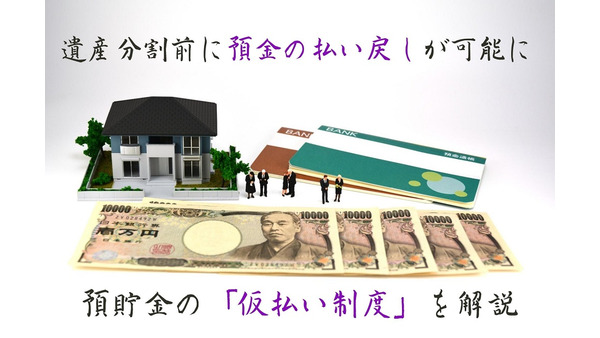
家族が亡くなった場合、葬儀費用や入院費用の支払いなどで多額の現金が必要になるケースがあります。 これまでは、遺産分割がまとまるまでは亡くなった方の預貯金は払い戻しができなかったため、当面の支払いができずに困ってしまうケー
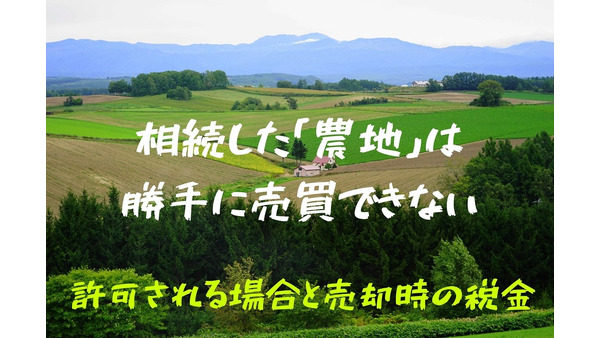
遠く離れて住む親が亡くなり、実家の土地を相続するというのはよく聞く話です。 しかし相続した土地が農地だった場合、新たに所有者となった者が勝手に売買はできません。 勝手に売買できない「農地法」とは 農地は「農地法」という法
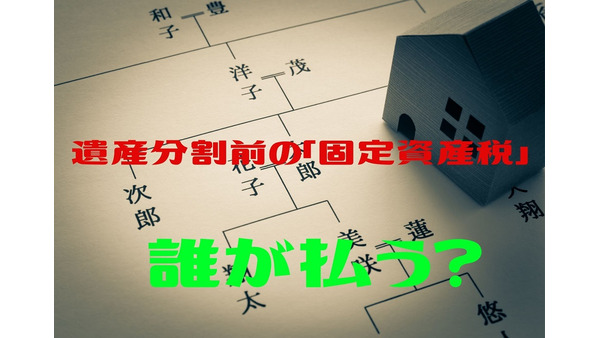
遺産の中に不動産がある場合、固定資産税の納期限になれば遺産分割前でも納税しなければなりません。 このように遺産分割前の不動産の固定資産税を支払わなければならないとき、誰が支払うべきなのかについて疑問をお持ちの方も多いと思
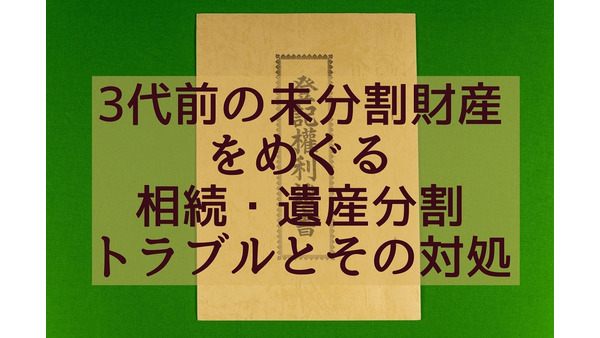
相続・遺産分割関係の記事を書いたりしているので率直に言ってお恥ずかしい話ですが、皆さまの参考になればと思い、昨年と今年にわが家を襲った相続・遺産分割トラブル事例を紹介したいと思います。 約60年前の未分割財産(曽祖父名義

遺産分割の話で、よくあるケース 遺産分割の前提は「話し合い」です。 難しいのは全員の合意が必要になるからです。 まとまるには、全員の合意が必要です。 事例は、いきなり相続人全員を集めてお話を開始した時のケースです。 【被
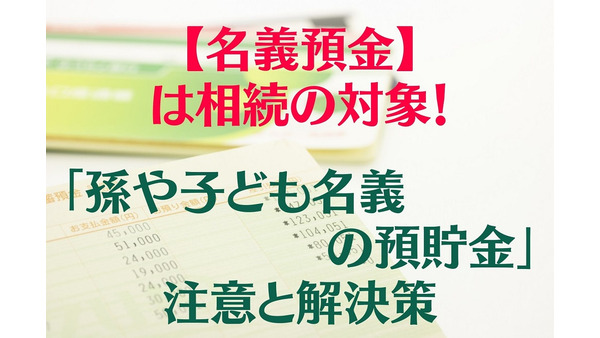
夫が妻や子どもなどの名前で本人たちには内緒で預貯金をしている場合、それは「名義預金」に該当する可能性があります。 「名義預金」は普段はさほど問題にはなりませんが、口座の真の管理者が亡くなって相続へと至った場合には、亡くな

マネーの達人が本を出しました! 今皆さんに知っておいてほしい情報を1冊の本にまとめました。 その一部をここで紹介します! 転載一覧はこちら 相続税をできるだけ安くすませるために、上手な生前贈与のしかたを一挙紹介します。
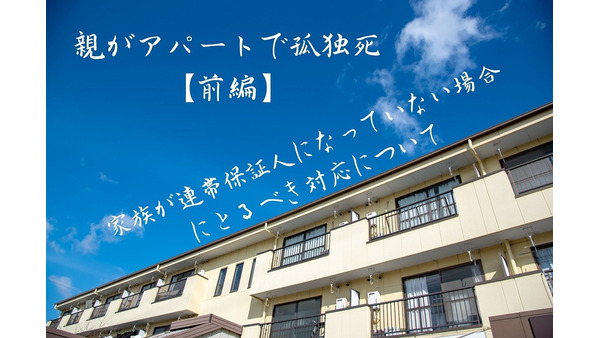
核家族化が進んだ現代では、高齢の親がアパートで独り暮らしをしているという方も多いことでしょう。 考えたくはないことですが、親が賃貸アパートで孤独死してしまった場合には、家族が家主から原状回復費用などを請求されることがあり

相続財産が債務超過になっていても、特定の財産だけ遺贈を受けておいて、その後に相続放棄できるならプラスの財産だけをもらうことができそうですよね。 しかし、本当にそのような都合のよいことができるのでしょうか。 この記事では、

キャッシュレス化が普及したいま、クレジットカードの利用によってポイントやマイルを貯めている人は多いと思います。 また、ポイントサイトを活用して貯めたポイントを貯金や節約などに役立てる「ポイ活」をしている人も少なくないこと

「この土地と建物だけは確実に長男に譲りたい」 このように、特定の財産だけを特定の相続人にのこす場合には「特定財産承継遺言」を活用できます。 今回は「特定財産承継遺言」とは具体的にどのような遺言なのか、「特定財産承継遺言」

昨今は結婚のかたちも多様化してきており、事実婚を選ぶ夫婦も増えています。 しかし、現在の法制度は法律婚の夫婦であることを前提とした制度が多いため、事実婚には一定のデメリットもあります。 とはいえ、このデメリットもうまくカ
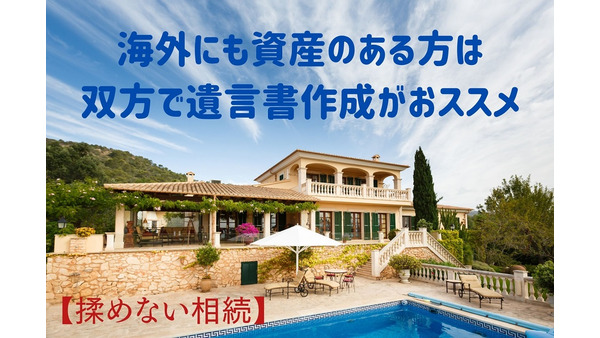
海外と日本の双方で資産を持っている場合、どうやって遺言を書いておけばいいのか悩まれる方も多いのではないでしょうか。 実は、適切な遺言を作成していなかったばかりに、相続人が相続手続きで苦労してしまうケースはよくあります。
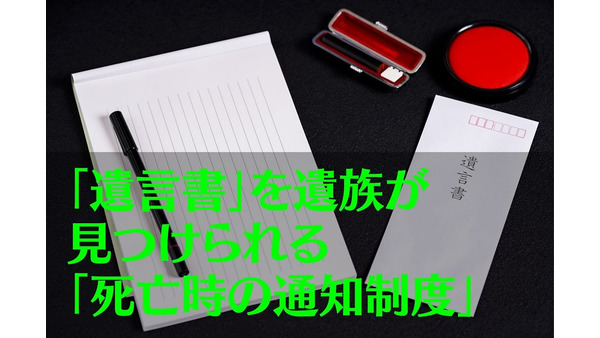
法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が2020年7月10日から始まりました。 既にこの制度を利用した人の話を見聞きするに、法務局の対応も比較的スムーズで概ね好評のようです。 しかし、この制度には現時点で1つの欠点が判

実家を取り壊し、2世帯住宅を建てる場合、どのようなメリットが考えられるでしょうか。 親世帯にとっては孫たちとすぐに遊べて、将来年齢を重ねて何かあったときでも子世帯を頼りにできます。 また、子世帯にとっては土地代の負担がな

お年玉や住宅購入の資金援助など、お金をもらった場合に贈与税の課税対象となりますが、財産をもらう以外でも、贈与税の対象となってしまうケースも存在します。 今回は財産をもらう以外で、贈与税が課されるケースについてご説明します

「相続対策として相続時精算課税制度を使えば、なんと2,500万円まで非課税で贈与できますよ」 こんな宣伝文句を聞いたことはありませんか。 昔は一部のお金持ちだけの悩みごとであった相続税も、今や一般的なサラリーマン世帯でも
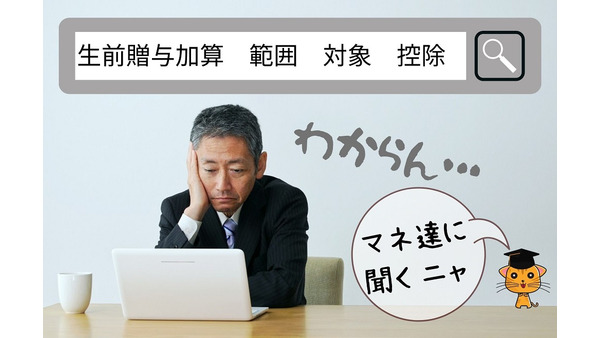
Q:今回、父が亡くなって相続が発生しましたが、生前、父は子供たちや孫に金銭を贈与して おりました。 相続税の申告をする際には、生前に贈与した額を加算して相続税の計算をすると聞きましたが、これはどういうことでしょうか? 生
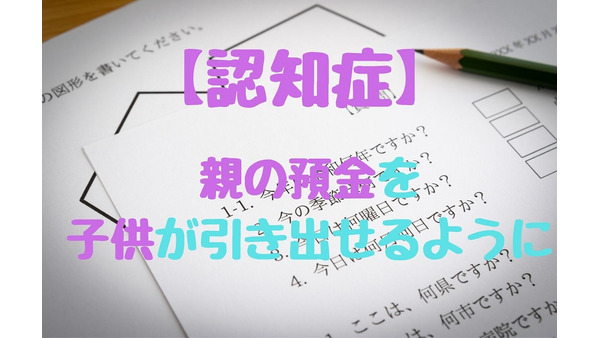
今年(2020年)7月15日に金融庁金融審議会が示した報告書案において、 「要件を充たせば認知症などで判断力が低下した人の預金を家族が引き出せるような対応をすることが望ましい」 という方針が示されました。 既に今年3月に
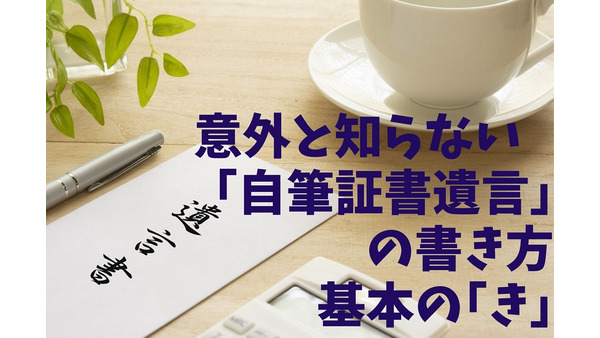
財産目録がコピーでもOKになり、法務局での保管制度が始まるなど、7月からの民法改正で自筆証書遺言の簡便性と信頼性が上がったことで、「遺言作成を自筆で」と考える方が増えたのではないでしょうか。 しかし、自筆証書遺言は公正証
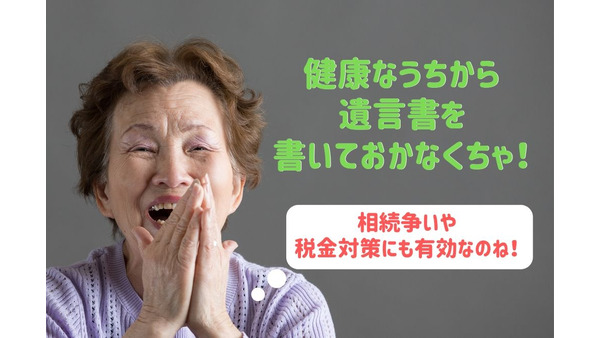
近年「終活」という言葉をよく耳にするようになりました。 平均寿命や健康寿命が年々伸びていることもあり、健康なうちから自分の死後のことを考える方が増えてきているようです。 終活をするうえ避けて通れないのが、自分の財産を誰に
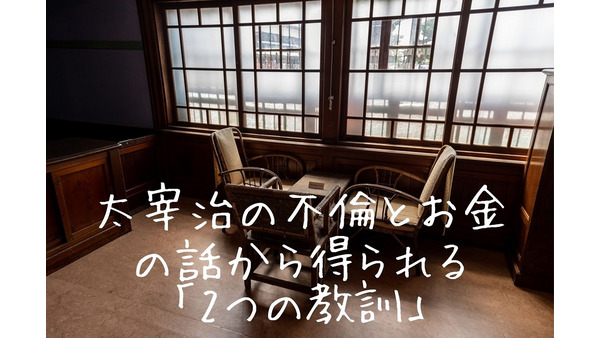
今回は、太宰治に関わる2冊の本をもとに太宰のお金と遺産相続にまつわるお話しをしたいと思います。 なお、文中において敬称は省略させていただきましたのでご了承ください。 太宰治の実生活でお金を握っていたのは 太宰の実生活につ