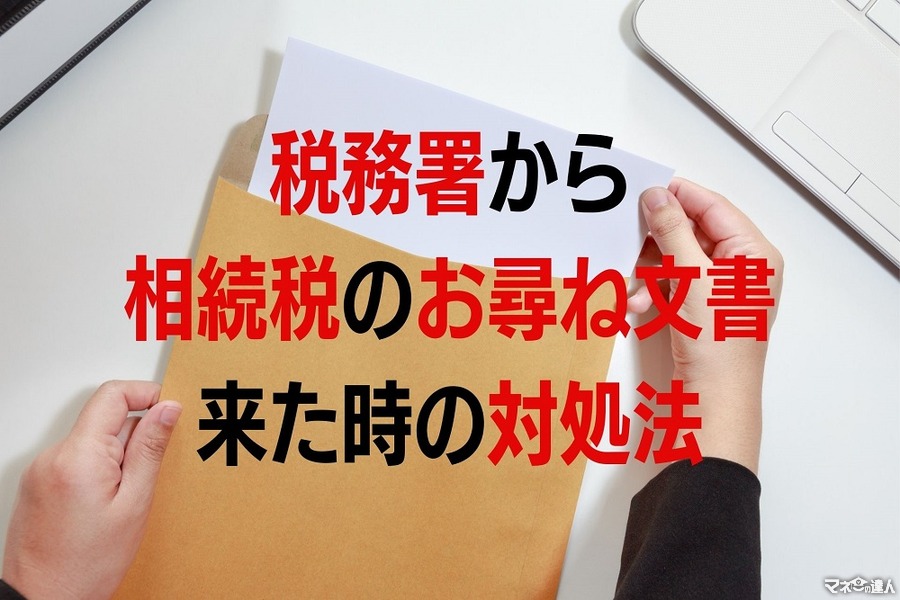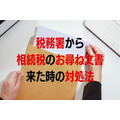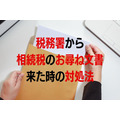相続税は、富裕層だけが支払う税金だと思っていませんか。
亡くなった人が相続税の基礎控除額を超える財産を保有していた場合、サラリーマン家庭でも相続税の申告をしなければなりません。
相続税の基礎控除額の計算式は以下です。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数 = 基礎控除額
また税務署は、相続税の申告期限前に「相続税についてのお尋ね文書」を送付することもあります。
急に書類が届いても驚かないために、お尋ね文書が来た際の対処法を解説します。
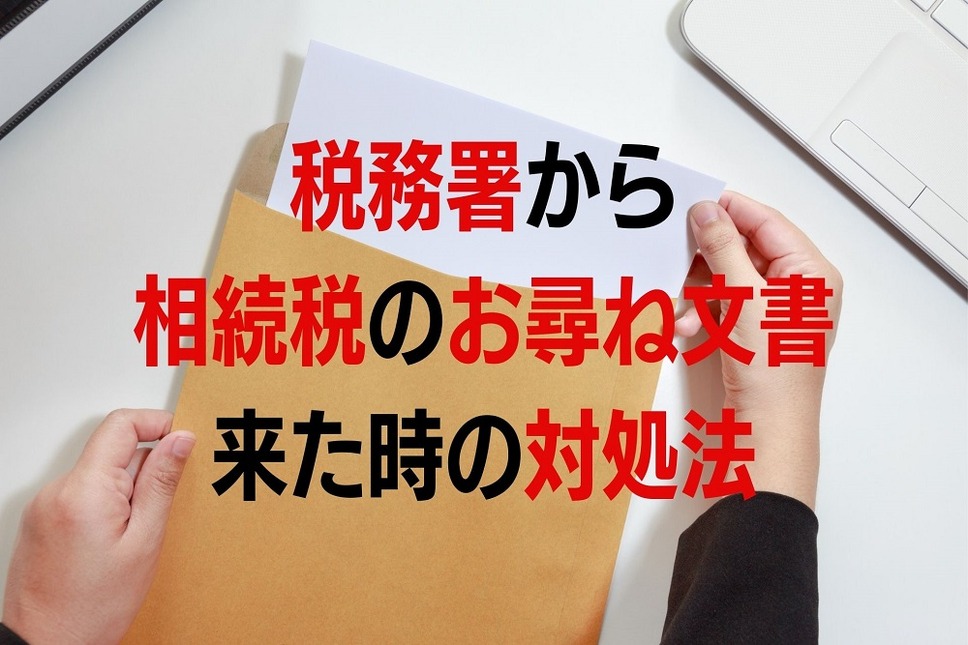
目次
「相続税のお尋ね文書」とは
相続税の申告期限前に送付されるお尋ね文書は、相続税の申告書または「申告要否検討表」の提出を求めるものです。
申告要否検討表とは、相続税の申告が必要かどうかを簡易的に判定する書類です。
基礎控除額を超える相続財産を保有していれば、申告書の提出が必要です。
相続財産が相続税の基礎控除額以内であれば、相続税の申告書を提出する必要はありません。
ただ税務署は相続財産を把握するために、申告不要の場合でも申告要否検討表の提出を求めてきます。
相続税のお尋ね文書に提出義務はない
お尋ね文書が送付されても、相続税の申告が不要なら申告書を提出する必要はなく、申告要否検討表についても提出は任意です。
ただ申告要否検討表を提出しない場合、回答を促してくることもあります。
申告要否検討表の提出催促をされたくない方は、お尋ね文書を送付した担当者に対し電話で
と伝えてください。
なお連絡を無視し続けていると、税務調査が行われる恐れもありますのでご注意ください。
相続税の申告義務がある人は申告書を提出すること
申告要否検討表は、相続税の申告書ではなく相続税に関する書類の1つです。
そのため相続税が発生する方は、申告要否検討表ではなく、必ず相続税の申告書を提出してください。
また申告要否検討表は簡易的に相続税の申告の有無を判定する書類ですので、実際の相続財産に基づき計算すると、基礎控除額を超えるケースもあります。
期限を過ぎてから相続税の申告書を提出すると、本税のほかに加算税・延滞税を支払うことになるため、相続財産をある程度保有している方は、具体的に相続税の計算を行ってください。

申告する予定ならお尋ね書を提出する必要はなし
お尋ね文書が届いても、相続税の申告をする予定の方は申告要否検討表を提出する必要はありません。
また相続税の申告書を提出する際に、申告要否検討表を添付する必要もないです。
相続税の申告期限および納付期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
申告が必要な方は早めに準備をはじめてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)