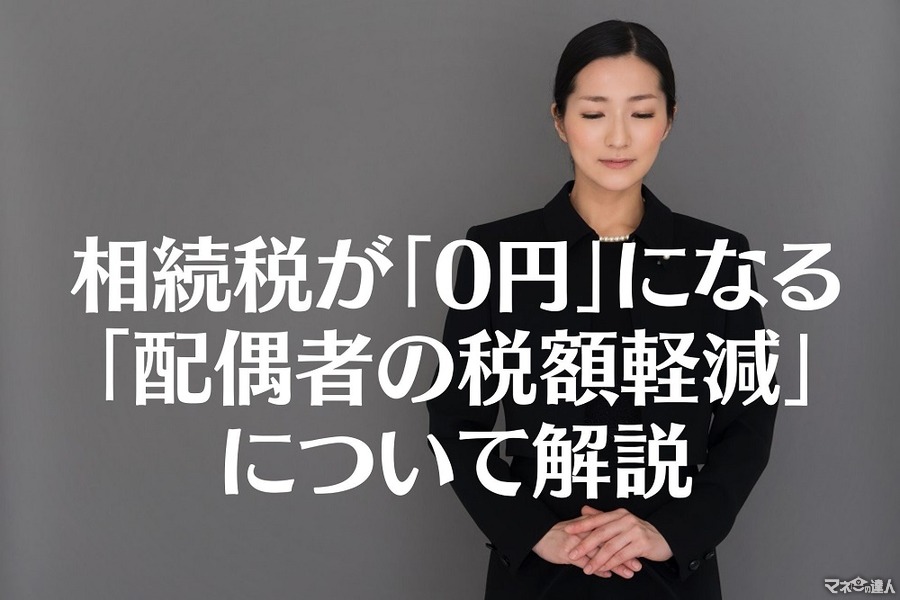相続税は、亡くなった人が相続財産を一定以上保有していた場合に課される税金です。
しかし、配偶者の相続した財産が1億6千万円までの場合、配偶者が支払う相続税をゼロにできる「配偶者の税額軽減」の制度を適用できます。
相続税の節税を考えるなら必ず活用したい、配偶者の税額軽減について解説します。
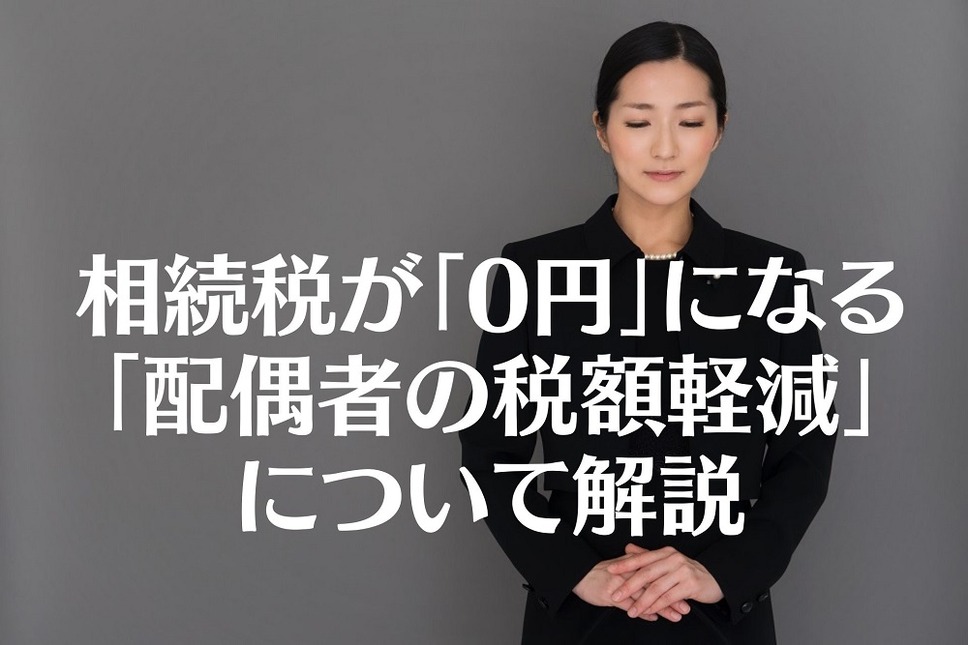
目次
配偶者の税額軽減の制度内容
相続税には基礎控除額があり、亡くなった人の相続財産が控除額を超えた場合に相続税を支払うことになります。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数 = 基礎控除額
一方で、配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した財産が1億6千万円以内であれば全額控除できる特例制度です。
相続財産は法定相続分の割合で分ける必要はなく、相続人同士が合意していれば、1人の相続人が全財産を相続することも可能です。
そのため
配偶者の税額軽減は年齢・性別に関係なく適用可能
節税効果の高い制度ほど適用する際の要件は厳しくなるケースが多いなかで、配偶者の税額軽減は配偶者が相続財産を取得するだけで受けられます。
相続する財産の種類に条件はありませんので、不動産などすぐに現金化できない財産は配偶者が相続し、相続税を支払う子は預金を相続すれば、相続税の支払いに苦労することも少なくなります。
未分割の財産には適用できないので注意
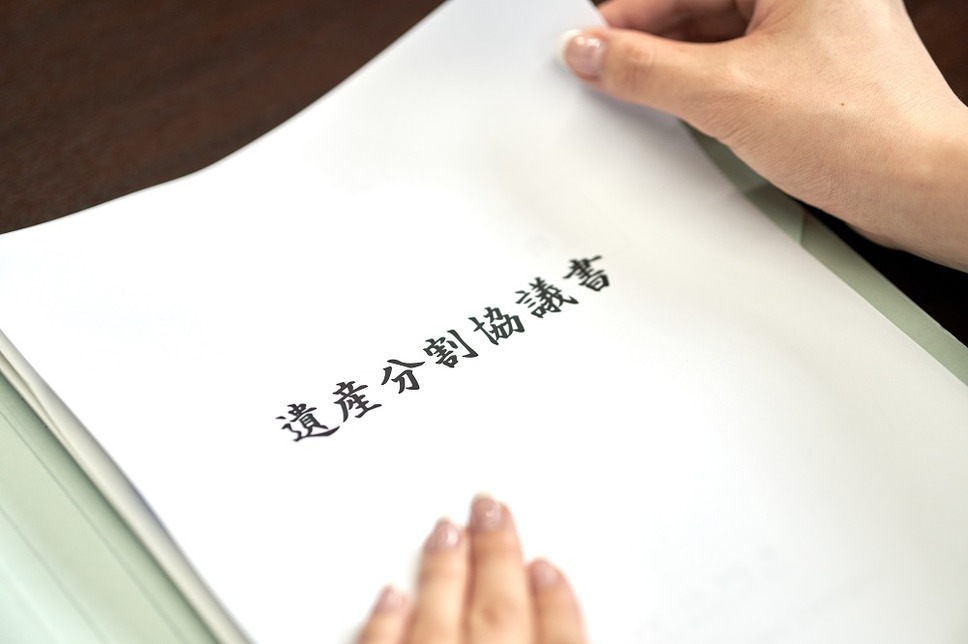
未分割の申告書を提出する場合には、法定相続分に応じた相続税を支払うことになります。
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産に対して適用するため、遺産分割が完了していない場合には控除を受けられません。
遺産分割協議の完了後に配偶者の税額軽減を適用した申告書(更正の請求書)を提出すれば、先に納めた相続税は還付されますが、一度は相続税を支払うことになりますのでご注意ください。
相続財産が多い人は2次相続対策も考える
配偶者の税額軽減をうまく利用すれば、支払う相続税を相当額抑えられます。
しかし、配偶者に大半の財産を渡すと、配偶者が亡くなった際に配偶者自身の財産と配偶者が1次相続で取得した財産を合計した金額に対して相続税が課されることになります。
配偶者が再婚していない限り、配偶者の相続の際に配偶者の税額軽減を適用できません。
そのため夫婦それぞれの相続を考えるのであれば、2次相続までを想定して遺産分割することも必要です。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)