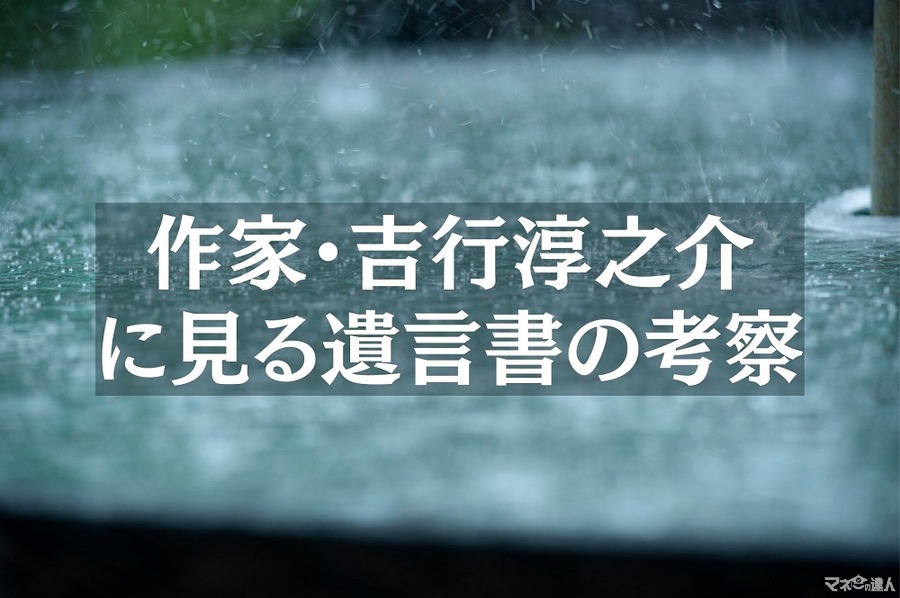今回は、作家・吉行淳之介の相続についてお話ししたいと思います。
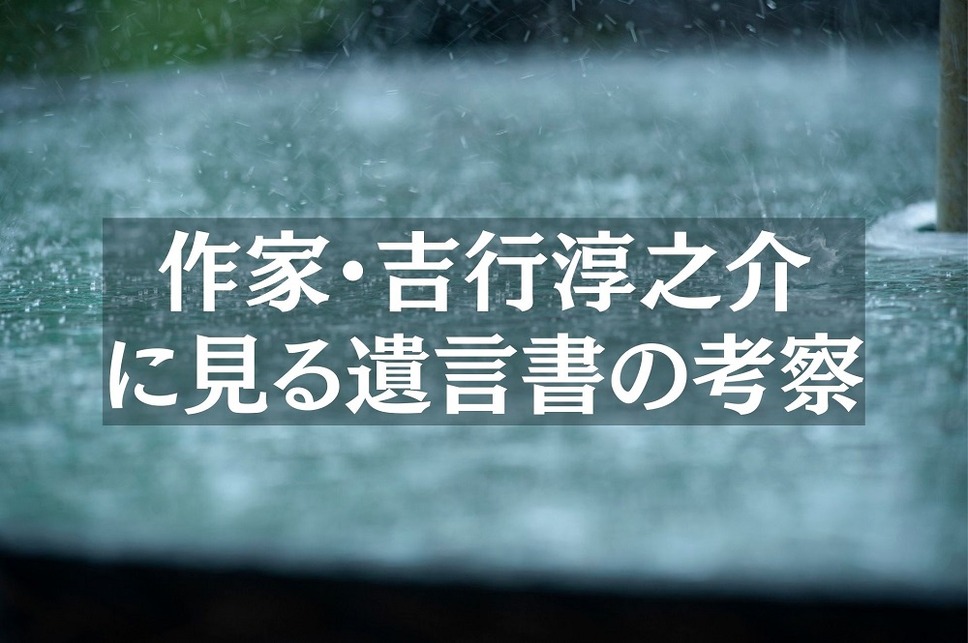
目次
遺言書を書かねばならなかった作家・吉行淳之介
遺言書は「書かなくてもよい人」と、「書く必要のある人」がいます。
作家・吉行淳之介は書く必要のある方でした。
なぜなら、長年のパートナーである宮城まり子さんと恋に落ちた時には、妻と長女Aさんがいたからです。
吉行は離婚を望みましたが、妻・文枝さんが生涯それを拒否し続けたため吉行が肝臓がんで亡くなる(70歳)まで戸籍はそのままでした。
吉行は家を出て、宮城まり子さんとは事実婚状態のままであったようです。
別居後は妻・文枝さんに生活費を支払い、さらに同居人である宮城まり子さんにも生活費を渡していたようです。
さて、その状態で吉行が亡くなった場合でも遺産として、結婚生活数年の妻・文枝さんと長女Aさんに全財産がいきます。
30年以上の同居人である宮城まり子さんは、法定相続人でないため財産の取得はできません。
そこで、遺言書の作成の必要が出てきます。
遺言書を書けば相続人以外の人に遺産をあげられるのです。
遺言書で著作権を遺贈
吉行の遺言書には「著作権は、宮城まり子に遺贈する」となっていたようです。
遺言で相続人以外の方に「全ての遺産をあげる」としても妻や子には遺留分があるため、預金や不動産にて調整してもらおうといった内容だったようです。
著作権も相続財産であり、相続税の課税対象にもなります。
また、宮城まり子さんが遺言書通りに遺産を取得された際には、取得された遺産に対して本来の相続税に2割が加算されます。
妻と子の遺留分はいくらなのか
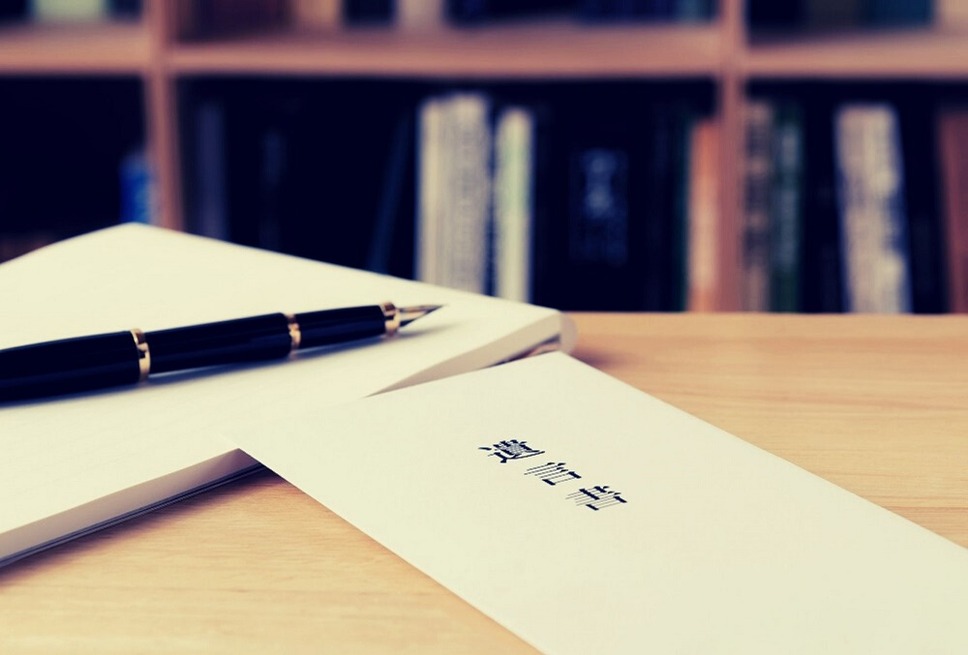
妻には法定割合1/2の1/2 = 1/4の遺留分があります。同様に長女にも1/2の1/2 = 1/4の遺留分があります。
遺言書のおかげで、宮城まり子さんは遺留分を請求されても、1/2 (1-1/4-1/4)は相続できるのです。
前提となる遺産の著作権の評価は相続発生時に行います。
筆者が気にかかっているのは、本妻である文枝さんとの結婚生活が数年しかないにも拘らず、著作権を遺留分の対象として計算する際に相続発生時の評価であるということです。
吉行の著作のほとんどが別居後に書かれていること考えると腑に落ちないところもあります。
作品自体が離婚騒動を体験することで成り立っているものもあると考えると悩ましいところです。
もし、離婚をしていたら
吉行は、宮城まり子さんと知り合った頃には芥川賞は受賞していたもののまだまだ流行作家とは言えず、離婚の際に財産分与として著作権を評価するには心配する額にならなかったと思います。
なぜなら、財産分与の評価基準は別居時になるからです。
離婚の原因が吉行の不倫であり、それを裁判で認めてもらうには、別居後も妻と未成熟の子に継続的に生活費を渡して財産分与でも相応の額を渡さなければ認められなかったと思われます。
子と同居者のために遺言は必要
配偶者は離婚すれば相続に関係しなくなりますが、実の子は離縁もできません(原則)ので相続人のままです。
特に同居人と子は相続でもめやすいものです。
そのためにも遺言書の作成が大切です。
遺留分を考慮したうえで、不動産は具体的に指定し、預金は割合等を決めておくことをおすすめします。(執筆者:1級FP、相続一筋20年 橋本 玄也)