※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事
贈与税や相続税の課税対象になるケースは、何となくイメージできると思います。 ただ一般的に贈与税の対象となるケースでも、一定の条件を満たすと相続税の対象になる場合や、相続税の対象だと思っていても実は贈与税として計算すべき場
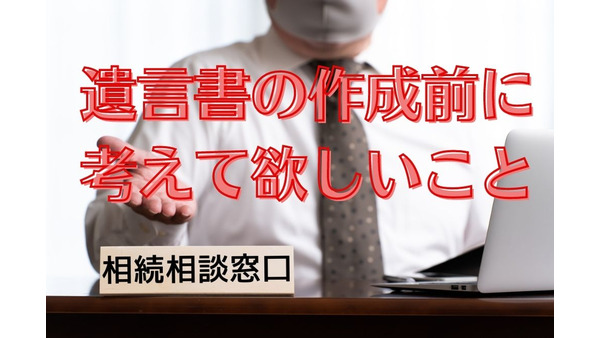
会計事務所で遺言書の作成のお手伝いをしていた時の話です。 事務所に相談にみえるのは、たいがい作成する本人ではなく、推定相続人(相続人となる予定の人)とか、そのご家族の人が相談にみえます。 「お父様はどんな事情で遺言書を書

先日、人気ゲーム実況者である加藤純一さんの結婚披露宴が生配信された際、スパチャ(スーパーチャット)の金額が約2億円になったと話題になりました。 結婚式のお祝いに参加した場合、ご祝儀を渡すのは一般的ですが、金額が大きく
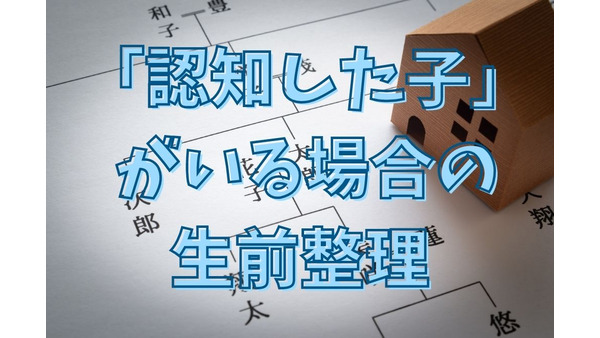
隠せない、認知の事実 そもそも婚姻外の子を認知している父親はどのくらいいるのでしょう。 先日亡くなられた、元都知事で、芥川賞作家でもあった石原慎太郎さんにも、「認知した婚外子がいて養育費も払っていた」(週刊誌情報)とのこ
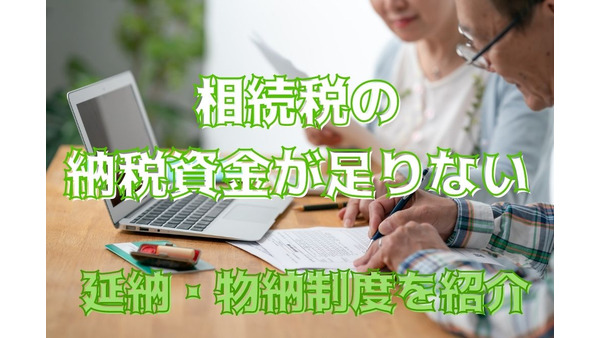
相続税を支払うために、相続した不動産を手放したなどの話を聞いたことがあるかもしれません。 相続税は取得した財産に応じて支払うことになるため、納税資金が足りなければ相続財産を処分することも選択肢です。 ただ売却するのが難し
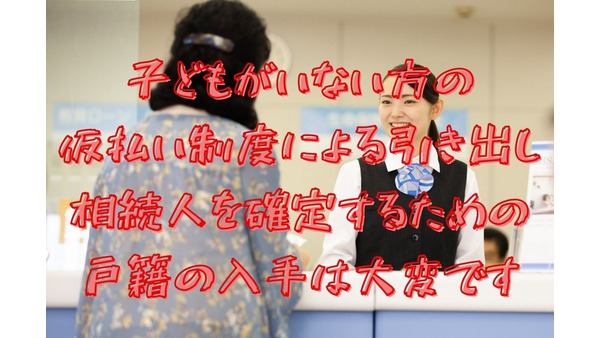
夫が亡くなり入院費を引き出しに行った佐藤さん 長期入院されていた夫の入院費用の支払いのため、夫の通帳を持って、某銀行に行った時のことです。 窓口の方からから「ご退院されたのですか?」と聞かれ「いえ亡くなりました」と答えた
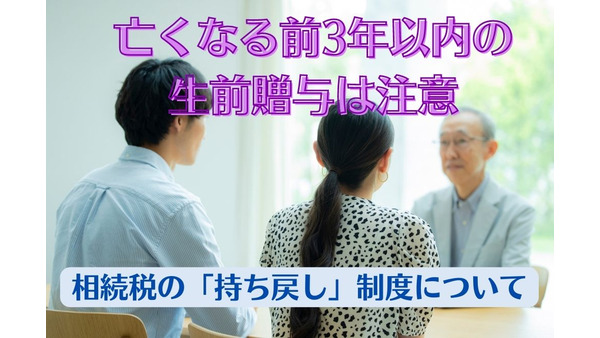
余命宣告された方から生前贈与についての一般的なご質問がありました。 亡くなる直前の生前贈与については税務当局も注視していますのでさまざまな点に注意して行う必要があります。 相続税の節税目的ではなく、親族への最後の心づくし

贈与税はお金をもらったり、無償で不動産の名義変更した際に課税対象となる税金です。 贈与税は所得税と同様、確定申告手続きが必要になりますが、所得税以上に申告する機会が少ない税金です。 そこで今回は、贈与税の確定申告時に知っ

親に、「遺言書」を書いてもらう方法 こんな見出しを先日、週刊誌の見出しで見かけました。 筆者も遺言書が、作成してあれば、「相続人がこんなつらい思いをしなくてよかった」と思ったことは何度も経験しています。 たとえば、子供が
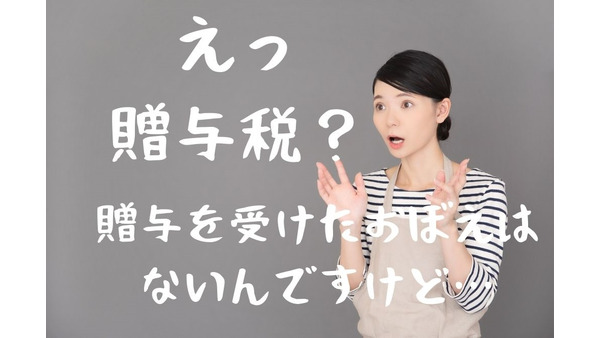
贈与税は贈与者から財産をもらった際に課される税金であり、贈与税の申告手続きをするのは受贈者(財産をもらった人)です。 贈与の認識を持って受け渡しするのであれば手続きを忘れることはありませんが、知らないうちに贈与税の対象と
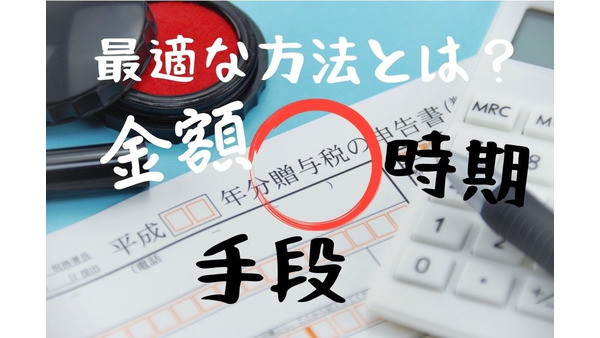
贈与税は財産を無償でもらった際に課される税金であり、子どもであっても納税者として申告・納税手続きが必要になるケースもあります。 一方で、贈与税には非課税控除や特例制度が多く存在するため、同じ贈与財産をもらった場合でも、贈
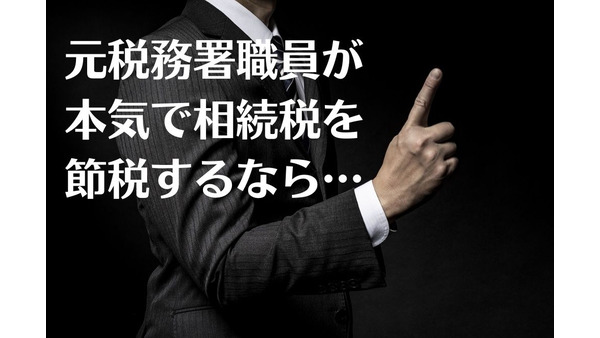
相続税対策の方法は数多く存在し、相続財産の種類によって活用できる制度も変わってきます。 一般の方が相続税の節税を考える場合、利用しやすく、それでいて費用対効果の高い制度を利用するのがポイントです。 本記事では、元税務署職
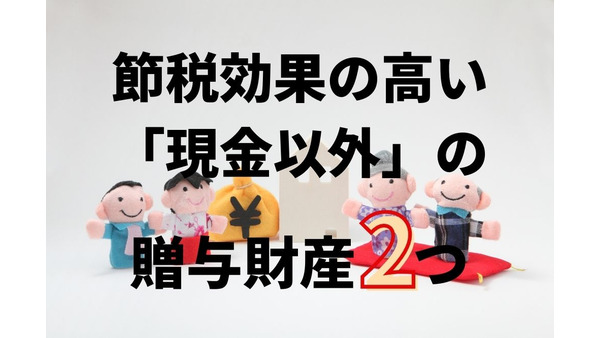
贈与税は贈与財産が110万円までなら、非課税で子や孫に財産を渡すことが可能です。 贈与財産で最初に思いつくのはお金ですが、お金以外の財産で渡した方が、より高い節税効果を得られるケースもあります。 本記事では、節税効果が期

最近、週刊誌等で、「暦年贈与がなくなるかも」といった記事をよく見かけます。 渡辺家の相続対策(どうする今年中の贈与) 現在63歳の渡辺さんも、自身が亡くなった時の相続税をちょうど気にしだしたところです。 暦年贈与とは、年

少し前の時代の話です。かっては、長男夫婦に子供が「いる」のか、「いない」のかは大きな問題でした。そこで、長男と長男のきょうだいとの子を養子にしている家も多かったようです。 養子に行った子に実の親がいて、養親との親子関係も
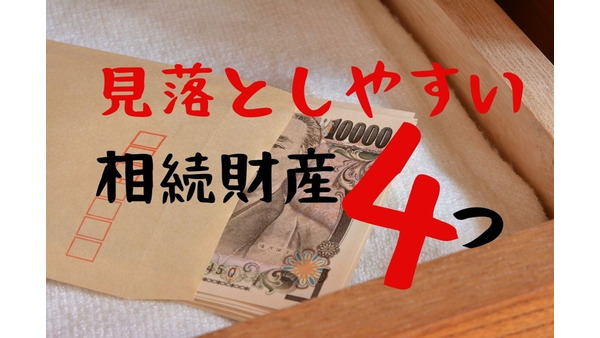
相続税の対象となる財産は、亡くなった人が保有していた財産すべてです。 税務署は、申告書に記載漏れとなっていた財産があれば、容赦なく指摘します。 よって相続人は、亡くなった人の財産をしっかりと調べる必要があります。 ただ「
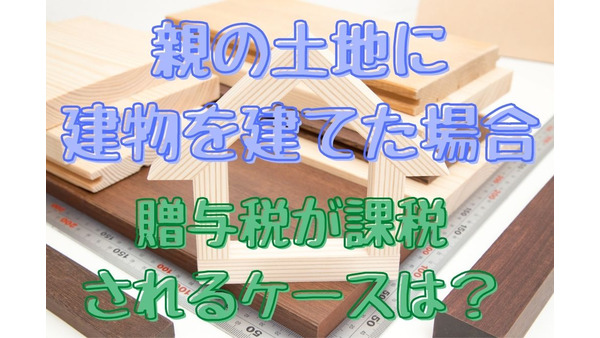
贈与税は財産を無償で得た際に課される税金です。 お金はもちろんのこと、不動産をもらった場合も贈与税の課税対象です。 また親が所有している土地の上に建物を建てるケースにおいても、一定の条件に該当すると贈与税が課されてしまう
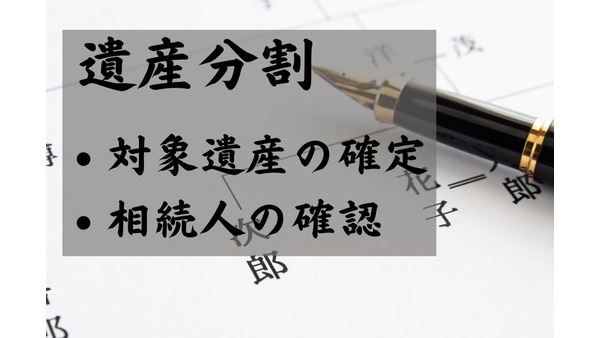
遺産分割を行うには、「対象遺産の確定」と「相続人の確認」が必要です。 故人の取引銀行の確認や残高等は相続人1人からの依頼でも行えますが、遺産分割を完了するためには、遺言書がある場合などを除き、原則相続人全員の合意がなけれ

相続が発生した場合、残された相続財産の金額によっては、相続税の申告書を提出しなければいけません。 相続税は亡くなった人の財産に対して課される税金であり、申告書を作成するのは財産を取得した相続人です。 相続税の申告書の作成
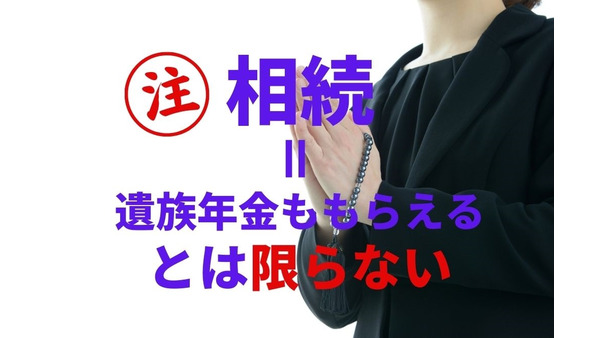
似て非なるものとして相続と遺族年金が挙げられます。 相続が認められるからといって、遺族年金も認められるという図式にはなっておらず、それぞれの特徴や注意点など、損をしないためのポイントとなる部分を確認していきましょう。 例

親と離れて暮らす子供夫婦からの「実家じまい」のご相談が徐々に増えてきております。 親がまだご健在の方やお亡くなりになられた方などタイミングはまちまちですが、新型コロナ禍でその動きが加速する可能性があります。 今回は「実家
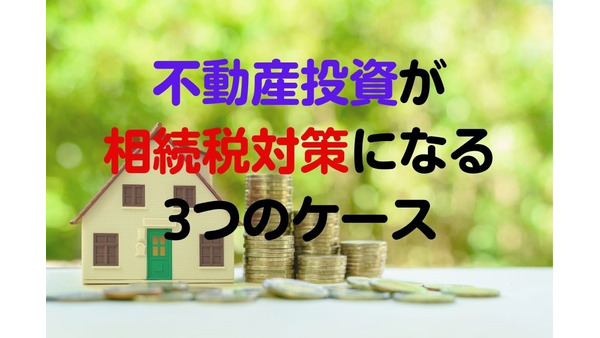
相続税を抑える手段は多数存在しますが、その中でもオススメされる方法の1つに不動産投資があります。 不動産投資は生前に不動産を購入し、賃貸用として利用することで相続税を抑える節税手段です。 ではどうして不動産投資が相続税の
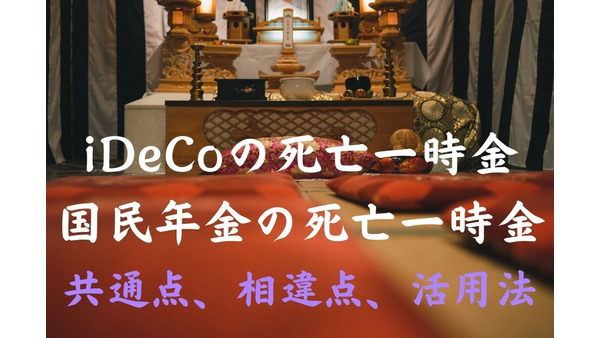
多くの税制優遇を受けながら、公的年金の上乗せを準備できる制度のひとつとして、iDeCo(個人型の確定拠出年金)があります。 iDeCoの年金資産(拠出した掛金とその運用益)は、60歳以降になると「老齢給付金」として受給で
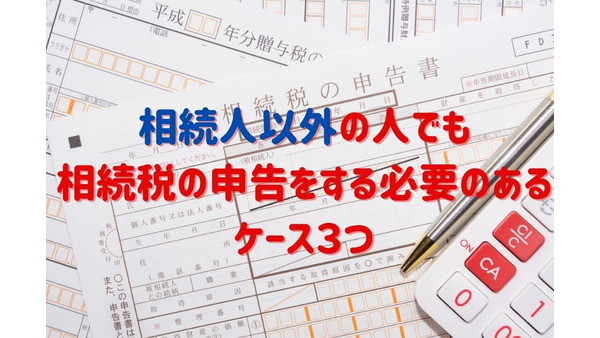
相続税は亡くなった人の財産に対して課される税金であり、基本的に相続人が相続税を支払うことになります。 しかし相続人以外の人であっても、相続税の申告・納税が必要となるケースが3パターンありますので、該当する場合は申告手続き

生前にタダで財産をもらうのは贈与です。 贈与とは (贈与) 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。e-gov 贈与は、勝手に子

満期保険金を受け取った場合、通常は受け取った人の所得として所得税が課されます。 しかし保険料を支払っている人「以外」が満期保険金を受け取った場合、所得税ではなく贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。 満期保険金に
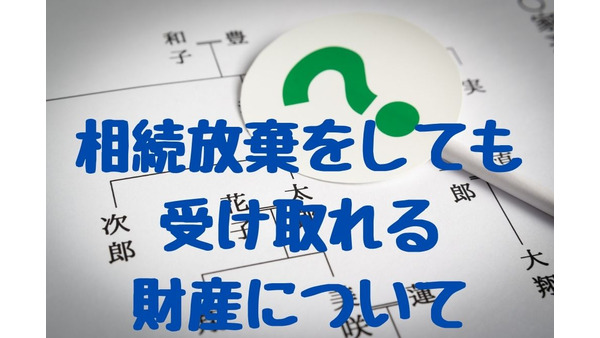
相続放棄を希望される場合は、故人に借金などのマイナス財産が多くてとか、故人の家とは今後関わりたくないなどのお気持ちがあったりしますので、財産を受け取ろうなどと考えることはあまりないかもしれません。 しかし、相続放棄をして
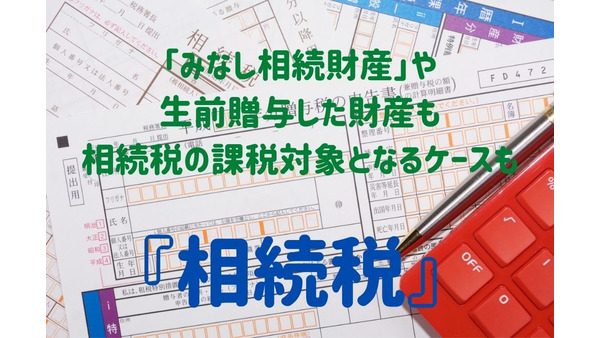
相続税は、亡くなった人が相続開始時点で保有していた財産に対して課される税金です。 しかし相続財産ではなくても、相続税の対象となる「みなし相続財産」や、生前贈与した財産も相続税の課税対象となるケースがありますのでご注意くだ
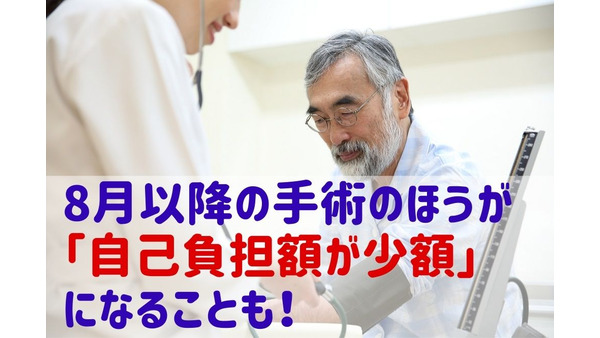
今回は、退職後に独立したある自営業者の男性の入院をきっかけにした終活の話をします。 目の不調から病院を受診 退職後に独立した自営業者の佐藤一男さんは、体に気になることがあり病院に行ってきました。最近、本を読むのに文字がぼ

故人が生前に投資会社を訴えている訴訟中の相続 宮田一郎(仮名)さんが亡くなり、1周忌を終えてホッとしたころです。 同居していた長男の学さんが、宮田一郎さん宛に届いた郵便物を中身を見て愕然としました。 驚いたことに一郎さん

コロナ禍がまだ当分続きそうな現在においては、昨日まで元気だった人が今日は病に倒れるかもしれないといった状況です。 もしも自分が急病になったら、あるいは急死してしまったら、残された家族はどうしたらよいのでしょうか。 やるべ
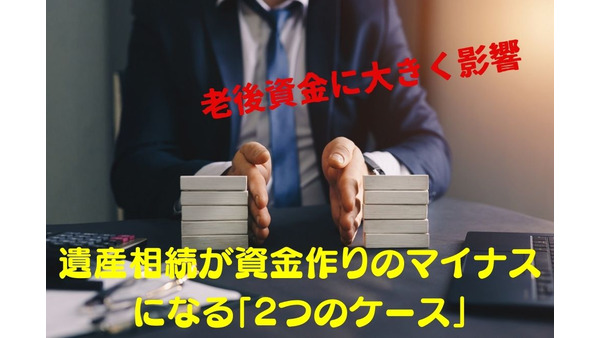
50代も後半になると、数年後には定年退職、さらにその先には年金生活が控えています。 豊かな老後の為には十分な資金が必要ですが、皆さんはどのように準備をしていますか。 老後資金作りと言えば、一般的に貯蓄や退職金を株、投資信
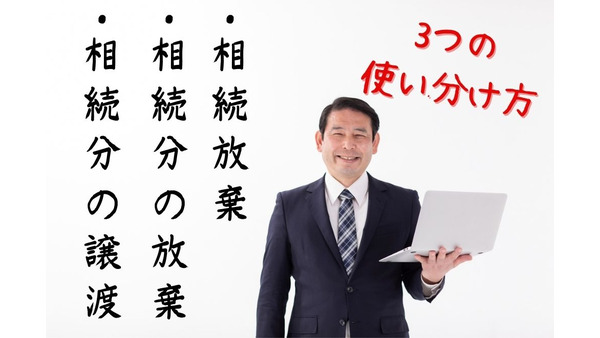
相続や遺産分割に関する争いが増えてきているようです。 多くの方が相続発生前には「うちは大丈夫」とお話されていたにもかかわらずです。 相続税申告には期限がありますが、遺産分割協議には期限はありませんので長引くと2~3年はす
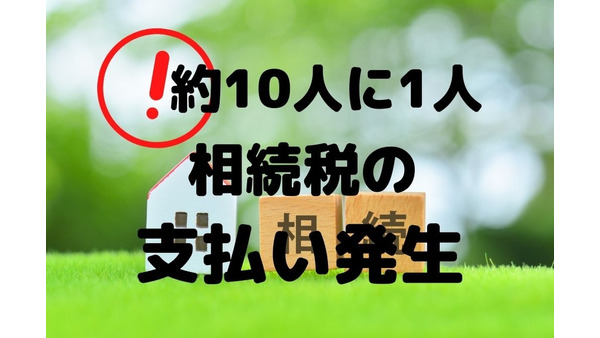
相続税は、富裕層に対する税金のイメージがあるかもしません。 しかし一般層の方々でも相続税の対象となる人はいますので、実は富裕層向けの税金ではありません。 また「富裕層」といっても、どのくらいの財産を所有してる場合に使用す
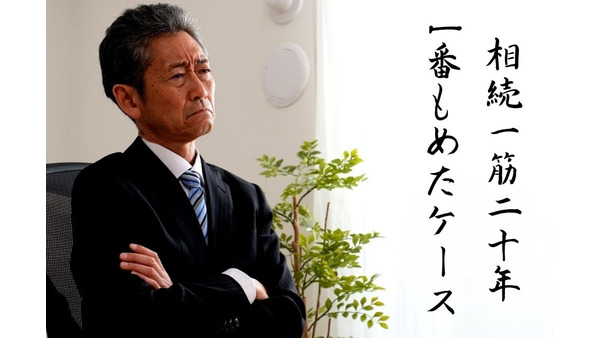
筆者が20年働いた相続専門部署にて1番もめた遺産分割は、子である相続人が兄と妹のケースでした。 兄と妹の遺産分割はもめやすいのか? 夫が亡くなり相続人は、妻の陽子さんと、長男(兄)の健さんと長女(妹)の恵子さんでした。夫

相続税は亡くなった人の財産に対して課される税金なので、贈与によって家族に財産を移すことにより、課税対象となる財産を減らすという節税方法もあります。 しかし、家族名義の預金でもあっても相続税の課税対象になる場合もありますの