※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事
2020年の4月から「配偶者居住権」という新制度が施工されます。 これは、残された配偶者の生活安定を目的に新設された制度であり、今後の相続について取り巻く環境が大きく変化するとも言われています。 そこで今回は、配偶者居住
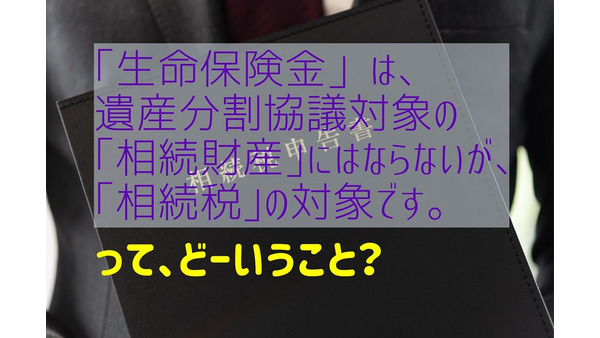
亡くなった人(被相続人)名義の預貯金や不動産などは、相続財産としていったん相続人全員の共有財産となり、遺産分割協議を経て名義変更などの相続手続をします。 では、被相続人が特定の相続人を受取人として掛けていた「生命保険金」
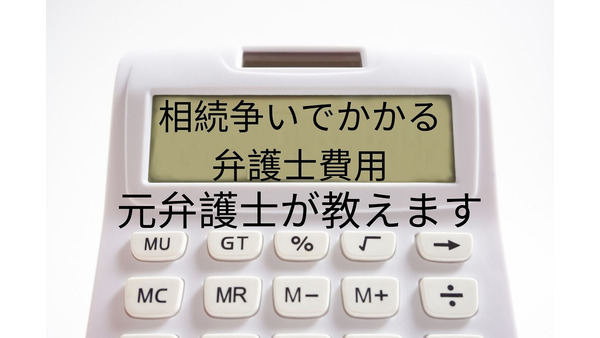
相続争いがいったん起こると、感情的な骨肉の争いが際限なく続くことが多いです。 そんな相続争いをおさめるためには、冷静に対応しつつ専門的な知識を駆使することが必要です。 弁護士に依頼することで適切な解決が期待できますが、弁
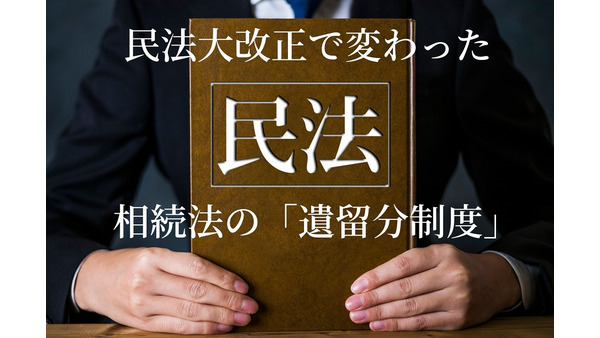
相続法を主とした民法の大改正について、こちらでもいくつか説明をしてきました。 今回は民法改正シリーズの遺留分制度に関する見直しについて説明します。 遺留分制度とは 遺留分制度については以前こちらで説明しました。 【関連記
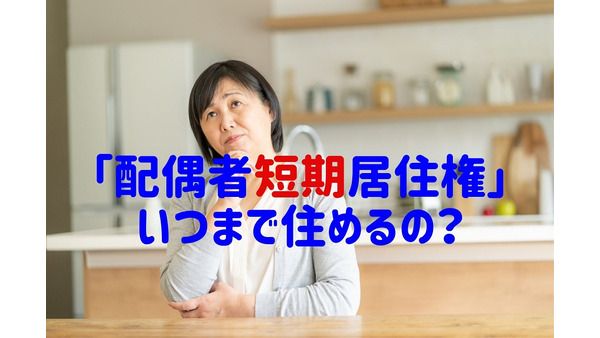
相続法の改正により「配偶者短期居住権」が創設されました。 これにより、相続発生前から被相続人の所有する建物に居住していた場合、配偶者は他の相続人や第3者に対して相続開始後も一定期間「家に住む権利」を主張できます。 ただし

葬儀費用は節税にもなる 相続税の基礎控除前後の方が、税理士事務所に相談に行けば、当然申告するようアドバイスされます。 当然です、申告書を作成するのが「お仕事」だからです。 例えば相続が発生し、相続人が3人(配偶者と子供2
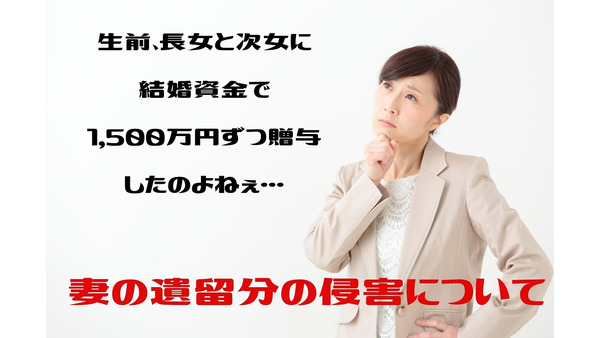
Q :「今回相続が発生しましたが、相続人は妻と長女と次女の3名です。 相続財産は600万円 しかありませんが、生前に長女と次女に結婚資金を1,500万円ずつ贈与していました。 妻の遺留分の侵害については、誰が負担するので
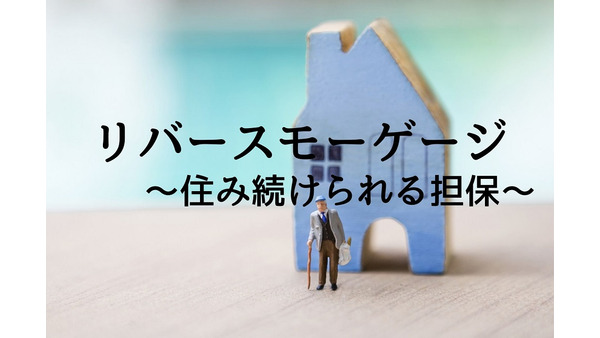
長寿高齢化で健康寿命を長く、という取り組みが加速している日本です。 健康的に、自分の望む暮らしを老後も送ることができるということは幸せなことです。 しかし、何らかの介護が必要になった時や、介護が必要ではなくても思った以上
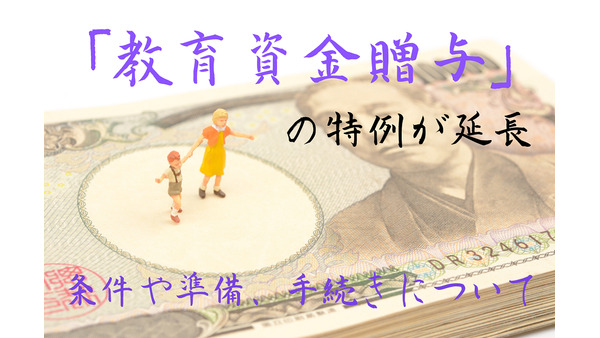
普段は中学生の娘と息子、夫と4人家族で育児と家事をしつつ、一級建築士の資格を活かした建物点検の業務をフリーで受託しています。 その我が家の子ども2人が義母から教育資金を贈与されました。 まとまった資金を教育のために直系尊

遺言の主流である「自筆証書」と「公正証書」 それぞれのメリット・デメリットについては、正に相反するといった感じです。 どちらがおすすめかは個人の事情にもより、一概には言えませんので、1度整理してみましょう。 自筆証書のメ

さまざまな事情でお墓の引っ越しや墓じまいをする人が増えています。 お墓を移すということは、そこにある墓石がなくなるだけではなく、供養をしてくれていたお寺との関係がなくなるということをも意味します。 そこで問題となるのが離
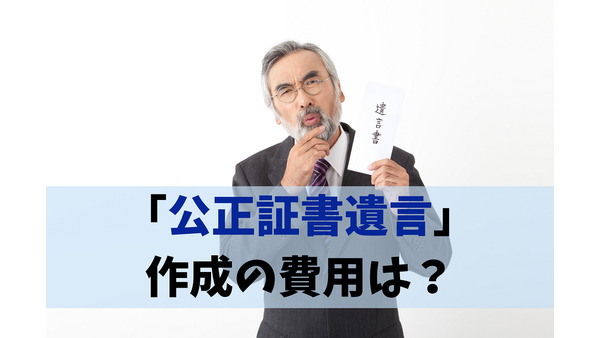
遺言書を作りたいと思い、法律の専門家などに相談した方はたいてい公正証書遺言を勧められるのではないでしょうか。 ・ 作成は専門家である公証人にお願いできる ・ いざという時手続不要で効力を発揮する ・ もし紛失しても原本は

元気なうちにお墓を建てるいわゆる「生前墓」は、縁起がいいと言われているだけでなく節税にもなります。 もしもお墓を建てることが分かっているのなら、元気なうちにお墓を建てるとさまざまなメリットがあります。 この記事では、生前

「相続が発生したけど、相続税がかかる財産なのかどうかが分からない!」 親が残してくれた預金や不動産などは、相続財産として相続税の課税対象ですが、「香典や準確定申告の還付金は?」どうなるのでしょう。 相続した財産や相続発生

リバースモーゲージ(Reverse mortgage) ウィキペディアでは次のように説明しています。 「リバースモーゲッジ(Reverse mortgage)とは、自宅を担保にした融資制度の一種。自宅を所有しているが現金

2020年4月から、民法の改正によって新設された「配偶者居住権」が施行されます。 「配偶者居住権」とは、被相続人の持ち家に住んでいた配偶者が、被相続人が亡くなった後、その家を相続しなくても自分が亡くなるまで無償で住み続け

亡くなった方の「預貯金の払戻し制度」(いわゆる仮払い制度、以降「仮払い制度」)が2019年7月から施行されていますが、あくまでも預貯金の一部の仮払いにすぎず、それほど多くの金額を引き出せるわけではありません。 それに、親
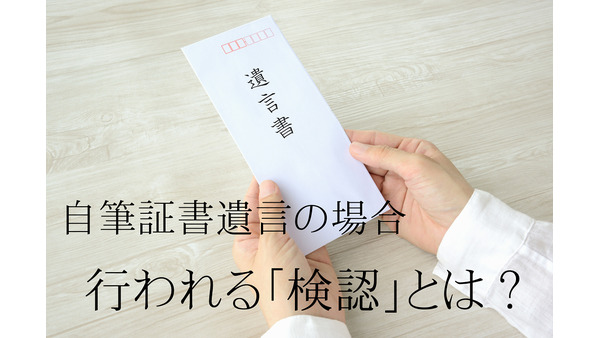
民法改正で、自筆証書遺言の作成が少し楽になったというお話を先日しました。 遺言には主に2種類、自筆証書遺言と公正証書遺言があるのはよく知られています。 自筆証書遺言の場合、遺言通りの相続を行うためにはまず家庭裁判所におい

被相続人に大きな借金などの負債がある場合には、相続放棄をすることによってその支払い義務を免れることができます。 しかし、その被相続人が住んでいた家が空き家になった場合、放置していると多額の出費を余儀なくされるケースがあり
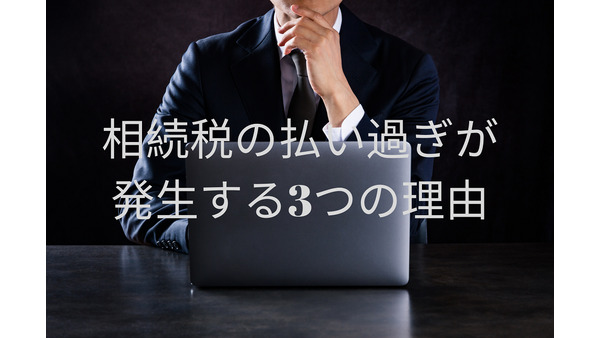
相続税の計算方法は法律で決まっていますが、実際には払い過ぎているケースがとても多く、税理士に依頼して相続税の申告をしたのに払い過ぎているケースも珍しくありません。 払い過ぎた相続税は、後から取り戻せます。 この記事では、
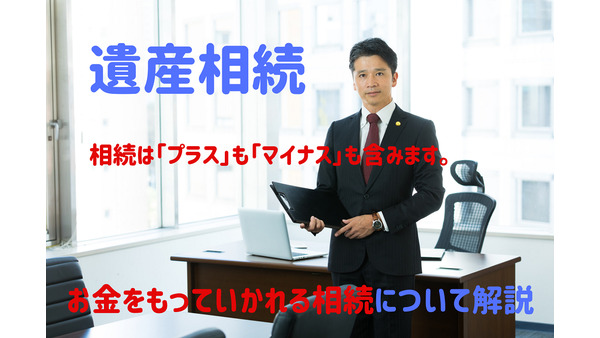
親からの遺産相続は、必ずしも「もらえる」とは限りません。 相続の中には、債務も含まれるため、相続する内容によってはマイナスつまり「お金をもっていかれる相続」になる可能性もあります。 今回は相続の中でも「お金をもっていかれ

昭和、平成、令和と変遷し、戦後の物資のない時代から、男女ともが社会に出て働くのが当たり前になり、家庭のお金も昔に比べるとずいぶんと余裕が出てきました。 昭和の頃は所帯を持っても同居するのが当たり前でしたが、平成には、我慢
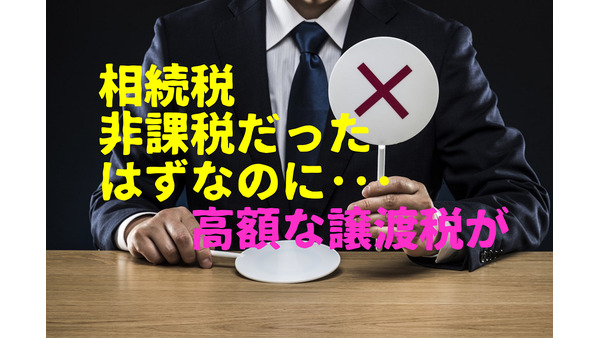
相続法(民法)が改正され、2019年7月1日の施行により遺留分制度の内容が変わっています。 今回は、理不尽とも思える税務通達により余計な税金等を払うことになりかねない事象をお話します。 「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵
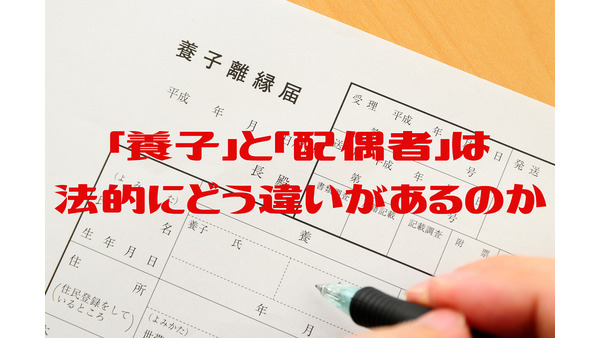
人生の末期にパートナーが、配偶者ではなく同居人の立場でしかなかった場合、いろいろと不都合がでてきます。 例えば、同居人では、パートナーの病状の説明を受けることや医療方針に関われないといった事態が起きるのです。 病院では、

贈与税の節税対策は、毎年やらないと損をする仕組みです。 贈与税には基礎控除額110万円があり、基礎控除額以下の財産であれば贈与税は非課税です。 ただ、この基礎控除額は毎年の使いきりであり、今使わないとそのまま切り捨てにな

亡くなった方(被相続人)の財産のうち、居住していた土地家屋(以下「家」)に関して、相続開始前から同じ家に居住していた配偶者はそのまま継続して家の使用が認められるうえに、家以外の財産も取得できるという、配偶者居住権制度が、

Q:「令和1年6月1日に相続が発生し、相続人が3人います。 被相続人の財産の中に賃貸不動産がありますが、相続人同士の遺産分割協議が済んだのが、10月31日です。 遺産分割前の6月から10月までの賃料収入は誰のものになるの
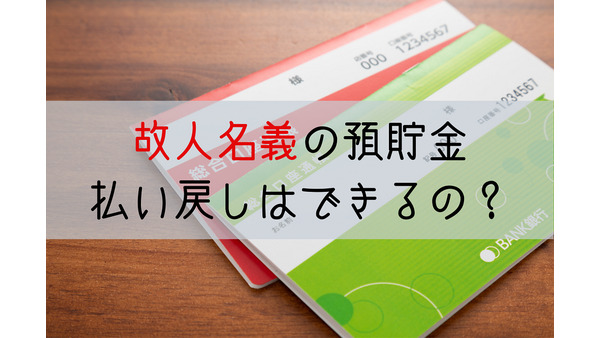
亡くなった方の預貯金は、相続による名義変更をしないと一切払戻しができないのが原則です。 たとえ相続人が自分の法定相続分の範囲内での払戻しを請求しても、金融機関は決して応じません。 しかし、平成30年7月に相続法が改正され
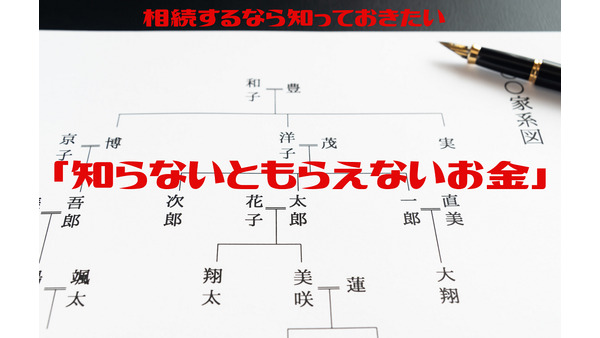
相続するなら絶対に知っておきたい言葉「遺留分」 「相続」は突然やってきます。 相続初心者の中には「自分の相続分は、黙って待っていれば自動的に届けられる」と思っている人がとても多いです。 しかし、相続は黙っていれば、始まる

2015年に相続税法が改正され非課税で相続できる金額が少なくなった事で、相続税がかかる人が増えました。 その対策として関心が高まっているのが、相続財産を減らすべく、生きてる内から財産をお子さんやお孫さん等に分けていく「生
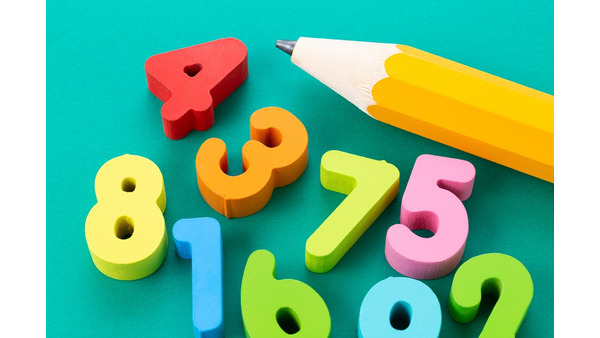
マイナンバー制度が始まって既に4年近く経っています(平成28年1月開始)。 公的機関や、保険、金融機関などでマイナンバーの記載が求められるようになった一方、マイナンバーカードの普及率は平成31年3月時点で約13%と低く、
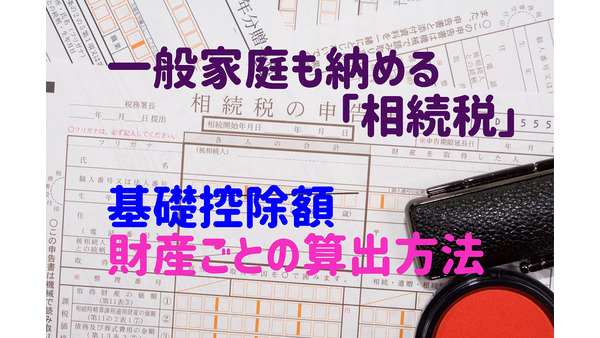
「相続税なんて、資産家だけの悩みでしょう」 などと思っていませんか。 実は2015年の税制改正で、より多くの人が相続税を納めなければならない可能性が出てきました。 いざという時に慌てないために、今のうちから考えておきまし
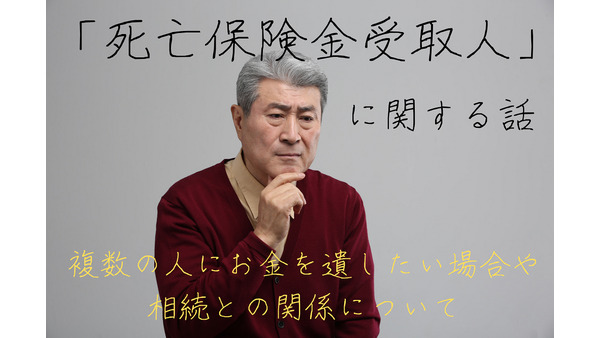
死亡保険金受取人欄にその名を書くだけで、遺したい人にお金を遺せる死亡保険ですが、お金を遺したい人が複数名いる場合や他の相続財産との関係で、遺されたお金がトラブルの種になる事もあります。 ここでは、死亡保険金受取人にまつわ
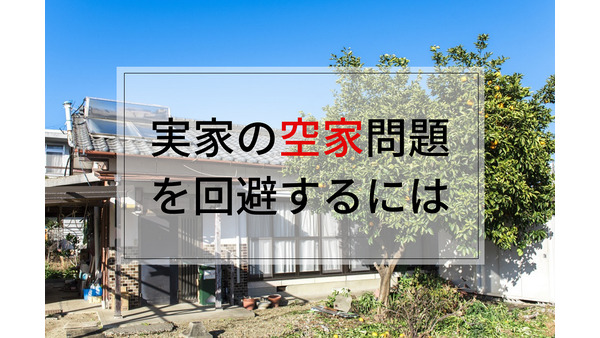
最近、空き家となっている「実家」をどう処分するのか悩まれる方が増えています。 親が施設に入所してしまい実家が空き家になってしまったり、親が遠方で子どもが実家の管理に行くことが難しかったりするケースです。 空き家のまま放置
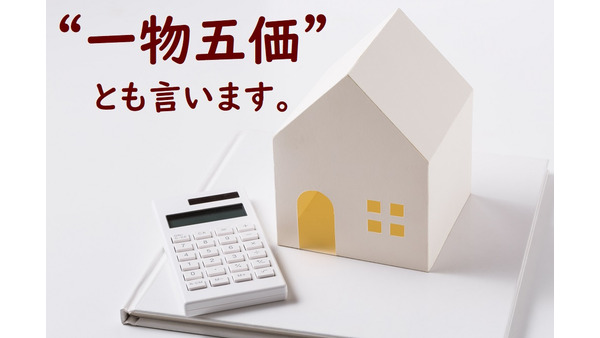
土地の価格には 1. 実勢価格(取引価格) 2. 地価公示価格(国土交通省地価公示) 3. 基準値の標準価格(都道府県地価調査) 4. 路線価(相続税路線価) 5. 固定資産税評価額 などがあります。 これらは何が違い、
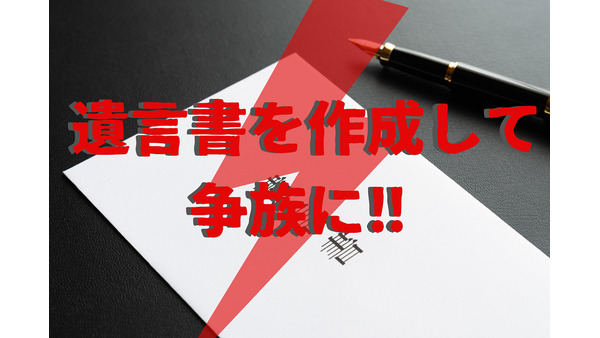
なぜ、遺言書を作成すると争族になるのか? 公正証書で作成 遺言書が無効になる事もない 税理士に相談 節税にも配慮した そんな遺言書であれば、完璧でしょうか? 遺言書を作成してはいけない理由が2つあります。 1. 親の遺産