※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事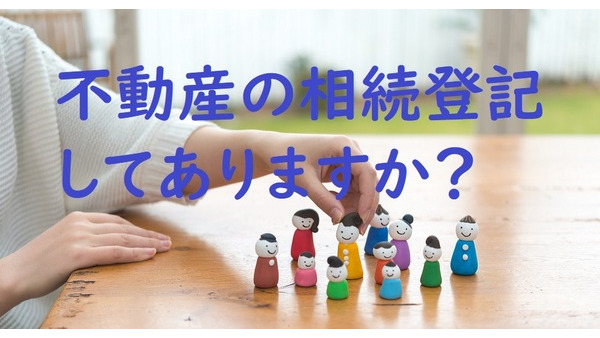
年末年始で親戚一同が集まる機会もあるかと思います。 こういうタイミングは、これまで後回しになっていた親族間の手続きを解決するのにも良い機会です。 最近、仕事でよくこの問題に遭遇するので、問題点と解決策をお伝えしたいと思い

1年が終わります 年末に近づいてきましたが1年の区切りというのは大事なことです。 1年間の貯蓄額の推移、投資を始めた結果の投資資産の確認や、放ってしまっていたものの片付けなどいろいろあります。 お金の話題ではありませんが
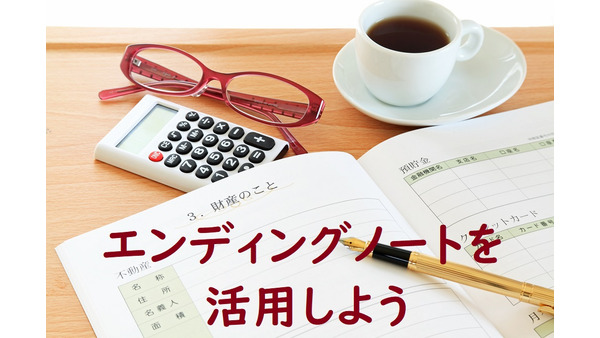
相続対策をする前に準備しておくべき5つのこと 相続について遺言の作成などの対策をしておくことは非常に大切ですが、いきなり相続対策はできません。 そのために実行しておくことや、対策をする前にしておいた方がよいことを紹介しま

境界確定していない土地を持っている場合、土地家屋調査士から 「隣地の依頼を受けたので境界確定で立ち会ってください」 と連絡があれば、あなたはどう対応しますか? 通常は、関係者が立ち会いの場で話し合いをして決めるのが普通だ

遺産分割の難しさ 相続人が多い場合はグループ分けをする 遺産分割の相談を故人の相続人Aさんからいただきました。 Aさんの話では故人の所有していたアパート1棟を他の相続人たちとどう分けるかといった相談内容でした。 主張も、

銀行と付き合っていくうえで、誰もが避けて通れないのが相続です。 「死亡すると、預金はどうなるの?」 「死んだ人のローンはどうやって返していくの?」 「相続手続きはどうやるの?」 こうした相続の疑問について、銀行員生活30

生命保険と葬式代の関係 「生命保険でお葬式代を準備しておきませんか?」 保険の販売員とお付き合いのある方は1度はそうやって生命保険を案内された事があるかもしれません。 「なぜ保険でお葬式代を準備するのかはよくわからない」
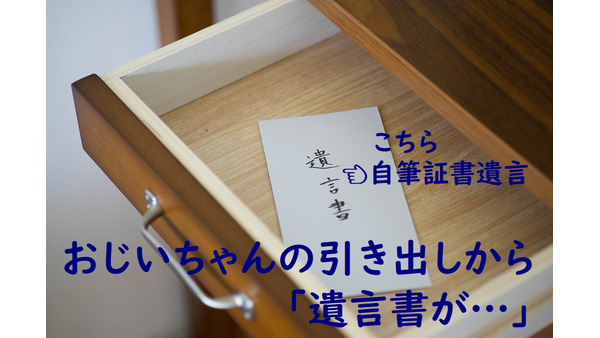
「遺言」というと、人によってさまざまなイメージがあるようです。 ドラマで出てくるような、資産家のおじいちゃんが亡くなった後に引き出しから「遺言」が出てきた! というシーンを想像する方も多いのではないでしょうか。 しかし、

2015年以降の相続に対する課税は、2014年までと比較すると格段に大きくなりました。 この税制改正は、 ・ どの程度税額が大きくなったのか ・ 自分あるいは親の相続には税金がかかるのか をきちんと知っている人は意外と少
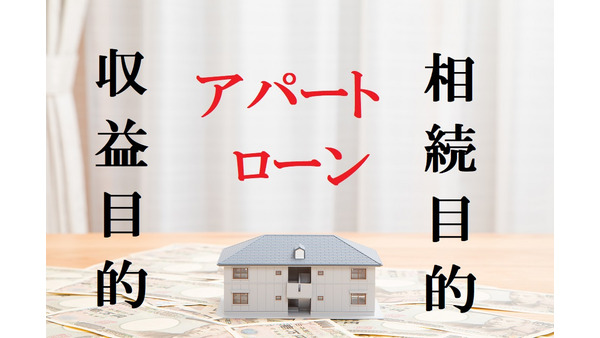
アパートローンの2つの目的 アパートローンの融資審査では動機、 何のためにアパートを建てるのか? という目的が重要な要素です。 目的は以下の2つ 1. 収益目的→ 不動産投資 2. 相続目的→ 相続対策、不動産の有効活用

2013年度の税制改革で導入された「教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置」ですが、来年(2019年)3月末日をもって一旦終了します。 新年度から、新制度に切り替わるとも言われていますが、現行の制度については、ご存じでし

親が住んでいた自宅や、管理をしていた事業用の土地などを相続することになった場合、気になるのは、その相続税評価額ではないかと思います。 特に自宅など、被相続人と相続人が同居していた場合は容易に売却をすることが出来ない重要な
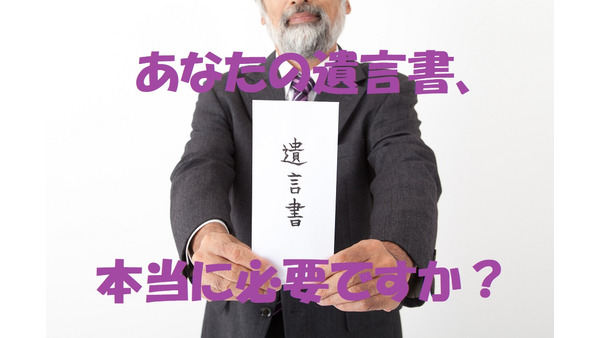
法改正で自筆遺言の作成が手軽になり、争族が増加する? 自筆遺言の場合、相続人が相続発生後、家庭裁判所に検認の手続きをしないと名義変更ができませんでした。 法改正で遺言書の保管を法務局でされるようになり、検認が不要になりま

生産緑地は売れない? 生産緑地に指定された農地をたくさん持っている知人から、 「生産緑地に指定されると固定資産税は安くなるけれど30年間の営農義務があり、その土地を、駐車場として貸すとか、建てるとか、売却もできないらしい

教育資金贈与とは 教育資金贈与とは子や孫に一括で贈与ができる制度です。 その金額は最大で1,500万円まで可能となり、教育資金として一括贈与されたものは非課税です。 この制度を適用するための条件は大きく3つあります。 条
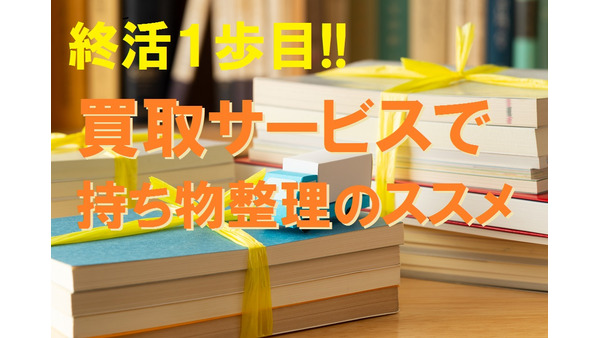
人生の締めくくりに向けて準備をする「終活」で多くの人が最初に行うのが持ち物整理です。 特に、思い入れのあったり高価な品物の場合は、人に譲ったり捨てたりすることが難しくなりがちです。 そこで活用したいのが、買取サービスです

父親の遺産相続のせいで、娘夫婦が熟年離婚 父親の遺産の分け前をめぐって、娘夫婦の関係がおかしくなり、離婚を避けられなくなる… そんなケースも世の中には一定数、存在するのですが、今回は私のところの相談実例をご紹介しましょう
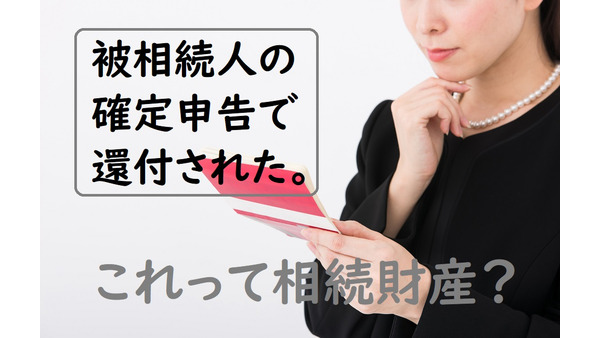
親族が亡くなったとき、やらなくてはならない税金の作業は相続税の申告・納付だけではありません。 相続人が被相続人の代わりに所得税の確定申告をしなくてはならないことがあります。 このとき、還付金や還付加算金が発生することもあ
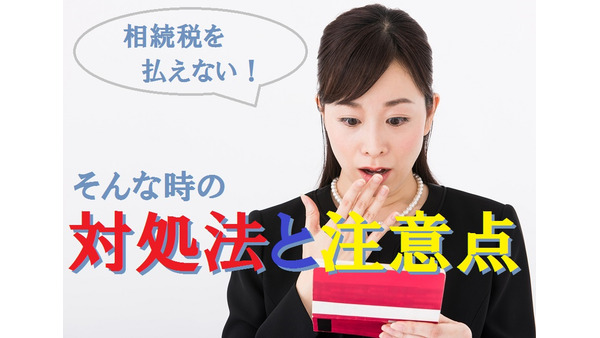
2015年の相続税法の改正により、相続税を納付しなくてはならない世帯が増えました。 「ウチには関係ない」と思っていた世帯でも、ふたを開けてみたら相続税を納めなくてはならないケースもあるのです。 けれど、手元に現金がなくて

名義変更をせず、放置していると思わぬ落とし穴が。 相続が発生したときに遺産として、土地や建物を相続した方も多いのではないでしょうか。 不動産を相続した方は不動産登記(名義変更)をきちんと行っていますか? 特に何も対応して

まず整理したいこと 「リアル相続」=どんな分け方でもよい。 「もめた時の相続」と「訳あり相続」=民法の法定相続分が基準 なのです。 遺産分割は、どうやって決めるのか 民法906条に 「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利
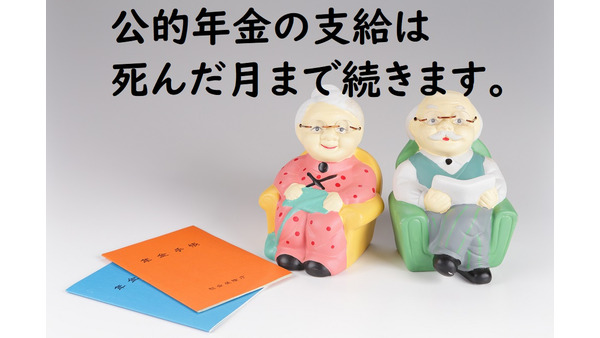
公的年金の支給は死んだ月まで続きます 公的年金は、ひとたび支給が始まると例外的なケースを除いて死ぬまでもらえます。 年金は基本的に月単位で支給されますから正確に言えば、「死んだ月まで支給される」ことになります。 最後の年

「毎年110万までの贈与は非課税」 ということをご存知の方も多くいらっしゃると思います。 筆者は銀行員でしたが、実際にこの非課税枠を利用して毎年贈与をされている方も多く、年末年始は特に、贈与のための振込手続きで来店される
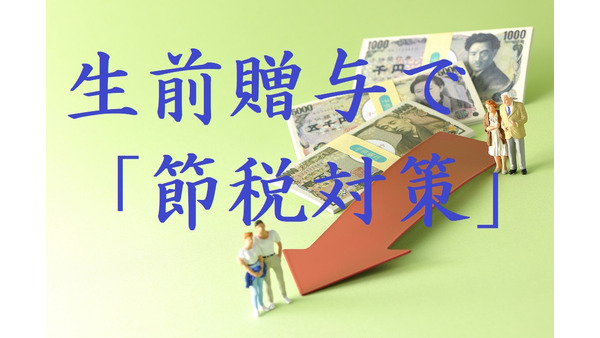
時がきたら誰もが必ず直面する「相続」。 ある一定の額に達しないと、相続税とは無縁であるものの、2015年に行われた相続税の基礎控除額が引き下げられたことで、その対象者は一気に増えることになりました。 さらに40年ぶりに相

特別寄与料とは 今までも、「寄与分」という考えはありました。 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者が
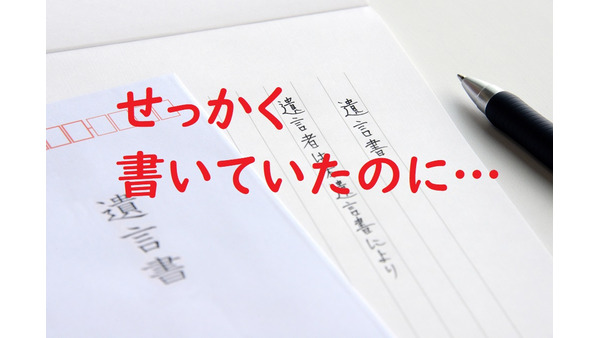
先日、相続ファシリテーター協会の研修に参加してきました。 この協会は相続のあらゆる問題を少しでも解決すべく弁護士や税理士など士業の方やFPと協力をして「生前対策」を推進しています。 現在の相続問題について、現状やその対策

お盆が過ぎてから2019年(平成31年)度の税制改正に向けて、各省庁が要望を出していますが、そのうちの1つとして、個人事業主の事業承継を税制優遇しようという案があります。 事業承継に関しては、法人経営者に対しては事業承継
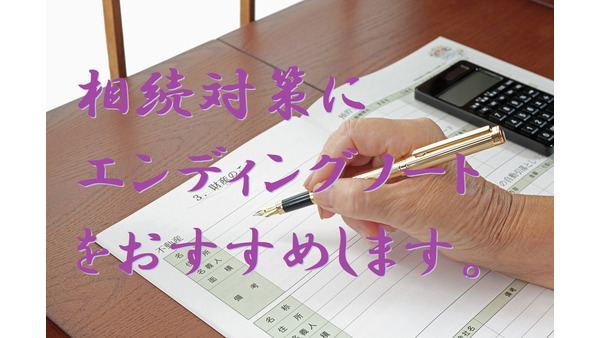
日本は少子高齢化、核家族化が進んでいます。 ご実家を離れて移り住み、その後、ご実家には盆と正月くらいしか帰らない、という方も少なくないでしょう。 親と離れて暮らす人は増えています。 なかなか親子でゆっくり話をする機会は少

Q:「私と姉は今年の3月に父から現金を200万円ずつの贈与を受けましたが、父は5か月後の8月に死亡しました。 父の遺産は母と姉が相続することになり、私は相続を放棄しました。 この場合、私は相続税、贈与税どちらの申告をすべ

亡くなった人の預貯金は引き出せない 愛する家族が亡くなって悲しむもつかの間、まず心配になるのは「生活」です。 これまで、妻や夫、親や祖父母といった生活の大黒柱が亡くなった場合、亡くなった人の預貯金は一切引き出せませんでし

相続が関わるトラブルは年々増加しています。 家庭裁判所への相続関係の相談件数は10年前からおよそ2倍に増加しており、「相続」が「争続」となっているケースも少なくありません。 そうならないためにも、今からできる対策をしてお
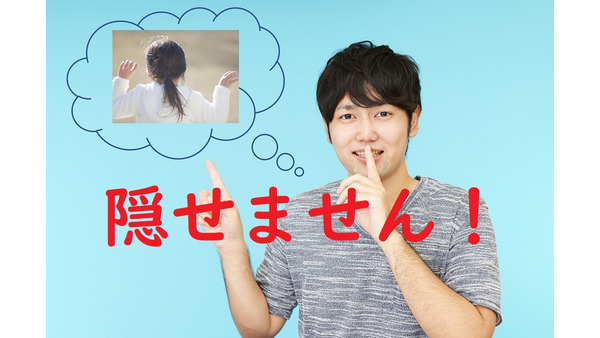
何故、出生から死亡までの戸籍が必要か 配偶者の確認は現在の戸籍謄本(故人)を取れば判明します。 相続人になれるのは、相続発生時の配偶者のみだからです。 相続人である子供が何人いるのかは、現在の戸籍のみでは分からないのです

株を相続しても、持ち続ける意味がないと考えるのであれば、空き家になってしまう不動産のように売却してしまおうとなるはずです。 金融・証券税制は税制の専門家でも理解しづらいところはあります。 まして普段株式投資をやったことの
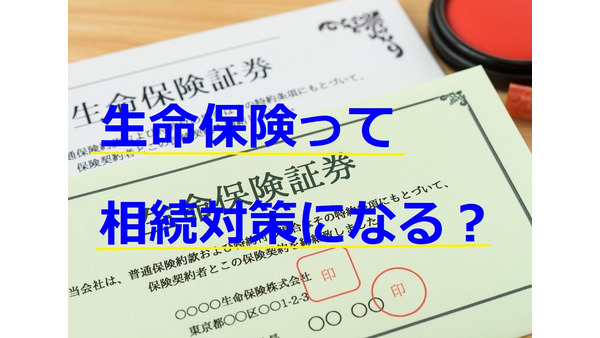
2015年以降、相続税の課税対象になる世帯が増えてから、 「生命保険は相続対策になりますよ。」 というキャッチコピーをよく聞くようになりました。 「そうなんだ、じゃあ入ろうかな」と思う人もいるかと思いますが、なぜ相続対策

最近、よく空き家問題が新聞、テレビで話題です。 ・そもそも「空き家」の何が問題で、何故、空き家が多くなったのか ・相続の実務家として相続後の自宅、農地をどうするのか といった相談を多く受けてきて、見えてきたものがあります

8月はお盆の季節です。 すでにご実家に戻った方、あるいはこれから帰省する方、さまざまだと思います。 中には仕事や他の用事で帰省できず、親御さんと電話で話すだけの方もいるかもしれません。 こんなふうにして実家と接点を持つ時