※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
注目記事
物に囲まれて生きている私たちは、死んだときにとても多くの物を残していくことになります。 しかしこのような「故人の思いが詰まった荷物」というのは、遺された家族にとってはなかなか処遇に困るものでもあります。 そのため現在では
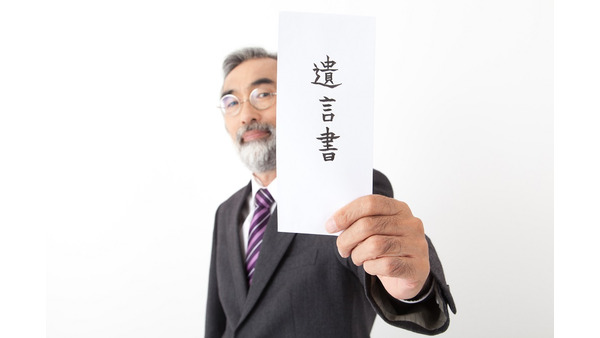
「夫が亡くなって1年経つが、この預金(郵貯)が下ろせない」 と婦人は相談に見えました。相続預金の解約は大変です。 相続預金の手続きの進め方 1. 死亡の事実が分かる戸籍 生きていれば、夫人が代理人で手続きすればよい。死亡

日本の現状と将来 最近、相続の事で遺言書だけでなく民事(家族)信託という言葉を聞く機会が増えて来ました。 要介護(要支援)認定者数 65~74歳…72万人 75歳以上…497万人 合計…約584万人 参照:平成25年度「

凍結解除の手続き 相続が発生すると、亡くなられた方の銀行口座は凍結させられてしまい、お金を引き出すことが出来なくなります。 この状態を解決するためには凍結解除の手続きを行わなくてはなりません。 この時にどのような書類が必

近年、相次いで子や孫にまとまった資金を非課税で贈与できる制度が制定されてきました。 子や孫への生前贈与は、上手く利用すれば非常に有効な相続対策となります。今回は、その中でも2015年に制定された「結婚・子育て資金の非課税

Q:母が一人暮らしをしていた家を昨年相続しましたが、私は別の場所に自宅をもっていますので、この相続した家はずっと空き家になっています。今のうちに売却するとかなりの節税になると聞きましたが、これはどういうことでしょうか?

相続税対策が「相続から贈与へ」という流れに変わっている中、さまざまな生前贈与制度に注目が集まっております。 そのさまざまな生前贈与制度のなかの「暦年贈与」を活用したサービス(商品)である『暦年贈与信託』について今回はお話

高齢者のパソコン・インターネット利用率が年々上昇しており、本人が亡くなったときに、PCのハードディスクや各種記録メディア、金融取引で必要なログインパスワードの管理、さらにはクラウド上に残された「デジタル遺品」をめぐってト

住宅の取得に際し、両親や祖父母から資金の贈与を受けるということは珍しくありません。 人生の中で最も大きな買い物であり、資金計画を考える上で非常にありがたいものです。 この住宅取得のための資金の贈与については、贈与税の非課

Q:被相続人の土地の上にある家屋に被相続人や親族などが住んでいた場合、小規模宅地等の特例の適用を受ける事が出来ると思いますが、毎月の家賃の受け取りがあった場合も適用されるのでしょうか? 解説 被相続人の宅地の上に住んでい

「自宅から遠い所に墓があって、思うように供養ができない」 「後継者がいない」 「子どもに迷惑をかけたくない」 等と言った理由で、実家の墓じまいをし、近くのお墓等に移す「改葬」を希望している方も増えているようです。 遺骨を

「相続大増税」 「相続税は、お金持ちの問題だけではなくなった…」というのが、平成27年以降のお話ですが 「相続税をどの程度、納税しなけれらばならないのか分からず、冷や冷やしている…」 という相談が増えています。 中には、

(1) 相続税の還付についての関心が高まっている 平成27年より相続税法が改正され、基礎控除額の引下げにより相続税申告対象者が大幅に増加していると言われています。 これに関連して、「相続税の還付」の関心が高まっています。

最近、独身のまま高齢になって亡くなる方が増えている。 結婚しない男女、しても離婚してしまう男女が増えていたり、少子高齢化が加速していることから、いずれこんな時代が来ることは分かっていたことではある。 しかし、納得して独身

この4月(平成28年4月)から、一人住まいの親が亡くなって相続人が空き家になった実家を売却したとき、一定の要件を満たした場合に適用できる優遇税制 「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、空き家特例) が施行されて

相続実務をやってきて分かってきたことがあります。まず相続は大きく4つのパターンがあります。 相続のパターン 1. きょうだい間の相続 きょうだい同士は比較をするものです。 分割内容に公平感をもたせることが大切です。 2.

相続税を少なくするうまい方法と称して、次のような話を聞きます。 その内容について検証してみます。 「相続財産は、現預金で持っていると相続税が高くなるので損」 この考えは、相続財産の評価の仕組みのことを言っているものと思わ

借金は、相続対策として、有効なのか…? 毎月行っている相続相談会で、必ず質問を受けるのが、こちらの質問。 「借金」の2つの性質 「借金」については、2つの性質があります。 1. 「被相続人が借金をする」 「被相続人(つま

なぜ? 10人に7人も「納め過ぎ」になってしまうのか? 相続税は自己申告納税制度と言って複雑な『土地評価』という作業を自ら行わなければならない。 納税者自らが申告してきた内容が正しいという前提 → 税務署側からは教えてく

まず、前提として保険料負担者は被保険者と同一であったとします。 被保険者が生存中に受け取る入院・手術・通院給付金(以下、給付金)につきましては、給付金受取人が誰であっても所得税については非課税となります。 これは所得税法

私の知人が今トラブルを抱えている問題をご紹介します。 これからもよく起こる問題なので参考になると思います。 前提:夫、妻の二人暮らしであった。子供なし。 父母・兄弟姉妹はすべて亡くなっているが代襲相続人がいる。 公正証書

相続対策の基本 相続対策は、大きく分けて 1. 争族対策 2. 納税資金対策 3. 節税対策 の3つがあります。 1. 争族対策 親族が遺産をめぐって争うことなく円満に遺産分割が進むようにするための対策で、まさに相続を争

二次相続とは 最近、「二次相続を考えた相続対策」なんてことが雑誌、セミナー等でよく言われます。 でも、それはあくまで子供目線で考えた対策であることに気づいていますか? 親のどちらかが亡くなり、残された母(または父)と子供

ここ最近、人生を一人で過ごす「おひとりさま」と呼ばれる人たちが増えています。またそれに伴って、「おひとりさま」の将来の相続についても注目されつつあります。 一般的に「遺産相続」といえば、親から子へ、子から孫へという下の世

Q:相続の開始があった場合、相続財産は相続人に継承されますが、相続人の有無が不明なときは、その財産はどうなるのでしょうか? また、その場合の手続きはどのようにおこなわれるのでしょうか? 解説 相続人の有無が不明な場合の手

はじめに 月に数回、マネーセミナーを実施して早いもので2年が経過しました。 これまで数多くの方にご参加いただき、お金について一緒に考える機会が得られたことをFPとして嬉しく思っております。 参加者の方は20代~50代まで

後継ぎのいないお墓 最近では、お墓を継承する後継ぎがいない、遠方にいるため墓地の管理が満足にできないなどの理由で、『墓じまい』する家が増えてきています。 墓じまいとは、その名の通りお墓を撤去して更地にしてしまうことです。

葬儀費用を安くしたいけれど、お式の質は悪くしたくない 実際の見積りの際には、どうしてもそういう見栄が働くため、祭壇の花を増やしたり、壺や棺のグレードアップをする人が多く、予定よりも葬儀費用が高くなる傾向にあります。 葬儀

元葬儀司会者の私が経験した、身内の葬儀体験談3回目です。 (今までの記事 第1回目、第2回目) 全3回の仏式葬儀はそれぞれ、24万円、61万円、113万円の費用がかかりました。 同県の親族の葬儀なのに、どうしてこのような

民法(相続法)の改正検討項目 婚外子の法定相続分について民法が改正されたのは記憶に新しいところです。旧態依然としていた民法にメスが入ったのに伴い、現在、民法上の相続ルールの見直し作業が法務省により進められています。 改正

先日、「マネーの達人」読者から法人を活用した相続対策のお問い合わせがありました。 節税として法人を活用するというと、一般的には収益分散による所得税対策を思い浮かべる方も多いと思いますが、ここではそれだけでなく、将来の相続

元葬儀司会者の私が経験した、身内の葬儀体験談2回目です。(第1回目はこちら) 全3回の仏式葬儀はそれぞれ、28万円、61万円、113万円の費用がかかりました。 同県の親族の葬儀なのに、どうしてこのような金額の開きが生まれ

私は20代のころ、某大手葬儀社で葬儀司会をしていました。そして、自分の身内の葬儀を3回経験しています。 葬儀費用に相場はあるのか? 葬儀社に勤めていたころから、葬儀費用についてよく質問されます。みなさん、身内の葬儀にどの

都心部で大人気のタワーマンション。一度好立地なロケーションに建設されれば即完売といったように凄まじい人気があります。 人気の理由としては、場所・景観によるものということもありますが、その他にも立地が良ければもし住むところ

平成27年の相続税法の改正により相続税の対象者が大幅に増加し、将来の相続に向けて様々な相続対策を考えている方も多いと思います。 そんな相続対策の中でも単純ですが有効な手段のひとつとして、生前の「贈与」という方法があります

先日、年始休暇で帰省していた高校時代の先輩から相談を受けました。 昨年の12月に定年退職をして退職金(2000万円)を貰ったけれど、何かいい活用法を相続も含めてアドバイスをして欲しいとの事です。条件は、手軽さと安全で換金