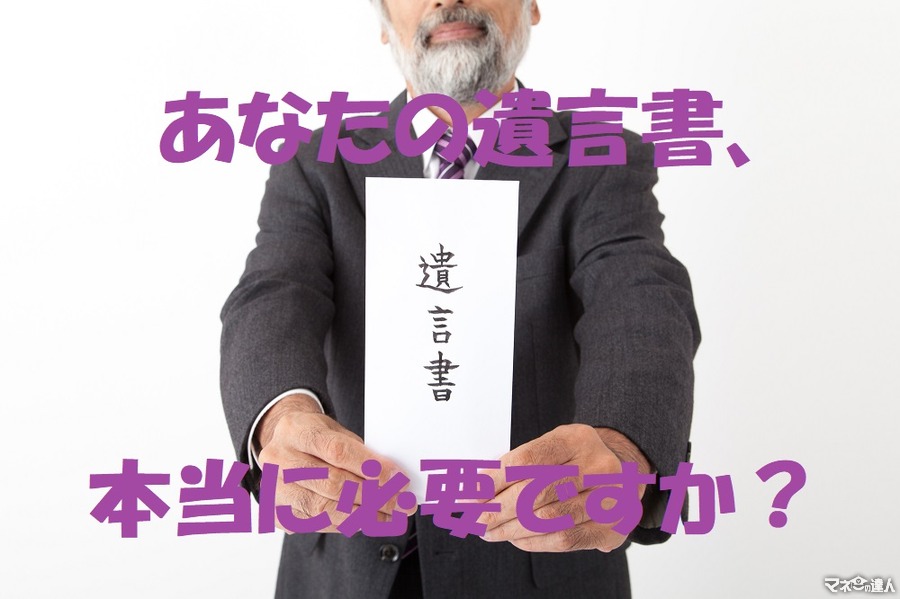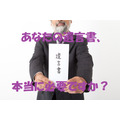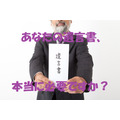目次
法改正で自筆遺言の作成が手軽になり、争族が増加する?
自筆遺言の場合、相続人が相続発生後、家庭裁判所に検認の手続きをしないと名義変更ができませんでした。
法改正で遺言書の保管を法務局でされるようになり、検認が不要になります。
手軽になった分、「遺言書を作らないでよい方」までが作成してしまい、ひいては争族の原因とならないか、実務経験者としては心配しています。
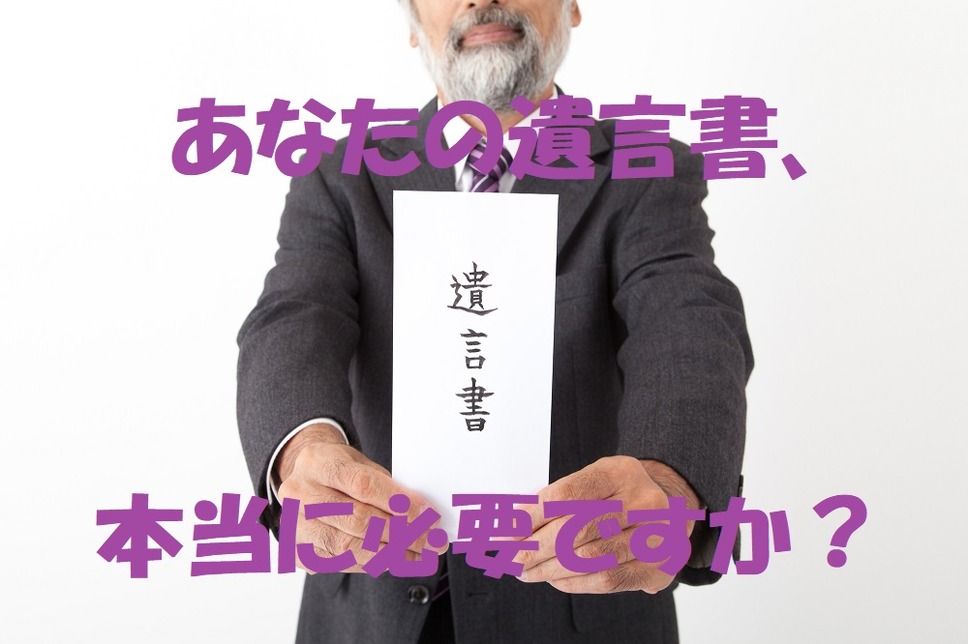
遺言書作成で「心に傷」が
とは現実にはいかないことが多いのです。
母が亡くなり、相続人は長女(姉)と長男(弟)でした。
遺言書は、公正証書遺言にて作成していました。
弟に2/3で姉に1/3の内容でした。
姉の遺留分は1/4ですので、後日、遺留分減殺請求されることもありません。
故人は、アパートを数棟所有しており、そのための銀行借入もありました。
姉はアパート1棟、弟は2棟でした。
各々の借入残高も違います。
ですが遺言書には
となっていました。
これに対し、
と姉は言います。
債権者の銀行も同じ意見です。表面上の理由は。
真因は…
真因は「弟より自分が少ない遺言書を母が書いたことを姉は許せなかった」のです。
姉も弟も生活は安定しており、お金に困っているわけではありません。
問題は、幼少の時から「弟の方が親に可愛がられた」という姉の想いでした。
遺言書をみて、「やはり親は自分より弟の方が可愛がっている」と確信したようです。
姉は金額の大小ではなく、あくまで弟と自分との比較が問題でした。
夜を徹して姉と話し合う
相談は弟からでしたが、この問題を解決するのにはまず、姉の話をじっくり聞くことです。

姉曰く、
成績も弟より良く、生活面でも困らせませんでした。
弟は、私立で学費も多くかかっていますが、私は公立で金銭面でも親に迷惑をかけていませんでした。
ところが母親は、私の相続分を少なくする遺言書をなぜか書いたのです。
もし母親が遺言を書いていなければ、弟には法定割合より譲ったと思います。
なぜ母は、頑張った私を低く評価したのか、そこが悔しい。」
といいます。
母は遺言書で、どうしてこの遺言書を書いたのか理由を書いていません。
そこで当方は、
とお話ししました。
遺言書はあっても分割協議書を作成する
遺言書があっても、相続人全員の合意をとり分割協議書による相続手続きとなることはよくあります。
ですが、遺言書がない時以上に気を使います。
結局、法的には問題のない遺言書でしたが、弟さんは分割協議をすることに応じました。
法定割合では分割協議はまとまったのですが、残ったのは、姉の「心の傷」です。
その他の財産・葬儀費用の記載も必要
遺言書に記載のない財産も、やはり相続人全員の合意が必要です。
等の記載が必要です。
ある相談者さんの場合。
やはり遺言書を作成されていましたが、葬儀費用のことは書かれていません。
実家を守っていた長男が少ない遺言に腹を立て、葬儀代金は多く相続した人に払うよう争ったこともあります。
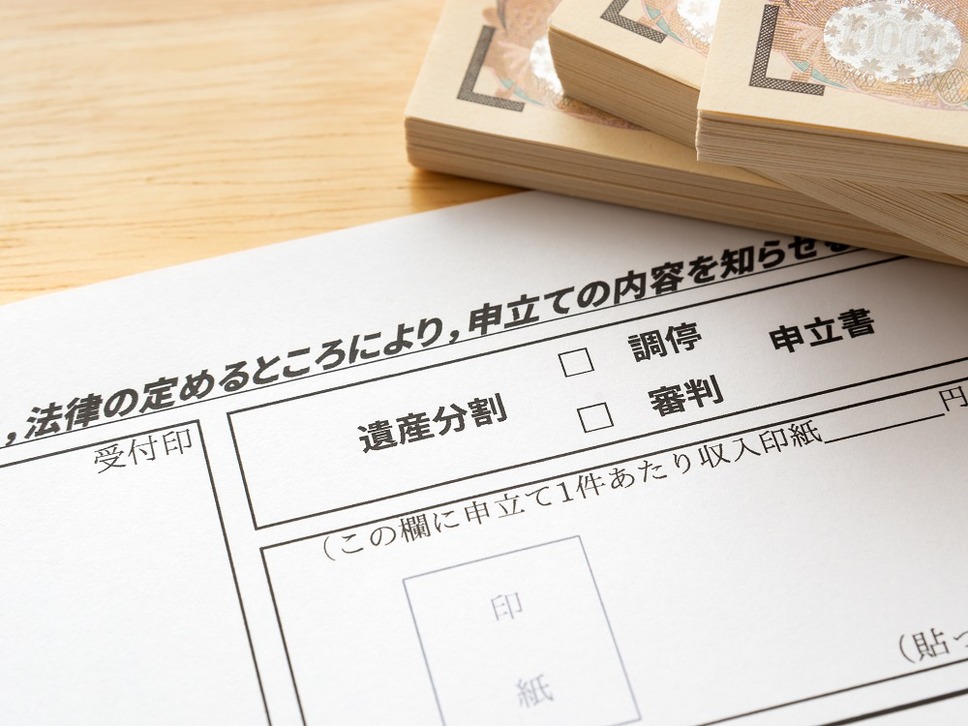
遺言書作成は様々な角度からの検証が必要
どの土地を誰が相続するかで、税金上の相違もあります。
孫に遺贈させることで節税できた税法が、改正で適用できなくなることもあります。
少ない人への配慮をどうするかといった問題もあります。
このように、遺言書は作らない方がよいケースもあります。
やはり、遺言書作成は経験豊富なところでの事前の相談が必要なようです。(執筆者:橋本 玄也)