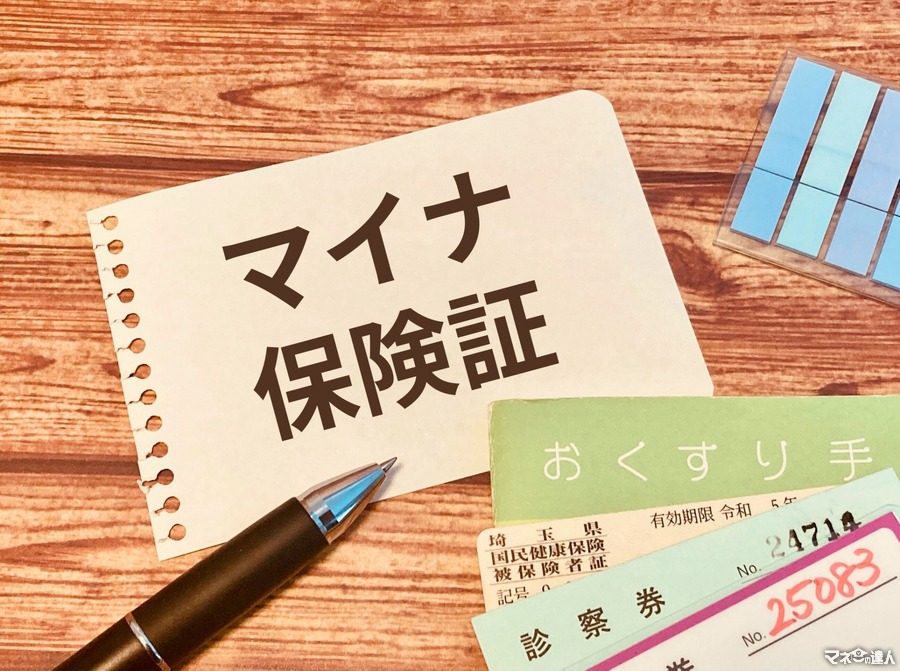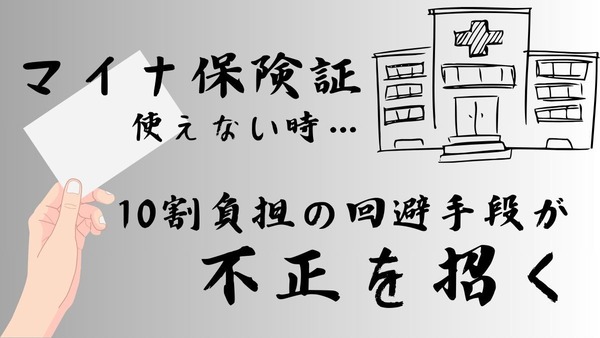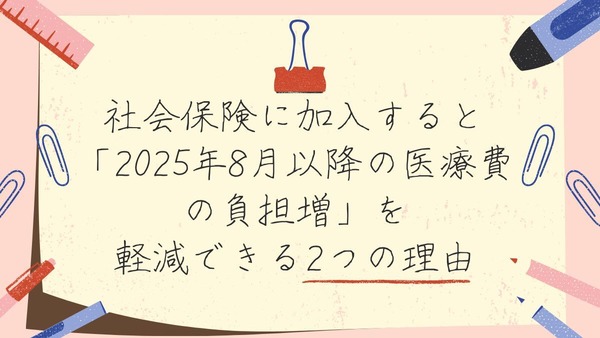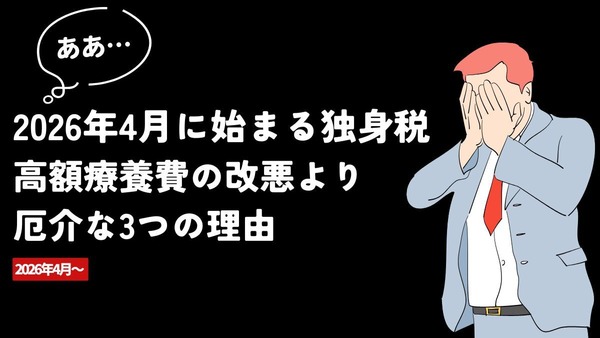マイナ保険証(マイナポータルなどから、健康保険証の利用登録を済ませたマイナンバーカード)に一本化するため、2024年12月2日に健康保険証は廃止になりました。
これ以降はマイナ保険証、または資格確認書(マイナンバーカードを持っていない方などに交付され、健康保険証の代わりになる)の、いずれかを使用する必要があります。
それなのにマイナ保険証の利用率が、次のように廃止日以降も低迷している理由のひとつは、廃止日から最長1年の経過措置期間が終わるまでは健康保険証を使用できるからです。
・2024年12月:25.42%
・2025年1月:25.42%
・2025年2月:26.62%
・2025年3月:27.26%
ただ2025年の中盤から後半になると、経過措置期間が終了する健康保険証が増えるため、マイナ保険証は徐々に普及していくと推測されます。これにブレーキをかけそうなのは、75歳以上に資格確認書を全員交付するという厚生労働省の方針転換ですが、その2つの理由と見通しは次のようになります。
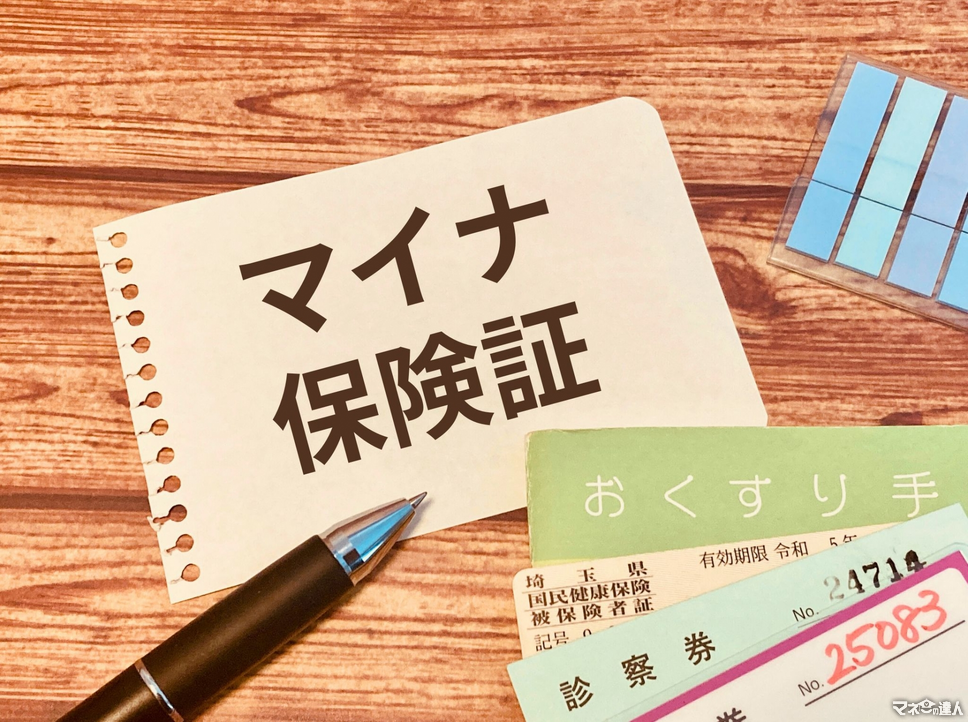
当面の問題になりそうな電子証明書の更新忘れ
マイナンバーカードは住所地の市区町村役場などで受け取りますが、作成しているのは市区町村ではなく、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)という組織です。またマイナンバーカード本体と、裏面のICチップに内蔵された電子証明書(利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書)には、次のような有効期限があります。
マイナンバーカード本体:発行から10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目の誕生日まで)
電子証明書:年齢にかかわらず発行から5回目の誕生日まで
これらの有効期限の2~3か月前くらいに、更新のために必要な書類を送ってくるのもJ-LISです。医療機関の窓口にある顔認証付きカードリーダーに、マイナ保険証を置いて受付する時は、利用者証明用電子証明書を使って本人確認を実施しています。
そのため電子証明の更新を忘れると、有効期限が属する月の月末から3か月後の月末が経過した後に、マイナ保険証を使用できなくなるのです。
マイナンバーカードを取得した方などに、ポイントを付与するマイナポイント事業は2020年~2023年に実施されたので、2025年から電子証明書の有効期限を迎える方が急増します。こういった点から電子証明書の更新忘れは、当面の問題になると推測されるため、J-LISから書類が送られてきたら、早めに中身を確認した方が良いのです。
資格確認書を交付するのは公的医療保険の保険者
健康保険証と資格確認書は両者とも、次のような保険者(公的医療保険の保険料を徴収したり、保険給付を支給したりする組織)が交付します。
主な加入者 | 保険者(運営主体) | 備考 | |
|---|---|---|---|
健康保険(協会けんぽ・組合健保) | 会社員とその親族(中小企業・大企業を問わず) | 協会けんぽ:全国健康保険協会 | 勤務先によって協会けんぽか組合健保かが分かれる |
国民健康保険 | 自営業者・フリーランス・無職の人とその親族 | 自治体(市区町村・都道府県) | 業種によっては国保組合が運営 |
後期高齢者医療制度 | 75歳以上の人 | 各都道府県の広域連合 | 申請の受付などは市区町村役場 |
以上のようになりますが、資格確認書の有効期限は5年以内の期間で各保険者が設定するため、マイナ保険証のように一律ではないのです。
健康保険証の経過措置期間が終わる日も保険者ごとに違いがあり、一律ではないのですが、その目安は次のようになります。
・健康保険:2025年12月1日
・国民健康保険:2025年7月末~11月末
・後期高齢者医療:2025年7月末
また国民健康保険は健康保険証に記載されている有効期限が、経過措置期間の終わる日という場合が多いのです。なお各保険者は電子証明書などの更新が済んでいるのかを、定期的にオンラインで確認するため、更新を忘れた方には申請しなくても、資格確認書が交付される見込みです。
75歳以上に資格確認書が全員交付される

マイナ保険証を次のような事情で使用できない方には、申請が必要になる場合もありますが、各保険者から資格確認書が交付されます。
・マイナンバーカードを持っていない
・マイナンバーカードを持っていても、健康保険証の利用登録をしていない、または保険者に申請して健康保険証の利用登録を解除した
またマイナ保険証を使用できる場合でも、例えば高齢の方や障害のある方などは、申請すると資格確認書が交付されるため、マイナ保険証と資格確認書を状況によって選択できます。逆に言えば資格確認書の交付を受けないと、これらの方でも経過措置期間が終わった後は、マイナ保険証を使用する必要がありますが、厚生労働省は2025年4月に方針転換しました。
その方針転換とは75歳以上(一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満を含む)に対して、資格確認書を全員交付するというものです。これにより75歳以上であれば、2025年7月末の経過措置期間が終わった後も、資格確認書の有効期限である2026年7月末までは、マイナ保険証を使用しなくても良いのです。
75歳以上に全員交付する2つの理由と見通し
少し古いデータになりますが、2024年9月時点のマイナ保険証の利用率は、全体の平均では13.87%でした。年齢階級別の平均を見てみると、例えば65歳~69歳は19.47%、70歳~74歳は17.54%、75歳以上は12.10%になるため、75歳以上だけは全体の平均を下回っています。
こういった他の年代と比較した時の、マイナ保険証の利用率の低さが、75歳以上に資格確認書を全員交付する1つ目の理由です。また経過措置期間が終わるタイミングで、資格確認書の交付を申請する方が市区町村役場へ押し寄せると、窓口が混乱するというのが、75歳以上に資格確認書を全員交付する2つ目の理由です。
すべての年代でマイナ保険証の利用率を比較してみると、次のように20歳未満の若年層の方が、75歳以上よりも利用率が低いのです。
・0歳~4歳:5.70%
・5歳~9歳:6.41%
・10歳~14歳:6.09%
・15歳~19歳:7.37%
厚生労働省は若年層の利用率が低い理由として、子ども医療費の受給者証とセットで提示することなどを挙げています。ただ先行する一部の自治体では、マイナ保険証と子ども医療費の受給者証の一体化が完了しているため、医療機関によってはマイナ保険証だけで受付ができるのです。
こういった新たな仕組みが普及しても若年層の利用率が改善せず、かつ健康保険証の利用登録の解除が相次いだら、今後は若年層にも資格確認書を全員交付するかもしれません。また75歳以上に資格確認書を全員交付する措置は、1年で終了する予定ですが、75歳以上の利用率が改善しなかったら、今後も継続するかもしれません。