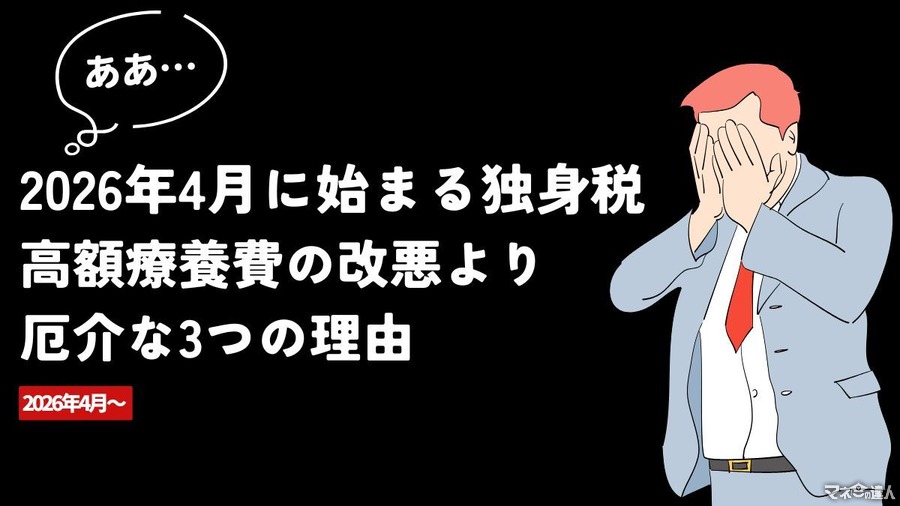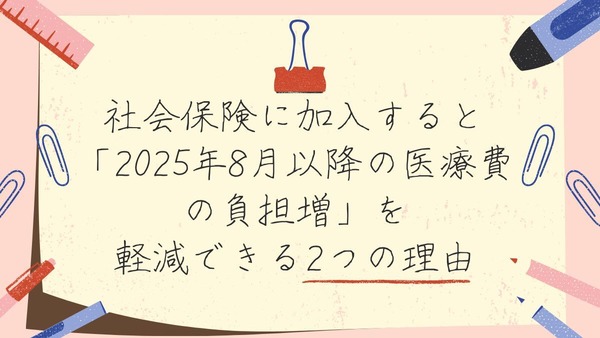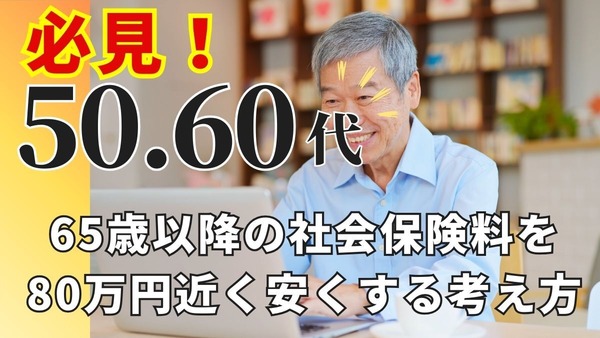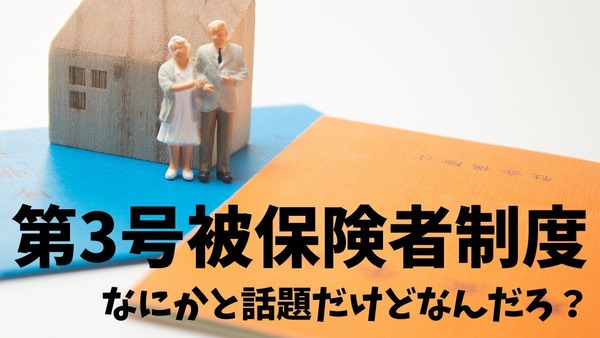公的医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療など)の改正で国民の負担が増えるのは、2つのケースに分かれると思います。
1つ目のケースは医療機関で診療を受けた時の、自己負担の割合などの引き上げであり、2つ目のケースは公的医療保険の保険料の引き上げです。例えば石破内閣が2025年8月からの実施を目指していた、高額療養費の自己負担限度額の引き上げは、1つ目のケースに当たります。
一方で2026年4月に始まる独身税は、公的医療保険の保険料に上乗せして徴収されるため、2つ目のケースに当たります。
前者の自己負担限度額の引き上げは、国民から改悪などと批判されたため、石破内閣は改正を見送りましたが、後者の独身税は予定通りに実施されるようです。このような対照的な結果になった理由のひとつは、独身税に対する国民からの批判の声が、高額療養費の時より弱かったからだと推測します。
しかし個人的には次のような3つの理由で、独身税の方が高額療養費の改悪より厄介だと思うのです。
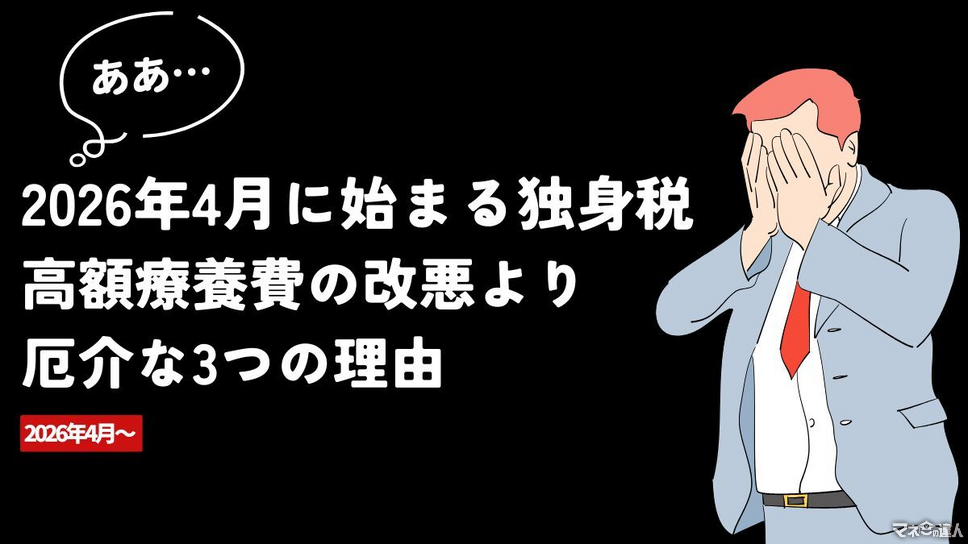
子ども・子育て支援金が独身税と呼ばれる理由
公的医療保険の保険料に上乗せして、2026年4月から徴収が始まる独身税の正式な名称は、子ども・子育て支援金になります。加入する公的医療保険の種類や収入によって徴収額は大きく変わり、月に1,000円を超える方もいます。
ただ全体的な平均は次のような金額になるため、幅広い方から少しずつ徴収するようです。
2026年4月以降:月250円
2027年4月以降:月350円
2028年4月以降:月450円
岸田内閣が2024年6月に子ども・子育て支援金の徴収を決めたのは、子育て世帯への経済的支援(例えば児童手当など)を拡充するためです。こういった経緯で創設された子ども・子育て支援金が、SNSなどで独身税と呼ばれているのは、独身の方は保険料の負担が増えても、直接的な恩恵がないからです。
ただ独身の方だけでなく、例えば子供のいない夫婦や、子供が成長して社会人になった夫婦なども、保険料の負担が増えても直接的な恩恵はないのです。民間の医療保険は給付金を一定期間受け取らなかった時に、支払った保険料の一部が、健康祝い金などとして返還される場合があります。
子ども・子育て支援金の直接的な恩恵がなかった方に、このような保険料の一部を返還する仕組みを作れば、不平等という批判は起こりにくいと思うのです。
厄介な理由1:長期間に渡って影響を受ける
公的医療保険には共通して高額療養費という制度があるため、1か月あたりの医療費の自己負担は、自己負担限度額までに抑えられます。例えば年齢が70歳未満で、年収が約370~770万円の方が入院して、100万円の医療費がかかった時の自己負担限度額は、次のような計算により月8万7,430円です。
8万100円+(医療費の100万円-26万7,000円)×1%(0.01)=8万7,430円
そのため医療機関に30万円(100万円の3割)を支払っている場合、申請によって21万2,570円(30万円-8万7,430円)が、高額療養費として還付されます。
2025年8月に高額療養費が改悪された場合、この例だと自己負担限度額は月8,100円ほど引き上げされる見込みでした。年収が多くなると更に引き上げされますが、治療が終われば高額療養費を利用する機会はなくなるため、引き上げの影響を受けるのは療養の期間中だけです。
一方で独身税は現役世代だけでなく、後期高齢者医療に加入する75歳以上の方も負担するため、社会人になってから亡くなるまでの長期間に渡って影響を受けます。また生涯に負担する独身税を総計すると、自己負担限度額の引き上げ額を上回る可能性があるため、独身税は高額療養費の改悪より厄介だと思うのです。
厄介な理由2:対策を立てるのが難しい
高額療養費の自己負担限度額は、入院した日から1か月を単位にして計算するのではなく、1日から月末を単位にして計算します。そのため月の初めに入院して、その月のうちに退院すると、月末に入院して月をまたいだ場合より、医療費が安くなる可能性があるのです。
また高額療養費の自己負担限度額が引き上げされた場合、一人分の自己負担を合算するだけでは、自己負担限度額を超えないケースが増えます。こういった時には同一世帯内の自己負担を合算して、自己負担限度額を超えた時に、その超えた分が高額療養費として還付される世帯合算の、対象になるのかを調べてみるのです。
高額療養費の改悪については、このような対策を立てられますが、独身税は収入によって徴収額が自動的に決まるため、対策を立てるのが難しいのです。給与から独身税が天引きされる会社員の方は特に、対策を立てるのが難しいため、独身税は高額療養費の改悪より厄介だと思うのです。
厄介な理由3:十分に周知されていない可能性がある
高額療養費の改悪が話題になってから、石破総理が二転三転の末に見送りを決定するまでに、数か月の期間がかかりました。この間に高額療養費の話題は、マスコミやSNSなどで頻繁に取り上げられたので、高額療養費が改悪になりそうなことが、多くの方に周知されたと思います。
一方で独身税はあっさりと徴収が決まり、マスコミやSNSなどで取り上げられる機会は高額療養費より少なかったので、十分に周知されていない可能性があります。
また2024年6月に独身税の徴収が決まりましたが、徴収が始まるのは約2年後の2026年4月になるため、徴収が決まったのを知っていても忘れる可能性があります。そうなると独身税の徴収が始まった時に、給与や年金の手取りが減って心配になる方が多くなるため、独身税は高額療養費の改悪より厄介だと思うのです。
独身税を税源にした国民年金の新たな免除制度

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の、国民年金の保険料の納付が免除される、産前産後期間の免除制度があります。この免除を受けた期間は、2025年度額で月1万7,510円となる国民年金の保険料を納付しなくても、納付したという取り扱いになるため、お得な制度だと思います。
ただ産前産後休業の期間だけでなく、満3歳未満の子を養育するための育児休業の期間も免除の対象になる厚生年金保険と比較すると、国民年金は免除期間が短いのです。そこで独身税を税源にして、父母のいずれであっても、子が1歳になるまで国民年金の保険料の納付が免除される育児期間の免除制度が、2026年10月に開始されます。
制度の詳細は明らかになっていませんが、産前産後期間の免除を受けるには届出が必要になるため、育児期間の免除も同じような届出が必要になると推測します。独身税を財源にした他の制度も、届出や申請が必要になる可能性があるため、子育て世帯の方は新たに始まる制度の種類だけでなく、手続き方法も調べた方が良いのです。