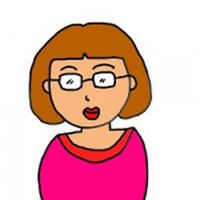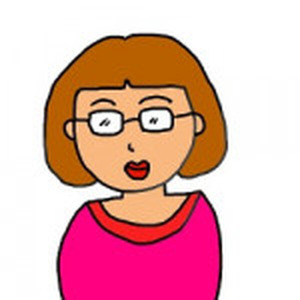私たちの生活に欠かせないスーパーですが、工夫次第でもっとお得に買い物できるとしたら嬉しいですよね。
そこで、スーパーで使える小技のあれこれについて調べてみました。
地道な毎日の努力が、じわじわと家計に効いてきますよ。
目次
1. 生鮮食品の値段が下がるタイミングをつかむ
乾物や缶詰などと違い、日持ちのしない生鮮食品は、スーパー側としてもなんとか売り切ってしまいたい商品。
肉、魚、野菜、果物、そして加工品であるお惣菜も、タイミングをみて買いにいけばお得にゲットできる可能性が高いです。
スーパー側はお客さんの動きに合わせて「最も売りやすいタイミング」を計っているので、調理の必要なものは夕方の比較的早い時間、すぐに食べられるものは夕食時に値下げになるケースが多いです。
私がいつも利用しているスーパーでも、肉や野菜などは夕方4時ぐらいから値段を下げ始めるし、お惣菜コーナーが盛り上がるのは夕方5~6時ぐらい。
狙っていたものにペタリと値下げシールが貼られる瞬間は、大げさじゃなく天にも昇る気持ちです。

2. 特売日の翌日は意外とねらい目
特売日にドカンと仕入れた生鮮食品は、売れ残ると翌日にどんどん値下げされます。
ですから、用事があって特売日に行けなかったとしても、翌日に行けば欲しかった商品を安く買えるかもしれません。
もちろん、売れ残らない場合もあるので、こればかりは運ですが…。
この場合、肉や野菜に比べるとまだ日持ちしやすい野菜や果物は、あまり安くなっていないケースが多いです。
3. 詰め放題で少しでも多くゲットするコツ
スーパーで実施していると、とたんにテンションが上がってしまう催し物といえば「詰め放題」。
決められた大きさのビニール袋に入れられるだけ詰めていくのですが、よく観察していると、人にとってその成果にかなりの差がありますよね。
私は不器用なのでよく途中でビニールを破いてしまったりしていたのですが、コツを知ったおかげで少しずつ詰め放題がうまくなりました。
詰め放題を成功させるために押さえておきたいポイント
・横向きではなく、縦方向に詰めていく
・大きさがバラバラのものは、隙間を細かく埋めながら詰める
・袋の口を留めなくてもいい場合は、放射状にどんどん詰めていく。ほんの少しの隙間も見逃さない!

実際にはこんなに整然と詰めることはできませんが、だいたいこんなイメージになると思います。
袋はあまり伸ばし過ぎると破れてやり直しになってしまうので、厚さに合わせて力の加減を調整してみてください。
4. 魚はまるごと一匹買ったほうが安い

スーパーの商品は、当然のことながら人の手がかかっていればいるほど値段が高くなります。
そのため、魚を買うにしても切り身になっているものは少々割高!
ぜひまるごと1匹買ってさばくことをおすすめします。
……とはいえ、自分で魚をさばくのって、けっこう難しいですよね。
私は何度か挑戦してみたのですが、せっかくの身がグズグズになるのに耐えきれず、今はそうしたサービスをしてくれるスーパーで購入しています。
ネットスーパーでも、注文時に加工サービスを受け付けてくれるところがあるので、ぜひ利用してみてください。
5. 予算を決めて、余分なものは視界に入れないようにする
スーパーに行くと、店内のあちこちに様々な仕掛けがしてありますよね。
特に、「本日限り」なんてポップが付いていると、必要なものじゃないのに「買っておかなきゃ損かも?」と思ってしまいます。
一週間分をまとめ買いするなんて人はまだマシですが、毎日その日の分を買いに行く人は要注意!
店内を一周するうちに、ふと気が付けば買う予定のなかった商品でカゴがてんこ盛り……なんてことにもなりかねません。
スーパーに行く時は、あらかじめ予算と必要なものを決めて置き、それ以外のものはできるだけ視界に入れないようにしましょう。
お腹がすいている時にスーパーに行かないのも、大切なことですね(笑)
6. ポイントサービスを利用する
スーパーによっては、買い物のたびにポイントを付け、それを次回の買い物で現金として使えるサービスを行っているところもあります。
また、近頃では「WAON」や「nanaco」のように、チャージしておいたカードで支払いをして、そのたびにポイントが加算される「電子マネー」を取り入れているところも増えてきました。


私はイトーヨーカドーをよく利用するので「nanacoカード」を持っていますが、レジにかざすだけだから支払いが簡単だし、1ポイントを1円に交換して買い物ができるので、かなり重宝しています。
イトーヨーカドーネットスーパーなら、nanacoポイントも貯まります。
まとめ
しょっちゅう利用するスーパーも、ただなんとなく買い物をするのと、ポイントを押さえて賢く買い物をするのとでは、食費のかかり方に大きく差が出てきます。
スーパーごとにお得なサービスを提供しているところも多いので、情報を集め、できるだけ安く買い物できるように頑張りましょう!(執筆者:畠山 まりこ)