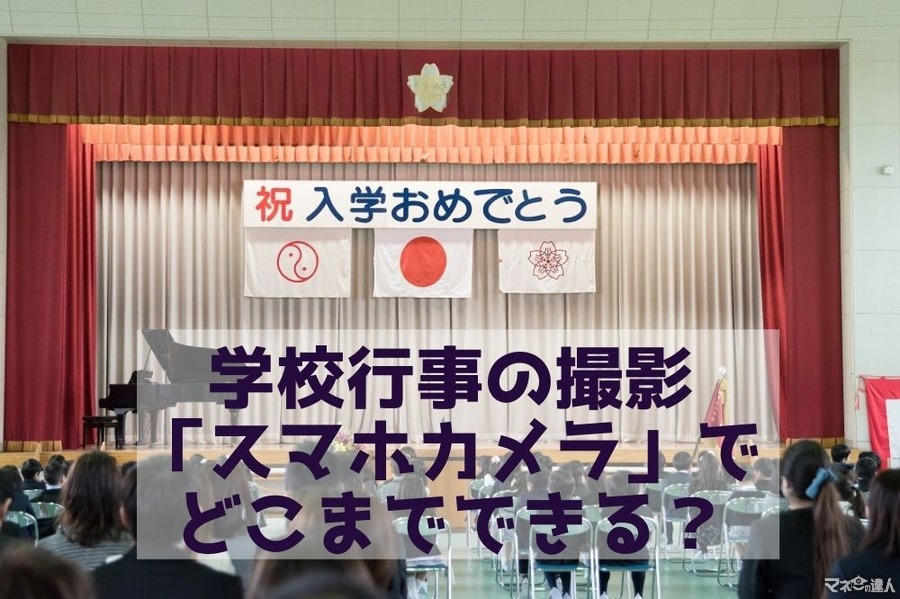子どもが入園、入学する際にはデジカメとビデオカメラを買おうかと考えますよね。
しかし、今はスマホカメラの性能が高いので「わざわざ買わなくてもいいかな」と考える方も多いようです。
そこで、デジカメ、ビデオカメラ、スマホを使ってわが子の写真を撮ってきた筆者が、シーン別にそれぞれのメリットとデメリットを紹介します。
目次
シーン1. 入学式・卒業式などの式典

写真撮影
校庭で撮影する場合には、晴れていればスマホでも明るくてきれいな写真が撮れます。
しかし、体育館で行われる式の最中には、シャッター音の鳴るスマホでは取りにくいかもしれません。
そもそも式の最中は保護者席から移動ができないことが多く、式が行われている間に写真を撮るのは難しいことでしょう。移動できない保護者が席から撮影できるのは、入退場で生徒が移動する時くらいです。
ビデオ撮影
保護者席から撮影するとほとんど後ろ姿しかビデオ撮影できないと思います。
式典の場合、学校によっては業者が写真を撮影して後日販売してくれることがあります。どのイベントで写真撮影が入るのかを確認しておくと良いことでしょう。
そもそも式典自体が保護者が撮影しにくい行事だと言えるかもしれません。
シーン2. 運動会
撮影場所を移動できる運動会は、スマホで撮影する方も多い行事です。しかし、被写体の子どもは常に動いてますので、スマホで静止画を撮るのは難しいことかもしれません。
ちょうどよい距離にいる場合にはスマホでも撮影できますが、走っている子どもをアップで撮りたいのであればスマホのズーム機能では限界があります。
筆者の場合、同じ服装の集団の中からわが子を探して撮影することに毎回苦労しています。少しでも操作が早く、ズームしやすいのはカメラのほうだと言えます。
運動会で活躍するのは一眼レフカメラです。素早く被写体を捉え、スマホではブレてしまうような躍動感のあるシーンもしっかりと撮影できます。
一眼レフで撮った写真を見せてもらうと通常のデジカメやスマホよりもくっきりと写っているので、一眼レフカメラを購入したくなるのですが、やはり価格と大きさに戸惑います。
「もう少し良い写真を撮りたいけが新しいカメラの購入に迷う」という方には、カメラをレンタルするという方法もあります。
購入すれば10万円を超える一眼レフカメラを2泊3日で1万円以下でレンタルできます。

運動会撮影「3つのコツ」
3姉妹をスマホやデジカメで撮影してきて、運動会の撮影には「3つのコツ」があることが分かりました。
コツ1. 子どもの位置を確認しておく
徒競走やダンスなど、どこから入場してどう動くのかを子どもに聞いておくと当日の撮影場所がイメージしやすくなります。
コツ2. 自分の子の前に練習しておく
徒競走の場合、走る子どもをカメラやスマホで追いかけて撮影すると思います。しかし、動いている対象を撮影するのは難しく、いざ子どもの出番になったらレンズが追い付けずにうまく撮影できなかったということもよくあることです。
そこで、自分の子の出番の前に、同じ動きで撮影できるかどうかの試し撮りをすることをおすすめします。カメラで追いかけて撮るのか、固定して撮るのかといった判断もしやすくなります。
コツ3. バッテリーは多めに準備しておく
ビデオもカメラも開会式などの全員参加のプログラムまで入れると、かなり長時間の撮影になります。試し撮りまでするとなるとなおさらです。
わが家のように子どもが複数いる家庭は特にバッテリーは多めに準備しておきましょう。スマホで撮影する方はスマホの予備バッテリーをもっていたほうが安心です。

シーン3. 体育館での発表会
体育館で発表会がある時にはスマホよりもビデオカメラやデジカメが活躍します。
学校側から「シャッターの音を鳴らさないでください」とアナウンスされることがあるからです。スマホの場合には、どうしても音が鳴るので設定で消音にできるカメラやビデオのほうが向いています。
さらにカーテンを閉めて体育館を暗くする場合があると思いますが、暗い部屋ではスマホではうまく取れない可能性が高くなります。しかも撮影場所が遠いとなると「暗さ+ズーム」で子どもの顔がよくわからない写真や動画になってしまいます。
きれいに残したいのであればカメラやデジカメが向いている行事です。
高性能のカメラはレンタルを検討する
スマホについているカメラと通常のカメラではやはり性能が違います。
しかし、カメラも数年で性能が変わるのでいつでも最新のカメラを手にしようとすると家計に悪影響を及ぼしかねません。
どのようなシーンをどのくらいのクオリティで残したいのかによって、スマホとカメラを使い分け、高性能のカメラは購入前にレンタルで使ってみてはいかがでしょうか。(執筆者:田中 よしえ)