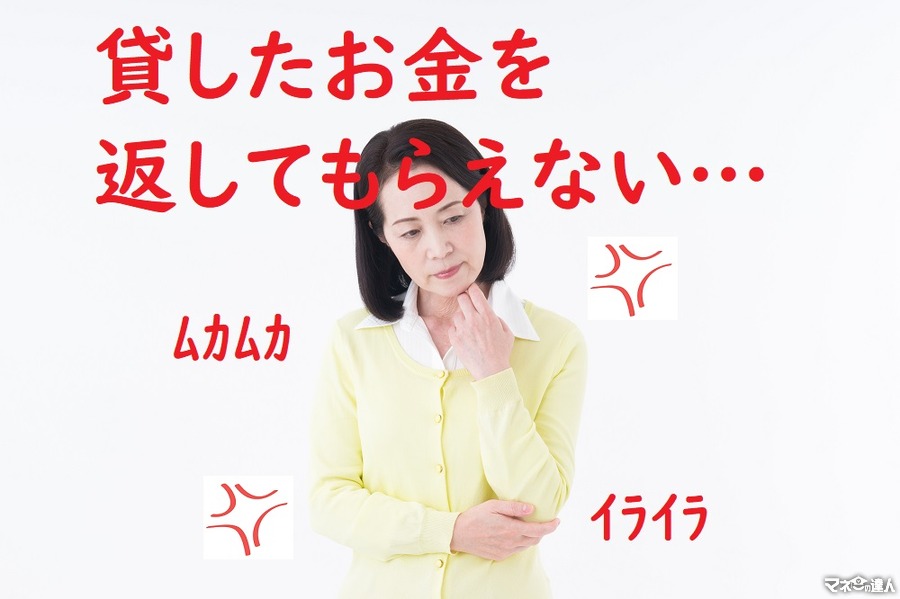「モノやサービスを提供したのにいつまでもお金を支払ってもらえない。」

こういったことで悩むことは誰でも1度はあるかと思います。
同時に、回収したい金額は裁判をするほどではない程度のものであることも。
こんなとき、「少額訴訟」という制度が使えるかもしれません。
目次
少額訴訟とは

少額訴訟とは、60万円以下の請求をする場合に、正式な訴訟よりも簡単な手続きで裁判所を経た法的な請求手続きを行うための制度です。
売掛金や貸付金などのお金を催促しても、なかなか支払ってもらえない場合、「内容証明郵便で請求するといい」と言われます。
相手がそれでびっくりして支払ってくれればよいのですが、公的機関を味方にしているわけではないので、強制力という点では弱いのです。
だからといって、裁判を通じて請求を行うのは、経済的にも時間的にもコストがかかります。
このような状態を改善すべく設けられたのが「少額訴訟制度」です。
次の要件を満たしている場合、少額訴訟を利用することができます。
・支払期限を過ぎて何度も書面やメールで催促したのに支払ってもらえない。
また、具体的には、以下のような場合に活用の余地があるといえるでしょう。
・交通事故の物損について、いつまでも賠償してもらえない場合
・業務委託料金や給料の他、さまざまな契約金を支払ってもらえない場合
少額訴訟の流れ
少額訴訟は次の流れで進んでいきます。
1. 訴状の提出
被告の住所地を管轄する簡易裁判所に作成した訴状を提出します。
2. 期日の連絡
訴状が受理された後、簡易裁判所から審理・判決の期日が通知されます。
3. 事前聴取
審理が1回で済むようにするための事前準備です。
4. 答弁書の受取
相手方の反論が書かれた答弁書が届きます。
5. 法廷での審理
実際に法定で裁判官や書記官などを交えて審理が行われます。
30分~2時間程度です。
6.判決
最後に判決が出ます。

少額訴訟のメリット
少額訴訟には次のようなメリットがあります。
・法律の知識がなくても訴状などを簡単に作成できる。
・簡易裁判所ならば、裁判官や書記官にアドバイスしてもらえる。
・手続き費用が安い。(印紙代、郵便切手代など)
・時間がかからない。
少額訴訟のデメリット
その一方、少額訴訟にもデメリットがあります。
主に次のような点です。
・請求先が「通常訴訟への移行を希望します」といったら、通常訴訟で手続きをしなくてはならない。
つまり、時間的にも経済的にも予想以上にコストがかかることになる。
・相手の住所や差押のための口座などを自ら知っていなくてはならない。
お金のトラブルは感情のエネルギーを消耗します。
そんなときは、少額訴訟を検討してみてもよいかもしれません。(執筆者:鈴木 まゆ子)