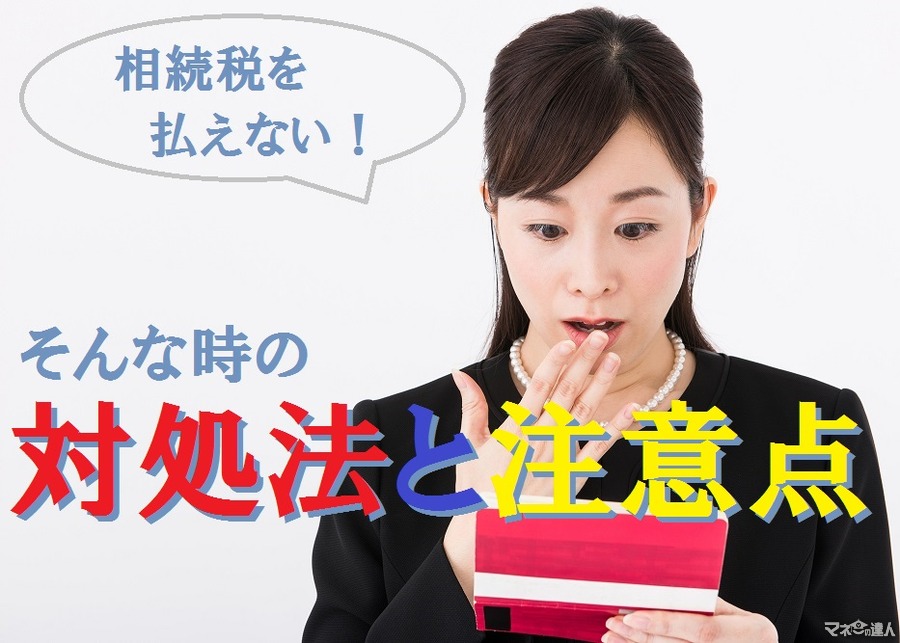2015年の相続税法の改正により、相続税を納付しなくてはならない世帯が増えました。
「ウチには関係ない」と思っていた世帯でも、ふたを開けてみたら相続税を納めなくてはならないケースもあるのです。
けれど、手元に現金がなくて納期限までに払えそうにない。
そんなときはどうしたらいいのでしょうか。
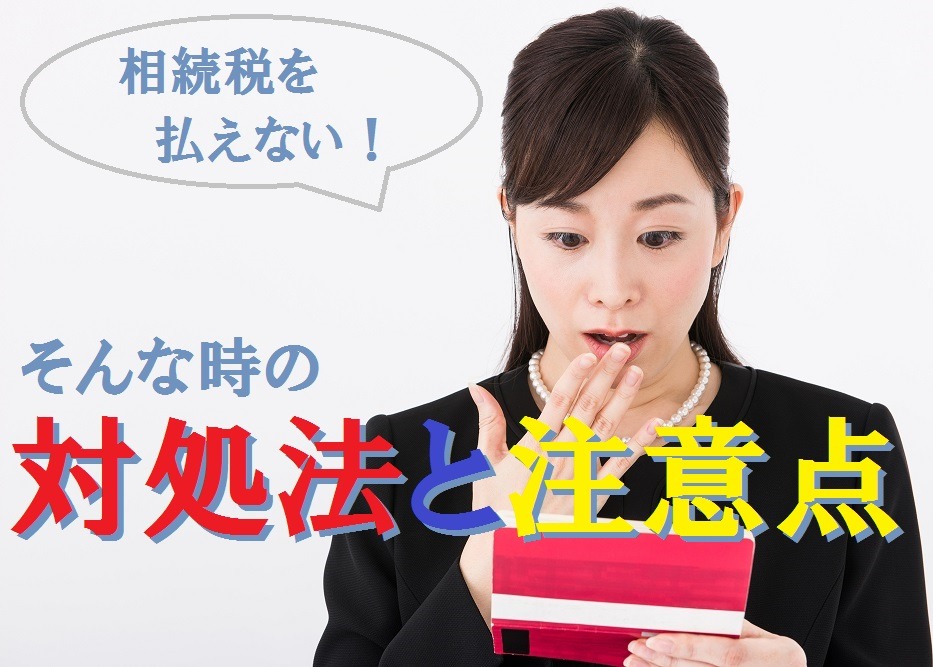
目次
相続税の納付で困るのはこんなケース
相続税の納付で困ることが多いのは「現預金が少ないけれどその他の資産が多い」ケースです。
具体的には、有価証券や不動産が相続財産の大半になっているケースになります。
「自宅だけだから大丈夫」と思っていても、その自宅が路線価の高いエリアにある場合、高額の相続税が課される可能性があります。
相続税の納期限は10か月以内で現金一括納付が基本
けれど、相続税は待ったなし。
相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税を行わなくてはなりません。
また、相続税の金額がいくらであっても、その納付については現金で一括納付が基本です。
税金が多額になる場合、一度に用意できないことも珍しくありません。
では、多額の相続税を一度に納められない場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
実は、一定の要件を満たした場合、「現金で一括」でなくても納める方法がいくつかあります。
その一つが「延納」という制度です。

基本通りが難しい時に知っておきたい制度「延納」とは
延納とは、現金で一括で払えない場合、分割によって納税することができる制度です。
延納を行うためには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 相続税額が10万円を超えること
2. 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
3. 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
※ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には、担保を提供する必要はありません。
4. 延納申請にかかる相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
具体的な例をあげるとすると、相続人が被相続人の配偶者と子ども2人の場合なら、正味の相続財産の総額(各相続人の課税価格の合計額)が8,400万円までなら、子どもそれぞれに課される相続税額が100万円以下になるため、担保の提供なしで延納の活用を検討できることになります(実際には利子税も加味したうえでの判断と事前の届出が必要です)。
注意点
ただし、注意点があります。
まず、延納する納税額を元本とした利子税も併せて納付しなくてはなりません。
また、納税額と利子税の合計額が100万円を超えるなら担保の提供が必要になります。
さらに、申請をしてすぐに延納OKになるわけではありません。
税務署側でも審査を行ったうえで承認または却下を行います。
審査期間は延納申請期限(=相続税の納付期限)から3か月以下、担保の状況によっては6か月以下となります。
一度相続が発生すると何かと忙しくなるもの。
活用するならば、早めに検討し準備するようにしましょう。(執筆者:鈴木 まゆ子)