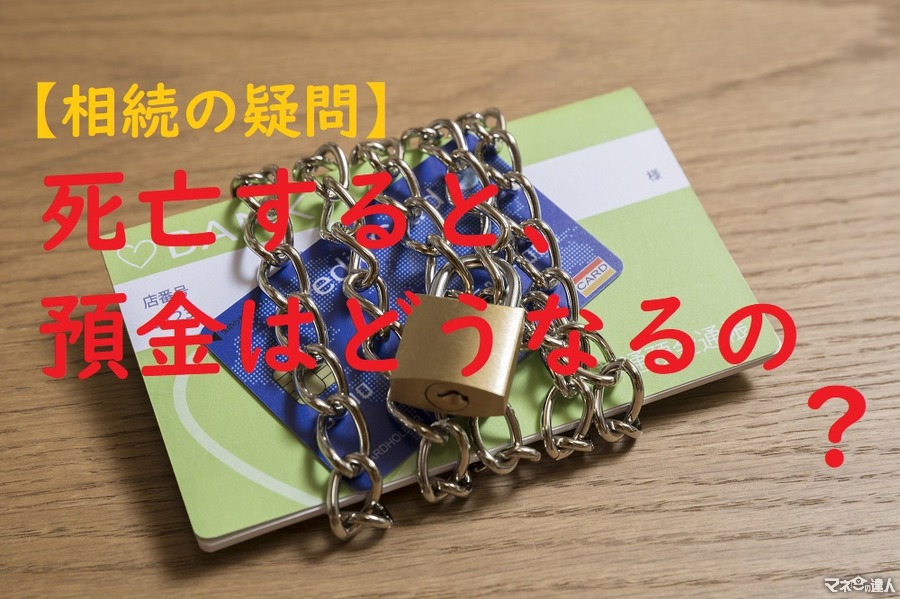銀行と付き合っていくうえで、誰もが避けて通れないのが相続です。
「死んだ人のローンはどうやって返していくの?」
「相続手続きはどうやるの?」
こうした相続の疑問について、銀行員生活30年の経験からお話したいと思います。
ぜひ今回のテーマを参考に、いつか訪れる「その日」の備えとしてください。
第1回 死亡すると、なぜ銀行は預金口座を凍結するの?
第2回 死亡したことを、いつまでに銀行へ伝えればいいの?
第3回 預金が凍結されるとどうなるの? ~預金の出金について
第4回 借入が残っていると、どうなるの? ~住宅ローンの場合
第5回 借入が残っていると、どうなるの? ~アパートローンや事業資金の場合
第6回 いまから準備できることはあるの? ~相続のときに困らないために
目次
死亡すると、なにが起きるの? ~預金の凍結
個人が死亡した場合、役所への死亡届などとはちがい、死亡後何日までに銀行へ届け出をする、といった決まりは特にありません。
家族が、自分たちのタイミングで銀行に伝えれば良いのです。
銀行では、取引している個人が死亡したと連絡を受けると、預金・ローンなど原則全ての取引を一時停止状態にします。
このことを一般的に預金の凍結と呼んでいます。

先ごろ改正された民法の「預貯金の仮払い制度」で、これまでよりも心配の種は減るかもしれません。
しかし、支払いに上限があったり、仮払いされた預貯金は遺産分割された財産だとみなされ、相続税がかかります。
なぜ預金が凍結されてしまうのか?
預金が凍結されてしまう理由は大きく2つあります。
(2) 相続トラブルを防ぐため~銀行はトラブルに巻き込まれたくないから
それぞれの理由について、説明していきましょう。
(1) 相続手続きのために残高を固定させる必要があるから
死亡した人の銀行取引は相続の手続きを踏まないと、解約などができません。
相続手続きには「遺産分割協議書」や「遺言書」といった書類が必要になりますが、こういった書類には必ず預金や借入金の残高が記載されています。
この場合、残高については本人が死亡した日の残高とするのが一般的です。
そのため、死亡したと届出があった日の時点で、残高を固定する必要があります。
たとえば定期預金が満期になり、利息がついて預金残高が増えてしまうと、遺産分割協議書の残高と変わってしまうことになり、手続きが面倒になってしまうためです。
ちなみに、これはローンなどの借入金についても同じです。
残高を固定させるために、毎月返済もできなくなります。
(ただし、これは相続手続きのためなので、延滞にはなりません。また銀行によっては、相続手続きまで、今まで通りの返済を続けていくことができる場合があります。)
(2) 相続トラブルを防ぐため ~銀行はトラブルに巻き込まれたくないから
(1) は手続き上の事務的な理由でしたが、重要なのはこちらの(2) 相続トラブルについてです。
これは銀行ホームページなどには一切載っていない、現場で実際におきている相続トラブルに関係することです。
実はこの部分こそ、銀行が預金などの取引を凍結させる一番重要な理由です。
相続の手続きを踏まないと、解約ができないと上述しました。
それはなぜでしょう?
「死亡した人の預金は家族のもの。引き出しできなくする権利が銀行にあるの?」
これらは一般の人が、相続手続きするときに感じる素朴な疑問です。
しかしながら、実際は夫の預金を妻がおろしてはいけないのです。
引き出しできなくする権利が銀行にあります。
それは「相続人全員の権利を守る」という理由があるためです。
わかりやすくイメージしてもらうために、ひとつのモデルケースで説明していきます。

男性80歳が死亡。
子供は長男と次男 妻には先立たれ、長男家族と同居していた。
次男は独立し、遠く離れた県で暮らしている。
男性は、それなりに預金があり、土地などの不動産も所有していた資産家。
このケースで自分が次男だったら…とイメージしながら読み進めて下さい。
父親が死んだと知らせを受け、葬儀など諸々の手続きも終わってしばらくたった。
兄から電話があり「相続の手続きをしなければならないので来て欲しい」との内容。
帰省し、遺産分割協議書を見せられた。
兄は「遺産分割協議書に書いてある内容に文句が無いなら実印を押してくれ。」
書類を見ると、預金の中身がおかしい。
父の面倒を見てくれたので、財産のほとんどを兄がもらうことには文句がない。
ただ、父が生前「あの銀行の1千万円はおまえにのこす」といっていた預金がない!
兄に問いただすと「俺は知らない」というが、どうも怪しい…
上記した事例は、相続ではよくあるケースです。
まず、父の生前に解約されていたのであれば、父と兄でどういう話しがあったのかなど、相続とは別次元の問題なので、今回のテーマには関係ありません。
ただし、父が死亡したあとに1千万円が解約されていた場合は大問題です。
銀行は相続手続きの時に、相続人全員の同意を確認します。
これは相続人が複数いる場合、相続人一人だけで解約などの手続きをさせてしまうと、他の相続人の権利を守れないからです。
モデルケースでいえば、「死亡した父の預金を弟にはいわずに、兄が勝手に解約して独り占めした」という部分です。
銀行は特定の相続人だけが預金を独り占めしたり、他の相続人に黙って解約したりするのを防ぐため、相続人全員の同意を確認しない限り、相続手続きには応じません。
具体的には、相続手続きの銀行申込書類に、相続人全員が自署・捺印をすることで相続人全員の同意を確認しています。
(申込書類には「同意する」という意味の記載があります。)
モデルケースに戻って、あなたが次男だったらどうしますか?

兄を問いただしたところ、
と言っている。
預金は戻ってきそうにない…。
私なら印鑑など押しません。
納得できなければ最悪、裁判に訴えるかも知れません。
そして銀行へ「兄が勝手に引き出したので取り消せ!」と言いに行くでしょう。

これが、銀行が恐れている
相続トラブルに巻き込まれるということです。
相続人の一人だけから解約の依頼を受けても、モデルケースのように、実は他の相続人に黙ってやっているかも知れません。
そのまま解約してしまった場合、当然他の相続人から銀行が非難されますし、最悪の場合裁判に巻き込まれてしまう可能性もあります。
相続のトラブルはよくあることです。
よほど悪質でなければ、逮捕されたり犯罪になったりすることはありません。
あくまで相続人、家族同士のもめ事です。
ですからなおのこと、銀行はそうしたトラブルに巻き込まれたくないのです。
「相続人全員の同意」
これらは決してタテマエではありませんが、
ともいえるのです。
相続人全員の同意を銀行が確認するためには、
→死亡した人、相続人それぞれ、生まれてから現在までの戸籍全て。
・相続人の本人確認
→免許など写真入りの身分証明と印鑑証明書、住民票。
(銀行は「身分証明」「実印・印鑑証明」「現住所」で本人確認をする。)
・同意の確認
→銀行手続き書類に相続人が自署・捺印する。
(遠く離れた銀行でも、相続人が行かなければならない。銀行員が訪問する場合もある。)
こうした書類や手続きが必要なため、銀行の相続手続きは大変になってしまいます。
銀行によって手続きや書類は違いますが、最近では遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印してあれば、相続人のうち一人だけで手続きできるなど、手続きは簡素化される方向になっています。(執筆者:加藤 隆二)