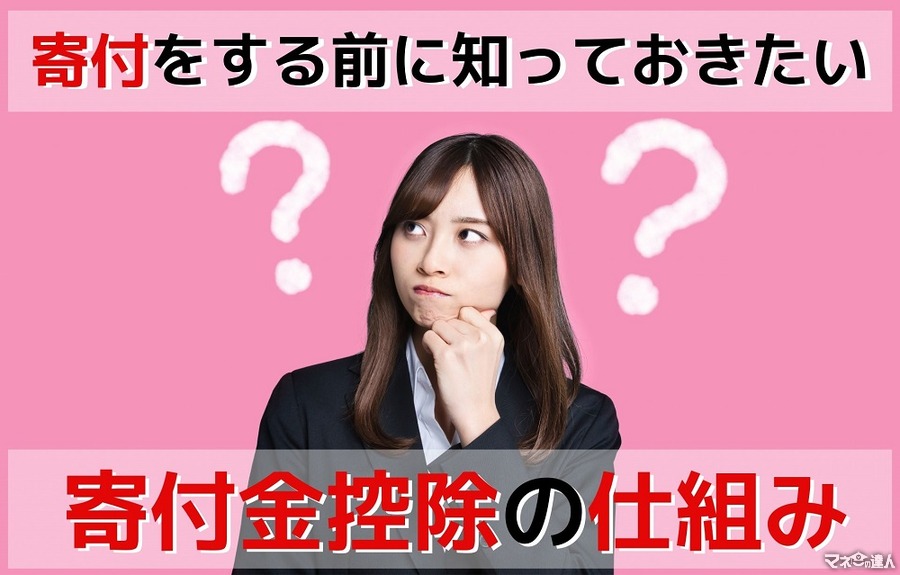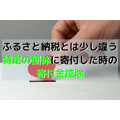新型コロナウイルスの蔓延(まんえん)により、世界が大規模なダメージを受けています。
誰もが未来に不安を抱いてしまう状況ですが、それでも、いま前線で闘う人たちのためにできる支援をしたいと思う方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、寄付した額の一部が戻ってくる「寄付金控除」の仕組みと利用方法について紹介します。
目次
寄付先によって違う「寄付金控除」
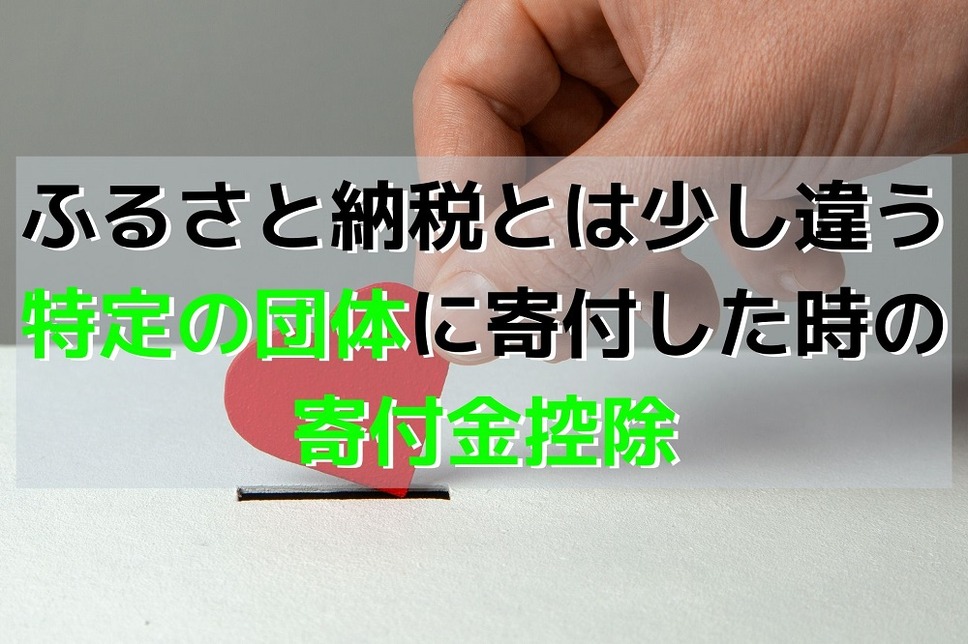
寄付金控除と言えば、今や大人気の制度となったふるさと納税を思い浮かべる方が多いかもしれません。
「寄付金控除」とは、ふるさと納税のような自治体を対象としたものに限らず、認定NPOなど特定の団体に対して寄付を行った際に受けられる税制優遇措置の総称です。
ふるさと納税の場合には実質2,000円の自己負担で返礼品をもらえますが、NPO法人などに寄付をした場合にも同じ自己負担額かというとそうではありません。
ふるさと納税に対して適用される特例控除が一般の寄付金控除にはないのです。
ことになるのです。
所得控除の場合には、
税額控除の場合には、
します。
何がどう違うのか非常に分かりづらいのですが、結論から言うと多くの場合、税額控除の方を選択した方がお得です。
認定NPO法人へ寄付を例に還付金を計算

仮に、年収600万円の人が5万円をある認定NPO法人へ寄付したとして計算してみます。
所得控除を選択した場合
所得控除を選択した場合の所得税の計算方法は、
となるので、この例の場合には、
になります。
寄付をしていない場合だと20.35万円なので、差し引き4,800円が還付されるのです。
5万円寄付して4,800円の還付なので、この場合の自己負担は4万5,200円です。
税額控除を選択した場合
税額控除を選択した場合には、
となるので、この例の場合には、
になります。
5万円寄付して1万9,200円還付されるので、この場合の自己負担額は3万800円です。
所得控除と税額控除のどちらを選ぶかで、1万4,400円もの差がつくことになるのです。
このように、
のです。
今回の例で使用した社会保険料控除についても概算で計算しており、個人の状況によって還付額は異なるので注意が必要です。
また、一部の自治体ではさらに住民税からも最大10%の控除を受けられるので、自分のケースでどのくらい税額が減るのかを知りたい場合にはお住まいの自治体や税務署へ相談することをおすすめします。
寄付金控除の利用方法

寄付金控除はどの団体に寄付しても認められる訳ではなく、寄付金控除の対象として認定された団体である必要があります。
寄付したい団体が対象となっているかどうかはホームページなどで確認できますので、寄付する前によく確認するようにしてください。
また、寄付金控除を受けるためには寄付した団体から発行される領収書を添付して確定申告を行う必要があります。
ふるさと納税のワンストップ特例にあたる制度はなく、年末調整でも申告できないので注意が必要です。
団体によっては、
ので選択する方を間違えないようにしないといけません。
また、寄付金合計の上限は所得金額の40%と定められており、それを超えた部分は控除に算入できないので金額にも気をつける必要があります。
各カード会社の規定に応じたポイント還元が受けられるので、決済にはクレジットカードを使うことをおすすめします。
寄付による新型コロナ関連の支援の例
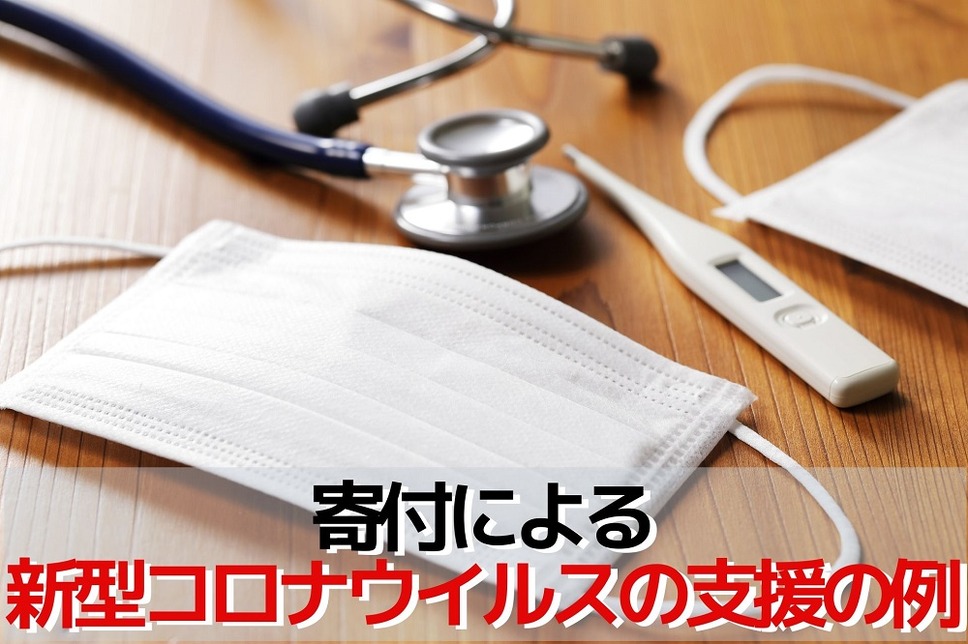
寄付というと大規模な額のイメージがあるかもしれませんが、1,000円単位や、それ以下でも好きな金額だけ寄付できる団体も多くあります。
また、寄付した金額で何ができるか、どういった使い道に充てられるのかといったことも各団体のホームページで確認できます。
新型コロナウイルスと闘っている医療従事者への支援の例として、例えば国境なき医師団では、
・ 5,000円で医療用フェイスシールド3点
・ 1万円で医療用防護ゴーグル6点
を提供できます。
他にも、ひとり親家庭の支援などさまざまな支援団体があるので、使い道に共感できる団体を探してみてください。
寄付でのサポートをする際に気をつけること
感染症の拡大や自然災害などが起こると見えない未来に誰もが不安になってしまいますが、今まさに苦境にある人に何か支援をしたいという場合には寄付をするというのもサポート1つの手段です。
新型コロナウイルスの救済策で一律給付される10万円の一部を寄付に充てるのもよいかもしれません。
寄付する前には寄付金控除の対象かどうかを必ず確認し、領収書をもらい忘れないようにご注意ください。(執筆者:島村 妃奈)