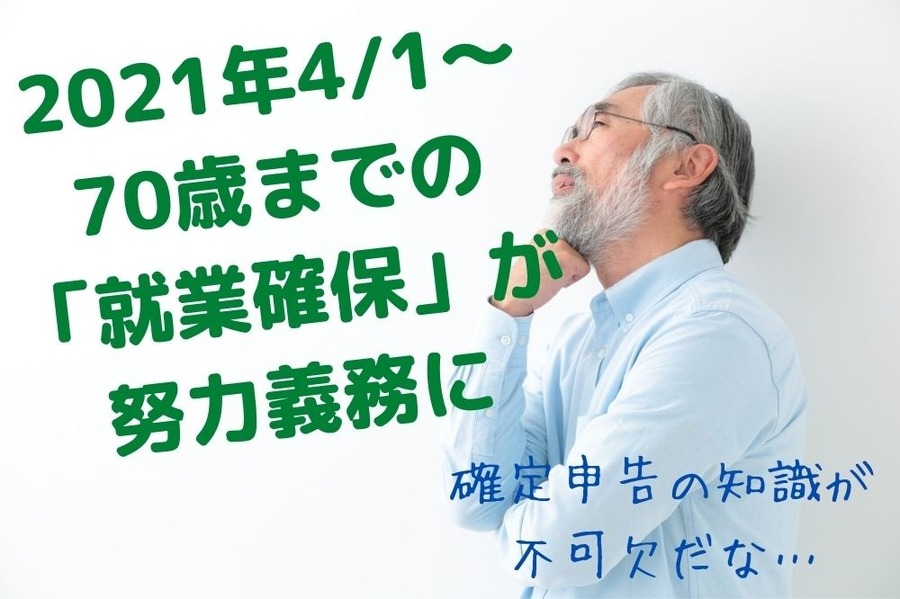原則65歳から支給される老齢年金は、国民年金から支給される「老齢基礎年金」と、厚生年金保険から支給される「老齢厚生年金」の、2種類に分かれているのです。
前者の老齢基礎年金を受給できるのは、公的年金(国民年金、厚生年金保険など)の保険料の納付済期間や、国民年金の保険料の免除期間などを合わせた期間が、原則として10年以上あって、受給資格期間を満たしている場合になります。
一方で後者の老齢厚生年金を受給できるのは、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたうえで、厚生年金保険の保険料の納付済期間が、1か月以上ある場合になります。
現在は60歳だった老齢厚生年金の支給開始を、65歳に引き上げしている最中のため、生年月日によっては老齢基礎年金や老齢厚生年金に加えて、60~64歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
また厚生年金保険に加入していた男性に関する、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、次のように定められているのです。
1953年4月2日から1955年4月1日生まれ:61歳から支給
1955年4月2日から1957年4月1日生まれ:62歳から支給
1957年4月2日から1959年4月1日生まれ:63歳から支給
1959年4月2日から1961年4月1日生まれ:64歳から支給
1961年4月2日以降生まれ:支給されない
ただ特別支給の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたうえで、厚生年金保険の保険料の納付済期間が、1年以上必要になります。
また厚生年金保険に加入していた女性は、5年遅れで引き上げが実施されているため、特別支給の老齢厚生年金を受給できなくなるのは、1966年4月2日以降生まれの方になります。
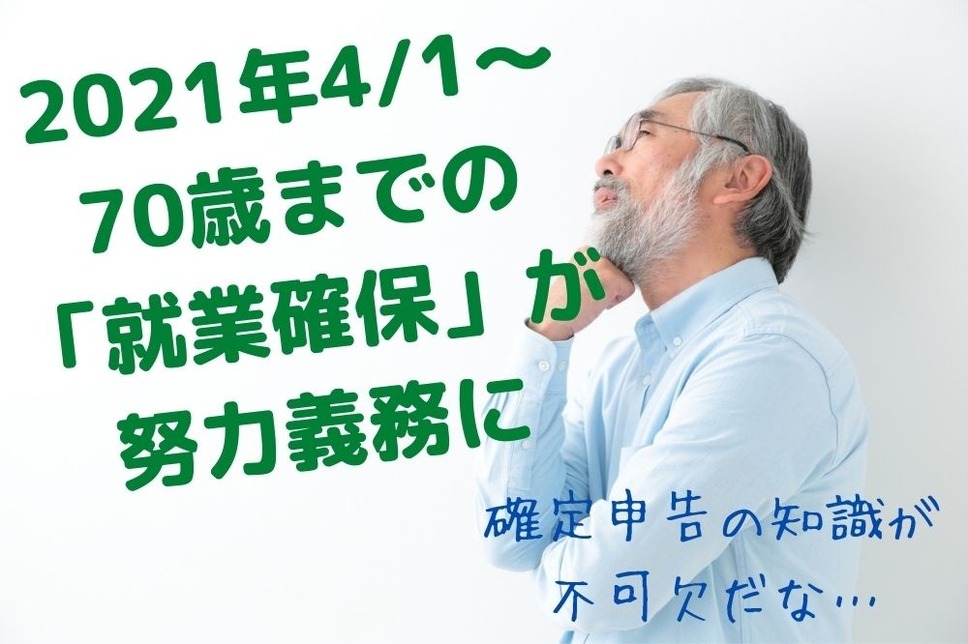
目次
「高年齢者雇用確保措置」は3種類の中から選択できる
特別支給の老齢厚生年金の支給開始は上記のように、数年ごとに引き上げされているため、例えば63歳から支給される方が、60歳で定年を迎えた後に、再就職しなかった場合には、約3年間は収入がなくなります。
これを回避するために政府は、企業の努力義務(努力することが義務づけられているが、違反しても罰則の対象にはならない)であった「高年齢者雇用確保措置」の実施を、企業の義務に変えたのです。
この高年齢者雇用確保措置とは、
「65歳までの継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の導入」
「定年制の廃止」
の、3種類を示しております。
企業はどれを実施するのかを選択できるのですが、大多数の企業は2番目の、継続雇用制度の導入を選択しているのです。
例えば再雇用制度を導入する企業に勤務している方は、最低でも特別支給の老齢厚生年金が支給される年齢に達するまで、希望すれば契約を更新できるのです。
また特別支給の老齢厚生年金の支給開始が引き上げされるごとに、契約を更新できる年齢も引き上げされます。
そのため2025年になって男性の引き上げが完了すると、どの制度を選択している場合でも、希望すれば65歳に達するまで、同じ企業で働けるようになるのです。
2021年4月1日から70歳までの就業確保が努力義務になる
少子高齢化が続く中で、公的年金などを維持していくためには、社会保障の支え手を増やす必要があります。
また会社員などが加入する厚生年金保険は、所定の加入要件を満たしていると、現状では70歳まで加入します。
こういった点から65歳以降も働けるようにする、新たな改正があるのではないかと思っていたら、70歳までの就業確保が2021年4月1日から、企業の努力義務になるようです。
あくまで現状は努力義務ですが、65歳までの雇用確保が当初は努力義務だった点から推測すると、いずれは企業の義務になる可能性があります。
また義務化するタイミングで老齢年金の支給開始を、65歳より後に引き上げするかもしれないので、70歳までの就業確保が企業の努力義務になるのは、けっこう重要なニュースだと思いました。
雇用以外の措置も「高年齢者就業確保措置」に含まれる
今回の改正の特徴としては、65歳まで働ける環境を整備するために義務化された「高年齢者雇用確保措置」ではなく、「高年齢者就業確保措置」の実施が、企業の努力義務になった点です。
つまり70歳までの就業が確保されるなら、雇用に関する措置に加えて、雇用以外の措置も認めるというわけです。
前者の雇用に関する措置としては、
「70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の導入」
「定年制の廃止」
があります。
一方で後者の雇用以外の措置としては、「70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入」があるため、雇われないで個人事業主として働く方が、増えていく可能性があります。
また「事業主が自ら実施する社会貢献事業や、事業主が委託や出資する団体が実施する社会貢献事業に、70歳まで継続して従事できる制度の導入」も、雇用以外の措置に含まれるため、企業内で働くだけではないのです。
このように雇用以外の措置としては、業務委託と社会貢献事業があるのですが、企業がこれらの制度を導入する際には、労働者の過半数を代表する労働組合、または労働者の過半数を代表する者の、同意が必要になります。

給与所得が20万円を超えると確定申告が必要になる
2011年度の税制改正の際に、「年金所得者に係る確定申告不要制度」が創設されたため、次のような2つの要件を満たす年金受給者は、所得税の確定申告をしなくても良いのです。
(2) 公的年金等に係る雑所得以外の所得が、20万円以下である
公的年金以外の収入がある方については、(2) の要件を満たせるか否かが、ポイントになってくると思います。
また(2) の中に記載されている、「公的年金等に係る雑所得以外の所得」の例を挙げると、生命保険の満期保険金(解約返戻金)を受け取った時に生じる「一時所得」や、給与を受け取った時に生じる「給与所得」があります。
この給与所得とは1年間の給与収入の合計から、会社員の必要経費にあたる「給与所得控除」を引いたものです。
勤務先から12月~翌年の1月頃に渡される、「給与所得者の源泉徴収票」の中にある、「給与所得控除後の金額」という部分を見ると、給与所得の具体的な金額がわかります。
また1年間の給与収入の合計が75万円を超えると、給与所得が20万円を超えてしまうため、65歳以降にパートやアルバイトの仕事をしている方でも、(2) の要件を満たせなくなる場合があります。
そのため70歳までの就業確保が企業の努力義務になると、確定申告の知識が不可欠になると思うのです。
ただ確定申告をすると公的年金から天引きされていた所得税が、還付される場合があるので、確定申告をしなければならないのは、悪いことばかりではないのです。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)