目次
故人が生前に投資会社を訴えている訴訟中の相続
宮田一郎(仮名)さんが亡くなり、1周忌を終えてホッとしたころです。
同居していた長男の学さんが、宮田一郎さん宛に届いた郵便物を中身を見て愕然としました。
驚いたことに一郎さんは、生前に投資会社の詐欺にあって係争中であることが判明したのです。
手紙は依頼弁護士からのもので、次回の期日を伝えるものでした。学さんは母親に確認しましたが、要領を得ません。
どうも一郎さんは家族に内緒で退職金を投資会社に預け、被害に遭い、訴訟上の被害総額は2,000万円とのことでした。

消えた退職金の行方
原告(訴えた側)、被告(訴えられた側)のいずれかの立場で訴訟中に亡くなることは現実に起こります。
前述の事件の内容を説明しましょう。
退職金の1/3である1,000万円を投資に使い、まずA投資会社の運用失敗で損失を出しました。
この損失を故人の知人の知人である損尾 進(仮名)から「A社は詐欺まがいの会社で、ちゃんとしたB投資会社に預け直したほうがよい」と勧められました。
損尾氏は、当初は「10万円、20万円の利益が出ました」といった具合に現金を故・宮田一郎さんに渡して信用させ、一郎さんが2,000万円を預けた途端に「ドカンとやられました」の一言であしらい、一郎さんは退職金すべてをなくしたという事件でした。
一郎さんにしてみれば、被害者を救う正義の人として近づいてきた人に騙されたのが許せなくなり訴訟を起こしたようでした。
相続税の財産に「訴訟中の損害賠償」は含まれるのか、また評価は
そもそもお金の貸し借りに関する訴訟は相続されます。損害賠償請求権として相続財産に含まれるのです。
その評価方法については、国税庁のホームページ → 法令等 → 財産評価を見ると、以下の画像のようになっています。
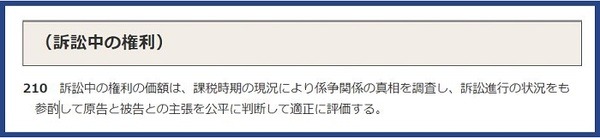
実務上は、依頼弁護士に裁判の行方を確認し評価し、金額が後日(5年以内)確定すれば、修正なり、更正することになることでしょう。
依頼弁護士に学さんが確認したところ
学さんが、依頼弁護士に父の訴訟を引き継ぐ意思を話して訴訟の行方を確認したところ、「お父さんは、被害救済者として現れたB投資会社外務員の損尾 進が許せなかったわけです。彼にある程度運用を任せていたのは事実のようですが、事前に確認していない銘柄の先物取引まで勝手に行ったところを訴えています。また、お母さまに投資の件がばれるのを恐れ、運用報告書も自宅には送らないよう指示していたことが被害を大きくしていたようです。実際いくら戻るかというと、残念ですが、30万円の和解金がもらえれば…」と言います。
「儲け話には乗るな」が故人の最後の言葉
訴訟は和解となり、30万円が支払われました。
ただし、その30万円は弁護士費用にそのまま支払われ、結局は相続人の手元に実質的なお金は戻りませんでした。
むしろ弁護士への依頼時に着手金が50万円払われていますので、依頼したことで実質的にはマイナスという結果です。
故人は長年教育者でした。当初、知人の知人であった損尾氏から自分の子供の相談を持ちかけられるなどして彼を信用してしまった人から「だまされた」という思いを、訴訟することで晴らしたのだと思います
相続人の頭には、「うまい投資話に乗るな」という父の遺言がしっかりと刻まれました。(執筆者:1級FP、相続一筋20年 橋本 玄也)








