
原油価格が大きく下落しています。かつてWTIで1バレル100ドルもあったものが、いまは30ドル台半ばです。
原油が安いということは、私たちの生活にとってはガソリン価格が安くなるのでうれしいことではあります。輸送代も下がり、原材料費が安くなりますね。
目次
なぜ原油価格が下落しているの?

原油価格は需給、つまり、原油を供給する量と使用する量とのバランスで決まります。原油が安いということは、
使う量よりも供給する量のほうが多いということになります。
供給サイドでは、中東産油国がどれだけ生産するか、シェールオイル側がどれだけ生産するかで原油価格は左右されます。いまは中東産油国は原油供給量を減らさないといっています。シェールオイル側も稼動リグ数は増えています。
リグとは、簡単に言えばけ石油掘削基地のことで、この稼動数が増えるということは、生産が盛んだということです。また、アメリカなどの原油消費国の在庫量も原油価格に大きく影響します。
今度は需要側の問題ですが、原油があまり使われていないということは、生産活動が鈍っているということにつながります。生産活動鈍化は、その後の景気にも悪影響となりかねません。生産活動が活発になってこそ、経済はよくなってくるのです。
ここまで世界の生産活動を引っ張ってきたのが中国です。その中国が景気低迷となったことで、世界経済の行方が不安視されています。そのバロメーターが原油を中心とした商品市場なのです。
鉄鋼はもちろん、銅やアルミニウム、亜鉛などの非鉄、原油や石炭、天然ガスなどのエネルギーの価格が上昇しないということは、物が動いていない、生産活動が鈍っていると判断されます。
特に景気の先行指数といわれる銅やアルミニウムの価格は重要です。ほとんどの商品生産に使われる素材ですからね。
余談ですが、これら原材料を運ぶ輸送賃金(バラ積み船)が上がるか下がるかも、景気を占う上では重要です。これらは直接、株式市場にも影響があり、株価が変動する要因となります。
原油価格の変動には金融の側面も

原油価格変動には、このような商品としての一面のほかに金融の側面があります。
原油市場には、株式と同じ先物取引市場があります。実際に原油を手にするのではなく、原油価格そのものを取引するのです。
投資家は、原油だけを取引するのではなく、株や債券、為替といったいくつもの市場に資金を分散します。投資家は資金をいくつもの市場を移動させながら殖やそうとするのです。
裁定取引というもので、為替と原油、株と原油など、いくつかの組み合わせで投資を行いますので、利益確定するときも、いくつもの市場同時に行うことになります。それがマーケットを大きく揺さぶることになります。
原油は金利を生まないので、金利が低いときは人気がありますが、金利が高いときは人気がなくなります。米利上げと関係があるわけですね。
基軸通貨ドルとの相関関係もあり、多くの投資家が取引しているドルが高くなれば原油は売られ、ドルの価値が下がれば原油価格は上がります。
原油生産国のリスクヘッジにも先物は使われます。生産国側が生産調整、原油供給量を減らさないことで、原油価格下落を容認していて、それで原油先物で売りポジションを持つことで、実物の原油価格下落のヘッジを行っているのです。
供給過多と原油先物の売り、ダブルで原油価格は下落の圧力が増しているといえます。
政治も原油価格変動に影響
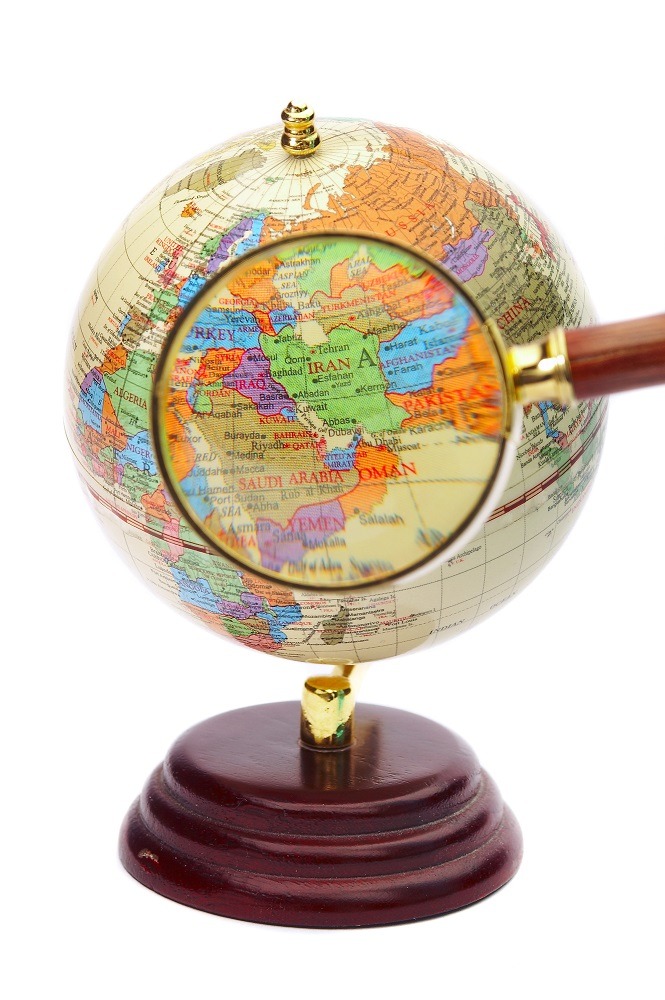
原油価格変動には政治が絡みます。政治的理由で原油価格をわざと安くしていることも伺えます。
よく言われるのは、「中東産油国vsシェールオイル」の構図です。
世界の原油シェアをめぐって、石油輸出国機構(OPEC)側が減産を行わないというもので、OPECによるシェールオイル潰しとも取れます。
原油価格が下落すると、会社経営は厳しくなります。OPEC側の石油よりも、硬い頁岩を砕くシェールオイルのほうが石油採掘のコストは高いです。それゆえ、シェールオイル側が、原油価格下落に先に音を上げるのを、OPEC側は待っているとも言われています。
ただこれは両刃の剣のようなもので、当然、OPEC側も財政は厳しくなります。国内での税製優遇廃止とか、新税設定、国債発行、国民サービスの縮小など、中東産油国も財政維持に必死です。
持っている株を売ることも行っています。サウジアラビアはこの1年間で10兆円超の保有資産を売却したようです。
アメリカが原油価格を下げたい理由

日本株の下落の背景には、サウジアラビアなどのオイルマネーによる日本株売りがあると見られます。日本株のみならず、世界の株価下落の背景にはオイルマネーの売りもあるのでしょう
。
中東産油国vsシェールオイルの構図は、単純化するとサウジアラビアとアメリカとの戦いとも言えます。
アメリカ側はシェールオイル会社救済の意味も含めて、40年続いた米国からの原油輸出禁止が解除され、米石油各社は持て余している原油を海外に販売できるように法律を変えてきました。
ただ輸出量はさほど多くはならないだろうとは言われていますが、原油価格下落の要因にはなりますね。
なぜアメリカはあえて原油価格が下がるようなことをするのでしょう。
アメリカ国内はシェールオイルで石油は十分に確保している。近隣資源国のメキシコとカナダは、アメリカとの貿易で通貨安の恩恵を受けている。となると、アメリカ大陸での保護貿易圏を構築しているのではと見る専門家もいます。
キューバとの国交回復の動きもその一環だと指摘しています。
それは対中国・ロシア包囲網の一環でもあるというのです。
ロシアにとってエネルギー価格の下落は、国家存続での致命傷になりかねません。ロシアが中東に軍事介入する裏側には、地政学的リスクを煽っているのではとの見方もあるくらいです。
さらに、アメリカとイランとの関係正常化を受け、イラン原油が市場に出回ることになります。供給サイドが広がることで、原油価格がなかなか上がらない要因となりそうな感じです。
このタイミングで利上げが行われました。新興国に向かった資金はアメリカに戻ってきます。米国債購入です。われわれの年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)やゆうちょ・かんぽによる米国債買いもアメリカを支えます。
失ったドルへの信任を取り戻す、確固たる基軸通貨としての地位を固めるため、ドルの対極である金に資金が行かないよう、商品市場の下落を演出していると深読みする人もいます。
原油価格下落はいつまで続くのか

原油価格のからくりをご紹介しましたが、かなり複雑な「絡み」があり、原油価格下落は、しばらくは止まらない状況かもしれませんね
。
ただ、いつまでも原油価格が低迷することは、アメリカにとっても良いこととは言えません。
クリスマス商戦や年末商戦のいまは、個人消費を支えるには原油安はガソリン価格下落につながり「ウェルカム」ではあります。ガソリン価格が安いということは、それは個人所得減税と同じような効果をもたらします。アメリカ政府は財政出動せずに個人所得減税ができているわけです。
1年の最大消費イベントが過ぎれば、アメリカ景気を考えれば、また、FRBによるインフレ目標達成を考えれば、原油価格を徐々に戻してくる動きが見られてもおかしくはないでしょうね。
アメリカ側がシェールオイル生産を調整するのか、リグ数が減るかどうか、注目ですね。(執筆者:原 彰宏)












