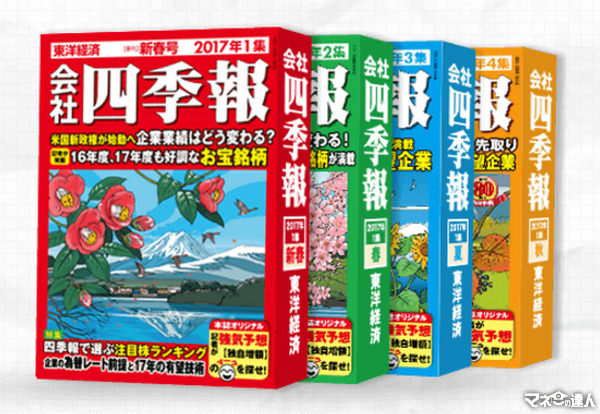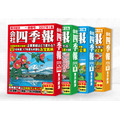目次
会社四季報の「株主」欄に注目
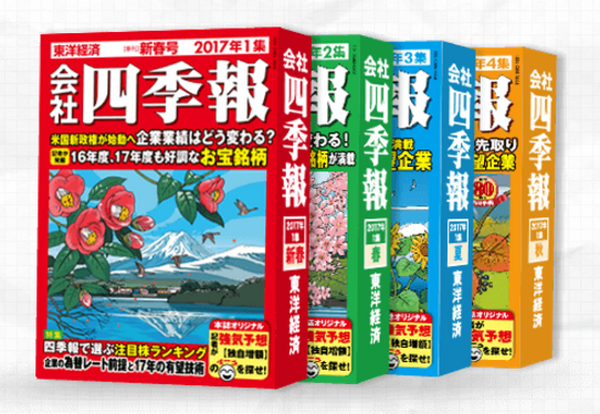
3・6・9・12月の年4回発行される会社四季報。
そこには上場する全企業についての説明や業績についての見通しなどの投資に重要な情報が盛り込まれており、株式投資のバイブルと位置づけられています。
最近では、口座保有者に無料で四季報を閲覧できるサービスを提供する証券会社もあり、特に業績に関する項目や投資指標の項目については、かなり読み込まれている方も多いかと思います。
今回はそういった業績などの項目ではなく、「株主」の項目について注目したいと思います。
株主の項目には持ち株比率上位10名の名前が記載されています。
個人名の場合もあれば、会社名の場合もあります。ではこれらの記載によって、どのようなことが読み取れるのでしょうか。
「〇〇信託口」は、突然売却するリスクの少ない大株主
株主欄を見ているとよく目に付くのが「〇〇信託口」という株主名です。
特に都市銀行などの株主欄にはこの「信託口」がずらりと並びます。これは信託銀行が、他から預かって管理している口座を表しています。
信託銀行は年金などの資金や投資信託の管理も行っており、信託口の多くは年金資金や投資信託だと考えられます。
いずれにしても「長期運用」を前提とする資金です。
決して短期で売買して利益を上げようという資金ではないため、
と考えられます。
ただ、中には海外金融機関も多くあります。
外国人投資家は、状況次第では機敏に売却に動く可能性がありますので注意が必要です。
投資ファンドはいつか必ず売る
大株主に「〇〇リミテッド」「〇〇キャピタル」などがある場合、投資ファンドであることが多いと言えます。
投資ファンドは資金を出資し、いずれ利益を回収できる段階で株を手放します。
一部売却・全株売却どちらにしても、保有株数が多いのでその影響は一時的には大きなものとなり得ます。
6月9日に、大株主参加のファンドが保有する株式の売却を発表したコメダホールディングスは、翌日に4.8%安となりました。
長期的に見れば一時的な下落となる可能性もありますが、投資ファンドが保有している場合は、大量に売る時が来ると思っておいた方が良いでしょう。

自社で保有する「自己株」の意味
上位株主の中に「自社(自社株口)」という記載がある場合があります。
これは企業が自社で保有している株のことです。
企業からすると、自社が大株主となることで買収されにくくなる、また自社株を使って株式交換による他社の企業買収を図りやすいというメリットがあります。
また株主還元策の一つとしても実施されます。
1株当たりの利益(EPS)は当期利益 ÷ 発行済株式数で計算しますが、この際に自社で保有する株は発行済株式数から引いて計算をします。
これにより自社株買いを行うと、計算上1株当たりの利益が増え、割安・割高の判断指標となる株価収益率(PER)が低くなり「割安」と判断されやすくなります。
発行済株式数100株、利益が100円、株価が20円とした場合
1株当たりの利益は100 ÷ 100 = 1円
株価収益率は20 ÷ 1 = 20倍
発行済株式数100株、利益が100円、株価が20円、50株を自社で保有していた場合
1株当たりの利益は100 ÷ (100 – 50)= 2円
株価収益率は20 ÷ 2 = 10倍
割安と判断されれば、株の買い手が増えることが期待でき、株価上昇にも繋がりやすくなるわけです。
大株主に自社があること自体は、投資家にとってメリットともデメリットともなりません。
その自社株を使って次にどのような手を打つのか、という点の方が重要です。
企業の資金状況などによって、この株を市場で再び売り、資金調達をすることもあり得るので、資金状況(キャッシュフロー)に注意は必要です。
株主構成比率でもいろいろと見える
「外国」とは外国人投資家のことです。保有率が多いということは海外投資家からの注目度の高い企業と言えます。
彼らの売買動向は株価にも大きな影響を与えます。
「投信」は投資信託などの保有比率です。比率が高いと、プロのファンドマネージャーが注目している会社と言えます。
「浮動株」とは市場に出回っていて一般に売買されている株のことです。
この比率が低いと市場で売買されている株式数が少ないということになり、株価の変動が大きくなりやすいと言われています。
「特定株」は役員などの利害関係者が保有していて、株式市場に流通しない株のことです。
彼らは売らずに保有し続けるので、売り手になりにくい株主の比率とも言えます。
まとめ

大株主の項目まで見ることはあまりないかもしれませんが、重要な情報源となりますのでぜひ確認してみてください。
見慣れない社名などを見つけたら、検索して調べてみることをおすすめします。(執筆者:高橋 珠実)