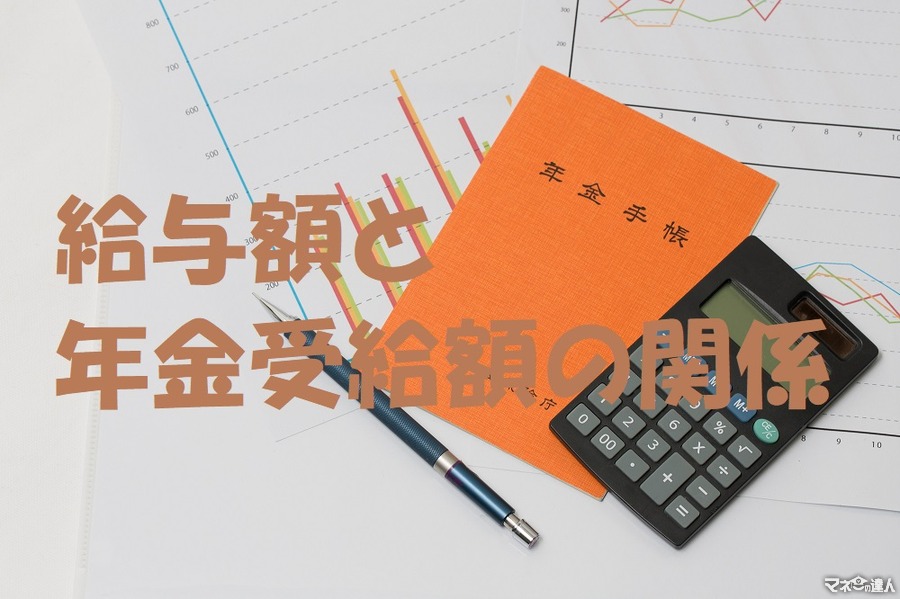「平成29年分民間給与実態統計調査」によると、平均給与が最も高い業種は電気・ガス・熱供給・水道業で、次が金融業・保険業、さらに情報通信業と続きます。
これらの業種で働く人たちの給与額は、平均値をうわまわっています。
このとき、「高給取り」たちが受給する公的年金額も同じように多額になるかといえば、そうはなりません。
年金受給額と給与額は、完全な相関関係(正比例)とはなっていません。
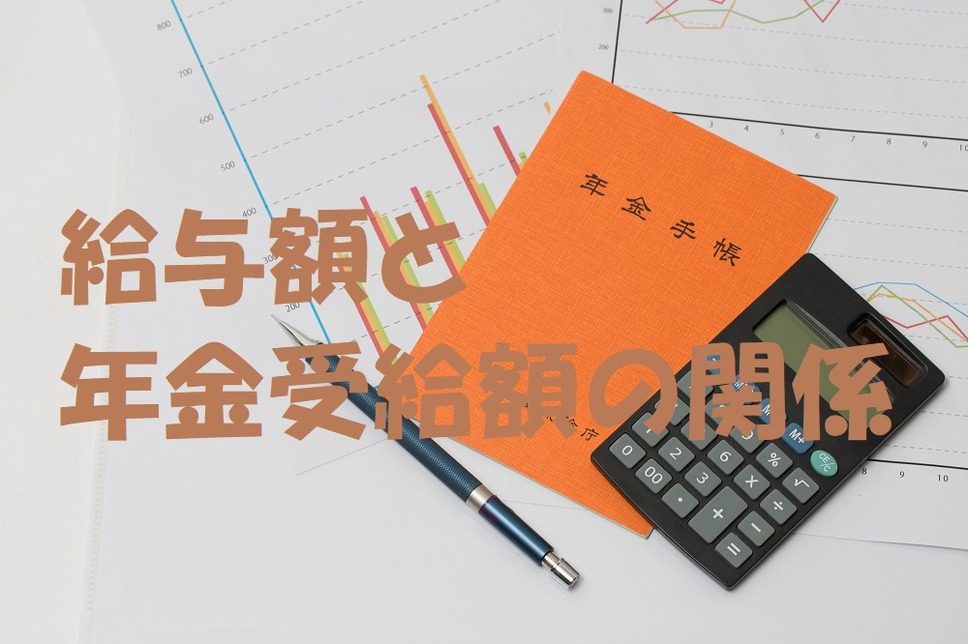
目次
保険料額表でわかる厚生年金保険料額
報酬月額をもとに、健康保険料額と厚生年金保険料額を算出した結果を一覧にした「保険料額表」というのがあります。
毎年更新され、都道府県ごとに発行されています。
保険料額表の厚生年金保険料の欄を見れば、記載が31等級までしかないことがわかります。
報酬月額が60万5,000円を超えると、そこから上は全て31等級として扱われることになります。
対照的に、健康保険料の場合、2019年4月分の保険料額表は50等級まであります。
報酬月額が135万5,000円まで細かく区分けされ、報酬月額が上がるごとに保険料負担額も増えていきます。
厚生年金保険料の上限は公的年金受給額の上限
厚生年金保険料は比較的低い等級で「上限」が来ます。
結果、負担する保険料額が頭打ちとなりますので、受給する公的年金額にも上限ができてしまうことになります。
現役時代に、(平均的な)人の何倍も給料をもらっていたからと言って、公的年金の受給額も人の何倍になる、ということはないのです。
この「上限」は、年金制度発足当初に意図してつくられたものです。
現役時代の格差を老後にまで持ち越さないという、ある種の「平等主義」を反映したものとなっています。
この平等主義は、公的年金が結構オトクな「負担と給付」のバランスだった時代に生まれたものです。
現状の厚生年金保険料負担と年金給付の関係
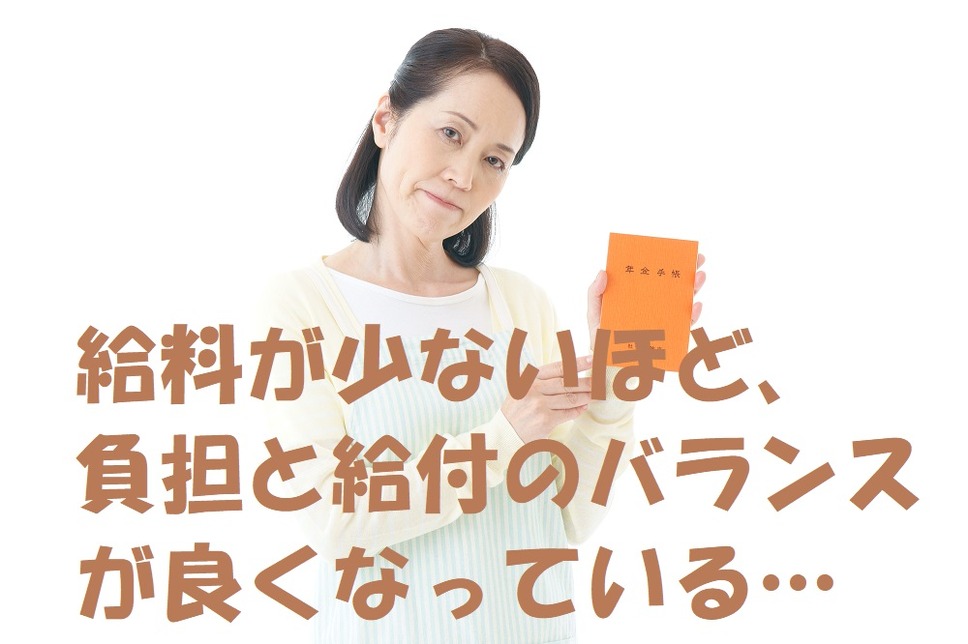
現在は、事情が変わりました。逆転現象が、おきています。
負担する厚生年金保険料が少ないほど、つまり、給料が少ないほど、負担と給付のバランスが良くなることが確認できます。
理由は、厚生年金の生涯収支が年々悪くなっているからです。
細かい計算をするまでもなく、60歳代前半の年金給付は年ごとに削られています。
2025年には1円も支給されなくなります。
年金は「老齢」だけではない
上記は、国全体が少子高齢化となった結果、取られた施策です。避けようがありません。
厚生年金保険料を多く支払うとパフォーマンスが悪くなるので、「給料を下げてくれ」というサラリーマンは存在しないに違いありません。
この点、確かに前の世代と比較すれば、明らかに不利となります。
しかし、年金という公的保険制度が補償する保険事故は老齢だけではないのです。
上記の話は、老齢年金の範囲だけのこと。
本人は「生涯不採算」で死んでも、保険料支払い原資は奥さんに遺族年金として引き継がれることになります。
また、負傷した場合には障害年金が支給されます。
公的年金の損得勘定は、簡単にはできないのです。(執筆者:金子 幸嗣)