
金融庁発の「老後に2,000万円不足問題」による指摘を受けるまでもなく、今後、公的年金だけで高齢者世帯の家計維持はムリであることは誰もが自覚するところとなりました。 「では具体的に何をやれば良いか?」 「どんな職をさがせ

年金財政については、別の記事でもふれました。 今回は、より深く考えてみたいと思います。 念のため確認しておくと、公的年金の財政状態は地方・国家公務員共済が赤字状態を継続しており、その赤字部分を制度統一まえの「本来の厚生年

あなたに金遣いのアラい親戚がいたとします。 家計の収支は万年赤字体質。 自分ひとりでの家計維持はムリにということになって、いつのまにか連帯保証人となっていたあなたが、これからは一緒に、その親戚の赤字の穴埋めを手助けするこ

年金制度を表現する場合に「100年安心」という言葉が使われるのを聞いたことがあるかもしれません。 平成16年、現在につながる大規模な年金制度の改革が行われました。 「100年安心」というのは、その時に使われたスローガンで
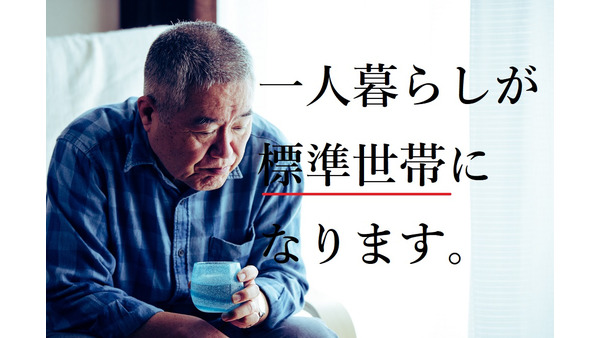
「一人暮らしの高齢者」と聞けば、多くの人は、 孤独、さびしい、かわいそう… といったコトバを連想するに違いありません。 また、自分には関係のない話と考えやすいです。 しかし、そうも言っていられない事態がやってきそうです。

新元号施行まもなく、突如広まった「年金破たん説」 令和元年5月下旬、突然、YouTubeに「公的年金が破たんした」といった趣旨の動画が続々とアッブされるようになりました。 発信元をたどっていくと、朝日新聞デジタルの5月2

最近、とあるユーチューバー兼ブロガーに注目しています。 新作動画がアップされるたびに、視聴しています。 注目している理由は、稼いでいる金額がハンパないからです。 しかも、その稼ぐ手法や金額の裏付け資料などを、ほぼ全公開し
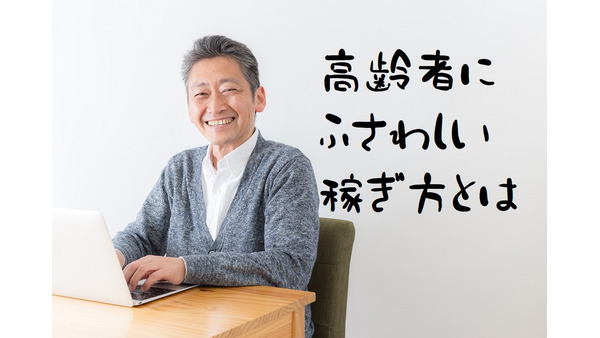
高齢者家計を再度確認 高齢者の家計は、統計上、現状でも恒常的な赤字状態です。 将来、この赤字幅は拡大していくものと考えられています。 つまり、公的年金に平均的な貯蓄額を足し合わせても、ある程度の年齢を超えて生き続けるには
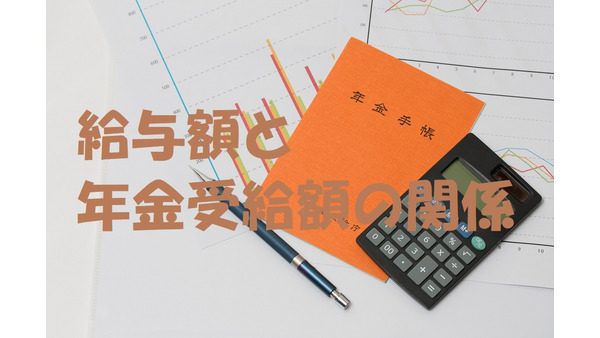
「平成29年分民間給与実態統計調査」によると、平均給与が最も高い業種は電気・ガス・熱供給・水道業で、次が金融業・保険業、さらに情報通信業と続きます。 これらの業種で働く人たちの給与額は、平均値をうわまわっています。 この

アマゾンプライム会員の年会費が値上げされ3,900円が4,900円になりました。 ニュースでも報道がありましたが、アマゾンからそのことを伝えるメールが送付されてきました。 米国では、アマゾンプライムの年会費は119ドルで

通知カードの廃止 ≪画像元:マイナンバーカード 総合サイト≫ 通知カードが廃止されます。 通知カードとは、付番されたマイナンバーを国民ひとりひとりに知らせるために郵送された紙のカードのことです。 デジタルファースト法成立

70歳以上の人も厚生年金の被保険者となる可能性が出てきました。 4月15日から各紙が伝えています。 厚生労働省は、現在のところ70歳未満と定められている厚生年金への加入義務を70歳以降にも延長する方向で検討に入ったとのこ
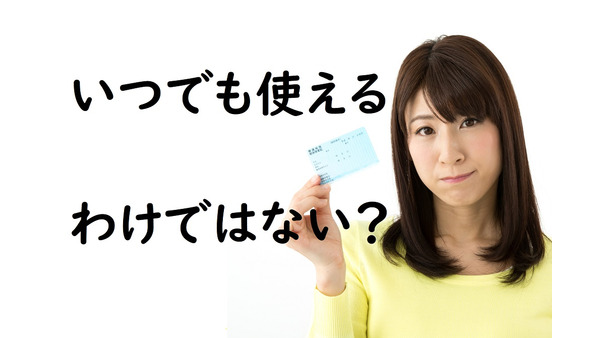
医療機関で診療を受ける際に、健康保険証を使えない、使ってはいけないケースがあります。 ケース1. 労働者災害補償保険 業務上のケガ(原則的には通勤途上のケガも含む)、病気などの場合は、労働者災害補償保険(労災)が適用され

厚生労働省は、年金生活者の実態を把握するために、毎年、年金基礎調査と称するアンケート調査を実施しています。 その最新版は、平成29年度分です。 平成30年年末に公表され、厚労省のサイトに詳細がアップされています。 ≪画像
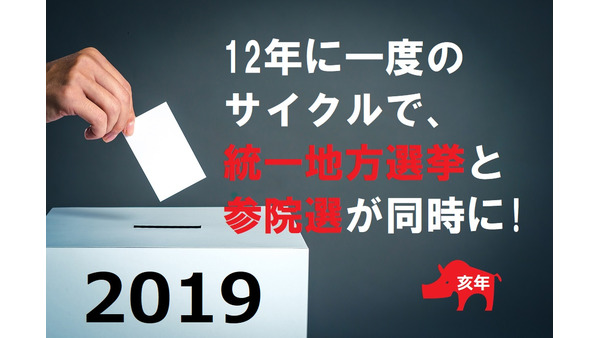
新元号が「令和」と決まりました。 本年、2019年は御代(みよ)代わりで、元号が変わるとともに、参院選も行われます。 亥年の選挙は、12年に一度のサイクルで、統一地方選挙と参院選が同時に行われます。 亥年の選挙は、地方選

最新データで確認する高齢者の家計収支 高齢者の家計収支を最新の数値で確認しておきます。 2017年の総務省家計調査報告によれば、高齢夫婦世帯(夫が65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)の平均消費月額支出は23.5
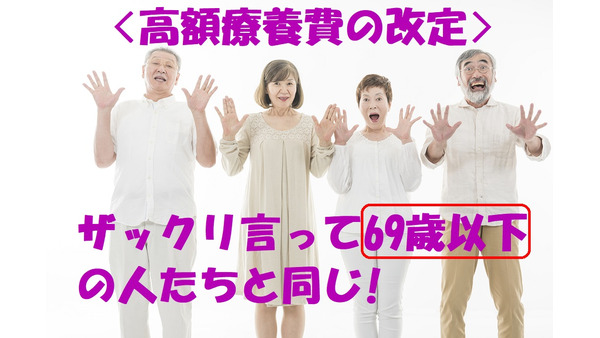
高額療養費の改定 平成30年8月、高齢者(70歳以上)に適用される高額療養費の負担限度額が改定されました。 具体的には、「現役並み所得者」というカテゴリーが改定され、ザックリ言って69歳以下の人たちと同じ負担を負うことに
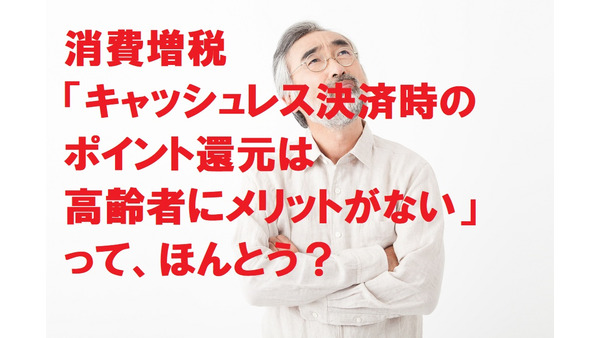
2019年10月から消費税が10%に増税します。 政府は景気減速を避けるためのさまざまな対策を考えています。 キャッシュレス決済時のポイント還元もそのひとつですが、この施策は高齢者にメリットがないとの声も聞かれます。 果

余命とは、特定の年齢以降に生き続ける期間の長さです。 ガン患者などに対して、「余命何か月」といった具合に使われる事例が多いです。 もちろん、健康な人にも適用されます。 平均寿命と平均余命 特定年齢に平均余命を足し算すると
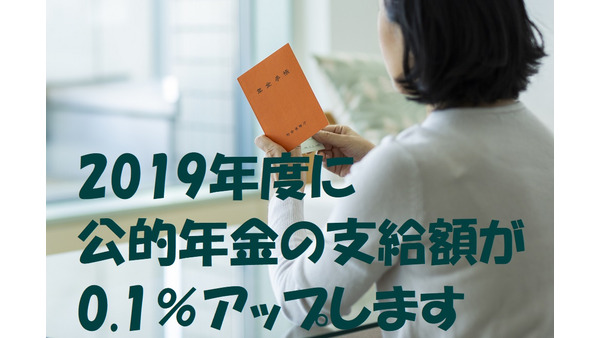
今年の4月から、つまり2019年度に公的年金の支給額は0.1%アップします。 年金支給額は、基本的に5年毎に実施される財政検証(もとは財政再計算)と呼ばれる作業で見直しになります。 その間の期間の改定について、過去を振り
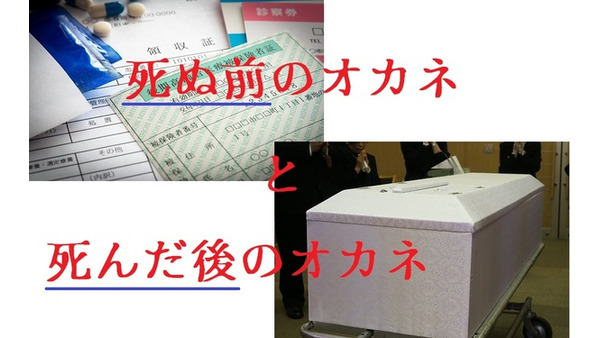
死者に使うおカネ 日本人は、亡くなった人におカネを使わなくなりました。 ここ10年から20年くらいの変化です。 以前は最低でも数十万円から数百万円単位のおカネを使ってお葬式をやったものです。 今は親族による密葬が「当たり

高額療養費の改定 平成30年8月、高齢者(70歳以上)に適用される高額療養費の負担限度額が改定されました。 具体的には、「現役並み所得者」というカテゴリーが改定され、ザックリ言って69歳以下の人たちと同じ負担を負うことに

確定拠出年金iDeCo。2018年8月現在加入者が100万人を超えました。 金融機関の強力なコマーシャルの影響もあって、会社を通じて、あるいは自営業者として、加入者は年々増えています。 確定拠出年金(iDeCo)は、政府

公的年金には、繰り下げ受給という制度があります。 本来の受給開始から1年以上経過した以降に年金を請求することによって、繰り下げ受給は実現します。 繰り下げ受給で、年金額は1か月ごとにつき0.7%増額されます。 65歳の受

GPIFというコトバを聞いたことはありますか? 年金積立金管理運用独立行政法人のことです。 日本語表記から判断すると、「私達の大切な年金を運用してくれているんだな」というイメージを持つかもしれません。が、よく考えると不思

「資格を取れば独立出来る。」 「資格があれば一生働けるから老後も安心だ。」 このようなフレーズとともに、「資格ブーム」と呼ばれる現象がありました。残念ながら、ブームは去りました(笑)。 今回は、一時のブームに左右されない
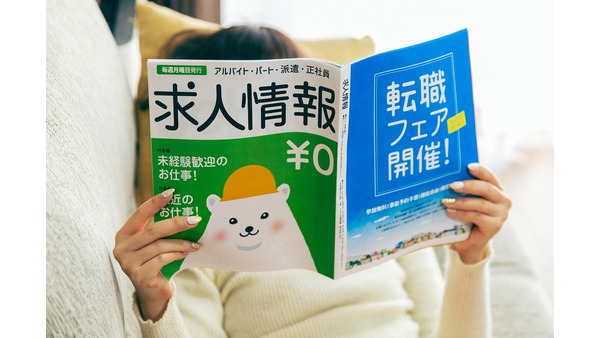
今回は、もしあなたがこれから就職するなら、あるいは、就職予定の人からアドバイスを求められたとしたら、どう考えれば良いかについてのお話です。 どの業界が儲かるのか? 日本の人口はすでに減少プロセスに入っています。 何の工夫
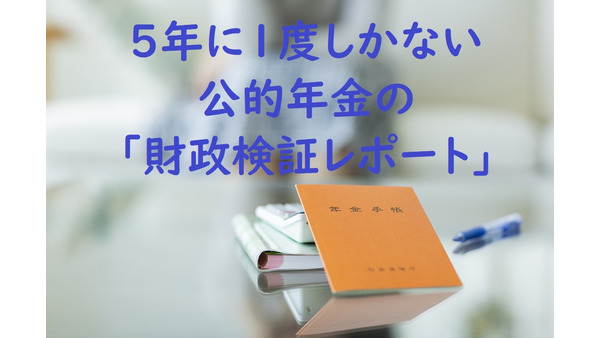
「平成も最後ですね」と言いつつ、少々感傷ぎみの一般人とは異なり、5年の歳月を超えて盛り上がる業界があります。 公的年金業界に他なりません。 平成31年には、公的年金の財政検証が行われます 公的年金の財政検証とは、5年に1

入国管理法改正案が成立 大量移民受入推進法案、正確には入国管理法改正案が成立しました。 2019月4月から施行されます。 国家の命運を左右するような重要法案をしっかりとした審議や議論をしないまま、可決・成立してしまいまし
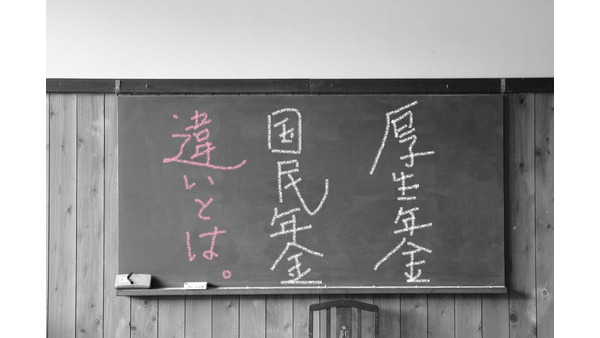
厚生年金制度の成立 厚生年金制度の成立は、1942年(昭和17年)です。 戦前の制度成立と聞いて、「ビックリ!」という人も少なくないでしょう。 注目すべきは、そのタイミングです。 日本は戦時下で、国家総動員法という法律が

2回目のマクロ経済スライドが発動 11月末の日経新聞電子版で、「2018年は、通年で消費者物価が1%を超えるアップとなる見込みとなり、結果、2回目のマクロ経済スライドが発動される可能性が高まった」という報道がありました。

公的年金は、男女不平等です。 ありがちの「男性優位」ではなく、「女性優位」という意味での男女不平等です。 ホントは、女性こそが年金について詳しく知っておけば、トクするケースが多いのです。 女性しかもらえない年金 まず、女
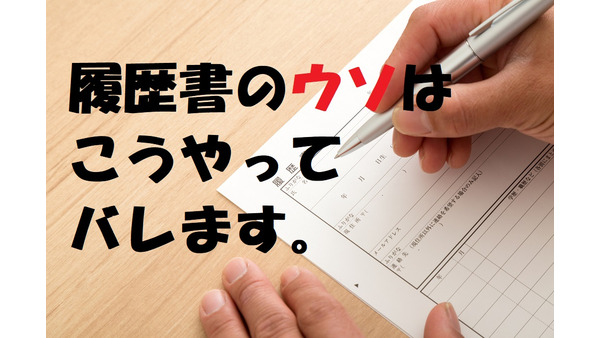
履歴書をゴマかす人は少なくありません。 私は以前、勤務先で中途採用者の募集・面接を担当していたことがあります。 その経験から言っても、 「都合の悪い過去」を勝手に書き変えてしまう人が実に多い という印象があります。 当時
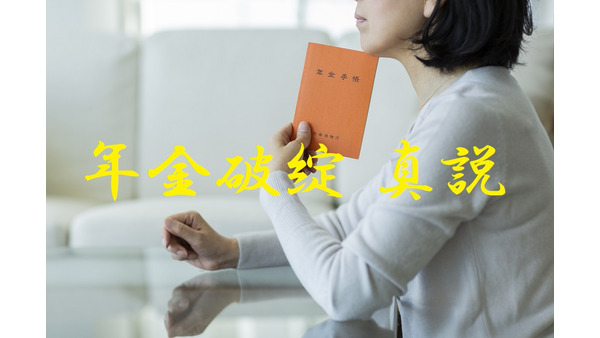
公的年金制度が破綻(ハタン)することはありえません。 理由は、破綻しないように法整備されているからです。 このように説明しても、長年マスコミ報道などに汚染され続けてきた人はカンタンには納得してくれません。 納得できない理

高齢者の人口は増え続けます すでに、日本の人口が減り始めていることはご存知のことと思います。 が、高齢者(65歳以上)の絶対数は今後もしばらく、2040年頃まで増加を続けます。 我が国の社会保障予算には限りがあります。

高齢者社会を生き抜くコツについて考えてみます。 1. 老後観そのものを変える まず、 あなたが漠然と持っている「老後」についてのイメージは捨てて下さい。 それなりの年月を生きていると、いろんなことに対する先入観ができてし