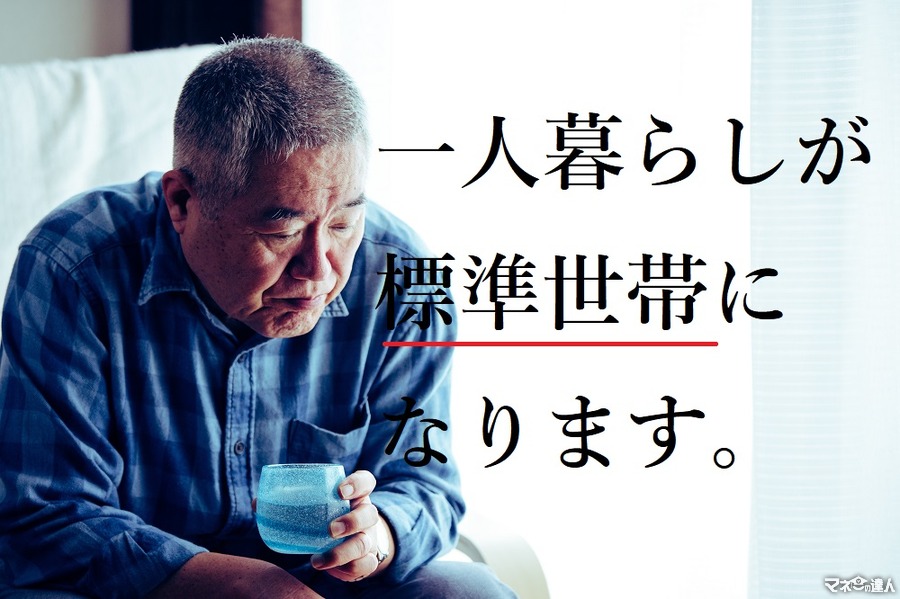「一人暮らしの高齢者」と聞けば、多くの人は、
といったコトバを連想するに違いありません。
また、自分には関係のない話と考えやすいです。
しかし、そうも言っていられない事態がやってきそうです。
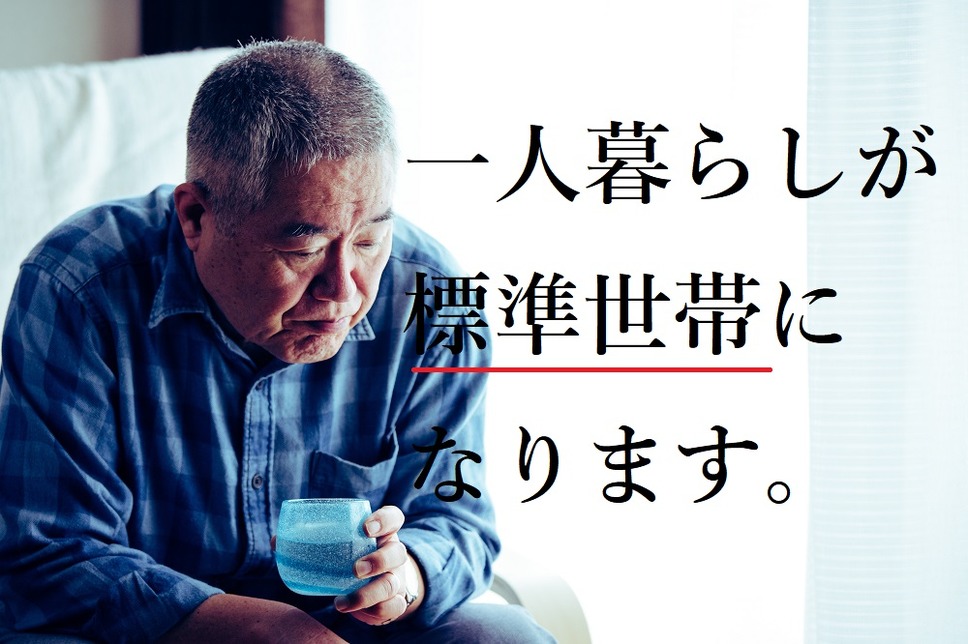
目次
標準世帯

ひと昔前、標準世帯と言えば、「夫婦に子供2人」と言われた時代がありましたが、今後は様変わりしそうです。
国立社会保障・人口問題研究所は2019年4月19日、2015年に実施された国勢調査をもとに、2015年~40年の25年間におよぶ「日本の世帯数の将来推計」を公表しました。
2035年までに沖縄を除いた46都道府県で世帯数が減少すると推計されました。
すでに、日本は人口減少プロセスに入っているわけですから、この推計自体については驚くことはありません。
しかし、2015年に41都道府県で最大の割合となっていた単身世帯(つまり、一人暮らし)が、2025年には全都道府県で最大の割合を占めるようになると報告されています。
世帯というものは構成する人員によって、いろんなカタチがあります。
夫婦のみ、夫婦と子供、ひとり親と子、など。
さまざまな世帯の中で、
というのです。
つまり、近未来の日本では、単身世帯が標準世帯となるということです。
今後は、「ウチは夫婦に子供2人」と言えば、「珍しいね」という答えが返ってきても、おかしくありません。
人口に関わる将来推計は、経済の予測などと違って、的中率がきわめて高いことで知られています。
ですから、この推計は「すでに決まった未来」と考えていた方が良いです。
高齢者より多い独身者

同じく2015年の国勢調査では、65歳以上人口が約3,280万人に対して、15歳以上の独身者の人口は約4,440万人となっています。
日本は高齢者の多い国というふうに語られることが多いです。
しかし、15歳以上の独身人口のほうが、高齢者よりも1,200万人も多いわけです。
2040年には独身率は47%、つまり、15歳以上人口の半分が独身者になると予測されています。
高齢者世帯の近未来

世帯主が65歳以上の世帯に占める単独世帯の割合は、2040年には全都道府県で30%以上となり、15都道府県で40%を超えます。
つまり、
ということになります。
一人暮らし世帯の家計は複数人からなる世帯と比較して、当然、支出総額は少なくてすみます。
しかし、「一人あたりの支出」は多くなります。
典型的なのが食費や住居費です。
複数で分けることがありませんから、「一人あたり」は割高になってしまいます。
複数人で暮らす方が、おトクであることは言うまでもありません。
一人暮らしの高齢者が増えていけば、ひとつは経済的な理由で、また、孤独を解消するためにも、一緒に暮らす人たちが増えていくかもしれません。
「シェアハウス」の高齢者版です。
世帯のあり方が劇的に変われば、これまでの習慣やライフスタイルも、様変わりするかもしれません。 (執筆者:金子 幸嗣)