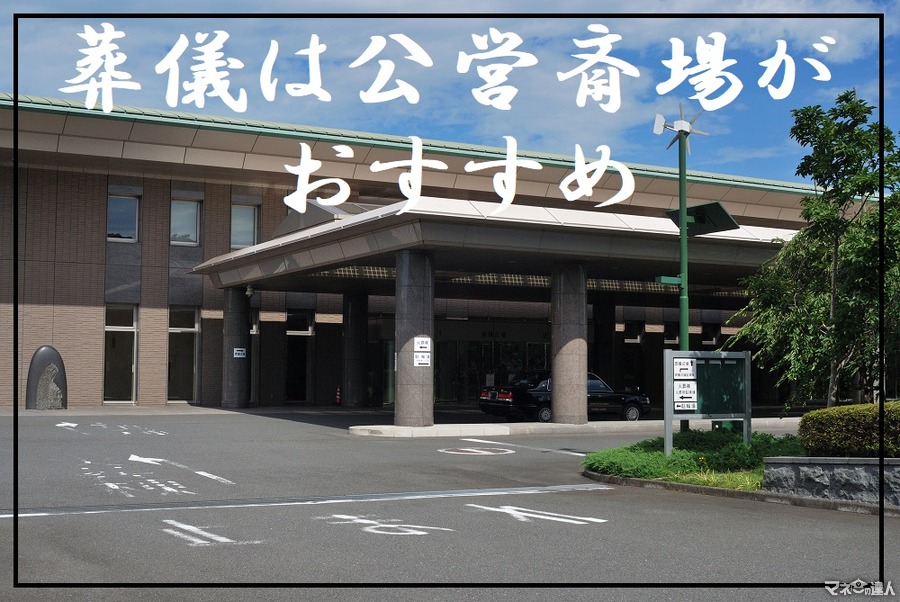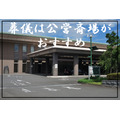葬儀を執り行う場所は、葬儀専門斎場、お寺の本堂、公民館、自宅などさまざまです。
しかし最近ではほとんどの場合、葬儀専門斎場が選ばれています。
これには自治体が運営する「公営斎場」、葬儀社が保有する「民営斎場」、寺院が有償で貸し出す「寺院斎場」などがあります。
そんな中でも、施設の充実度や価格の面から圧倒的におすすめなのが公営斎場です。
他の斎場に比べてどのような点がおすすめなのか、5つの理由をご紹介します。

目次
公営斎場おススメの5つの理由
(1) 費用が安い
公営斎場は住民向けに作られた公共施設です。
そのため、住民の利用料は民営斎場や寺院斎場に比べて圧倒的に安い傾向があります。
また自治体によっては、斎場に飾る祭壇も割安で、あるいは無料で利用できます。
(2) 設備が充実している
税金で作られた施設ですから、館内の設備が充実しています。
清潔感のあるロビーや、バリアフリーへの配慮など、不快を感じることなく故人を送り出せるでしょう。
(3) 火葬場が併設しているので移動が楽
多くの公営斎場は、葬儀式場と火葬場が併設されています。
そのため、葬儀を終えた後の出棺が不要で、移動の手間や費用の負担が大幅に軽減できます。
(4) 駐車場が広い
公営斎場は土地が充分に確保されており、駐車台数にも余裕があります。
参列してみたはいいけれど車を止める場所がなくて困るというようなことはないでしょう。
(5) 認知度が高く、場所が伝わりやすい
公営斎場は、地元住民であれば誰もが知っているでしょう。
訃報や葬儀の連絡の際に、場所が伝わりやすいです。
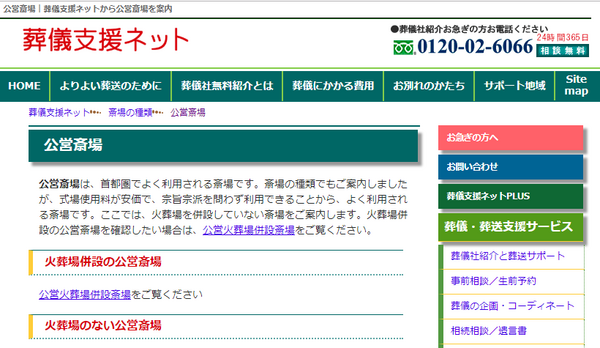
人気ゆえのデメリット
このように、人気の高い公営斎場ですが、それゆえにデメリットも存在します。
(1) 混雑のためなかなか予約できない
人気が高い公営斎場ではすぐに予約が埋まってしまいます。
公営斎場での葬儀にこだわることで数日間待たなければならないこともあるでしょう。
(2) 複数の葬家が同時に利用するため利用時の制限がある
公営斎場は複数の式場が用意されているため、他の葬家に迷惑がかからないよう、いくつか利用時の制限があります。
祭壇の飾りつけ上のルールや、BGMを禁止するような音響や騒音に関わるものなど。
自分たちらしい葬儀の演出がしたくても、実現できないこともあるかもしれません。
(3) 住民外の利用は割高
公営斎場はその自治体に暮らす住民向けの施設です。
住民外の利用は逆に割高になるので充分に注意しましょう。
公営斎場は葬儀を安く、きちんと行いたい人にとっては何かと便利な場所です。
しかし、自治体や斎場によっては利用条件や費用などが異なることがあります。
まずは、詳しい事柄を地元の葬儀社に相談してみるのがよいでしょう。(執筆者:五十嵐 信博)