子供が小学校や保育園に行くようになると、お弁当を作る機会が増えてきますが、お弁当を作るアイテムをいろいろと買ってしまうと、かなりの出費になってしまいます。
100均のお弁当グッズは豊富なので、楽しく作れるうえに節約もできます。
便利グッズもあるので、お弁当作りの初心者ママさん必見です。

目次
定番&あると便利なおすすめお弁当グッズ
子供のお弁当を作る際に使う定番の商品や「これはあると便利!」だと思うオススメの100均お弁当グッズを紹介します。
1. お弁当箱
お弁当箱は子供の好きなキャラクターの物を買う人が多いようですが、「キャラ物はいやだ」と言う子どももいます。
また、保育園児などの場合、お弁当を食べられる量がいまひとつわからないことがあるので、お弁当箱のサイズも迷ってしまうので親としては悩みどころです。
お弁当箱は2種類用意すると便利です。
1つは「仕切りが付いたお弁当箱」、もう1つは「おかずだけ入れる小さめのお弁当箱」です。
写真のようにサイズに違いがあると、用途によって使い分けられます。
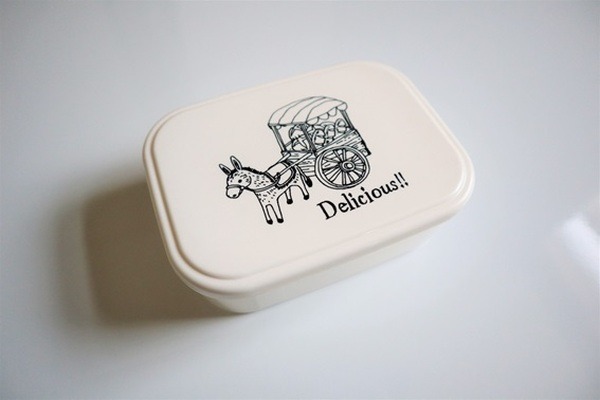

「仕切りが付いたお弁当箱」には、ご飯とおかずを一緒に入れられます。
おにぎりを作らなくてもよいお弁当の時には、パパっとご飯とおかずを入れるだけでお弁当が完成します。
写真のお弁当箱のポイントは、タッパーのようになっているので子供が開けやすく、汁漏れしにくいところです。

「おかずだけ入れる小さめのお弁当箱」は、おにぎりと一緒のお弁当を作る際に便利です。
保育園や学校によっては「お弁当のご飯はおにぎりを持たせてください」と言われることがあるからです。

写真の容器は小さいのですが、パッキンが付いているので汁漏れしないのがポイントです。
おにぎり入れは子供次第
おにぎり入れにもかわいいとは思うのですが、不器用な子供だと開けづらいことがありそうです。
もし、おにぎり入れを子供に持たせたいと考えるならば、子供が開けられるかどうかを確認してから持たせるとよいでしょう。
2. エッグタイマー
ゆで卵を作る際に茹で具合がわからないといったことはありませんか。
固ゆでにしたいのに時間が足りなかった、半熟にしたいのに茹で過ぎたなど、私の場合にはコレを使うまではよくあることでした。

エッグタイマーは、ゆで卵を作る際に一緒に入れて茹でると色が変わる仕組みです。
写真にあるように、エッグタイマーを見ると卵の茹で具合が分かるようになっています。
お弁当を作る際には、朝食の用意もしなければいけないので何かと忙しいものです。
エッグタイマーを時折見ながらだと、忙しい時にも安心して卵を茹でられます。
3. 抗菌シート
暖かくなってくると心配になるのが食中毒です。
そこで、おすすめするのが「お弁当用の抗菌シート」です。

特に、夏のお弁当には保冷剤と一緒に入れておくことをおすすめします。
100均のものだから枚数は少ないのかと思いきや、驚くことに50枚以上も入っていました。
食中毒対策は子供だけではなく、お父さんのお弁当にも必要なので抗菌シートは重宝します。
4. 柄入りアルミホイル
柄入りアルミホイルは、子供のおにぎりを包む時などに使えるので、とても便利です。
節約の観点から言えば、柄のないアルミホイルの方が柄入りのものよりもお得です。
ところが、楽しい柄のアルミホイルにおにぎりが包んであると子供が喜ぶのです。


いろいろなアルミホイルがあって、男の子や女の子がそれぞれ喜びそうな柄がそろっていました。
ちなみに、オトナ女子が好きそうなオシャレな柄のアルミホイルもありました。
お母さんも目移りしそうです。
5. デコレーション用品
100均にはお弁当のためのデコレーション用品もいろいろとそろっています。
他で買うと500円程するアイテムも100円で購入できるのが魅力的です。
ウインナーカッターセット
ウインナーを楽しい形に切れるセットです。
ウインナーのデコレーションは定番ですが、包丁で飾り切りとなるとなかなか難しいものがあります。
不器用な人には特におすすめです。


ウインナーにグッと差し込むと顔ができるものもあります。
カットの種類は複数あるので子供が喜ぶこと請け合いです。
海苔用パンチ
海苔用パンチにもいろいろな種類があるのですが、好きな形を見つけやすい商品です。
人気商品のためか、買いに行った時には在庫がほとんどありませんでした。

100円なのであれもこれも欲しくなりそうです。
ご飯やおにぎりを飾ると、それだけでかわいいお弁当になります。
100円で気軽に試せる豊富なお弁当アイテム
100均のお弁当アイテムの種類は豊富です。
試しに使ってみたいと思った商品があっても、100円ならば気軽に購入できるのが魅力です。
スーパーなどで倍以上の価格の商品も100均で見つかることが多いものです。
お目当てのアイテムがある場合には、まずは100均で探してみることをおすすめします。
選ぶのが楽しくなって買いすぎないように気をつけてください。(執筆者:藤代 聖子)


















