
公務員が加入する共済年金が平成27年10月1日に、会社員が加入する厚生年金保険に統合されました。新聞やテレビなどで頻繁に特集されていたので、ご存知の方は多いかと思います。
それでは共済年金と厚生年金保険の統合は、今回が初めてではなく、過去にもあったという話は知っているでしょうか?
例えば日本たばこ産業(JT)、日本電信電話(NTT)、日本鉄道(JR)の従業員が加入する共済年金は、平成9年4月1日に厚生年金保険に統合されました。
また農林漁業団体の従業員が加入する、「農林年金」と呼ばれる共済年金も、平成14年4月1日に厚生年金保険に統合されました。
これらの統合は公務員の企業年金と位置づけられる、「職域加算」の統合後の取り扱いなどの面において、公務員が加入する共済年金の統合と、似ている部分が多いのです。
これはおそらく偶然ではなく、公務員が加入する共済年金の統合に携わった方々は、過去の統合をモデルにしたのだと思います。
もしそうであるならば「歴史は繰り返す」のですから、過去の統合がどんな過程を経たのかを調べていけば、公務員が加入する共済年金の未来図を予想できるはずです。
年金の請求先は段階的に移行する
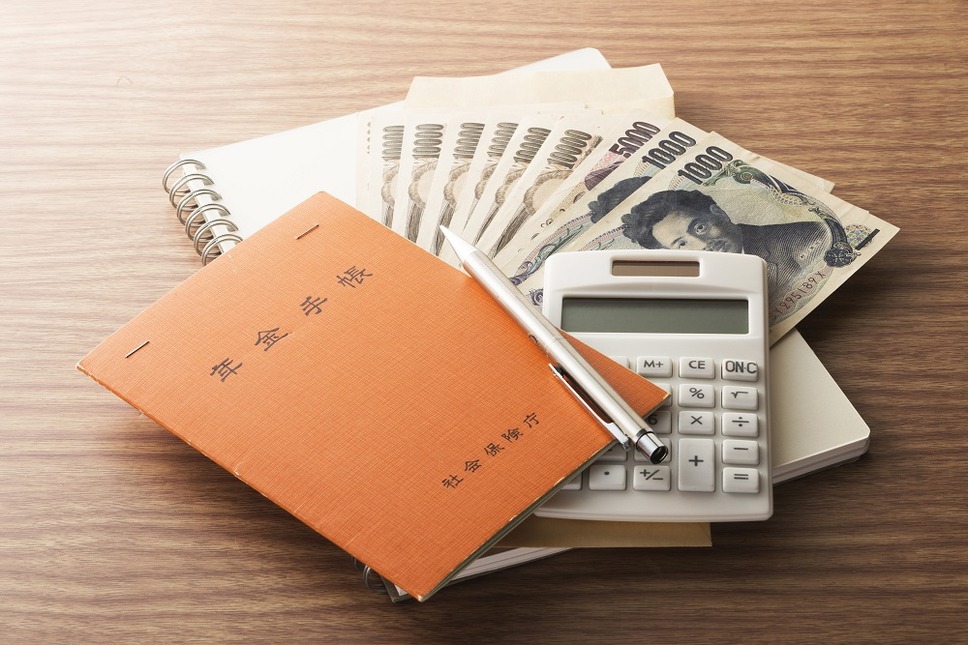
厚生年金保険から支給される「老齢厚生年金」の請求手続きは、住所地の年金事務所で行ないます。
また共済年金から支給される「退職共済年金」の請求手続きは、各人が加入する共済組合で行います。
そのため公務員の方が平成27年10月1日以降に、老齢厚生年金の請求手続きを行う場合、年金事務所で行なえば良いと、考えてしまうのではないでしょうか?
しかし共済組合などのウェブサイトを見てみると、各人が加入する共済組合でも、引き続き手続きができると記載されております。
過去の歴史を見てみても、農林漁業団体の従業員が老齢厚生年金の請求手続きを、完全に年金事務所で行なうようになったのは、平成24年4月1日からであり、それまでは農林年金の存続組合で行なっておりました。
ですから公務員の方が受給する老齢厚生年金についても、しばらくは各人が加入する共済組合と年金事務所の、どちらでも請求手続きができるようにして、数十年の期間が経過した後に、年金事務所のみで行なうようになると予想しております。
もしそうなった場合、老齢厚生年金の請求手続きは年金事務所、統合前の期間に関する職域加算や、新設された「年金払い退職給付」の請求手続きは各人が加入する共済組合というように、手続きを行う場所が2つになります。
個人的にはこのような変化が、次のような問題を引き起こすと考えているのです。
請求忘れが多い企業年金

会社によっては福利厚生として企業年金の一種である、「確定拠出年金」を実施しております。
平成26年9月7日の毎日新聞によると、この確定拠出年金の積立金を請求も移換もせず、放置したままにしている方が、平成25年度末時点で、約43万人もいると記載されておりました。
また企業年金の一種である「厚生年金基金」から支給される年金を受給できるのに、請求手続きを済ませていない方が、平成19年9月時点で約120万人もいるというデータが、企業年金連合会から発表されました。
このようなことが発生する原因について考えてみると、老齢厚生年金と企業年金の請求手続きは、別々に行なう必要があるというのも、原因のひとつになっていると思うのです。
もし企業年金の請求手続きを、老齢厚生年金の請求手続きと一緒にできてしまうとしたら、こんなに請求忘れが発生するはずはありません。
そのため公務員の方が老齢厚生年金の請求手続きを行う場所が、年金事務所と各人が加入する共済組合の2つになった場合、同じような問題が起きないかと懸念しております。
また会社員の方は企業年金連合会のウェブサイトなどを活用して、請求忘れの企業年金がないかを、調べてみるべきだと思います。(執筆者:木村 公司)









