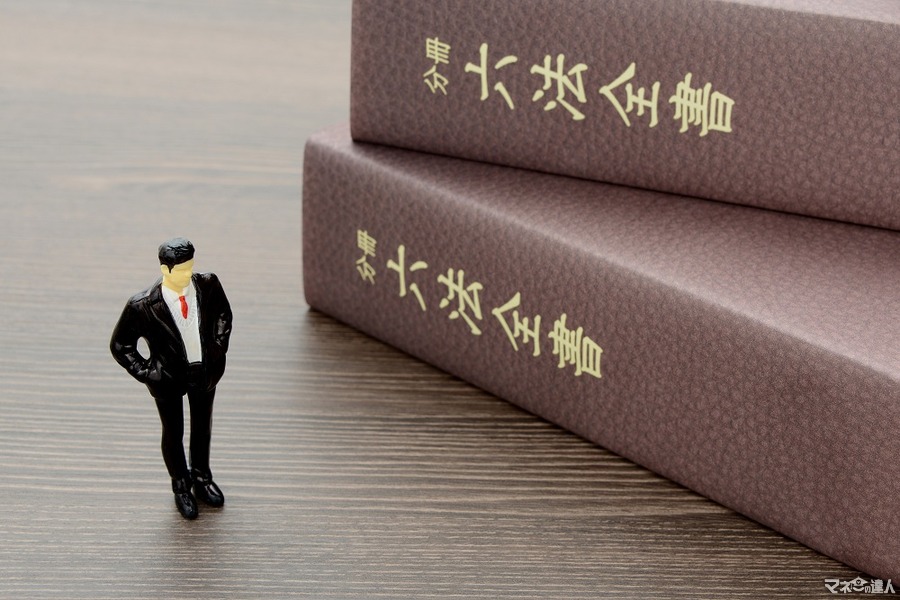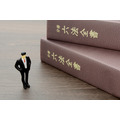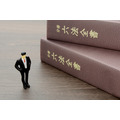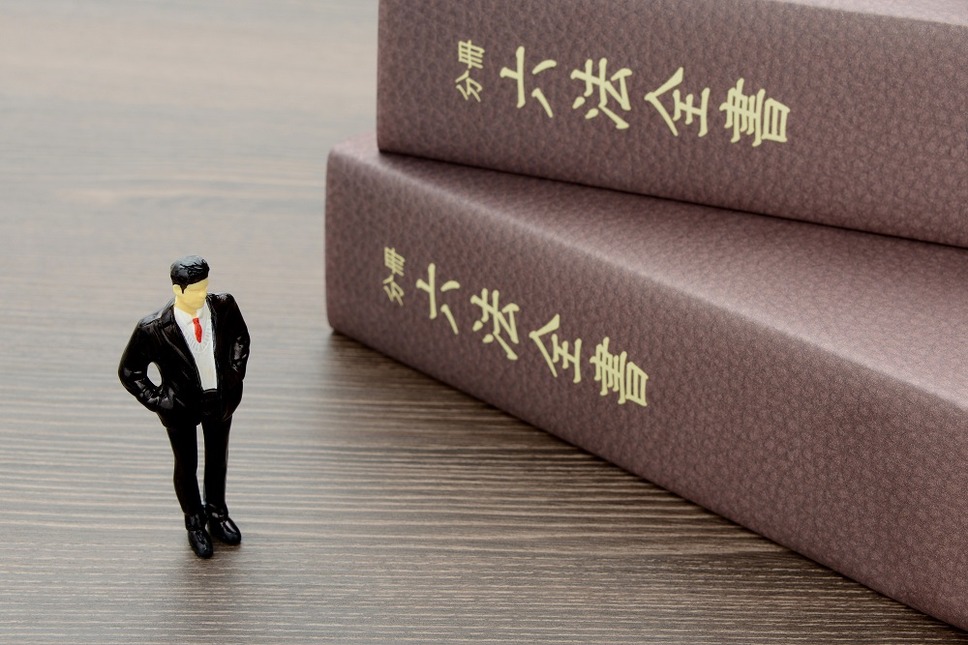
債権法の改正が予定されていますが、法定利率の改正もその議論の対象となっています。
これまでは、当事者が利息の定めを置いていなかったとしても、遅延損害金には法定利率が適用される結果、民事法定利率は年5%、商事法定利率は年6%の計算によってきました。
改正案によれば、関連法令の改正により商事民事の区別はなくなり、年3%と減率されることとなりますが、法務省令に定めるところにより3年を1期として見直しが行われる点も重要です。
従来日銀が公表している短期貸付の平均利率(過去5年の平均値)を基準割合とし、直近において法定利率の変動のあった期(初回は改正法施行時)の基準割合と当該期の基準割合の差が1%以上あった場合、1%単位の加算又は減算を行った割合をもって新たな法定利率とされることになります。
法定利率の減率と法定利率変動制による将来の適用利率の不明確化は、企業等の債権管理面に多くの影響を与えるものです。
当事者が約定利率や遅延利率を定めていた場合は、約定の利率が適用され、法定利率は適用されないため、今後は、契約書等に約定利息や遅延利率の定めを明確に定めておくことが重要となるでしょう。
この際、遅延利息について、消費者契約法の上限である14.6%などの法定利息を上回る利率が設定されることも多々ありました。
民法改正の法定利率の引下げにより、一方が提示した契約書の約定利率について、他方当事者が減率を求める交渉を行う場面も増えるのではないかと考えるところです。(執筆者:大西 隆司)