目次
ご夫婦で同じ銀行に預けてませんか?
ご主人が給与の受け取り等で銀行に口座を保有しているケースで、奥さまも同じ銀行に口座を持たれているケースがあります。
奥さまとしては、へそくりだったり、生活資金だったり、または子供の学費分の積み立てであったりというケースがあります。
これは絶対に避けるべきなのです。

こんなケースがあります
ご主人が事業をされていたり、または個人的な借入があったとします。
なかなか業績等が厳しく、返済が滞り始めています。
こうした折に不幸にもご主人が亡くなられてしまうケースがあります。
銀行への返済は延滞中で、何とか改善しようしているタイミングでした。

奥さまとしては、落ち着かれたのちに、まずは住宅ローンの手続きが必要で、これについては当初から設定されている団信(生命保険)によって住宅ローンは完済となります。
そして司法書士に登記事務を委ねて、自宅の名義を奥さま名義に変更します。
とここまでは問題ありません。問題は住宅ローン以外の借入です。
銀行はこう動く
銀行としては、住宅ローンについては保険により完済となったので良かった、では次に個人の延滞中の融資をどうするかと考えます。
その時に、借入人って誰になるのかを考えます。
不幸にもご主人がなくなっているので、法的に考えますと、資産(預金や不動産)や負債(借入や未払金)も相続される事となります。
では誰が承継する人となるのでしょうか。
保有資産を調査する
銀行は、まず資産をどなたが承継したのかを調査します。
これは不動産登記簿謄を閲覧する事で確認できます。
すると、相続発生を理由として奥さまに名義変更されていることが分かりました。
この時点で、銀行としては、延滞中の借入は奥さまに請求するという事が確定します。
つまり相続において、資産と負債があったときに、資産だけを相続するという事は、法的に許されていません。
つまり、資産を相続する限りは、負債も相続せざるを得ないということになります。
よって銀行としては奥さまに対して、現在延滞中の借入を、延滞中なのだから、一括ですぐに返してくれ、と言わざるを得ません。
この時、奥さまの預金はどうなる
銀行からすると、今度は奥さまが借入人ですから、奥さまに返す力があるか、返済に充当できる資産を持っているのかを調べます。
当然に自行の銀行預金から調査を開始します。
このケースにおいては、奥さまが将来の生活費のために、またお子さんの教育資金としてコツコツためてきた預金があったとします。
こうした事情には関わらず、銀行としては即座にこの預金の引き出しができないようにロックを掛けます。
というのも、銀行としては延滞状態にある借入がある一方で、目に見える自行の預金を自由にお使いいただくわけにはいかないのです。
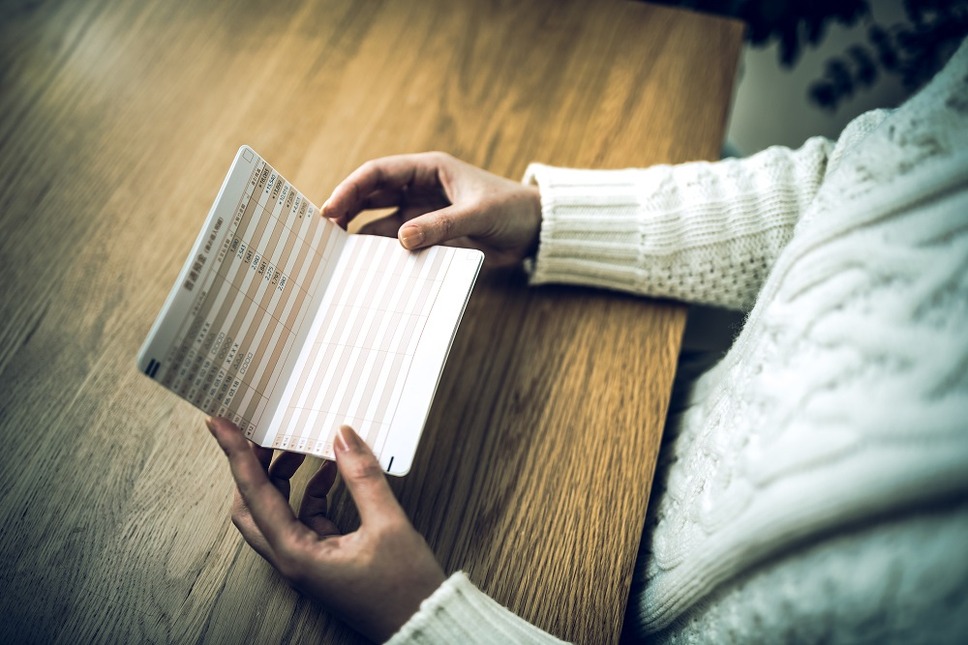
総括
ご主人に不幸があったとしても、必要な資金が生活のために必要であっても、お子様の学費であったとしても、どんな理由でも銀行としては、いったんは支払いをロックせざるを得ません。
銀行としても預金として預かった資金でもってご融資している以上、預金者に対する責任として可能な限りの債権管理は必ず求められるのです。
事情が分かれば、分かるほど何とかしてあげたいという気持ちにはなりますが、ここは仕事として、銀行員はやらなければならないという結論となります。
ですので、まずは奥さまの口座は、必ずご主人を別の銀行に開設し、借入をしている銀行からは奥さまの預金は見えないようにさせておくべきなのです。(執筆者:松野 のりこ)
自分でしっかり貯金しておきたい… そんなあなたには↓
貯金アプリfinbee 【iOS】
貯金アプリfinbee 【Android】









