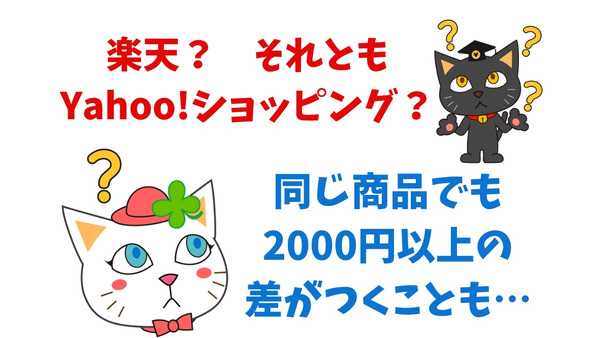目次
日本のスマホでの電子決済

8/21の日経新聞で、
との記事が掲載された。
背景は、海外からの観光客の誘致のためのインフラ整備の一環である。
以前の記事で、日本への観光客は、約3,000万人に到達する可能性があると言及され、国別では主に韓国、中国、台湾がメインであることを述べた。
その後2018年7月までの統計を見る限り、推計値で約1,800万人を超えている。
このペースで行くと、年間約3,000万人の可能性がより高まっている。
観光客の誘致のために、急ぐ電子決済の他国および日本での状況と、個人としての活用術を述べたい。
出所:日本政府観光局JNTO
他国のビジネスモデル

中国
電子決済のインフラ:主にAlipay(支付宝)およびWe Chat(微信)の2社寡占
ビジネスモデル:AlipayやWe ChatがそれぞれのQRコードのインフラを小売店に普及させている。
使用者は、小売店のQRコードをスキャンすると、銀行口座から引き落とされる。
ビジネスモデル構築:We ChatはAlibabaグループでオンライン小売で稼いだキャッシュを元に信用構築し、Alipayはゲーム事業で稼いだ信用をベースに、消費者と小売、支払い銀行をつなぐ役割をしている。
中国の場合は、民間企業が、
・ 個人のメッセージのやりとりで、少額のお金のやり取りを電子決済で慣れた状況で、店頭での買い物の電子決済が広がる
・ クレジットカードの普及の前に、電子決済が広がる
ということがわかる。
インド
電子決済のインフラ:ソフトバンク社とAlibabaグループが出資するPaytm、FBが買収した米国のショートメッセージアプリのWhatsApp、その他、即時支払サービス「IMPS」、デビットカード・サービス「Rupay」
ビジネスモデル:中国とは違い、ビジネスモデルは確立されておらず、インド政府主導で、10年前にインド決済公社(NPCI)を設立し、研究している。
スマートフォンでの決済だけではなく、スマートフォンが使えないインフラ状況での決済もできるように推進中である。
また、2016年にNPCIがスマートフォン用電子決済アプリ「BHIM」を導入し、高額紙幣を廃止したタイミングで普及に努めている。
QRコードは、インド政府として、統一規格で進めるという考えを示しているようである。
インドの場合の電子決済のインフラ整備の目的は、
・ 偽札の撲滅
・ 銀行口座を持たないインド国民の管理強化や少ない銀行ATMでお金をおろさなくても利用できる仕組み
など多くの課題解決が背景にあるようだ。
日本の動き
日本の場合は外国の観光客を誘致するためのインフラ整備と言っており、必ずしも自国民の利用の便利性を言っているわけではない。
そういう状況の中でスタートしているサービスがいくつか存在している。
1. 楽天Pay

楽天の会員数は不明であるが、将来の会員拡大に合わせて、規模拡大の可能性が秘められている。
中国やインドのような銀行口座直接での登録ではなく、クレジットカードを通した決済になっている。
リスクはクレジットカード会社を通して回避したうえでこのモデルが成立しているようです。
小売店ではローソンで使用できるが、利用できる店はあまり多くありません。
2. LINE Pay

現在利用者は7,500万人存在しているので、現段階では、最も規模が大きくなりそうである。
出所:We Love Social(2018年6月時点)
LINE Payのビジネスは、中国のWe Chatと同様に友人同士のSNSのビジネスモデルのインフラ基盤を利用して拡大している。
そして、LINEそのものは銀行ではないが、クレジットカードをを通すことにより、決済が可能となる。
導入店舗が少ないので、普及が不透明
中国やインドと違い、クレジットカードがある程度普及した日本では、スマホによる電子決済は、クレジットカードの代替手段にはなりにくい。
また決済そのものが、クレジットカードを登録するので、最初の手続きの煩雑さを厭わなければ、普及する可能性がある。
QRコードではない電子決済「Apple Pay」

ビジネスモデルとしては、クレジットカードを登録して使用するのは、楽天PayやLine Payと変わらない。
異なる点は、Apple PayはQRコードの決済ではなく、既存のiDとQUICPayとSuicaのインフラで決済できる点である。
よって、楽天PayやLINE Payよりも使用できる店舗が多い。
保有するデバイスがiPhoneと限定され、iPhone7以上のバージョンが必要とされるものの、現段階では楽天PayやLINE Payよりも対象店舗が多いため、利用が広がる可能性がある。
小売店が負担する手数料
小売店は、スマホの電子決済のインフラを導入したとして手数料を負担してまで、導入するかがカギとなる。
楽天Pay… 3.24%~3.74%(税別)
LINE Pay… 2.45%(税別)
We Chat… 2.0%(税別)
Apple Payは新たな手数料を小売店が支払う必要がないので、一番負担が少ないと言える。
僕自身は、中国のWe ChatやAlipayで慣れてしまったので、メリットは理解しているが、各コンビニやスーパーマーケット、飲食店でクレジットカードが利用できることを考えると、QRコードによるスマホの電子決済に乗り換えるメリットは感じられない。
一方で、クレジットカードを持たない人(若年層)等は、代替手段が現金なので、QRコード電子決済は進むと思う。
ポイント集める人であれば、楽天ポイントや各小売りのポイントをダブルで集められるので、メリットがある人もあるでしょう。
マーケティングのターゲットをどこに絞るかによって変わります。
出所:業界オンライン
観光客で可能性が広がるも、問題点はある

「日本は外圧に弱いと」いろんな方面で言われているが、お客さんが増加している観光客(現在は中国人や韓国人が多い)が多い都市、分野(旅館、ホテル、デパート)で一気に進む可能性があります。
その場合は残念ながら中国人が使うWe ChatやAlipayがスタンダードになるだろう。
We ChatやAlipayの問題点
・ WeChatやAlipayは中国の銀行に紐づけした中国人しか利用できない
・ 中国の銀行と紐づけした日本人は、日本では利用できない
この分野は、まだまだブルーオーシャンで、サービスの開拓の余地があると言える。
客観的に見ると、現段階ではApple Payが最も使いやすい。
消費者にとってみれば、電子決済の規格が複数あることによる不便さもあるので(クレジットカードを5~6枚持たないのと同じ)、僕自身は日本の場合しばらく様子を眺めることとしたい。(執筆者:廣田 廣達)