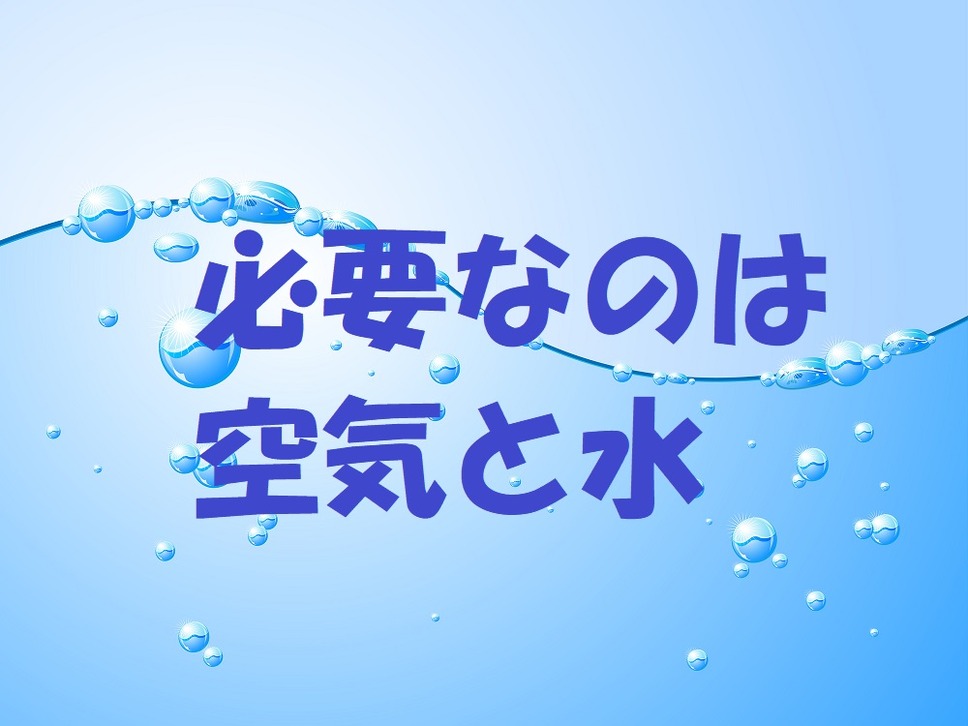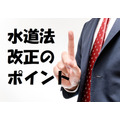目次
「水道法改正」審議8時間で可決
2018年7月5日、水道事業の運営権を民間に売却できる仕組みを導入することなどが盛り込まれた水道法の改正案の採決が衆院本会議で行われ、自民・公明両党と日本維新の会と希望の党(当時)などの賛成多数で可決されました。
審議時間はたったの8時間でした。
2018年6月18日に大阪北部地震が発生し、21万人以上が水道の被害を受けました。
そこで「水道管の老朽化」が問題となり、6月27日に水道法改正が審議入りし、8時間の審議を経て7月5日に衆議院本会議で可決されました。
「水道管の老朽化」と「水道法改正」は、どのように関係するのでしょう。
「数の論理」で成立した水道法改正 について、命にかかわる問題の内容を検証していきましょう。
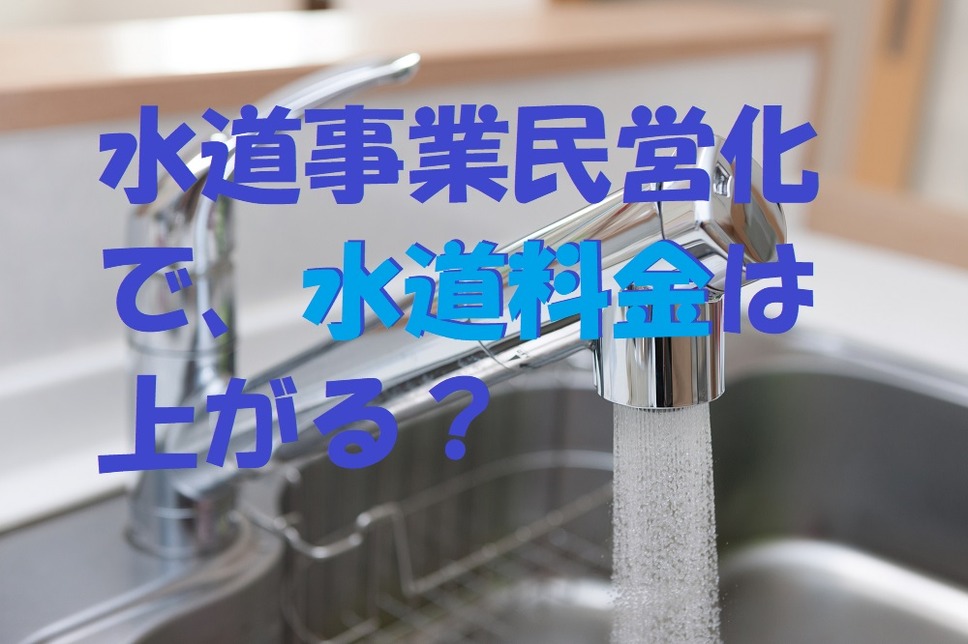
水道法改正に至る経緯
水道法改正に関するキーワード
2. 人口減少
3. コンセッション方式
1. 老朽化

日本の浄水設備の多くは1960年代から70年代の高度経済成長期に建設されたもので、今後も老朽施設の更新需要は年々増加していきます。
現在、耐用年数40年以上を超える水道管は約10万kmです。
これは地球2周半に相当します。
更新費用は1kmあたり1億円以上もかかるそうです。
これを早急に対処しなければならないのですが、現状ではかなり困難だというのが政府の見解です。
老朽化した水道管の更新のための「資金・人材」が不足しているようです。
これまで日本の水道運営は、企業会計原則に基づく地方公営企業法上の財務規定が適用されるため、独立採算で運営しています。
原則として、水道料金収入と地方自治体が発行する企業債(地方債の一種)で水道事業の運営・更新費用などが賄われてきました。
基本的には徴収した水道料金で運営や設備の補修などが賄われています。
2. 人口減少

人口減少により、水道料金収入が減少しています。
水道事業の大部分は固定費で、人口減少で水道需要が減っても、大きく運営コストが下がるものではありません。
厚生労働省は、約40年後には水需要が約4割減少すると試算しています。
人口減少による水道料金収入減少は、水道事業維持を困難にしています。
それゆえ毎年、水道料金は値上げされます。
4年間ずっと水道料金は値上げ
家庭用水道料金の、立方メートルあたりの月額料金は、過去最高の3,228円です。
日本政策投資銀行の試算によれば、このままだと30年後には6割も上がるそうです。
水道料金を値上げしても、水道事業者は赤字だそうです。
厚生労働省によると、市町村が運営する水道事業は全国で約3割が赤字となっているそうです。
自治体の水道事業赤字は、そのまま私たちが支払う水道料金アップにつながります。
老朽化した水道管を更新する費用も、私たちが支払う水道料金に跳ね返ってきます。
日本中の老朽化した水道管を全て更新するには、現状だと130年もかかるそうです。
少子化が進めば、水道料金値上げもどんどん進んでいくことになりそうです。
人材不足も影響
公的運営では人材の流動性が見込めず、高齢化に伴い人材が不足しているようです。
というのが、政府の主張です。
3. コンセッション方式

「コンセッション」とは、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の「所有権」は公共主体が有したまま、施設の「運営権」を民間事業者に設定する方式です。
コンセッション方式では、高速道路、空港で実施した例があります。
空港の場合、空港の土地は自治体の所有のまま、レストランや駐車場等の運営を民間企業が行います。
民間企業のコスト管理から収益を得るノウハウを活用するというものです。
水道管老朽化対策促進の名目で、市町村などが経営する原則は維持しながら、民間企業に運営権を売却できる仕組み(コンセッション方式)も盛り込んだのが、今回の水道法改正です。
ということです。
しかし空港施設や高速道路といった業務には適していても、国民の命にかかわる水道業務に関して、営利を目的とした民間企業を活用することに、反対派は抵抗しているようです。
政府は、自治体が民間企業の運営をしっかりと管理することを強調していて、不当な水道料金値上げを抑えるために、料金に上限を儲けることを決めるとしています。
民間企業を活用することで、地域の雇用を創出することにも繋がるとしています。
水道法改正のポイント
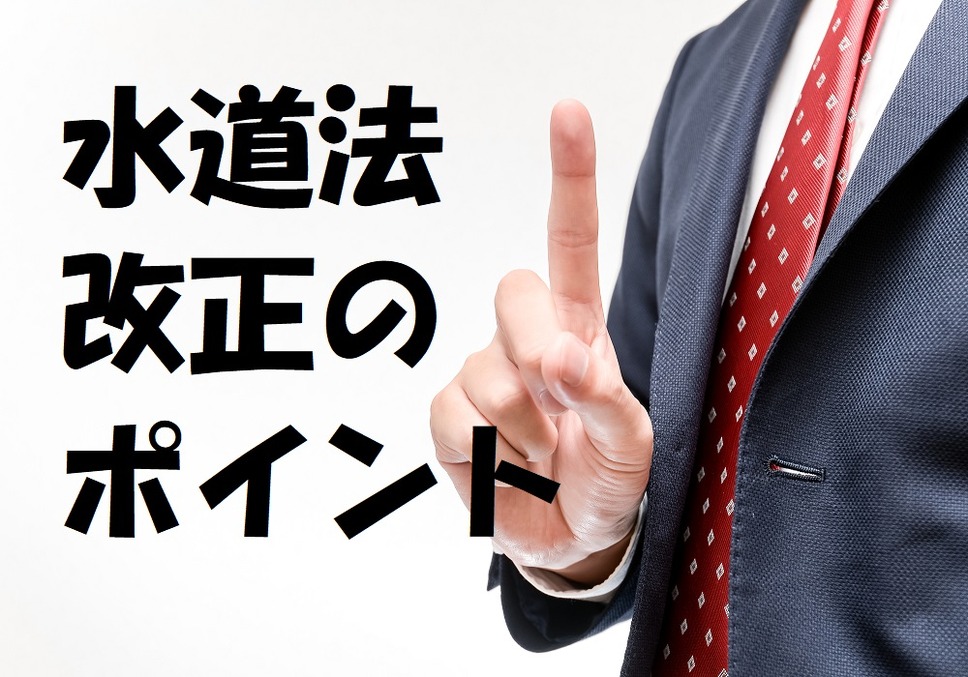
今審議されている「水道法改正のポイント」は以下の通りです。
・ 国が水道の基盤強化のために基本方針策定。都道府県、市町村の責務を規定
・ 広域連携を進めるため、都道府県が市町村などでつくる協議会を設置可能に
・ 自治体が水道事業の認可や施設の所有権を持ったまま、民間企業に運営権を委託できるコンセッション方式の導入
どこにも水道事業の「民営化」とは書かれてはいませんが、民間企業を選定し、自治体が管理するということは、間違いありません。
入国法改正は「移民政策ではない」と主張するのと同じように、安部総理は、水道法改正は「水道事業の民営化ではない」と主張しています。
ただ、2013年4月にアメリカのシンクタンクCSIS(戦略国際問題研究所)で行われた麻生太郎財務大臣兼副総理の講演で
と述べています。
明確に麻生大臣は「水道の民営化」を目指すと断言しています。
民営化ではないとしても、老朽化がすすんだ水道管を更新するには、自治体運営には限界があるから民間企業にやってもらうということは、まちがいありません。
なぜ自治体がダメで、民間企業ならできるのか…まだよくわかりません。
水道法改正のポイントの注目点
水道法改正のポイントの注目点は「広域連携」と「コンセッション方式」です。
水道法改正の流れは、
というものです。
政府は、
「自治体よりも民間企業のほうがコスト削減のノウハウがある」
「民間企業を参入させることで競争原理が働いて、さらなるコスト削減が期待できる」
「更新コストの削減は、水道料金アップを抑制することにも繋がる」
と政府は期待しています。
はたして、そううまくいくのでしょうか。
・ 民間企業は営利団体で、利益を拡大するためにコストを削減します。
・ コスト削減は不採算部分のカットでもあります。
・ 裁量は企業側にあり、利益を優先するあまり、住民サービスが削減されるのではないかという懸念が出てきます。
・ 人口減少による料金収入減少が水道事業を困難にしているので、人口減少が目立つ自治体や、規模が小さな自治体は、民間企業が参入しても、厳しい状況は変わりません。
営利を求める民間企業なら、小さな自治体を相手にしないのではと危惧されます。
人口減少が顕著な小さな自治体は「見捨てられる」ことにならないかということです。
不採算ではありますが絶対に必要な住民サービスこそ、営利を目的としない国や自治体が行うべきです。
広域連携
人口増加が見込めない小さな自治体での水道事業を考えてみましょう。
「広域連携」は複数の自治体を一つのグループとして住民サービスを提供するものです。
小さい自治体を1つにすることで、サービスコストの効率化をはかろうとするものです。
広域連携の意義はよく理解できます。
自治体単位という垣根を越えるというものですが、それはなにも民営化する理由にはならないでしょう。
広域連携をしても採算性が悪いとなれば、民間企業は切り捨てないかという懸念は残ります。
住民サービスを削減しないかという心配は常に付きまといます。
厚生労働省側は、水道事業民営化が実現しても小規模自治体には効果がないことを認めています。 コスト削減のため、あえて老朽化した水道管補修を、更に限界まで引き伸ばすことを、民間企業は考えないでしょうか。 反対派の意見では「不採算事業の切捨て」を心配する声が大きいようです。 営利団体の宿命で、企業は「利益の最大化のために動かず、倒産リスクの最小化のために動く」ものです。 道路事業関係者の間には「花の建設、涙の補修」というのがあるそうです。 建設事業は華々しいものがありますが、補修事業は地味な作業です。 企業にとって見れば という風潮が、まだあるのではないでしょうか。 民間企業に任せるとコスト削減が期待できるという政府見解にも、反対派は疑問を投げかけています。 「競争原理によるコスト削減ということが実際に起こるのか?」 「水道事業は独占事業といえ、競争が行われる事業なのか?」 水道料金値上げに上限が設けられれば、利益追求のためにサービスの質を落とすのは目に見えていると反対派は指摘します。 自治体は「住民」に目を向けますが、民間団体は「株主」を強く意識するものだという指摘もあります。 なにより水道事業って、民間企業にとって魅力あるものなのでしょうか。 公共事業は、談合や癒着は当たり前の世界です。 海外では、水道事業を民営化した後、さまざまな問題が生じて公営化に戻す「再公営化」の動きが目立ち、2000年から2015年の15年間で、37カ国235都市で再公営化がされています。 水道の民営化の失敗例としてよく知られているのが、マニラとボリビアの事例です。 米ベクテル社などが参入すると水道料金は4~5倍になり、低所得者は水道の使用を禁じられました。 アメリカのベクテルが水道料金を一気に倍以上に引き上げ、耐えかねた住民たちは大規模デモを起こし、200人近い死傷者を出す紛争に発展しました。 当時のボリビア・コチャバンバ市の平均月収は100ドル程度で、ベクテル社は一気に月20ドルへと値上げしたのです。 大規模デモは当時の政権側は武力で鎮圧されましたが、その後、コチャバンバ市はベクテルに契約解除を申し出ると、同社は違約金と賠償金を要求してきたそうです。 外資が参入してきて水道料金を引き上げ、水道料金が支払えない低所得者層は水が飲めずに、衛生上よくない水を飲んで病気になるケースがみられ、民間の水道事業者が利益ばかり追いかけたことにより、「再公営化」が世界の潮流となりつつあるという指摘もあります。 この外資企業と言われるのが「水メジャー」と呼ばれる企業で、2強と呼ばれるのがスエズ・エンバイロメント(フランスや中国、アルゼンチンに進出)とヴェオリア・エンバイロメント(中国、メキシコ、ドイツに進出)です。 30年で水道料金が5倍になったことで、2010年に再公営化したそうです。 企業の人員削減で水処理が不十分になり、茶色の水が出るという水質低下が見られたという例があります。 コスト削減による補修工事の延期の結果、老朽化放置で漏水率が上がっている都市もあれば、鉛が溶け出して水道汚染事故も起きています。 老朽化した水道管の更新を急ぐことは重要で、それは災害対策の一環としても大切です。 しかし、コンセッション方式による民間企業活用が良いのかどうか、水道料金の右肩上がりの値上げだけでなく、安全面でも、私たちはもっと関心を持つべき法案だと思います。 いずれにしても水道法改正は可決される見込みです。 私たちはどう向き合っていくべきなのか、ひとりひとり真剣に考えていきましょう。(執筆者:原 彰宏)水道法改正反対派の意見
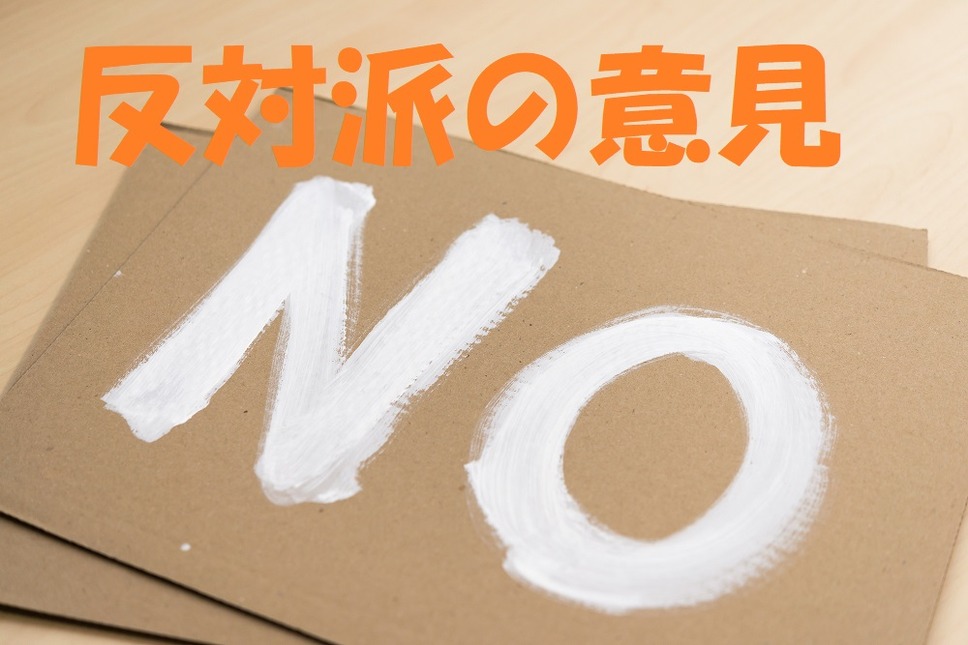
2000年~2015年で、37カ国235都市で再公営化

マニラ 1997年に水道事業を民営化
ボリビア 1999年に水道事業を民営化
パリ 1980年代に民営化
アメリカ アトランタ
人間が生きていくうえで必要なのは「空気」と「水」