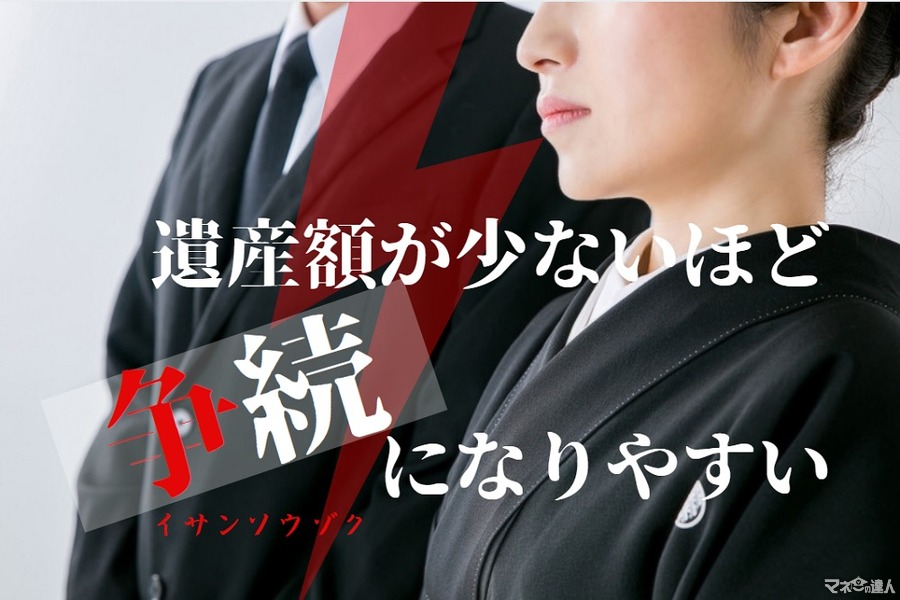一般の方は「遺産争い」、「相続トラブル」などと聞くと「一部の資産家・富裕層の抱える問題」と考えているケースが多々あります。
親が生きている間は子どもたちも仲も良さそうなので「うちに限って相続争いなんて起きるはずがない」と考えている方もたくさんいます。
しかし実際にはそういったご家庭でこそ、遺産争いの危険があります。
遺産相続の場面においては、相続財産が少ないケースにおいて多数の相続トラブルが発生しています。
今回は、
・ なぜ遺産額が少ないのに相続争いが起こるのか
・ トラブルを予防するにはどうしたらよいのか
弁護士が解説していきます。
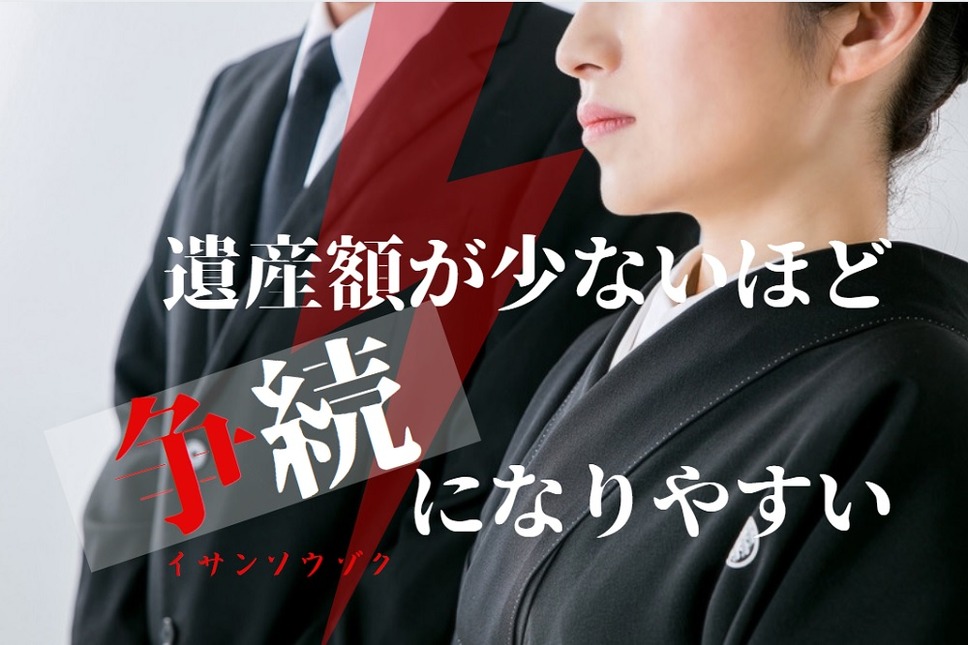
目次
遺産が少なくても相続トラブルが発生する
相続トラブルになると、自分達で話し合っても遺産分割協議が成立しないので、家庭裁判所で「遺産分割調停」を行う必要があります。
その遺産分割調停において、相続財産が5,000万円未満の案件の割合が、ここ最近毎年70%を超えています。
裁判所が発表している直近のデータ(司法統計 2017年度pdf)では、遺産分割調停の申立のあった総数が7,596件、相続財産価格が1,000万円以下の案件が2,451件で32.2%、1,000万円超5,000万円以下の案件が3285件で43.2%、合計で5,000万円以下の案件が75%以上になっています。
このように、相続トラブルになって家庭裁判所に持ち込まれるケースのうち4分の3は相続財産が5,000万円以下、約3割は相続財産が1,000万円以下という状況ですから、「相続トラブルは富裕層の問題」という認識が誤っていることがわかります。
遺産が少ないのに相続トラブルが起こる理由
遺産が少ないのにトラブルが起こると聞くと「なぜ?」と思われる方が多いでしょう。
以下では、相続財産が少ない場合に相続争いが起こる理由をご説明します。

1. 遺産が不動産しかない
相続財産が少ないケースでは、主な遺産として両親が居住していた不動産しかないことがよくあります。
不動産が1つしかないのに子どもたちが複数いたら、不動産を公平に分けるのは難しくなります。
特に両親と同居していた長男夫婦などがいる場合、家を売って分けることもできず、対応に窮してしまいます。
他の子どもたちが長男に家を譲れば良いのですが、譲らなければ長男は家を取得するために代償金を払わねばなりません。
資力がなかったら家を売って賃貸住宅などに移り住むか、長期分割払いで払っていくしかなくなります。
長男としても納得できず「このような結果は両親も望んでいなかったはず」と主張して争うので、兄弟との間で深い対立が生まれます。
2. 権利意識の高まり
昔の日本人は「家は長男が継ぐもの」、「家を継ぐ兄に自分の相続分を譲ろう」などと考えている方が多数いました。
しかし今はそういう時代ではありません。
長男を特別扱いせず、すべての相続人がめいっぱいの法定相続分を主張してきます。
しかし長男側は「自分が家を継ぐのだから、多めにもらえて当然」と考えており、意識のずれが発生します。
このような意識の変化によっても相続トラブルに発展しやすくなっています。
3. 介護をしていた相続人がいる
もう1つ、最近問題になりやすいのが親の介護です。
親と同居して献身的に介護を行ってきた相続人がいる場合、そういった相続人は「私の相続分を増やしてもらって当然」と考えます。
このように、相続財産の増加に特別な貢献をした人の遺産取得分を増やすことを「寄与分」と言います。
しかし他の相続人は、そのような特別扱いに納得できません。
「子どもだから介護しても当然」「寄与分など認めない」と主張するので、介護した相続人とそれ以外の相続人との間でトラブルが発生します。
4. 生前贈与を受けた相続人がいる
両親から生前贈与を受けた相続人がいる場合にもトラブルが起こりやすいです。
生前贈与を受けた相続人がいる場合には「特別受益」があるとしてその人の相続分を減らす計算をします。
この計算方法のことを「特別受益の持ち戻し計算」と言います。
しかし生前贈与を受けた相続人は「贈与を受けていない」と言い出したり「贈与ではなく代金を払った」と言ったりして、特別受益の持ち戻し計算を否定しようとします。
すると他の相続人と意見が合わずトラブルになります。
5. 離婚前の子どもがいる
最近では離婚も随分一般的になり、離婚前の子どもと今の家庭の子どもがいる方も増えています。
そういった方が亡くなると、離婚前の子どもにも今の家庭の子どもと同等の遺産相続分が認められます。
随分と前に離婚してその後一切没交渉で、遺産の形成にまったく関与していない前妻や前夫の子どもにも、今の子どもと同じだけの遺産を渡さねばなりません。
認知した婚外子も同じです。
そうなってくると、今の家庭の子どもはとうてい納得できないでしょう。
何とか遺産を渡さない方法はないかと考えます。
前妻の子どもに、いきなり何の挨拶もなく「放棄書にサインしてほしい」などと書面を送りつけたりしてトラブルになる例もあります。
6. 遺産の使いこみ
両親が認知症になってしまい、同居の長男などが両親の預貯金を使い込んでしまうケースがあります。
すると相続開始後、他の子どもたちが「遺産を返してほしい」と主張します。
長男は「使い込んでいない、両親のために使った」などと反論するのでトラブルに発展します。
相続トラブルを避ける方法
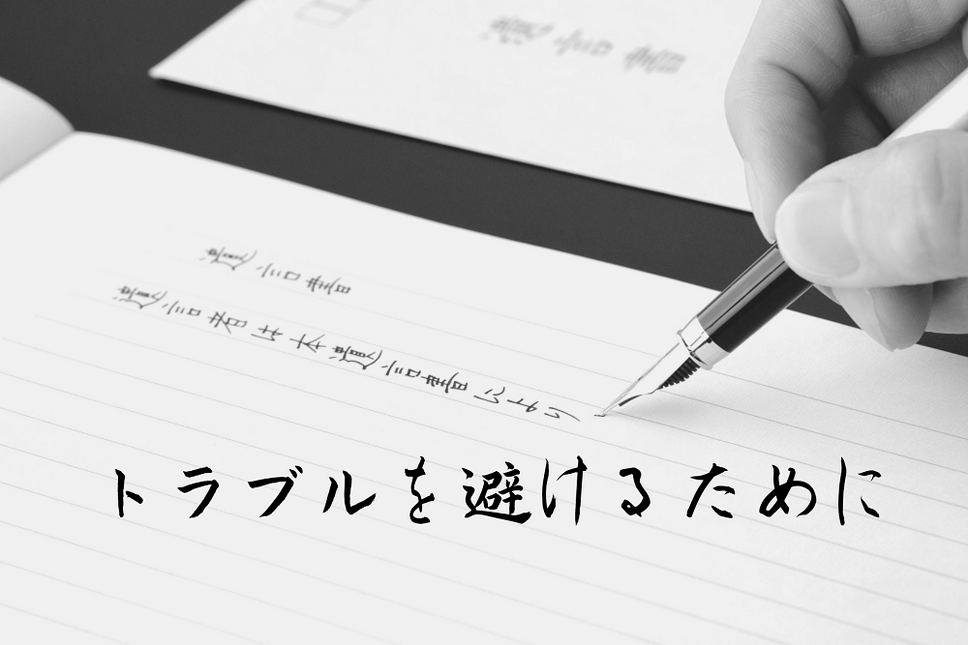
一般家庭でも起こりうる相続トラブルを避けるには、どのような対応をすれば良いのでしょうか?
1. 生命保険を利用する
1つは、生命保険に入っておくことです。
生命保険金は受取人の固有の権利と考えられており、相続財産の範囲に入りません。
そこで多めに遺産を相続させたい相続人がいたら、生命保険の受取人にしておくとスムーズに財産の受け渡しができます。
たとえば長男に自宅不動産を残したい場合、遺言によって不動産を長男に残すと共に生命保険の受取人にしておきます。
すると親の死亡後には長男が不動産を相続し、他の兄弟に対しては生命保険金から代償金を支払うことが可能となります。
そうすれば他の兄弟ともめて遺産分割調停をする必要はありません。
2.遺言をする
非常に有効な方法として遺言があります。
遺言をすると、自由に相続財産の処分方法を決定できます。
長男に不動産を残すこともできますし、介護してくれた子どもに多くの遺産を相続させることも可能です。
前妻の子どもと今の家庭の子どもがいる場合には、今の家庭の子どもに多くの財産を残すこともできますし、遺言で特別受益の持ち戻し計算を免除することも可能です。
ただし遺言によって遺産を多く相続させたり遺贈したりすると、「遺留分侵害額請求」の対象になります。
配偶者や子どもなどの法定相続人には、遺産の最低取得分として「遺留分」が認められます。
遺留分を侵害する遺言があると、侵害された相続人は侵害した相続人に金銭による賠償を請求できるのです。
遺留分侵害額請求が起こると、請求者と被請求者との間でトラブルになるので、せっかくの遺言が紛争の種になってしまいます。
遺言をするときには、遺留分侵害額請求がなるべく起こらないように、遺留分権利者にも一定の遺産を与えるなど配慮しておきましょう。
また遺言書は「公正証書」で作成すると確実性が高まります。
自筆証書遺言だと、どうしても遺言によって不利益を受ける相続人が「無効」「偽造」などと言い出しトラブルになる可能性が高まりますし、隠されたり破棄されたりするリスクもあるので、お勧めできません。
3. 後見制度を利用する
認知症などによる判断能力の低下が心配であれば「後見制度」を利用して、生前から適切な方法で財産管理をしておくことをお勧めします。
後見制度によって選任した後見人に財産管理をしてもらっておけば、同居の長男などが財産を使い込むことはできませんし、他の相続人における疑心暗鬼も生み出さずに済みます。
親の生前からトラブル予防の対策
遺産相続トラブルが起こると、2年も3年も「争続」の紛争が続いてしまい、相続人の方達が疲弊します。
親の生前からトラブル予防の対策を進めておきましょう。(執筆者:松村 茉里)