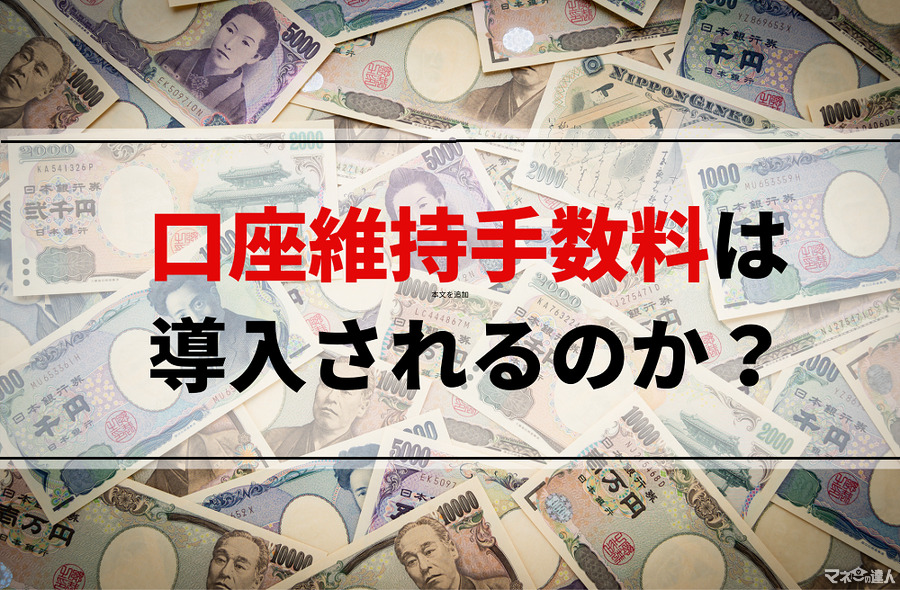最近、
「銀行の普通預金口座における口座維持手数料が導入されるかもしれない」
というニュースをよく耳にしないでしょうか?
実は、これについては数年前から大手銀行を中心に検討されており、現在その可能性が非常に高くなっています。
一方で、欧米では口座維持手数料は当たり前で、
ほとんどの銀行で導入されていると言われていますが本当なのでしょうか。
今回は、報道された内容などをもとに日本の銀行での口座維持手数料導入の可能性について議論をし、欧米での口座維持手数料について解説します。
欧米での状況をみれば、それを参考にして日本の銀行がどのように導入するのか大体予測できると思います。
目次
発端は日銀のマイナス金利政策

2017年12月、産経ニュースは、
・ 三菱UFJ銀行
・ 三井住友銀行
・ みずほ銀行
の3つのメガバンクが口座維持手数料の導入の検討を始めたことを報じました。
2016年に日銀は、民間の銀行の貸し出しを増やすために、民間銀行が日銀に預けている預金金利をマイナス(−1%)にしたことがその背景にありました。
このマイナス金利政策により、民間銀行の経営が苦しくなったのです。
特に、地方銀行が大きな影響を受けたようです。
現時点でも、口座維持手数料の導入はまだ検討段階ではあるようです。
しかし、三井住友信託銀行の橋本社長は、2019年9月における産経新聞との単独会見において、口座維持手数料導入ついてもう少し踏み込んだ発言をしました。
と述べたのです。
三井住友信託銀行は大手銀行のひとつであるため、この発言は重いですし、他の銀行もこのように考えているとみて良いでしょう。
その後、2019年10月31日、日銀の黒田総裁は必要があればマイナス金利をさらに引き下げる可能性を示唆したことが多くのメディアで報じられました。
以上のことから、口座維持手数料の導入はほぼ行われると覚悟しておいた方がよさそうです。
欧米での口座維持手数料は必ずしも当たり前ではない
日本のメディアなどでは、欧米において口座維持手数料はほとんど全ての銀行に導入されていると言われているのですが、本当なのでしょうか?
アメリカでのケース
例えば、US bankという銀行におけるEasy checking口座では月に6.95ドル(約760円)徴収されます。
ただし、合計で1,000ドル(約10万9,000円)以上が毎月入金されれば無料になります。
つまり、給料支払いをこの銀行口座に指定していれば手数料は取られません。
他の銀行を見てみると、多くの銀行は口座維持手数料を取っています。
場合によっては、月に30ドル(約3,200円)取られますが、多くの場合US bankと同様に条件付きで無料になるようです。
ヨーロッパ(イギリスとスペイン)でのケース
イギリスでは、スペインのメガバンクであるSantander(サンタンデル)を除いた主要な銀行では口座維持手数料は取っていません。
主要な銀行として、他にはHSBCやRBSがあります。
Santanderでの代表的な銀行口座では月に口座維持手数料として5ポンド(約700円)取られますが、1.5%(変動)の利息で相殺できます。
一方、口座維持費を取らないベーシックアカウントもありますが、利息は0%です。

スペインのほとんどの銀行では、口座維持手数料が取られます。
しかし、同様に利息で手数料を相殺できますし、もしくは給与が毎月振り込まれていれば無料になるケースがほとんどです。
以上のことから、欧米では口座維持手数料は必ずしも当たり前ではなく、またあったとしても何とか無料にできるケースが多いです。
日本の口座維持手数料を予想
日本の銀行で口座維持手数料導入される場合、同様に条件付きで手数料をとるのではないでしょうか。
日本の場合、金利が低すぎて利息で手数料を相殺させるのは困難なので、一定以上の金額が入金されれば手数料は免除されるということになればよいのですが。
欧米の例を参考にすると、口座維持手数料の金額は月に数百円から数千円くらいになることが予測されます。
ただし、銀行業界(特に地方銀行)は預金者の反発に対する警戒感が強い上にほとんどの日本人は経験したことがないため、最初に導入される手数料はかなり低いか限定的である可能性があります。
その後、他の手数料と同様に少しずつ口座維持手数料は上がっていくかもしれません。
一方で、消費税が上がった後に口座維持手数料が導入されるとなると、消費者心理に悪影響を与え、消費動向指数が低下するのではないかと考えられます。
これは日本経済をさらに悪化させるので、むしろこれが一番大きな問題になるかもしれません。
口座維持手数料に対する対策
口座維持手数料は月ごとで見るとそれほど高くはないのですが、年単位で見ると結構な値段で無視できません。
したがって、口座維持手数料が導入された場合、使っていない銀行口座を閉じるなどの対策をするべきでしょう。
もしくは今から準備しておいても良いかもしれません。(執筆者:小田 茂和)