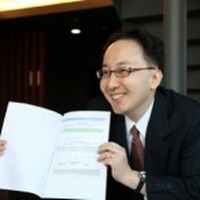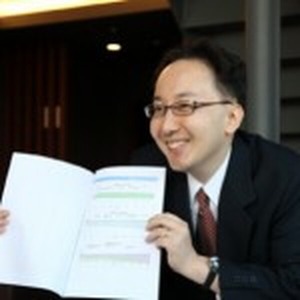令和元年(2019年)は、米中貿易摩擦に代表されるように、世界的にも景気が不安定な年となりました。
結果として、米やEUが利下げや金融緩和を行い、日本でも日銀への追加緩和期待から、8月には「長期金利」が過去最低水準まで低下しました。
これにより、変動金利と全期間固定金利の金利差が1%未満まで接近し、「フラット35」などを考える人には、大変有利な状況となりました。
以上の背景を踏まえ、今年も令和2年(2020年)の住宅金利動向を占ってみたいと思います。
今回も、変動金利と全期間固定金利に分けてお送りします。
目次
「変動金利」の動向

変動金利は「短期プライムレート」に連動しており、その「短期プライムレート」は日銀の政策金利に連動する仕組みになっています。
したがって、変動金利の動向を知るには、日銀の金融政策決定会合に注目すれば良いのですが、日銀は現在マイナス金利政策を採用しています。
つまり、このマイナス金利政策が目標とする、「2%の物価上昇率」を達成すれば動きがあると思いますが、現時点では達成の目途は立っていません。
故に、変動金利は現在の水準を維持し、低位のまま推移する見込みです。
「全期間固定金利」の動向
全期間固定金利は、10年もの国債の利回りである「長期金利」や、10年もの以上の国債利回りである「超長期金利」に連動する仕組みになっています。
国債は相対で取引されており、世界のさまざまなリスクに連動するため、全期間固定金利は変動金利よりも、金利が上下しやすいので注意が必要です。
日銀が追加緩和を行うと、通常は「長期金利」や「超長期金利」が低下しますが、「超長期金利」の低下は保険会社の運用難などマイナス面も見過ごせません。
今年8月に、「長期金利」が過去最低水準まで低下した時、日銀の黒田総裁が
超長期金利の低下は望まない」
と発言し、「超長期金利」は一転して上昇しました。

これらの動きを勘案すると、追加緩和で「長期金利」や「超長期金利」が低下しても、一定以上低下すると、日銀の口先介入が入るものと考えられます。
故に、今年8月ほどの水準までは低下しないとしても、「フラット35」に代表される全期間固定金利は、有利な状況で推移する見込みです。
民間銀行の「ミックスプラン」も選択肢
変動金利にこれ以上の下げ余地がない中で、全期間固定金利がここまで低下すると、通常は全期間固定金利で返済額を確定させた方が有利です。
ただ、変動金利も捨てがたいと考えている人は、民間銀行が採用している、変動金利と全期間固定金利を組み合わせる、「ミックスプラン」を利用すると良いでしょう。
を基本に、住宅ローンを有効活用してください。(執筆者:1級FP技能士、宅地建物取引士 沼田 順)