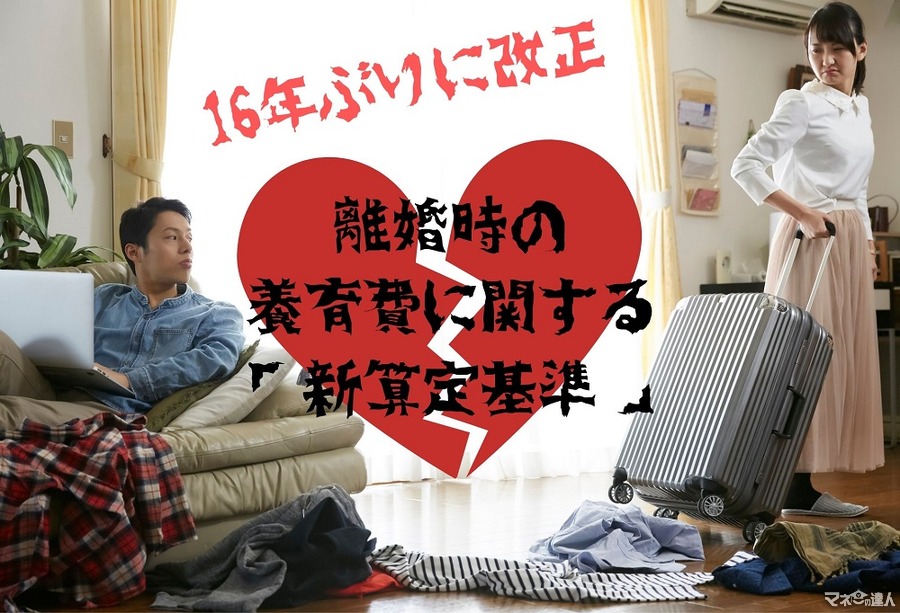2018年の婚姻に関する統計では婚姻件数59万組に対し、離婚件数は20万7,000組となっており、およそ3組に1組の夫婦が離婚を経験する可能性があります。
離婚時の関心事のひとつとして、「子供に対する養育費」が挙げられます。
実際の金額は個々のケースを勘案し金額が決定することが多いのですが、一定の目安として利用できるよう裁判所は養育費に関する算定基準を公開しています。
そして、2019年12月23日にこの算定基準が16年ぶりに改正されました。
今回は離婚時の養育費の目安として使用される養育費の新算定基準について解説していきます。
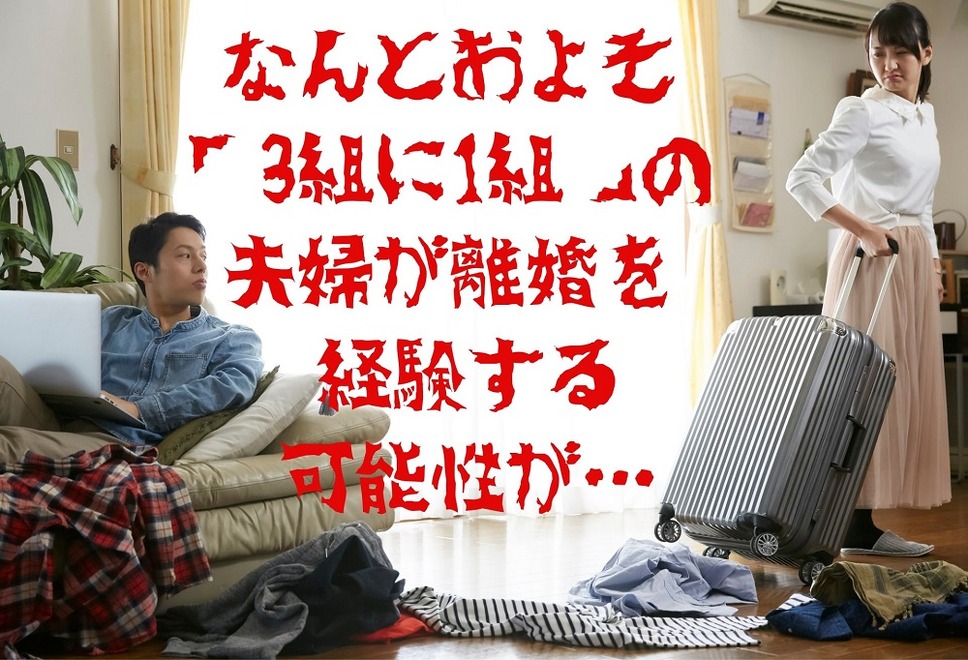
目次
養育費の算定基準の仕組みについて
養育費の金額を左右する要素として、
・ 年齢(0~14歳と15歳以上で区分)
・ 養育費の支払い義務者の年収(多くの場合で男親)
・ 養育費の受け取り権利者の年収(多くの場合で女親)
・ 自営業か会社員かなど
によって金額が変化していきます。
新算定基準においては旧算定基準よりも養育費は全体的に値上がりしており、値下がりするケースは存在していませんでした。
新旧算定基準の養育費の違いをシミュレーション
実際に新旧算定基準において養育費はどれほど値上がりするのでしょうか。
2018年における男女の1年間の平均給与(男性約550万円、女性約300万円)を基に、14歳以下の子供2人の場合の養育費を試算してみたところ、その結果は旧算定基準では月額4~6万円であったのに対し新算定基準では6~8万円となりました。
しかし、今回の算定基準の変更はあくまで今後の離婚調停での養育費の支払い目安として用いられるため、すでに養育費について合意している場合は個別の事情を基に増額の交渉を行う必要があります。
今回の算定基準の改正は増額を検討すべき事情とは見なされていませんので注意しましょう。
自営業の場合は養育費の支払金額が大きくなっているので注意
養育費の算定基準は権利者・義務者の年収と雇用形態および子供の人数と年齢を勘案されます。
新算定基準では旧算定基準よりも全体的に養育費は値上がり傾向となっており、値下がりするケースは存在しませんでした。
中でも権利者・義務者の雇用形態が自営業の場合は給与所得者よりも年収に対する養育費の支払い金額が大きくなっていますので注意が必要です。(執筆者:菊原 浩司)