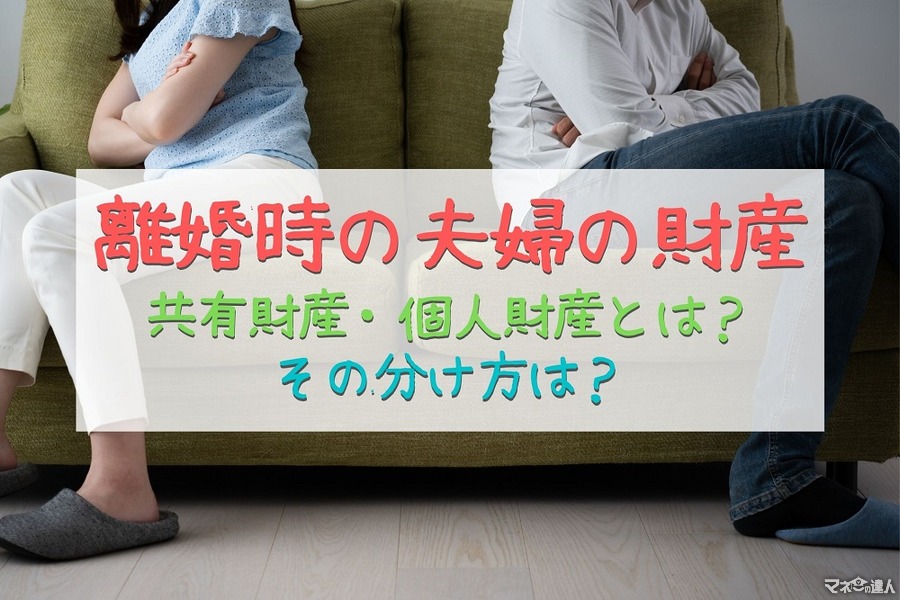離婚することになってしまった場合、親権や養育費の取り決め同様に大切なのが、夫婦の財産をどう分けるかということです。
婚姻前から夫婦の一方が持っているなどで、
・ 分与の対象となる「共有財産」
について説明します。
目次
「財産分与」とは

離婚時における財産分与は民法で認められた制度であり、配偶者の一方は相手方に対して、離婚協議の際、当然に分与の請求ができます。
参照:民法768条1項
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いてきた「財産」につき、どの財産をどのように夫婦間で分配するかということです。
婚姻期間中に双方に生じたすべての財産のうち、分与の対象になるのは「共有財産」のみとはいえ、共有財産の範囲は意外と広いのです。
原則は「夫婦共有」

婚姻中の収入は全て夫が稼ぎ、妻は専業主婦であったとしても、それらの収入は全て夫婦の共有財産とみなされます。
これは実際がどうであっても、
との考えによるものです。
法律の明文はないものの、裁判では、ほぼこの考えに沿った判決がなされています。
共有財産なので、分配の割合は1/2ずつが基本です。
共有財産の具体的な内容

実際に共有と認められる主な財産としては、
・ 現金
・ 預貯金
・ 保険料
・ 退職金
などがあります。
結婚後に購入した不動産は、大きな共有財産といえます。
ただし、
・ 結婚後であっても、どちらかの親族の援助により購入したもの
については、共有とはいえ分与割合がその分少なくなります。
個人財産(特有財産)とは
「個人財産=特有財産」とは、夫婦がそれぞれに婚姻前から有していた財産や、婚姻後であっても相続で得た財産のことです。
こういった財産は共同で形成したものとはいえず、夫婦それぞれの財産となり、財産分与の対象になりません。
預貯金の名義は無関係
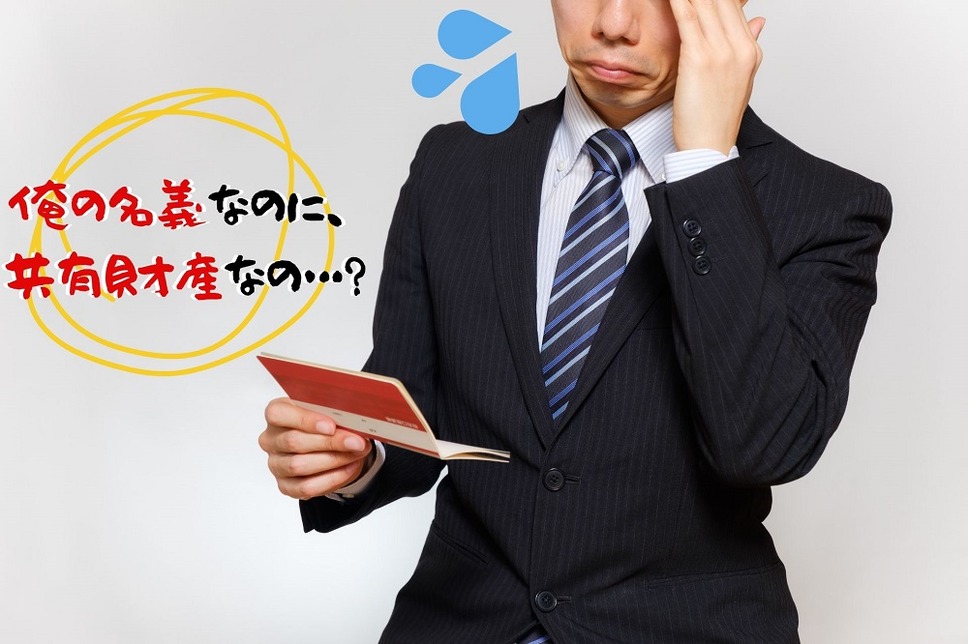
預貯金は、結婚後に発生したものであれば、たとえすべての名義が夫となっていても、共同して形成した共有財産であることをしっかり覚えておきましょう。
婚姻中に加入した保険金を解約する場合は、その返戻金が共有財産となります。
退職金についての考え方
退職金は、配偶者の貢献があって得られると考え、やはり共有財産となります。
ただし、共有と認められるのは婚姻中に仕事をしていた期間のみです。
また、あまり若い年齢での離婚だと、そもそも退職金が受け取れるかも分からないため、分与財産には含まれないとするのが一般的です。
正当な権利を主張して後悔しない分配を
結婚していた期間が長いほど、財産分与は離婚時の重要な協議事項となってきます。
財産を「もらう」のではなく「分配する」という意識を持ち、正当な権利として堂々と主張することが大切です。(執筆者:橋本 玲子)