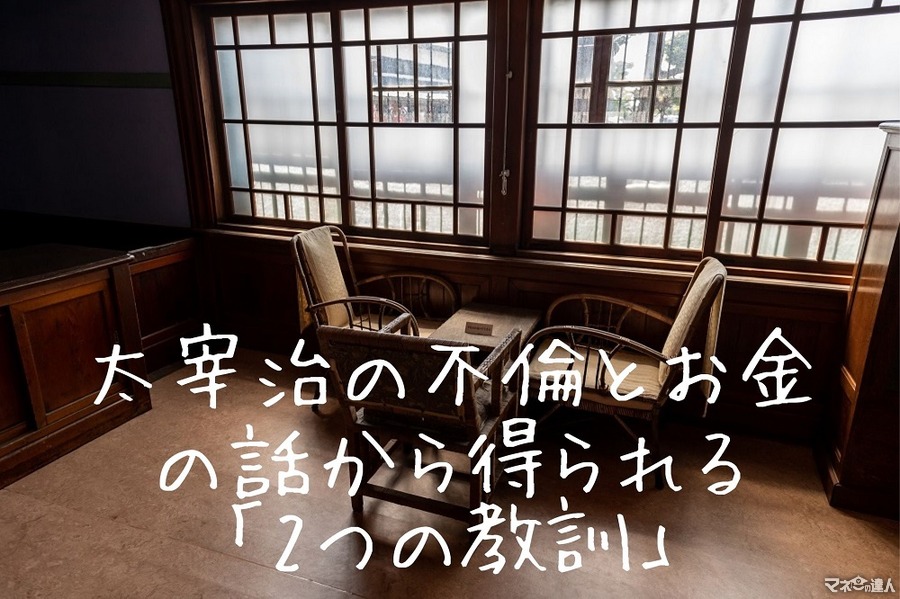今回は、太宰治に関わる2冊の本をもとに太宰のお金と遺産相続にまつわるお話しをしたいと思います。
なお、文中において敬称は省略させていただきましたのでご了承ください。
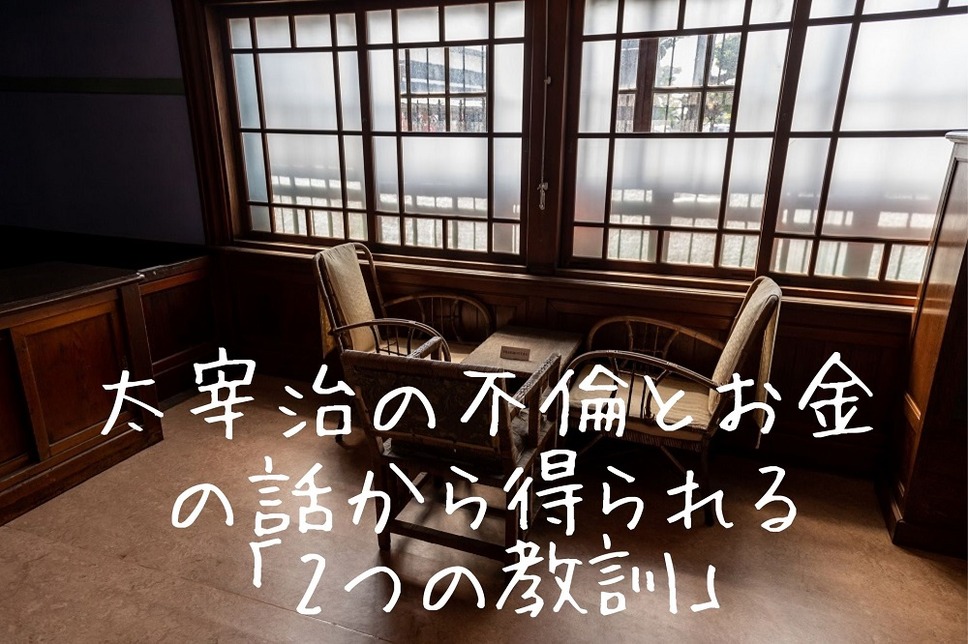
目次
太宰治の実生活でお金を握っていたのは
太宰の実生活について妻の津島美知子が「回想の太宰治」にて書いています。
生活費の原資は、大地主であった実家からの仕送りであったようです。
結婚当初は妻が財布を握っていたようですが、長女が生まれてからは「ごく自然に、財布はとり上げられ」と書かれています。
太宰治は作家ですので、作品を生み出すためには取材が必要です。
ベストセラーになった「斜陽」の取材先であった太田静子に、太宰は生活費としてのお金を渡していたようです(太田治子「明るい方へ」)。
静子との関係を妻にばれないようにするためにも、作品の印税は太宰自身で管理していたと推察されます。
さまざまな女性と付き合いそれをリアルタイムで作品にしてきただけに、自由になるお金は必要だったのでしょう。
太宰治の相続人は誰なのか
太宰が取材先の女性である太田静子と愛人関係になり、生まれた子が作家としても活躍している太田治子です。
太宰自身の筆で昭和22年11月12日付で認知しています。
その7か月後である昭和23年6月13日に、玉川上水で山崎富栄と入水自殺をしました。
この頃に民法は大きく改正されました。
具体的には、昭和22年5月2日までに相続が発生していれば、家督相続といって原則的には、長男(年長の男)がすべてを相続したわけですが、太宰が認知した太田治子には改正後民法(昭和22年5月3日以降の相続)が適用され、相続人の地位が与えられたというわけです。
認知された子(太田治子)は相続放棄していた
相続人であった太田治子が自身の著書である「明るい方へ」に、そのあたりの事情を書いています。
太宰の亡くなった後、「津島(太宰の本名)家から解決金として金10万円が支払われた」とのことです。
認知された太田治子は「家庭裁判所を通じ遺産放棄の手続きをした」と書かれていました。
太宰の相続人は妻美知子と実子が3人(長女園子・長男正樹・次女里子)と認知した子 治子がいました。
当時の法定割合は、妻が1/3、子は全員で2/3、さらに非嫡出子は1人当たりの相続分が嫡出子の1/2です。
当時の妻の法定割合は1/3(現在は1/2です)、子(全員で)は2/3です。
嫡出子(夫婦間の子)と非嫡出子(婚姻外の子)では、1人当たりの相続分が2分の1であるため、治子の相続分は、
となり、子全員の中では1/7(2+2+2+1)となり、全体の遺産から見ると
あったわけです。
太宰の遺産額は不明ですが、治子の親権者である静子の意思で放棄したということでしょう。
解決金10万円の考え方

この解決金10万円は、おそらく大田静子に提供してもらった「斜陽日記」の取材費として払われたのではないかと推察します。
なぜなら相続人である治子に太宰の遺産として10万円を渡してしまえば、治子は単純承認したとして相続放棄が認められなくなってしまうからです。
10万円については、当時の太宰の所得と比較できます。
「税務署からの通知で、昭和22年の所得が21万円。それに対する所得税が11万7,000円」(津島美知子「回想の太宰治」)と書かれています。
となると税引後9万3,000円であり、10万円は太宰の手取り額以上です。
実際の太宰は、前年あったはずの21万円は使い果たしており翌年請求された納税金額に困惑していたそうですから、遺産はあまりなかったと思われます。
太宰治から得られる教訓1「遺言」
心中事件を起こすことで、「認知した子」が相続人となり、津島家と太田家に軋轢を生んでしまうことを太宰自身は想像していたのでしょうか。
恐らく、治子の「養育費」は頭にあっても、相続問題までは頭になかったのではないかと思われます。
時代は家督相続からの転換期でした。
現代では、不倫の子と夫婦間の子の相続分は同じです。
ちなみに、愛人には法定相続分はありませんが、遺言を書いてもらえば遺産をもらうことは可能です。
太宰は「遺書」は残していますが、「遺言書は」書いていません。
夫婦間以外の子がいる方はぜひ遺言を残してください。
折しも、令和2年7月10日から法務局での自筆証書遺言の保管制度も始まりました。
自筆証書遺言でよいのか、公正証書遺言の方がよいのかは、ご家庭の事情にもよりますが、遺言書の作成が必要なのは確かです。
また、認知した子に生前に贈与して「遺留分の放棄」をしてもらうといった方法もあります。
太宰治から得られる教訓2「納税」
太宰が納税資金に苦しんだところにも時代背景がみえてきます。
昭和23年から税制は「申告納税」に変わりました。
恐らく、当時たまたま「斜陽」がベストセラーになった太宰が無申告であったため、当局が目を付けたのではないでしょうか。
現在でもさまざまなところから情報収集されており、無申告でも「バレナイだろう」は通用しません。
自営業の場合には、前年の所得に対して翌年にさまざまな税を支払うことになります。
所得税、市区町村県民税、国民健康保険税などです。
従って、コロナの影響で今年の所得が少ない方が前年に好調だった場合には、これらの納税で困ることになるのは明白です。
売上が多い年こそ翌年の納税資金を事前に確保しておくことが大切です。(執筆者:1級FP、相続一筋20年 橋本 玄也)