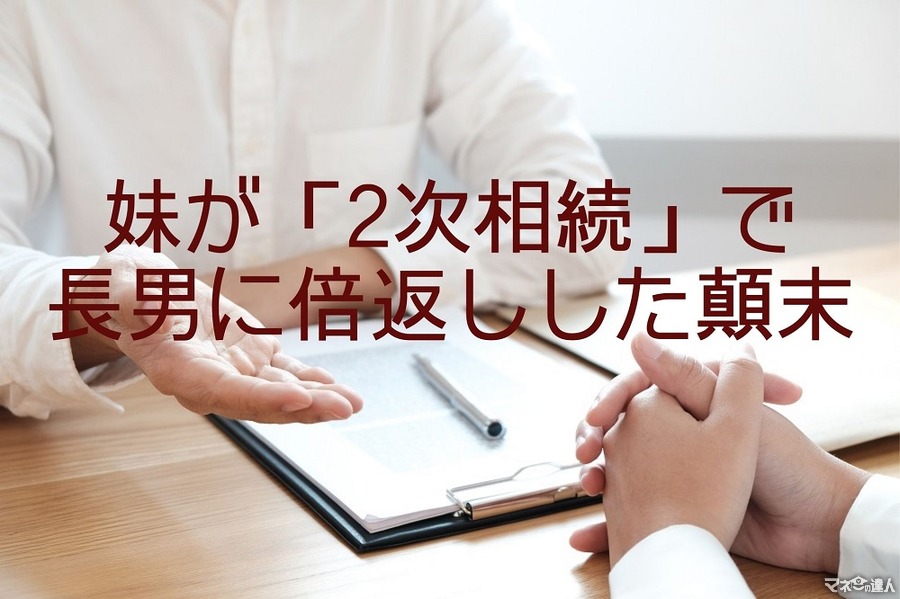今回は、ある家族の相続の問題を見ていきます。
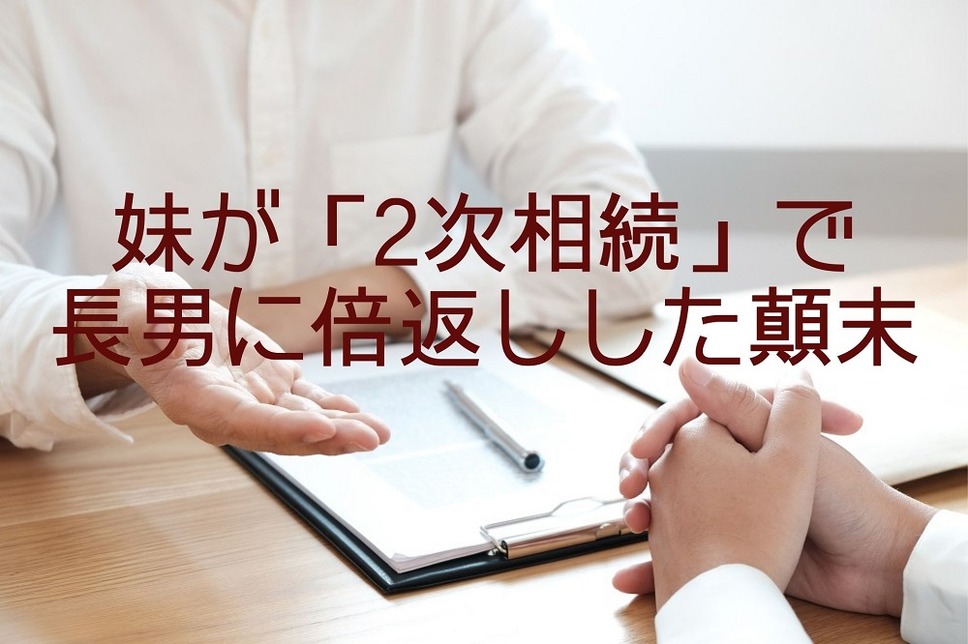
目次
相続の税金対策だけ考えていた長男
木村(仮名)家は、先祖代々の地主で農業を行っていました。
もっとも農業を本業にしていたのは祖父までです。父・木村誠は会社員をやりながらの兼業農家で、その長男の木村一郎は会社員です。
先祖代々の農地が市街化区域に指定されて固定資産税が高くなってきましたが、農業収入だけでは固定資産税も支払えない状態でした。
そのうえ父・誠が亡くなった際の相続税には、長男・一郎の退職金をすべて持っていかれそうです。
土地を売却して納税資金を作るという考えはありませんでした。長男・木村一郎は「先祖代々の土地を減らす訳にはいかない」と考えていたからです。
長男の相続対策1.
父・木村誠は、生前に長男 木村一郎さんの妻を養子にしました。
これには、
・ 相続税の総額を出すうえでの法定相続分も減少させられる
という相続税の対策として大きな効果があります。
養子縁組は市役所に届け出(証人2人必要です)だけで済み、手続きは簡単です。費用もほとんどかかりません。
長男・木村一郎には妹・良子がいますが、養子縁組時には妹の承諾は不要です。
長男の相続対策2.
相続人でない孫への贈与は、相続税の3年以内の加算の対象にもなりません。
父は毎年自分の口座から預金を引き出し、長男・一郎の子(孫)に孫名義の預金口座に移していました。
長女(妹)にも子はいましたが、長女・良子の子(孫)名義はの預金口座はありませんでした。
父が亡くなり1次相続が発生、対策の結果は
長男・一郎は、父の遺した不動産の半分は母に相続してもらい、残りの財産は長男である自分がすべて相続すると主張します。
預金は相続税の支払いに充てるため、妹・良子へは、相続放棄を求めました。
長女(妹)は、そもそも法定割合まで遺産を求める気はありませんでしたが、「相続放棄」の言葉を聞いて考えが変わりました。
1円も譲らないといった長男(兄)の姿勢に怒り心頭でした。
弁護士に相談したところ、「長男(兄)の妻」と父が養子縁組をしているので、その結果として長女(妹)の法定割合は1/4から1/6に減ってしまっていることを知らされました。
自分の知らないところで養子縁組が行われていたことも怒りの原因です。
父の遺言書はなく、遺産分割は申告期限ぎりぎりまで揉めましたが、実家の繁栄のためと思い妹は分割協議書に押印しました。
1年後相続税調査の連絡が
故人(父)の銀行口座から毎年預金が引き出されていたことについて税務署から質問されると一郎は、
と答えました。
税務署の方は
さらに定期の証書を故人が管理していたとなりますと、贈与ではなく預かり物です。
お孫さんはお祖父さまから贈与を受けたことをご存じでしたか? 贈与でなければ名義に関係なく相続財産になるのです」
との説明を受け、追加の税金を支払うことになりました。
一方、自分の子の名義の定期がなかったことを母から聞くと、長女(妹)の怒りはさらに強くなりました。
妹が2次相続(母の相続)で倍返し計画

長男夫婦と同居している母は、長女が遊びに来るたびに何かと不満をこぼします。
そこで、長女(妹)と母が相談し、今度は「母が亡くなったらすべての財産は長女に相続させる」という公正遺言を作成しました。
また、母の生前中に長女の子が実際に使っている通帳に振り込み、その都度、贈与契約書も作成しておきました。
兄妹喧嘩で残るもの
2次相続を終えて長女(妹)の気分は心底晴れたのでしょうか。筆者はそうは思いません。
相続人の家族はこの兄妹喧嘩を見ています。
孫や親族の方は、自分たちの相続時には円満な相続にするにはどうしたらよいのかということを学んだに違いありません。(執筆者:1級FP、相続一筋20年 橋本 玄也)