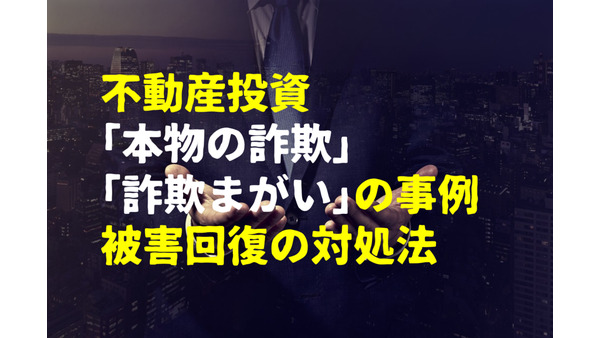居住用物件における立退料が多くとも数百万円規模にとどまるのとは異なり、店舗や事務所といった事業用物件での立退料は桁が違うこともあります。
事業用物件は賃借面積が比較的広く、家賃も高額なことが多いだけが理由ではありません。
居住用物件では移転実費や賃料差額の補償により損害が補填されるのに対して、事業用物件では、
- 開業時やその後の営業継続中に物件へかけた内装・設備の費用
- 移転に伴い営業できない期間の補填
- 一時的な営業利益の減少や廃業可能性
といったことも問題となることが理由です。
そのため、従業員を何人も抱える大規模な事業者だけでなく、小規模な会社や個人事業主、家族経営のような小さなお店であっても立ち退きの問題を意識する必要があります。
居住用と事業用の併用で物件を借りている場合も、同じ理由から用途が居住用だけの場合より立退料は高額となりえます。
■オーナーチェンジ後のタイミングに注意
立ち退き問題が浮上してくる可能性がある
■定期借家のリスク
4つのリスクを解説
■締結した定期借家契約を争うことは難しい
事業者は未然に定期借家制度のことを知っておく必要がある

目次
立ち退きの持ちかけられ方
立ち退きの問題は、長年付き合いのあった賃貸人が建物を売却した、いわゆるオーナーチェンジのタイミングで問題が浮上してくることが多く、普通借家契約で長く借りている事業用物件でオーナーチェンジが起きた場合は要注意といえます。
既存の建物を取り壊して再開発による有効活用や土地の更地売却を目的として建物を取得する事業者にとっては、早期に入居中テナントの立ち退きを実現することに加え、退去させる際に支払う立退料を低く抑えることも重要です。
そのため、立ち退きの問題は、立退料を払うから出て行ってほしいというわかりやすい形で出てくるとは限りません。
老朽化や耐震強度不足による取り壊し、高度利用の必要性が高いことを理由に、立退料には触れずに解約の申入れや更新をしない(更新拒絶)という主張がされることや、また、定期借家契約(借地借家法38条の定期建物賃貸借)へ切り替えを行いたいという打診がなされることもあります。
この定期借家契約への切り替えでよくある説明は、
「現在の契約の更新はしないので、定期借家契約の締結に応じない場合出て行ってもらう必要がある」
「定期借家契約でも再契約という手段があり、必ずしも期間満了で出て行くことにはならない」
というものです。
更新料が不要であるという説明や、定期借家契約にする場合は賃料を従来より減額するという提案がされることもあります。
しかしこの話に飛びついてはいけません。
法定更新制度の存在
賃貸人が更新はできないといっても、普通借家契約では借地借家法上、賃借人を保護するために法定更新(借地借家法26条1項)という制度があります。
契約期間の定めはなくなりますが、従前の契約と同一の条件で普通賃貸借契約を継続させることができます。
従来の賃貸借期間の満了をもって自動的に契約が更新されるので、合意や新たな契約の締結は必要ありません。
つまり、賃貸人から合意更新をしないという姿勢を示されても契約更新はできるので、定期借家契約の締結をしなくとも原則として出て行く必要はないのです。
例外的に賃貸人の更新拒絶が認められるのは、更新しない旨の通知(更新拒絶通知)が契約期間満了の「1年前から6か月前まで」(借地借家法26条1項)に出されたこと、期間満了後も使用を継続した場合に賃貸人から遅滞のない異議が出されたこと(同2項)に加え、賃貸人の更新拒絶に正当の事由(同28条)がある場合です。
正当の事由が簡単に認められないことは、以下の記事で説明をしています。↓
定期借家のリスク
定期借家契約は、普通賃貸借契約と比べると賃借人保護を弱めた賃貸人に有利な制度で、普通借家契約にはなかったリスクがあります。
再契約の権利がない
契約期間終了後に再契約がありえるという点ですが、再契約について法的な権利が賃借人にあるわけではなく、再契約できるかできないかは賃貸人の意向次第です。
取り壊す場合に限らず、契約解除事由にはならない程度の賃貸人や他テナントとのトラブルでも再契約を断わられることがありえます。
条件見直しの可能性
再契約自体はできても、賃料の大幅な値上げをはじめ、契約の期間や条件を見直すという内容で再契約の条件を提示されることもあります。
再契約は新規の契約であり、従来の契約内容より不利な内容を提示されても、賃借人側から同じ条件で契約を続けたいと交渉することは法的に不可能なため、賃貸人の提示する条件を受け入れて再契約するか、受け入れずに契約満了をもって退去するかというどちらかの選択を迫られることとなります。
中途解約の制限
居住用建物では、定期借家契約でも一定の条件の下で賃借人からの契約期間中の解約申入れが可能とされています(借地借家法38条7項)。
しかし事業用物件にこのような規定はなく、締結した契約条項に賃借人による中途解約を認める旨の条項がなければ、原則として契約期間中に賃借人から中途解約をすることはできません。
解約は可能だが契約満了までの残期間に相当する賃料相当額が違約金となる旨の規定がされることも多く、このような内容の契約条項自体も、期間中の契約継続を想定して締結される定期借家契約では裁判上も認められる傾向にあります。(違約金が何年分にものぼるなど解約の事由を極端に制約する条項と判断される場合、公序良俗違反で部分的に無効となることもあります。)
事業や経営状況に急な変化が生じて定期借家の期間満了前にお店を畳んだり賃料の安い物件へ移転を考える場合に大きな負担となります。
立退料の支払いが受けられない
定期借家契約への切り替えは、従来の賃貸借契約を合意で終了させ、新たに定期借家契約を締結することを意味します。
そのため、切り替え後は、賃貸人が普通借家契約を終了させる際に必要とされていた正当の事由は不要となり、賃借人は立退料の支払いが受けられなくなります。
また、法定更新の規定の適用もなく、定期借家契約の期間満了により賃貸借関係は確定的に終了するため、期間満了後に出て行かないと従来の賃料と同じ金額を払ったとしても法的には不法占拠の状態となります。
締結した定期借家契約を争うことは難しい
定期借家契約は賃借人にとってリスクをはらむものであることから、
- 期間が定められていること
- 更新を否定する旨の条項があること
- 書面による契約であること
- 更新がないことについての事前の説明(事前説明)があること(そしてこの事前説明を行うには定期借家契約とは別の書面の交付をすること)
という厳格な条件の下で成立します。
要件を1つでも満たさない場合は、賃貸借は普通借家契約として成立します。
このうち事前説明とは、「賃貸人は、契約前にあらかじめ、賃借人に対し、更新がないことについて、説明をしなければならない(借地借家法38条3項)」というものです。
定期借家契約を締結した後に、賃貸人からの明渡請求に対して、説明の意味を理解せずに契約を締結してしまったとして事前説明が不十分であった点が争われる事例もありますが、事前説明が否定されて普通賃貸借が認められる裁判例は多くはありません。
裁判所は、定期借家の要件である事前説明の程度について、現実の賃借人の理解までを求めず、客観的に個々の賃借人が理解しうる程度の説明で足りると判断しています。
実務上も、事前説明についての書面の交付に加え、「借地借家法38条3項の説明を受けた」旨の確認書が作成されることが多く、説明がされていないと争うことが難しいことも理由です。
締結した定期借家契約の効力を事後的に争うことは現実的には難しいため、定期借家契約とはどのようなものか、どういったリスクがあるのかを知識として知っておくことが重要となります。

小規模事業者こそ気をつけるべき
規模の大きい事業者であればある程度以上の法的知識もあり、切り替えに応じるケースは少ないと考えられますが、小さなお店の場合、特に疑問もなく定期借家契約への切り替えを行ってしまうと、数年後に上で述べたような問題に直面することとなります。
私が弁護士として立ち退き問題の相談を受けた中でも、デメリットを十分理解せずして定期借家契約を締結されていたため、残念ながらお力になれなかった事案があります。
保証人(特に連帯保証人)に気をつけるという意識は日本社会に浸透していますが、定期借家に気をつけるという意識はそこまで一般的でないように思います。
特に店舗を経営する小規模事業者にはこの意識が浸透していくことを願います。(執筆者:弁護士 古賀 麻里子)