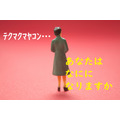目次
人生100年時代
今ごろ読みました。
リンダ=グラットン,アンドリュー=スコット共著の『LIFE SHIFT』。
副題の『100年時代の人生戦略』は、「人生100年時代」としてユーキャンの新語・流行語大賞に昨年ノミネートされていましたね。
今年になってからも、政府では「人生100年時代構想会議」なんてものが重ねられているようです。

資産には無形のものがある
ざっと読んだだけですので理解が及ばない点はご容赦いただきたいのですが、要旨は3点だったように思います。
1. 寿命が延びるため「教育」、「仕事」、「引退」の3ステージの人生では、資産を食いつぶす「引退」が長すぎ破綻してしまう。
2. このため、世界を探索したり自分を見つめなおしたり、プチ起業したり複業したり学び直しをしたりすることも含めた、マルチステージ(4ステージ以上)の人生を送りましょう。
3. マルチステージの人生では、有形資産と無形資産とのバランスを取って人生をマネジメントすることが重要です。
うん。おもしろかった…。
まぁ著者たちの言うように政策が時代の変化に追い付いてくれるのはどうしても遅れるので、だからといってその変化の準備を今すぐに始めるのは難しいと思いますが。
上記の主張のなかで、私が特に興味をそそられたのは、3つめの「有形資産」と「無形資産」の分類です。
これ、以前の記事に登場した金森重樹さんの「地位財」、「非地位財」とは異なる分類になるようです。
有形資産

・ マイホームなどの不動産
・ 貯蓄などの金融資産
ようするにお金による計上が比較的容易な資産。
無形資産
・ スキル
・ 知識
・ 人脈
・ 評判
・ 心身の健康
・ 友情
・ 愛情
・ 人生のシフトチェンジのための自己理解や挑戦する姿勢
両者は密接に結びついており、無形資産が有形資産の取得を助け、有形資産によって無形資産を育むことができるとのことです。
うまく両者がからみあって豊かになっていくのが理想的ですね。
無形の資産は専業主婦が担ってきた

そして、こうも書かれてありました。
と。
この場合の無形資産とは、
・ 子どもの世話
・ 地域コミュニティでのお付き合い
などを指します。
伝統的とはいっても、「共働き」ですら相変わらず夫が残業しまくり妻に家事を丸投げなわが国では、完全に現在進行形の話だと思います。
こうもクリアに性的役割分業を言い当てていただけるとスッキリしますね。
はい、専業主婦の私、夫の無形資産を維持しています。
夫は私と結婚してから、
なんて不満を垂れています。
屈折していますよね。
ただ私の夫は、週末には子どもを連れ出してくれますし、洗濯ものを干してお風呂を洗うことを毎朝のルーチンにしている人です。
地域の集まりにも積極的。けっこう無形資産のためにも尽力してくれています。
有形資産を「生前贈与」してしまう夫

そんな夫の姿には、ありがたいことだとただただ感心していました。
しかし、この書籍を読んでわかったのです。
彼はなかなかな戦略眼を持って、家事と育児に勤しんでいたのでした。
この書籍の別の場面では、シェークスピアの『リア王』よろしく、遺産を早期に生前贈与したために実の子どもから冷たい扱いを受ける老人の姿が指摘されています。
資産は死ぬ直前まで握り続けるのが吉なんですって。
話を有形資産と無形資産に戻しましょう。
専業主婦世帯では、有形資産は主に夫が築きます。
これは夫の退職で終了。
その後も年金が受け取れ有形資産は得られますが、その対価である保険料支払いは在職中に済んでいます。
これって先ほどの「生前贈与」そっくりじゃないですか。
もう夫は用済みというか、居なけりゃ収入が減るから困るけれども、居る以上は必要ないというかになってしまいます。
一方妻は無形資産の維持に引き続き勤しみます。
この無形資産は、それまで妻がせっせと蓄えてきたものです。
子どももご近所付き合いも、妻を中心に回っています。
そのウマ味を、もう用済みの夫になんて…ねぇ……。
そうです。
だから、私の夫は我が家の無形資産の構築に現時点から唾をつけようとしているのです。
考えていないようで、考えていますね。賢いのかもしれない。
専業主婦にはライフシフトが待っている?
この書籍『LIFE SHIFT』の面白いところは、マルチステージの人生を生きるために必要な人生のシフトチェンジには、そのための資産が必要だと論じているところです。
うん、夫たちはチェンジのための資産を蓄えるべきだ。
しかしその資産は、夫がタッチしていないほうの無形資産なんです。
だから従来型の夫は、役立たずだしだからといって変身もできないし、まさにドン詰まりということ。
悲惨です。悲惨なのは彼だけではなく家族ごとなので、早期に手を打つべきなのです。
専業主婦こそ変身しやすい
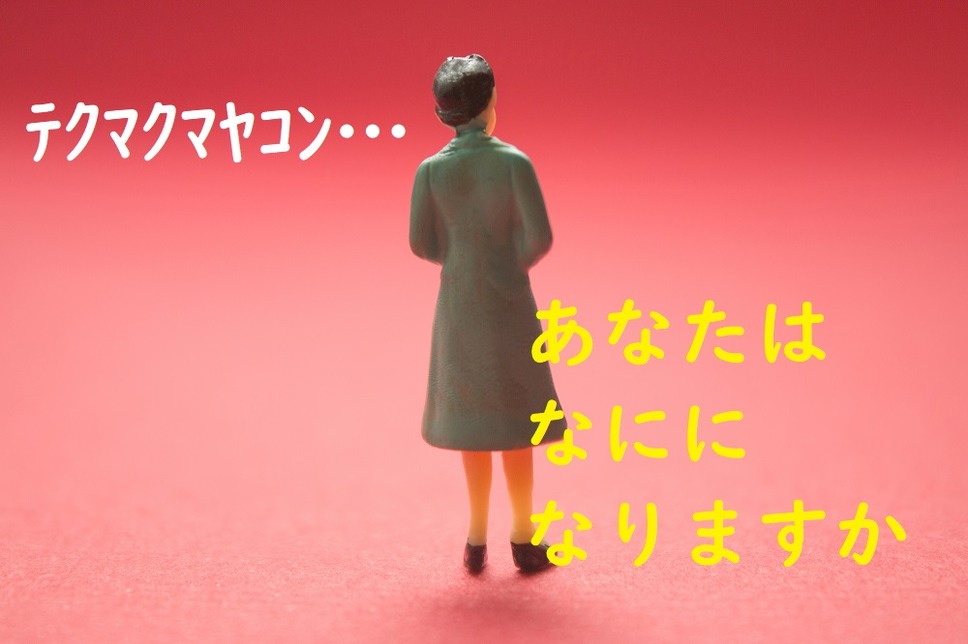
ということは一方、専業主婦の妻のほうは変身しやすいということです。
さて私…子育てがひと段落したら、どうしようかしら。
私が働いて、夫を大学に入れようかしら。
企業の姿勢や法制度が一気に柔軟になってくれて、専業主婦の再就職チャンスと夫の退職リスクが適度になっていれば良いのですが…。(執筆者:徳田 仁美)