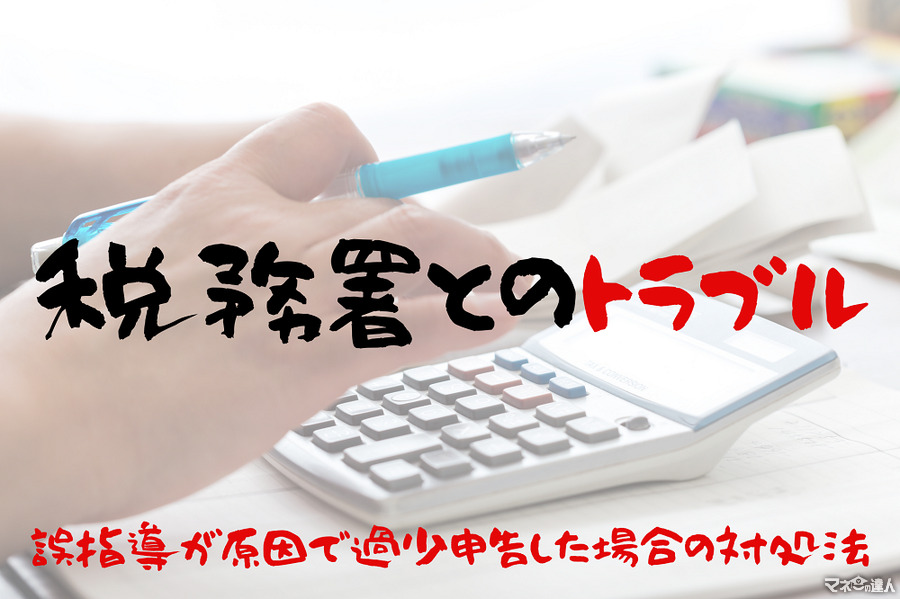税務署でのトラブルの一つが、税金相談や申告相談の際に職員が誤指導をしてしまうことです。
自分で作成した申告書が間違っていた場合には、指摘されても納得はできます。
しかし、税務署に相談して申告書を作成したのに、後日その税務署から「申告内容が間違ってます」と言われても、納得できませんよね。
ですので、もしそのようなトラブルに巻き込まれた際の対処法について、ご説明します。
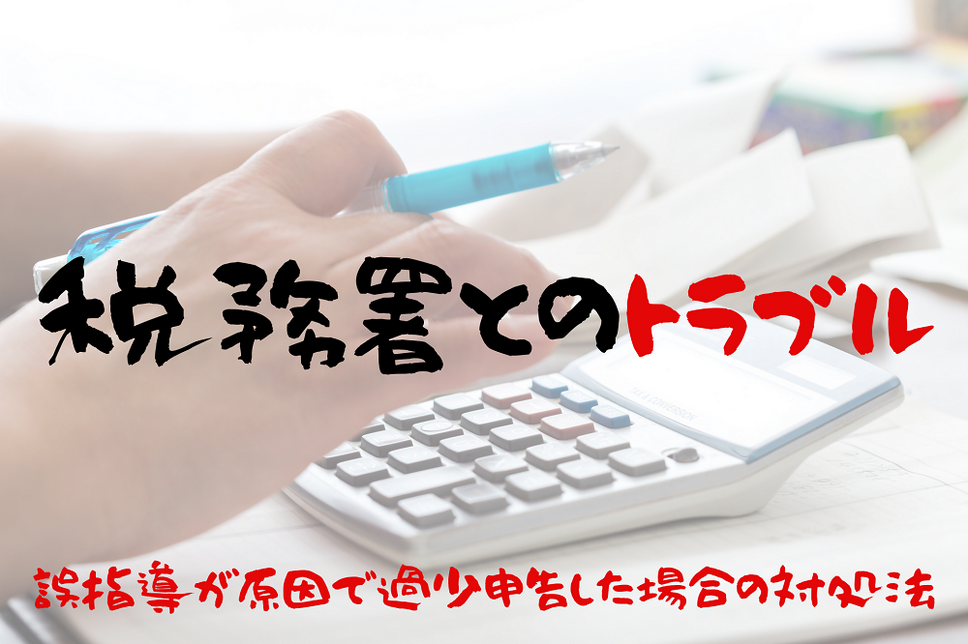
目次
結果的には自分で申告を修正する必要がある
本来、税務署職員が誤指導することはあってはなりません。
民間企業であれば誤指導をした補償もありえますが、税務署の場合、謝罪はしても、最終的には法律に沿った申告内容に修正させます。
したがって、こちら側としては、申告をもう一度やり直す負担だけが増え、納得ができない状況になります。
加算税の支払いを求められる可能性も
税務署の誤指導であったとしても、最終的には自分自身で適切な内容に直し、修正申告書を提出することになります。
しかし、そこで問題になるのが、加算税などペナルティの税金についての取り扱いです。
税務署は明らかに誤指導であった場合には加算税を賦課しませんが、電話相談など税務署の誤指導だと断定できない場合には、加算税はそのまま賦課します。
加算税の免除には、誤指導の証拠が必要
税務署の誤指導による過少申告をしたとき、明らかに税務署の誤指導が原因と判断できる場合には、加算税は免除されます。
国税庁が公表している、申告所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税および無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)を要約しますと、加算税が免除される条件は3つあります。
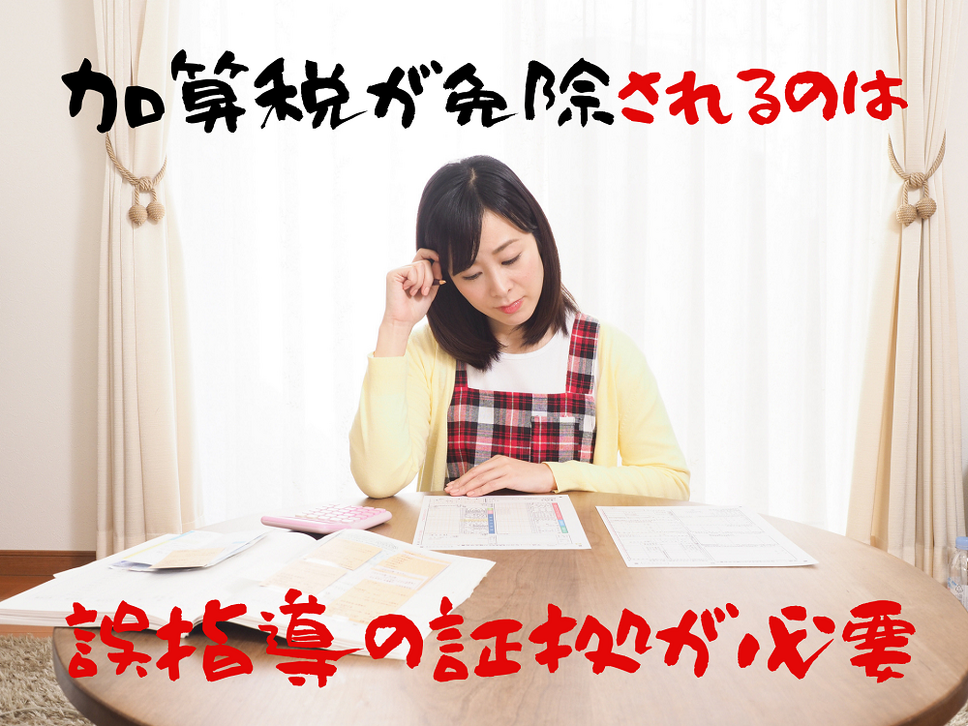
誤指導で加算税の支払いが免除される条件
・ 税務署の誤指導により、過少な申告をしてしまったこと
・ 税務署の指導が信じるに足る内容であったこと
電話や一般相談では、税務署に十分な書類を提出しているとは言えません。
また、誤指導と過少な申告したことの因果関係があることが必要です。
なお、税務署の指摘が明らかに間違っているのを知りながら、過少に申告した場合にも加算税は免除されませんので、ご注意ください。
やり取りをメモに残してトラブルを回避しよう
税務署も無用なトラブルを避けるために、できるだけ相談事績を残すようにしています。
ですので、税務署へ相談する場合には、必要書類を提示し、その内容に基づいた回答をメモに残せば後からお互いの意見を確認できるので、最小限のトラブルで済みます。
税務署は税の専門家ですが、完璧ではありません。
回答がおかしいと感じたら、根拠となる条文の提示を求めたり、税理士などに聞いてみましょう(執筆者:平井 拓)