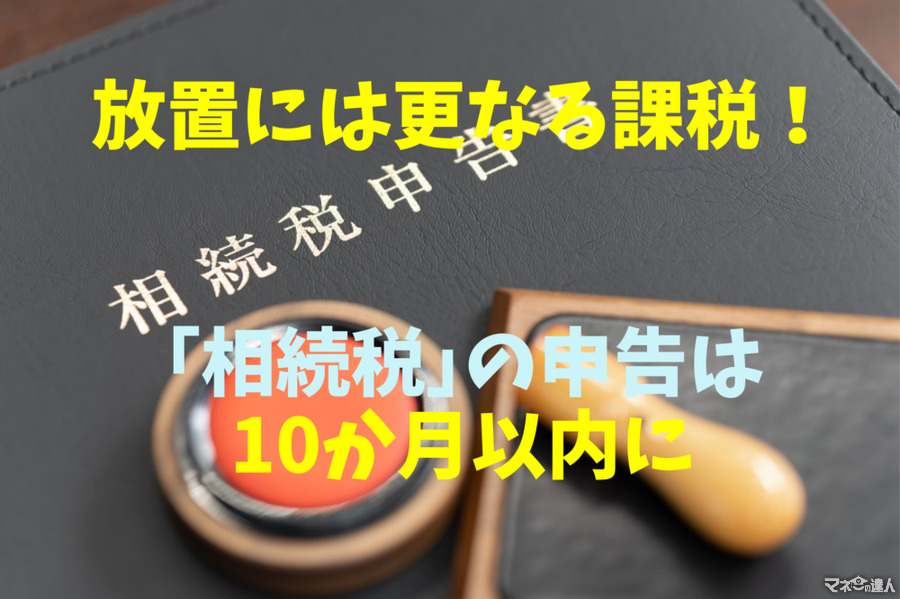相続財産が多いと、額に応じた相続税を申告し、納めなければなりません。
とはいえ、実際に課税対象となるのは全相続人の1割以下です(2017年度は8.3%)。
大多数のケースでは基礎控除額などを差し引けば相続税はゼロとなっています。
一方で、「うちは大丈夫」と思いこんでいて財産額を計算しないまま申告しないといったこともあります。
また、額は把握しているものの、払うのがいやでそのままにしているといったケースもあるようです。
では、相続税を申告・納付せずに放っておいたりした場合にはどうなるのでしょうか。
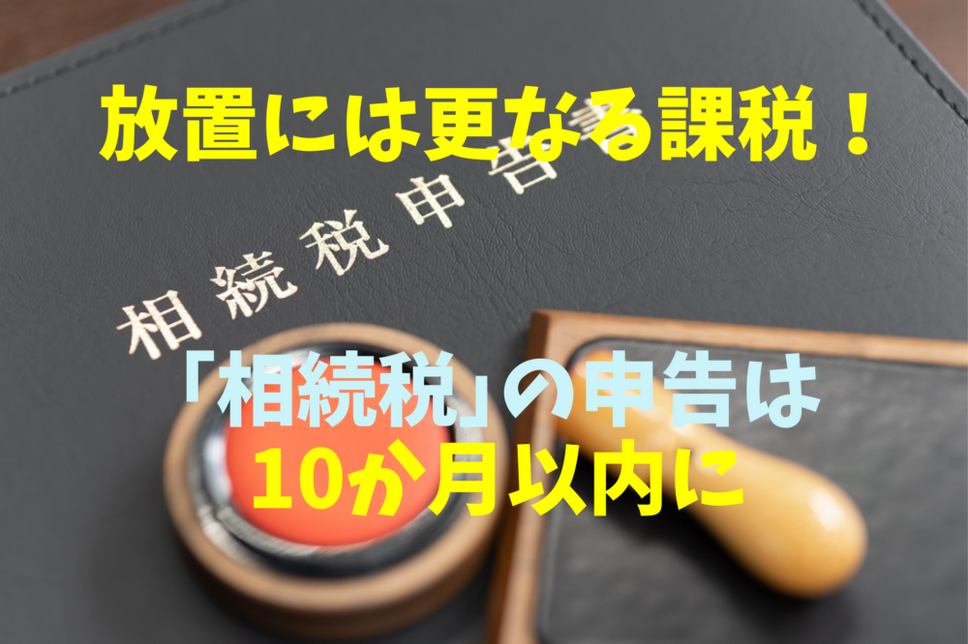
目次
期限延長はできない
その間に相続人を確定し、財産を名義変更し、各財産の評価額を出さなければなりません。
不動産財産の種類が多い場合や、相続人同士に争いがある場合には決して長い期間とはいえません。
ところが、この申告・納付期限はいかなる理由があっても原則として延長してもらえないのです。
相続財産総額が課税対象になりそうな方は、早めの準備を怠らないことです。
延滞税と無申告加算税
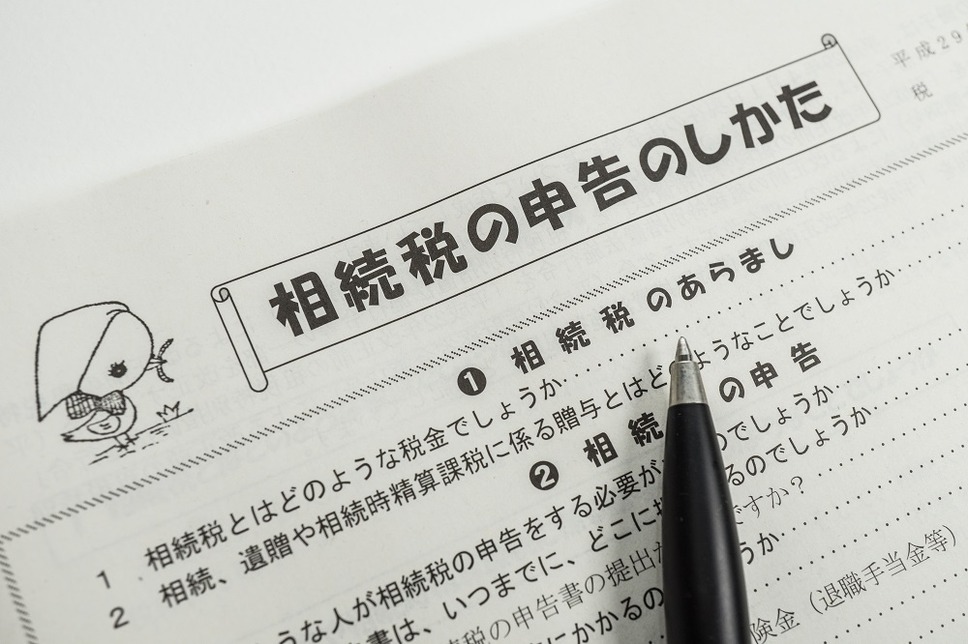
きちんと申告しようと頑張ったけれども、どうしても期限に間に合わなかった場合には、さらなる税金がかかります。
1. 延滞税
まずは、延滞税がかかってきます。
延滞税の相続税額に対する割合は、
それ以降:年9.0%
です。
遅れれば遅れるほど延滞税率が上がっていきます。
2. 無申告加算税
次に、無申告加算税もかかってきます。
制裁金の意味合いを持つもので、こちらは納めるべき相続税額の5%をさらに納めなければなりません。
相続税逃れには、厳しい税金が課される
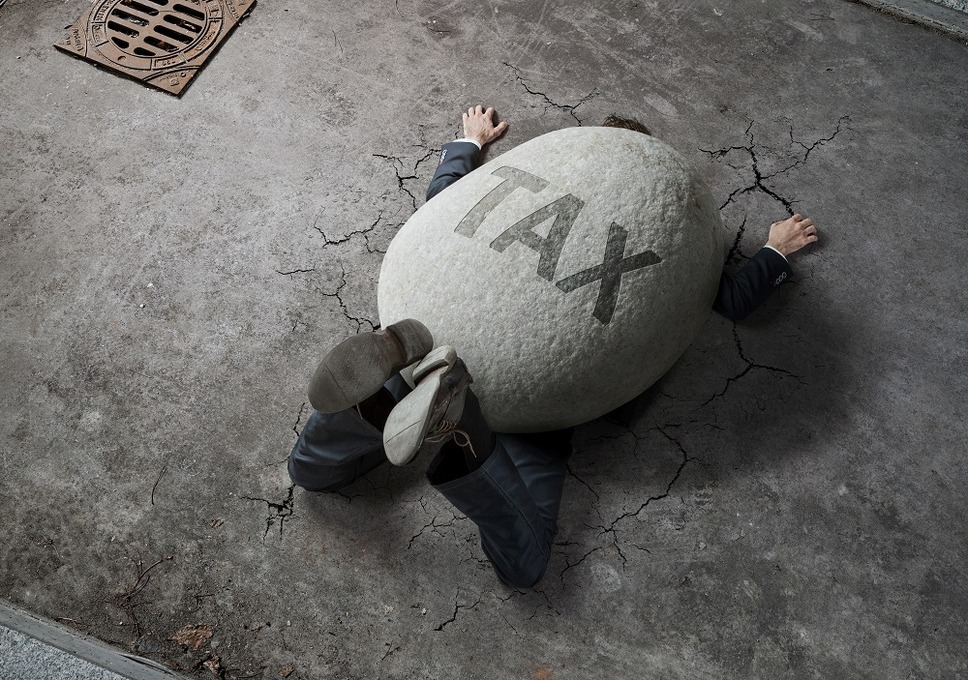
実は、前述のペナルティーは、相続税を申告する意思のある人向けの、まだ軽い方です。
1. 連絡があるまで放置:無申告加算税率アップ
税務署から連絡があるまで申告をしなかった場合には、申告及び納税の意思がなかったとみなされ、
となってしまいます。
2. 納税逃れが発覚:重加算税
さらに、税務署の調査の結果、納税を逃れようといわゆる財産隠しなどをしていたことが発覚すると、重加算税が課せられます。
割合は、実に相続税額の40%という大変厳しいペナルティーです。
「相続税申告の案内」に注意する
税務署は、亡くなった方の財産をある程度把握しています。
これまでの提出書類をチェックしているからです。
また、マイナンバー制度を軸にさまざまな機関が扱う情報にも目を光らせています。
従って、相続税がかかりそうな財産を持つ方が亡くなった場合には、同居の家族などに「相続税申告の案内」が送られてきます。
つまり、
という言い訳は通用しないようになっています。
相続開始後、申告の案内が届いたらできる限り速やかに準備に取りかかるようにしましょう。
もし、さまざまな事情で期限に間に合わない際には、必ず税務署にその旨を伝えることが大切です。
万一のペナルティーは少ないに越したことはありません。(執筆者:橋本 玲子)