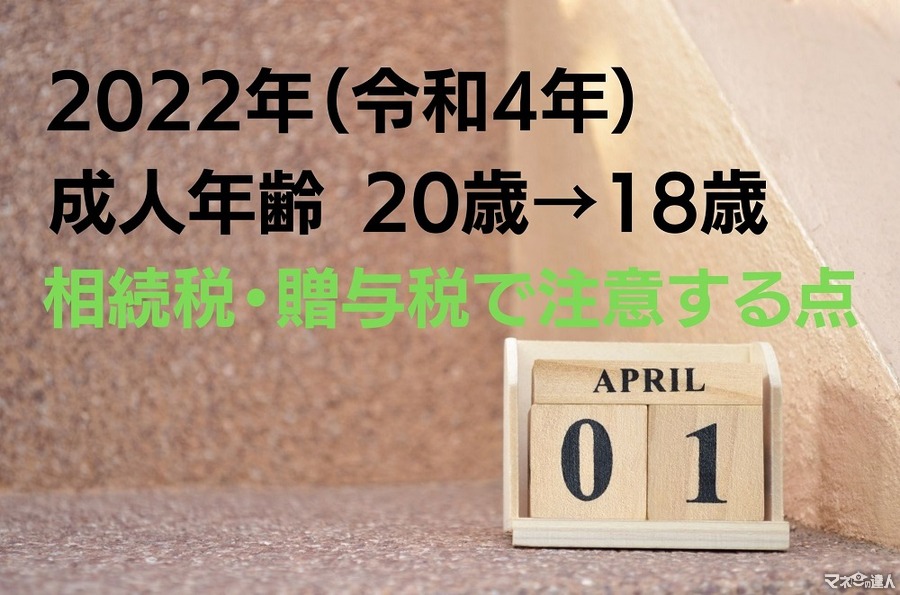2022年(令和4年)4月1日から、日本の成人年齢は20歳から18歳に変わります。
従来から、相続税は未成年者でも申告が必要ですし、贈与税も受贈者(もらった人)の年齢に関係なく、申告手続きが必要です。
一方で、相続税・贈与税には成人年齢が18歳になることで影響する制度も存在しますので、ご注意ください。
目次
相続税の未成年者控除の基準年齢

相続税には、未成年者控除があります。
財産を取得する相続人が未成年者の場合、成人に達するまでの年数に応じて控除額を計算し、相続税から差し引けるのです。
相続税の未成年者の税額控除の計算式
※1年未満の端数は切り捨て
※執筆時点の法律
たとえば相続人の年齢が16歳4か月の場合、現行法での未成年者控除は40万円です。
(20歳 – 16歳 = 4歳)× 10万円 = 40万円
しかし、成人年齢が18歳に引き下がる2022年4月1日以降は、18歳に達するまでの年齢が未成年者控除の基準の年齢となるため、控除額が現在よりも20万円(2年分)減少します。
贈与税の税率は2種類
贈与税は成人年齢が下がることで低い税率が適用されます。
贈与税の税率には、「特別贈与財産用」と「一般贈与財産用」の2種類があります。
特別贈与財産用
贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の受贈者が、直系尊属(親や祖父母)から贈与を受けた際に適用される税率で、一般贈与財産用よりも税率は低く設定されています。
一般贈与財産用
特別財産用に該当しない贈与が対象です。
現在の特別贈与財産用の適用年齢は20歳以上ですが、成人年齢が18歳になる2022年4月1日以降においては18歳以上です。
ただし、対象年齢の18歳は、2022年4月1日以降に受けた贈与から適用されます。
そのため2022年1月1日現在で18歳に到達していても、3月31日までに受けた贈与は20歳以上が対象ですので、ご注意ください。
相続時精算課税の適用年齢

相続時精算課税の適用年齢は18歳からです。
相続時相続時精算課税制度とは、親や祖父母からの贈与を最大2,500万円まで控除を受けられる特例です。
現行制度では相続時精算課税が適用される年齢は、贈与を受けた年の1月1日現在で受贈者は20歳以上でなければなりません。
しかし、2022年4月1日以降、特例の適用は18歳からです。
特例が適用される際の注意点は、先ほど説明した「特別贈与財産用」と同様で、18歳以上になるのは、2022年4月1日以降の贈与からということです。
そのため2022年1月1日現在で18歳に到達している受贈者であっても、2022年3月31日までにもらった贈与については、20歳以上の受贈者しか相続時精算課税が適用されません。
特例制度の適用年齢変更に注意
今後新たに創設される特例制度の適用年齢は18歳が基準となる可能性が高いと言えます。
今回説明した制度以外にも、NISAなど、現在の適用年齢が20歳以上の制度も18歳以上に変更されます。
制度によって18歳から適用される際の時期は異なります。
また、住宅ローン控除や住宅購入資金の非課税制度などについても、今後は対象年齢が18歳以上になる可能性があります。
2022年4月1日は少し先の話ですが、実際に特例や制度を利用する際には適用年齢を確認してください。(執筆者:平井 拓)